【発達障害と勉強法】ADHD・ASD・LD別のオススメ勉強法と教え方、環境調整のポイント
・がんばって勉強しているのに成績が伸びない
・発達障害別の適切な勉強方法が分からない
そんなお子様も多いのではないでしょうか。
こちらの記事では、はじめに発達障害について、その後に発達障害を持ったお子さまが集中して勉強に取り組める環境の作り方や勉強方法についてご紹介します。
ご紹介した内容は、発達障害や不登校のお子様に特化したプロ家庭教師を務める私妻鹿潤が、担当したお子さまと接する際に心がけている点や実際の経験からご紹介するおすすめの方法です。

発達障害専門の受験プロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▼目次
発達障害とは

発達障害とは、先天的な脳の使い方が他の方とは少し異なり、行動や感情の動きが違う特徴がある障害です。
一般的には、ADHD、ASD、LDなどが知られています。「障害」という名前ではありますが、家族や学校、職場での理解や特性に応じたサポートがあれば能力を発揮することもあります。
そのため、私は「でこぼこ個性」と呼ぶ様にしております。実際に障害があるかどうかは、病院にてWISC(ウィスク)検査やDSM-Ⅳ/DSM-Ⅴなどを通して、医師による複合的な診断により下されます。
次に、一般的に知られている発達障害に関してご紹介していきます。
WISCに関しては、こちらの記事にて詳しくご紹介しております。
注意欠陥・多動性障害(ADHD:Attention Deficit Hyperactivity Disability)
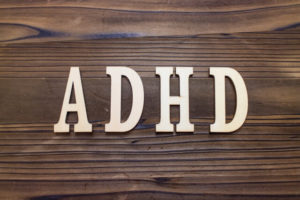
ADHDは、注意欠如障害:ADD(Attention Deficit Disability)と、多動性障害:HD(Hyperactivity Disability)の特徴のうち、そのどちらもを認められる障害です。
文部科学省のガイドラインでは、「年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力及び/又は衝動性多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。」と定義されています。
具体的には以下のような特徴です。
注意欠陥
・物をすぐに失くす/忘れ物が多い
・作業にミスが多い
・計画を立ててひとつづつこなしていくのが苦手
など
多動性(衝動性)
・突然大きな声を出す
・人の邪魔をしてしまう/待てない
など
自閉スペクトラム症(ASD:Autism Spectrum Disability)

これまで様々な呼称がありましたが、DSM-Ⅴの発表があり、「自閉スペクトラム症」と呼称が統一されました。
とはいえ、まだ従来のような「自閉症」や「アスペルガー症候群」などの呼称のほうが一般的と言えるでしょう。
文部科学省のガイドラインでは「他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。」と定義されています。
具体的には以下のような特徴です。
・強いこだわりがある
・一つのことを深堀りする
・会話とは関係のない話を突然話し出す
など
学習症(LD:Learing Disability) / 限局性学習症(SLD:Specific Learning Disablity)

学習や勉強では、様々な能力を駆使しながら習得していきます。
LDでは、特に勉強をする際に使用する能力を習得することや、使用することが苦手である障害です。
また、ADHDやASDをなどを伴う場合もあります。文部科学省のガイドラインでは「基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する、又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を示すものである。」と定義されています。
上記6つの特性の内、代表的な名称がつけられている3つについてご紹介します。
読字障害・読みの困難(ディスレクシア:Dyslexia)
・単語や文節で区切りながら読む
・文章の意味の取り違えなどがある
など
書字表出障害・書きの困難(ディスグラフィア:Dysgraphia)
・文字の一部分を付け加えたり、入れ忘れたり、置き換えたりすることがある
・段落ごとに内容がうまくまとまっていない
など
算数障害・算数、推論の困難(ディスカリキュリア:Dyscalculia)
・数字やその大小、関係性の理解が弱い
・計算の途中で迷ってしまい別の方法に変える
など
それぞれの発達障害の症状はここに記載されているもの以外にも、ひとりひとりによって違います。
また、その上記の特性があったとしても発達障害ではないこともあります。もしかしたら…と思った際には最寄りの病院にて医師の診察を受けるようにしましょう。
おすすめの勉強環境 / 勉強方法

では、発達障害をお持ちのお子様は勉強に集中することや学力を伸ばすことが難しいのでしょうか?
そんなことはありません!
私の経験上、それぞれの特性や傾向を知り適切なアプローチをすることで、しっかりと勉強に集中・学力の向上につなげることができます。
ここでは家庭内で手軽に行えるノウハウだけでなく、コミュニケーションの考え方やアプローチの方法といった接し方までご紹介します。
ご紹介しているものを全て一気に全部やろうとせず、まずは自分ができそうだと感じたものからひとつずつ始めていくことをおすすめします。
勉強環境について
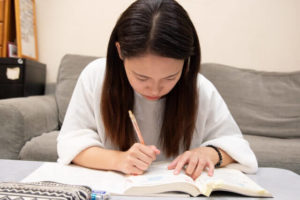
お子様の集中力が切れる要因は様々です。
環境音や身近にあるもの、さらには問題文や教えている際の会話などもきっかけのひとつとなりえます。
勉強する環境から、集中力が切れてしまった要因のものをひとつずつ取り除いていきましょう。教材や勉強時の会話が要因となった場合は、次回よりそれらに意識が向かないようにコミュニケーションを取りながら教えていきましょう。
一番最適なのは、勉強のために必要なもの(教材、筆記用具、ノートなど)以外は机の上から片付けてしまうことです。
勉強部屋は必要?
「じゃあ勉強部屋を作ったほうがいいの?」という疑問を持たれるかと思います。
勉強以外のものがない勉強部屋を作ることは有効です。
しかし一点気をつけなければならないことがあります。それは集中力が切れた際にまた勉強に戻れるかどうか、です。
勉強部屋で一人で勉強をしている際になんらかの理由で集中力が切れた際、親の目が届かないが故に時間が過ぎてしまうこともあります。
はじめは集中力が切れた際に勉強に戻らせるため、保護者の方が一緒について勉強するほうがよいでしょう。
自主学習に慣れ、集中力の持続や、その子なりの勉強のルーティーンができるようになれば、一人でも大丈夫でしょう。
勉強方法について

こちらでは保護者の方が付き添って勉強を教える際の方法をお伝えします。
こだわりが強い場合
数学や英語などで解き方や方法にこだわる場合は、そのこだわりの特性をしっかり理解することが大切です。
そしてそのこだわりがわかれば自ずと納得してもらう言い回しや方向性も見えてくるかと思います。
他にも高校受験や大学受験など最終的に目標としているものがある場合、その解き方などのこだわりは目標につながらないよ、と説明してあげるのも有効です。
ここで重要なのは感情的にならず、ロジカルに説明してあげることです。
お子様がそのこだわりに固執する原因のひとつに「過去の成功体験」が上げられます。今の方法より提案した方法のほうが良いと理論的に納得することができればスムーズに受け入れてくれるかと思います。
集中力が切れてしまった場合
集中力が切れてしまった場合、すぐにまた集中状態に戻ることは困難です。
唐突に勉強とは別のことや雑談を始めてしまった場合などは、その欲求に満足してもらうため放っておくことも有効です。
その代わり、ある程度発散できたなと感じた際にタイミングを見計らって切り替えさせるとすんなりと受け入れてくれることもあります。
「じゃあそろそろ勉強はじめようか?/この問題問いてみようか?」などといった感じで、スパンと切り替えさせることにより集中のスイッチを入れることができます。
勉強時の接し方について

よく集中力がきれてしまうお子様でも、実はその原因を突き詰めていくとはっきりしてくることがあります。
その原因は先程ご紹介したとおり環境、問題、得意不得意な教科、目につくもの、音、匂い、時間帯などなど…。
これは千差万別でひとりひとり理由は違います。原因がわかるまでじっくり向き合ってあげることも大切です。
こちらの記事では、私が担当したOさんというお子様の集中力が切れる時の傾向をご紹介しております。ぜひこちらもご覧いただければと思います。
とはいえ、何も傾向が見つけられないからといって保護者の方が悪いわけではありません。
逆にそれがストレスとなってお子様とのコミュニケーションがギクシャクするほうがデメリットです。
フラットな気持ちでお子様と接するように心がけましょう。
お気軽にご相談ください
私妻鹿潤は教育業界にて16年以上携わり、のべ1,500名以上の生徒を受け持ってきました。
発達障害をお持ちのお子様の傾向はひとりひとり違います。
まずはお子様に「勉強がわかる、できるんだ、楽しい!」と学習意欲を取り戻してもらうことが第一です。
そのためにそれぞれのお子様の目標や保護者様のお話をお伺いし、保護者様、お子様、妻鹿の3人4脚で一歩づつ目標達成に向かって進んで行くことを大事にしております。
ご質問や、少し話を聞いてみたいなど、ほんの少しの理由で大丈夫です。
まずはご気軽にお問い合わせください。
まずは一歩ずつ

発達障害が原因で勉強についていけなかったり、イライラしてしまって集中できず、最終的に不登校になってしまうようなケースは往々にしてあります。
しかし、実は教え方や接し方に工夫をすれば、しっかり勉強に集中することができます。
「できない、嫌い」から「楽しい、できる」にお子様が変化できるきっかけのひとつになれば幸いです。




