発達障害グレーゾーンの高校受験はどうする?合格しやすさと進学後の過ごしやすさを重視した学校選びのコツ
このようなお悩みをお持ちの保護者さまはいらっしゃいませんか?
発達障害の診断がついているわけではないものの、学習のつまずきや集団生活の難しさを感じるお子さまは「グレーゾーン」と呼ばれることがあります。
グレーゾーンのお子さまは、明確な診断を受けていないことから、周囲から「普通にやればできるはず」と見られることもあります。
しかし、本人にとっては 「どうしてもうまくいかない」「周りと同じようにできない」 といった悩みを抱えやすく、自己肯定感が下がりやすい傾向があります。
また、高校に進学することで環境が大きく変わり、
- 授業の進度が早くなる
- 対人関係の難しさが増す(新しいクラス・先生・友人関係)
- 進級・卒業に必要な単位制や成績評価が厳しくなる
といった課題が出てくることもあります。
そのため、グレーゾーンのお子さまにおかれては、「高校でつまずかないためにどんな高校を選ぶべきか?」「どのような環境なら無理なく学べるのか?」を慎重に考えることが大切です。
この記事では、
について詳しく解説します。
グレーゾーンのお子さまの高校選びの参考となる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
▼目次
発達障害グレーゾーンでも高校受験合格は十分可能

まず、発達障害グレーゾーンのお子さまでも高校受験合格は十分可能であると言えます。
ただし、その際には「志望校選び」と「お子さまに合わせた勉強法」が非常に重要です。
逆に、「志望校選び」と「お子さまに合わせた勉強法」の2つさえ上手く上手く抑えることができれば、定型発達のお子さま以上の結果が出せることも多いです。
グレーゾーンの場合は私立高校が圧倒的におすすめ
発達障害グレーゾーンのお子さまの場合は、公立高校よりも私立高校の方が相性が良い場合がほとんどです。
というのも、私立高校の入試には、
- 内申点なしの当日試験一発勝負であることが多い
- 入試科目の配点や難易度に偏りがある
といった特徴があります。
ですので、内申点に不安があったり、得意と不得意の差が大きかったりする発達障害グレーゾーンのお子さまの場合は、内申点が要らず、得意な科目や好きな科目に振り切って対策ができる私立高校の方が相性が良いと言えます。
また、私立高校は学校によって受験方式がかなり異なります。
5教科ではなく英語・数学・国語の3科目受験の学校もあれば、国際コースでは英語の得点が2倍にされたり、英検などの外部試験の得点が加算されたり、あるいは数学の問題だけ異常に難易度が高い学校など、学校ごとに様々な違いがあります。
そのため、例えば理数科目が得意で、国語の読解が苦手なお子さまであれば、「理科・数学の配点が高く、難易度も高い」かつ「国語の古文・漢文、文法・漢字の配点が高い(=読解問題の配点が低い)学校」を選ぶことで、合格率を格段に上げることができます。
志望校の選び方としては、まずは2~3年分の過去問を解いた得点と、合格平均点との乖離を見てみましょう。
乖離が少ないほど相性の良い学校であると言えますし、そこからさらに「どの科目の、どの大問で何点を取るか」までを決めれば、自ずと合格までの学習計画も立てられます。
同じ偏差値帯でも、「A高校だと合格平均点からマイナス30点だったけれど、B高校だと合格平均点以上を取れた」というケースは非常によくありますので、ぜひいろいろな学校の入試問題をまずは解いてみていただきたいと思います。
なお、ケアレスミスが多い(=ケアレスミスの失点が全体の10%以上ある)お子さまの場合は、「記述式の問題が多く、部分点がもらえる学校」を選ぶと良いでしょう。
公立高校の場合は内申点が重要
公立高校の場合は都道府県ごとに傾向が違うものの、内申点・当日入試とも5教科の配点は均等配分であることが多く、さらに副教科が内申点に高い得点で含まれることも多いです。
つまり、公立高校の入試では「オールラウンドに出来るお子さま」が求められているため、好き嫌い・得意不得意がハッキリしている発達障害・グレーゾーンのお子さまと相性が悪いと言えます。
実際に、好きな科目や得意な科目の実力は相当あるにもかかわらず、不得意な科目に引っ張られてしまい、実際の実力よりも2段下の偏差値の高校に入学したなどのケースはよくあります。
ですので、発達障害グレーゾーンのお子さまには、公立高校はあまりおすすめできません。ただし、内申点が高い場合は公立高校を受験しても良いでしょう。
内申点を取るためのコツは、以下のとおりです。
発達障害グレーゾーンにおすすめの校風

「1.発達障害グレーゾーンでも高校受験合格は十分可能」では、合格しやすさの観点から、発達障害グレーゾーンのお子さまにおすすめの高校選びについて解説してきました。
この章では、校風の観点から発達障害グレーゾーンのお子さまにおすすめの高校の特徴を紹介していきます。
発達障害グレーゾーンのお子さまにおすすめの高校の特徴は、
となります。
①少しでも偏差値の高い学校
少しでも偏差値の高い学校に入った方が良い理由は、
といったことが挙げられます。
実際に、偏差値の高い学校の方が落ち着いており、発達障害グレーゾーンのお子さまを「個性的だから」といって攻撃するような生徒は少ない環境にあります。
また、東大や京大といった超難関校にも発達障害の特性を持つ学生は多く在籍しています。このことから、発達障害だからといって必ずしも勉強が苦手ではないこともお分かりいただけるかと思います。(参考:東大・京大合格者は発達障害の性質を持つ人が多い!?)
②自由度が高く、課題の少ない学校
発達障害グレーゾーンのお子さまは、自由度が高く、課題が少ない学校とも相性が良いです。
課題の多さは学校によってかなり差があり、課題が多いところは毎日2-3時間、土日も4-5時間勉強しないと課題が終わらない学校もあれば、課題が全く無い学校もあります。
また、自由度の高さについては、私服OK・髪の毛を染めてもピアスを開けてもOKな学校から、かなり厳しい校則の学校まで様々です。
発達障害グレーゾーンのお子さまは好き嫌いがハッキリしていることが多いため、校則が厳しいなどの管理型の学校は窮屈さを感じやすいです。
また、課題が多い学校ではお子さまに合った勉強をする余裕がなく、精神的に潰れてしまうケースがよくあります。
発達障害グレーゾーンかつコツコツ頑張ることが得意なお子さまもいらっしゃいますが、コツコツ型のお子さまであっても課題の多さがプレッシャーになってしんどくなるケースもあるため、特に課題の多さには注意が必要です。
他にも、私立高校はコース制である場合が多く、一番上の特進コースは受験対策に力を入れて、課題が多くなり自由度も下がる傾向にあります。
そのため、私立高校を受験する際には、「どのコースで受験するか」「そのコースの自由度・課題の多さはどれくらいか」まで事前に把握することが大切です。
大学附属校ではない学校
最後に、大学附属校の受験はあまりオススメしません。というのも、大学附属校と言っても、内部進学率は10~90%とかなり幅があります。
ですので、高校に入ってから全科目において良い成績を取ることができないと、そもそも内部進学できない学校もたくさんあります。
また、内部進学率90%以上の学校であっても、「成績の良い人から順番に好きな学部を選べる」という制度である場合が多く、好き嫌い・得意不得意がハッキリしている発達障害グレーゾーンのお子さまは、行きたい学部に行けないというリスクが高くなります。
内部進学で不本意な学部に進学するくらいなら、大学受験でも自分と相性の良い学校をしっかりと選んで受験した方が、お子さまの人生にとってより良い選択肢になると言えます。
加えて、経済状況が不安定な昨今においては、大学附属校はの人気は未だ根強く倍率がかなり高くなっていることも、大学附属校をあまりお勧めしない理由の一つとなっています。(参考:大学附属校に入れば安心?内部進学だと就職に不利? 附属校のメリット・デメリット)
定時制高校・通信制高校という選択
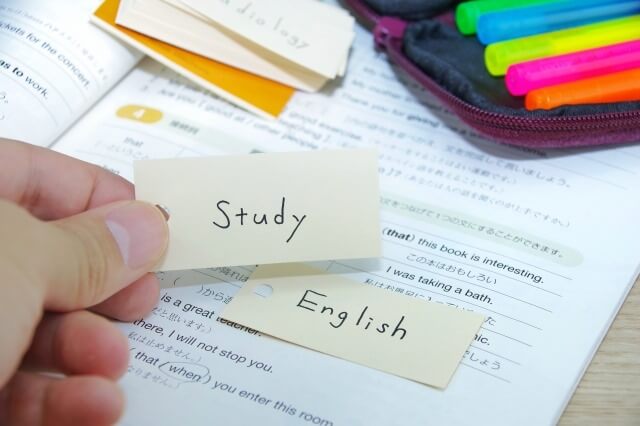
発達障害の特性が特に強かったり、周りのお子さまとのコミュニケーションが本当に苦手であれば、通信制高校も選択肢の一つとなります。
通信制高校は登校日が非常に少なく、学校から送られてくる教材を使って勉強をこなせば高校卒業となります。
また、起立性調節障害でどうしても朝起きられなかったり、大勢と一緒に学ぶ教室が苦手であったりするお子さまは、定時制高校を選ぶのも良いかもしれません。
定時制高校は夕方から夜にかけて、あるいその他の時間帯で授業を受けるため、朝早く起きる必要がありません。また、少人数授業であることも多く、大人数での活動が苦手な方にとっては相性が良いと言えます。
このように、現在は多様な高校があり、発達障害の特性があったり、不登校の経験があったりするお子さまでも通いやすい高校も多数存在しています。
保護者さまの時代に比べるとかなり選択肢は増えていますので、ぜひいろいろな選択肢を検討していただければと思います。
生活面や勉強面でのサポートが必要な場合は、プロ家庭教師メガジュンの「通信制高校サポートコース」や「学習フォローアップ」をご利用ください。
経験豊富なプロ講師がお子さま一人ひとりの性質に寄り添いサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
お子さまの意思が何よりも大切

ここまで、お子さまに合わせた高校選びについて解説してきましたが、お子さまの意思も高校選びにおいてはとても大切です。
特に、発達障害グレーゾーンのお子さまは、好き嫌いや合う/合わないがはっきりしています。そのため、本人の意思を尊重せずに進路を決めてしまうと、不登校になったり、学習意欲が下がったりしてしまうケースは実際によくあります。
また、受験が目の前に近づくと、どうしても合格に意識がいってしまい、「そもそも、なぜ勉強するのか?受験するのか?」という、本来の目的を忘れてしまいがちになります。
目的を見失ってしまうと、やがてモチベーションを失って息切れを起こしてしまいますので、目の前の受験勉強だけでなく、「なぜ勉強するのか?」「合格した後、何をしたいのか?」ということを定期的に振り返っていただければと思います。
お子さまだけで振り返りを行うのは難しいので、「○○高校ではこんな授業があるんだって」など、ご家庭での自然な会話の中で合格後のイメージについてお話していただければと思います。
グレーゾーンであることを学校に言うべき?

結論として、グレーゾーンであることを学校に告知する義務はありませんが、伝えていた方が学校側も配慮してくれることが多いです。
「合否にどこまで影響するか」については、公立高校受験ではまず影響しませんが、私立高校の場合は正直なところ、学校次第ということになります。
表向きは「影響しない」と言われると思いますが、合否の結果は完全に学校に一任されているため、学校が考慮している可能性もあります。
そのため、合格してから告知することが安全策であると言えます。
発達障害ごとの高校受験対策・勉強法

以下からは、発達障害の種類ごとにおすすめの受験対策や勉強方法を紹介します。
発達障害グレーゾーンのお子さまの場合は、苦手な科目や嫌いな科目の対策に相当な時間をかけても、ほとんど成果が現れないというケースがよくあります。
一方で、ADHDやASDの性質を持っていながら、地域のトップ校に合格されたお子さまもたくさんいらっしゃいます。「発達障害だから」と可能性を閉ざさず、お子さまのポテンシャルを最大限に活かすための参考になれば幸いです。
ADHD(注意欠如多動性)の高校受験
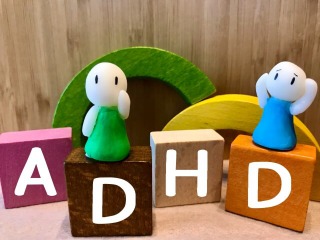
ADHDのお子さまは、「①注意不足」「②衝動性」「③多動性」の3つの性質があることを踏まえた上で、勉強法を見直すことが大切です。
①注意不足
ADHDの注意不足については、厳密には「注意が不足する」というより、特定のことへの意識が強い反面、他の物事を意識することが難しい性質であると言えます。
そのため、好きなこと・興味があることについては意識が強く、高い成果を出せることが多いです。
ですので、受験においては「好きなこと・興味があること」が多く出題され、「嫌いなこと・興味が無いこと」があまり出題されない学校を選ぶことがポイントです。
②衝動性
ADHDの衝動性については、注意不足の延長で、「突然何かに意識が強く奪われる」性質です。
ただ、他人からは衝動的に見えても、お子さまによって衝動性が出やすいタイミングは決まっているので、一定予測することができます。
ですので、衝動性が出やすいタイミングを把握し、衝動が生まれないような環境作りをすれば、かなりのミスを防ぐことができます。
③多動性
ADHDの多動性とは、そわそわしたり、じっとしていられない性質を指します。興味関心が惹かれるものが目に入ってしまうため、多動になるケースが多いです。
そのため、以下のような対策が有効です。
ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)の高校受験
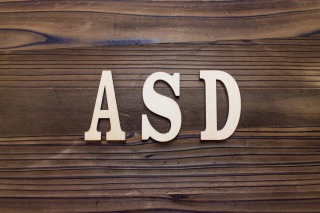
ASDは、「他者の観点に立って何かしらのイメージをしたことがない。もしくはイメージした機会が少ないため、妥当なイメージができない」といったことが特徴です。
逆に、「人の目を気にしないこと」や「興味のあることには一直線に進めること」が強みであるとも言えます。
知的能力が高いお子さまも比較的多いため、学習指導の際には、
の3つを実践することで勉強の成果が出やすくなります。
①言葉選びの特徴を掴む
ASDのお子さまは、「他人は違う考えや価値観を持っている」ということを理解するのが難しいため、お子さま独自の世界で築きあげてきた言葉選びをすることが多いです。
そのため、言葉選びの特徴から「これを言いたいんだな」と掴み、適切にコミュニケーションを取りながら学習内容の伝達やモチベーションのフォローをしてあげることが大切です。
②やるべきことをチェックリストにする
ASDのお子さまは、ルールに従ってやるべきことをやり続けられる力が強いため、チェックリストにするとモチベーションを保ちながら勉強に取り組むことができます。
逆に、やるべきことが曖昧なままだったり、項目分けされていないと、どれをやれば良いか分からなくなってしまうことが多いです。
③最適な伝え方を模索する
ASDのお子さまは、適切な速度や声の大きさ・テンポで話すことが特に重要です。というのも、雰囲気やイントネーションから察することが苦手なお子さまが多いからです。
逆に、お子さまにとって最適な伝え方をすることによって、理解やモチベーションが高まることが多いです。
LD(学習障害)の高校受験

LDとは、全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く・話す・読む・書く・計算する・推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す状態を指します。
LDの勉強法については、こちらの記事(→LD(学習障害)を持つお子さまへの教え方)で詳細解説していますので、併せてご覧ください。
発達障害グレーゾーンの高校受験|まとめ

この記事では、発達障害グレーゾーンのお子さまの高校受験について詳しく解説してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 発達障害の種類や程度にもよるが、高校受験は「やり方次第でうまくいく」
- 合格しやすさのポイントは「得意な科目や好きな科目に振り切った学校選び」
- 発達障害グレーゾーンのお子さまには、偏差値が高くて自由度が高く、課題が少ない学校がおすすめ
- 現代では、定時制か通信制など様々な選択肢がある
- 高校選びにはお子さまの意思も大切
- 発達障害の告知義務はないため、合格後に伝える方が安全
「うちの子の場合は、どんな学校が合っているの?どんな勉強をすれば良いの?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にプロ家庭教師メガジュンまでお問合せください。お子さまの性質や状況を踏まえ、丁寧にお答えいたします。
プロ家庭教師メガジュンでは、発達障害について確かな知見があるプロ講師が一人ひとりのお子さまに徹底的に寄り添いサポートします。
お子さまの性質に合わせた学習指導をお探しの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンの学習サポートをお試しください。
また、授業や面談はオンラインでも承っています。
これまで日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方にも利用いただき、ご好評をいただいてきました。初回相談と初回授業は無料ですので、「オンラインは少し不安・・・」という方も、お気軽にご利用いただけます。
一人でも多くのお子さまが、自分の力でより良い人生を切り拓いていけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




