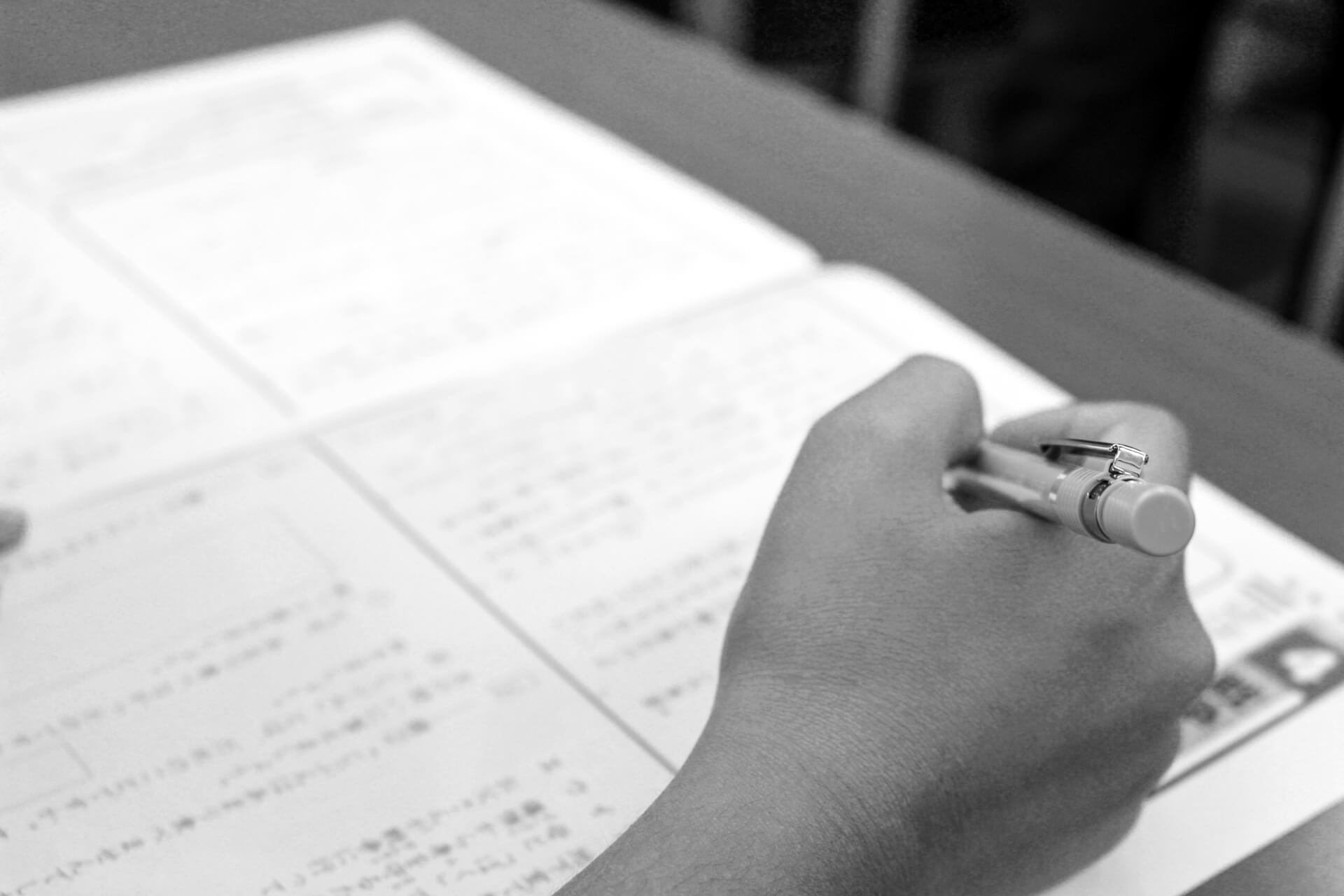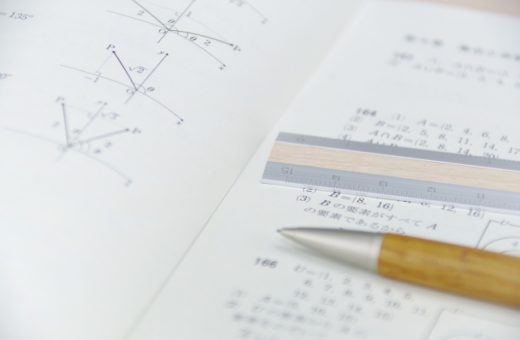ADHDのケアレスミス対策7選!受験対策にも効果◎
- ADHDのお子さまによくある「ケアレスミス」の原因と、それを防ぐための対策
- 学習におけるケアレスミスの7つの具体的な事例と、効果的な改善方法
- ADHDの特性を持つお子さまでも適切なサポートで成果を上げる方法
ADHDのお子さまがよく経験する「ケアレスミス」。「何度注意してもミスが直らない」とお悩みの保護者さまも多いと思います。
私は16年の教育経験を活かし、ADHDを中心とした発達障害専門の受験プロ家庭教師として、多くのご相談を受けてきました。
「うちの子、ADHDだからか、ケアレスミスが減らない…」
「どんな対策をとれば、学習がうまくいくのでしょうか?」
実は、ADHDの特性を持つお子さまでも、東大や京大に進学する方は多くいらっしゃいます。こちらの記事でもご紹介していますが、適切なサポートで成果を上げた例はたくさんあります。
この記事では、ADHDのお子さまが学習でよく起こすケアレスミスと、その具体的な対策を7つのポイントに分けて紹介します。
気になる箇所からチェックして、ぜひ実践してみていただければと思います。
この記事はこんな方におすすめ
- ケアレスミスを繰り返すお子さまのことでお悩みの保護者さま
- ADHDのお子さまに合った学習法やサポート方法を探している方
- 発達障害に関する理解を深め、効果的な対策を実践したい方
▼目次
ADHDのケアレスミスって、そもそも直せる?どこまでが許容範囲?
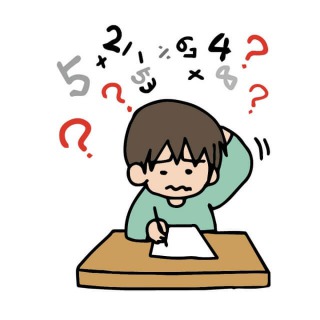
ケアレスミスは完全には直せない、でもほぼ直せる。
これが、16年以上の指導経験から私が出した結論です。
まず、これまで1500人以上のお子さまを指導してきた中で、どれだけ点数が高い・ケアレスミスが少ないお子さまでも、ケアレスミスを全くしないお子さまはいらっしゃいませんでした。
では、どこまでのケアレスミスが許容範囲でしょうか?
それはズバリ、「5点以下」です。
ケアレスミスによる失点が5点以下であれば十分で、6〜10点の失点は平均的な範囲であると言えます。ただし、6~10点の失点がある場合はまだ改善の余地はありますので、ケアレスミス対策に力を入れても良いでしょう。
そして、10点(10%)以上ケアレスミスで落としていれば、優先して対策する必要があります。
ただし、経験上、ADHDのお子さまの場合はケアレスミスによる失点が6〜7点までは許容範囲であると言えます。
この範囲内であれば、ケアレスミス対策よりも未対策の単元や得意科目を伸ばすような勉強をする方が良いケースが多いです。
ADHDのケアレスミス対策の注意点
ADHDのケアレスミス対策の注意点は、以下の2点です。
対策に掛かるコストを考慮する
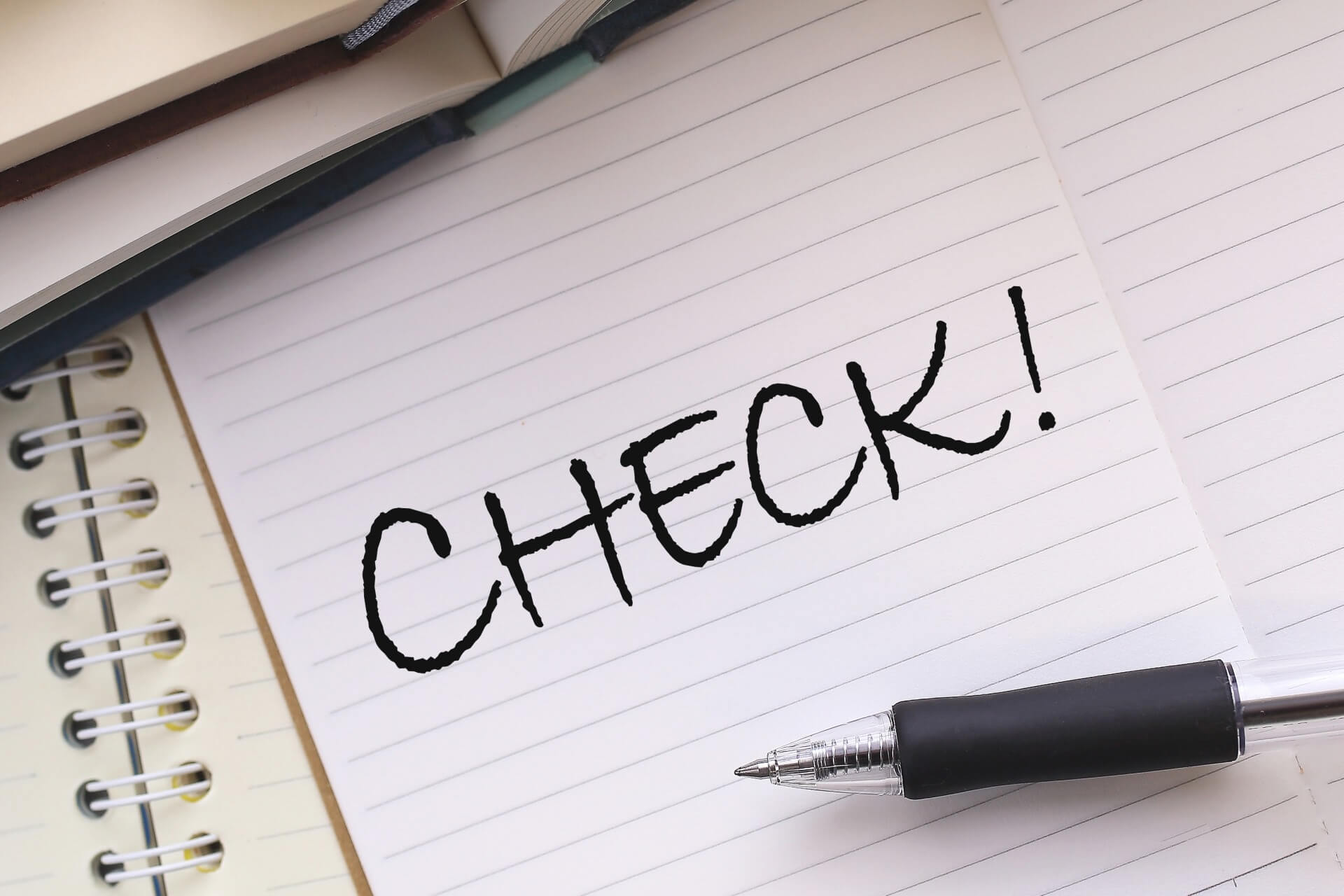
特に受験間近のお子さまにとって、時間は非常に貴重です。
そのため、限られた時間をいかに効率よく使い、点数を上げられる部分に集中するかが重要になります。いわゆる、コストパフォーマンスにこだわった学習法が求められるのです。
ケアレスミスは、単なる偶然ではなく、お子さまの性格や傾向に深く関連しています。
そのため、同じお子さまでも「すぐに直せるケアレスミス」と「直すのが難しいケアレスミス」の2種類に分けることができます。
「すぐに直せるケアレスミス」は、早急に対策を講じるべきです。
しかし、「直すことが相当に難しいケアレスミス」については、無理に直そうとするより、他のミス対策に時間をかけるか、あえてそのケアレスミスを「仕方ないもの」と割り切ることも一つの方法です。
その上で、無駄な時間を省き、点数の取りやすい部分や配点の高い部分に時間をかける方が、結果として高得点が取れる可能性が高くなります。
ADHDの特性を理解する
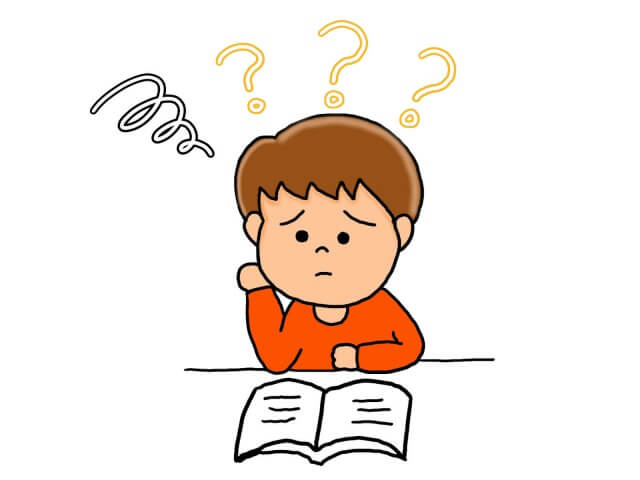
ADHDの特性は、「注意力の欠如」「衝動性」「多動性」の3つです。
ADHDのお子さまのケアレスミスが多いのは、これらの特性が原因であると言えます。ですので、それぞれの特性について正しく理解し、適切に支援することが大切です。
ADHDでよくある学習のケアレスミスと対策7選
この章では、ADHDのお子さまによくある7つのケアレスミスの具体例とその対策をご紹介します。
これらはどれも起こりがちなことですが、全てに当てはまるお子さまもいれば、部分的に当てはまるお子さまもいらっしゃいます。
お子さまがどのケアレスミスを起こしやすいのかイメージしながら読んでいただくと、より理解が深まるかと思います。
①問題文を読み間違える
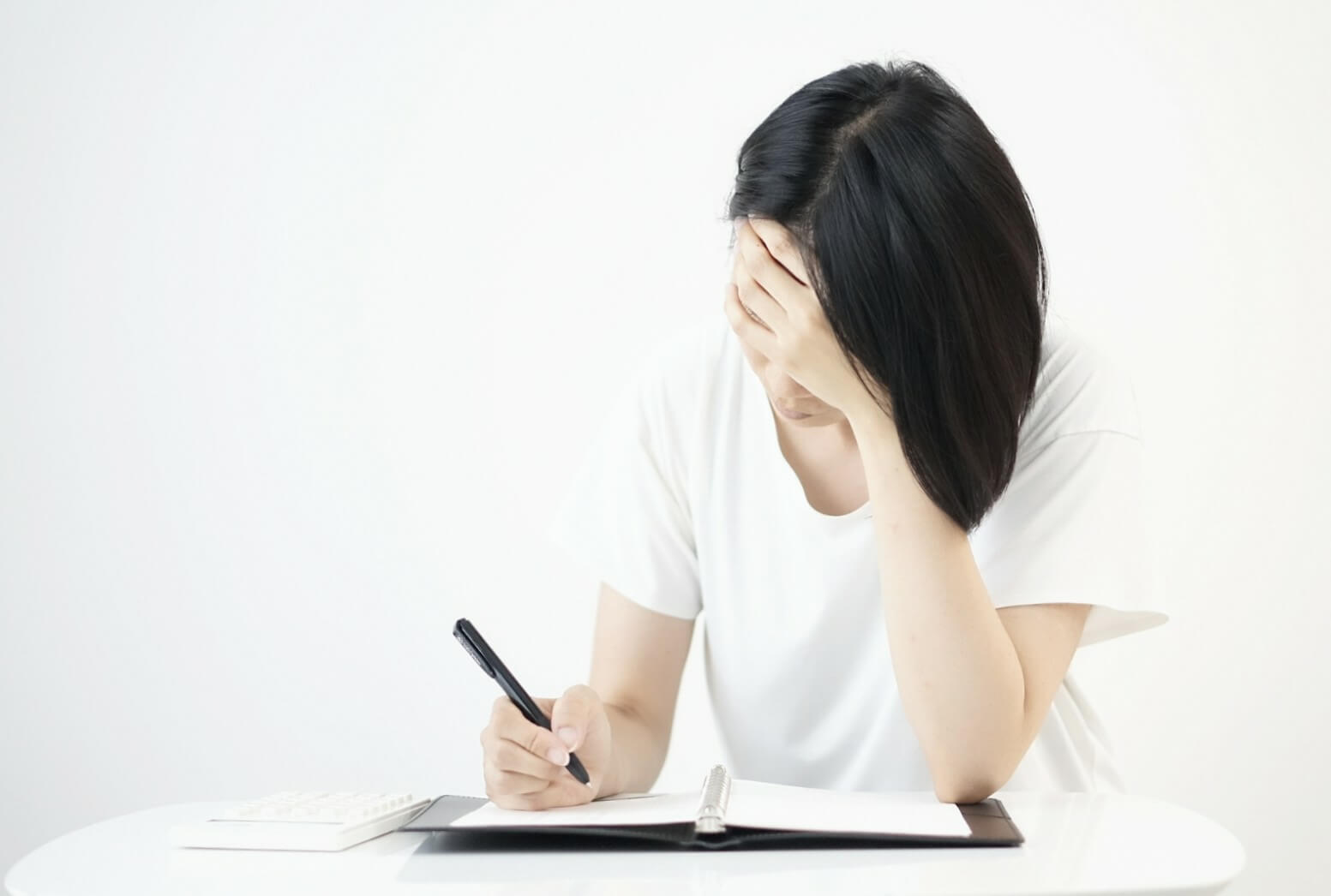
ADHDのお子さまでよくあるケアレスミスとして、「文章を読んでいるようで読んでいない」ということがあります。
文章の最初の方にある文字だけを見て「あ、これは○○のことを言っている」と思い込んでしまい、後半は流し読みで頭に入っていないようなケースです。
例えば、算数の問題で「次の三角形は~」という冒頭の文字を見ると、途端に「これは三角形の面積の公式を使うのだ」と思い込んでしまって、そのまま解き出すようなケースです。
対策としては「問題文は最後まで読むように習慣づける」ということが挙げられます。声に出して問題文を読み上げたり、問題文を指でなぞりながら読んだりして、最後までしっかりと読む癖を付けましょう。
「問題文を最後まで読む練習」はお子さま一人ではやりにくい(楽をするためにサボってしまう)ため、保護者さまや先生と一緒に取り組むようにすると良いでしょう。
②計算ミス
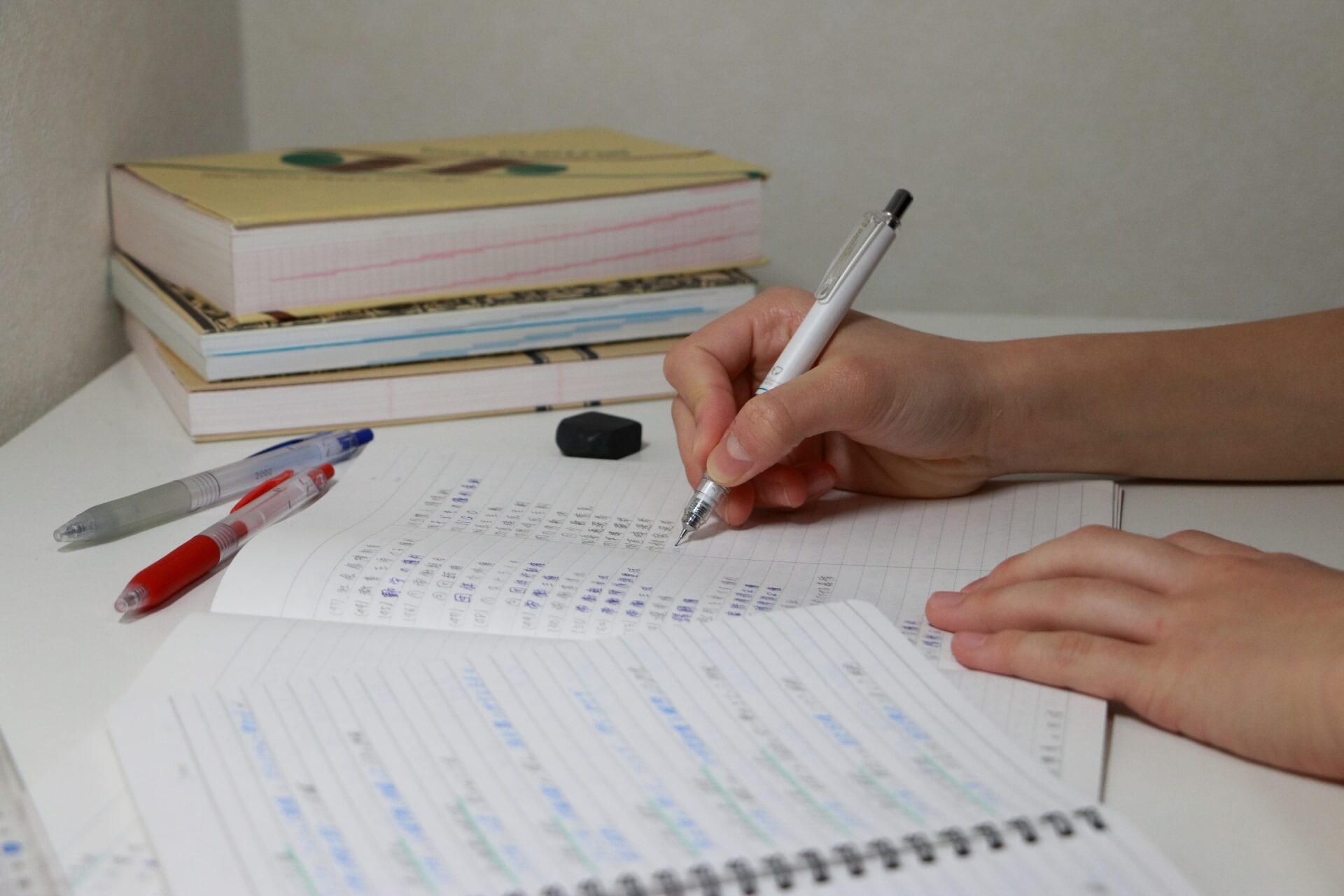
ケアレスミスによる計算ミスについては、さらに細かく分類することができます。計算ミスの分類とそれぞれの対策方法は以下のとおりです。
- ・途中式を書かない
- 途中式を書く習慣をつける。
- ・1度に2つ以上のことをする(通分をして、さらに、かけ算とマイナスをかけるなど)
- 1度に1つの計算しかしないようにする。
- ・途中式をバラバラに書いてしまう
- 行頭を揃え、一か所にまとめて書く習慣をつける。
- ・暗算で解こうとする
- 単純な計算でも必ず筆算をする。
- ・字が小さい。数字の形の判別がしづらい(0と6、1と7など)
- 大きく書く。判別しづらい数字はより丁寧に書くよう意識する。
それぞれの対策については、お子さま自身にメリットを実感してもらうことが大切です。例えば、暗算で解こうとするお子さまの場合は、「筆算する方が見直すときに時間短縮になる」ということを実感してもらいます。
といった形で声をかけ、お子さまが筆算のメリットに気付けるようにサポートしてあげることが大切です。
筆算以外のケアレスミスについても、「丁寧に計算するようになったら、ケアレスミスが〇点減ったね」という形で具体的に成果を示してあげましょう。
丁寧に計算すれば点数が上がるというメリットが実感できると、お子さまは自主的に丁寧に計算できるようになっていきます。
③単位や「。」「、」を付け忘れる
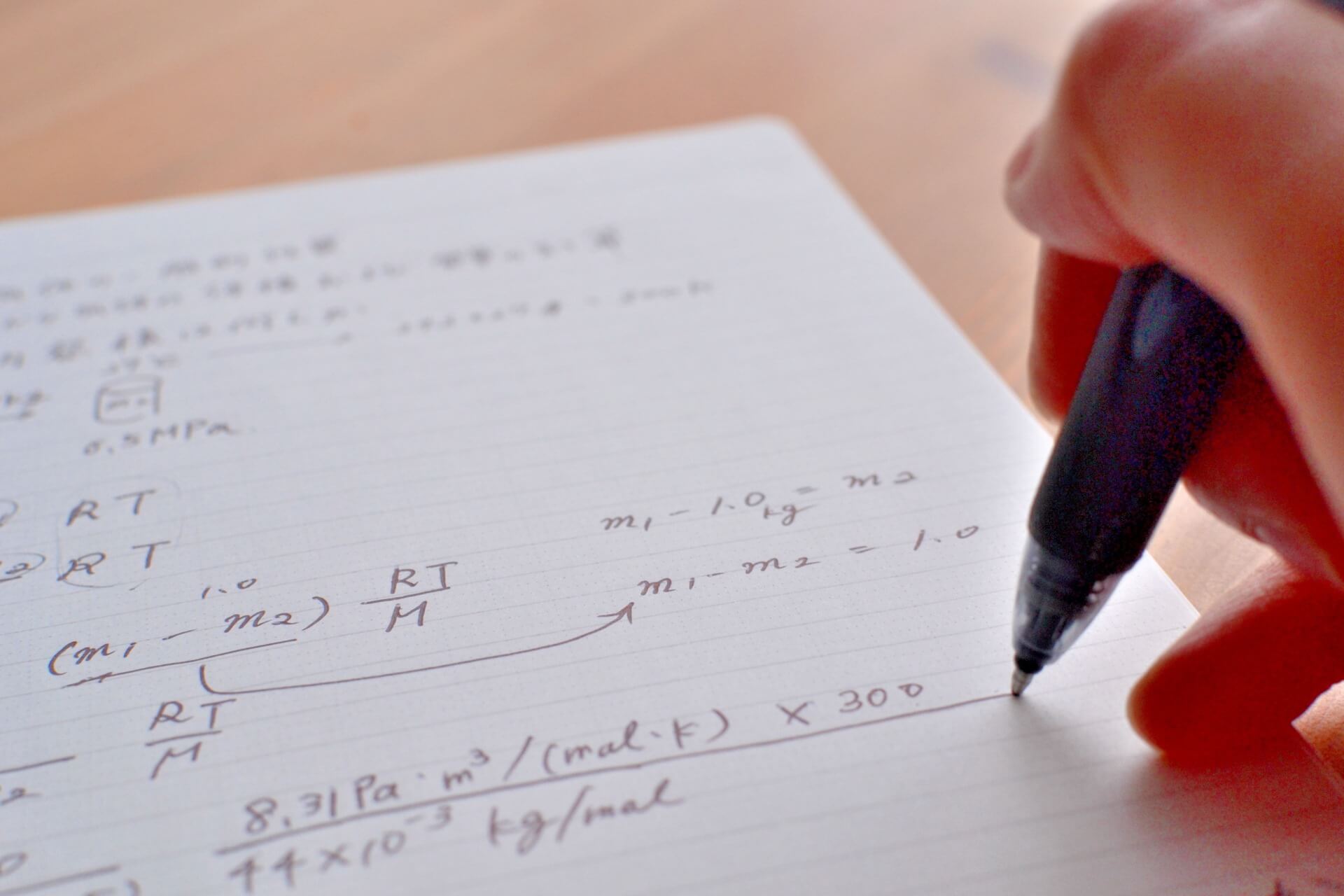
ADHDのお子さま以外でもケアレスミスはよく見られますが、特に単位や「。」「、」の付け忘れなどは、ADHDのお子さまに多く見られる特徴的なミスです。
こうした単純なミスが多いお子さまには、よくあるミスの一覧を作成し、チェックリストを活用することをおすすめします。具体的には、「この問題では、どの部分をどのようにチェックするか」を細かくチェックリストに盛り込みます。
ADHDのお子さまは、やるべきことが明確になるとゲーム感覚で取り組める傾向があります。そのため、チェックリストを作成し、一つずつクリアしていくことでミスを減らすことができます。
例えば、単位の付け忘れが多いお子さまには、問題を見たら最初に単位に◯をつけるというチェック項目を取り入れると良いでしょう。
また、「.」や「?」の付け忘れや、アルファベットの最初の文字を大文字にし忘れることが多いお子さまには、見直しの際に「文章の終わりに『.』や『?』が付いているか」「文章の最初が大文字かどうか」を確認する項目を加えると良いでしょう。
ただし、本番のテストでは、チェックリストを見ながら見直しすることはできません。ですので、事前にチェックリストを使って何度も見直しの練習をすることが大切です。
習慣として身につけることで、自然にチェック作業ができるようになり、ケアレスミスを減らすことができます。
④集中力が切れる
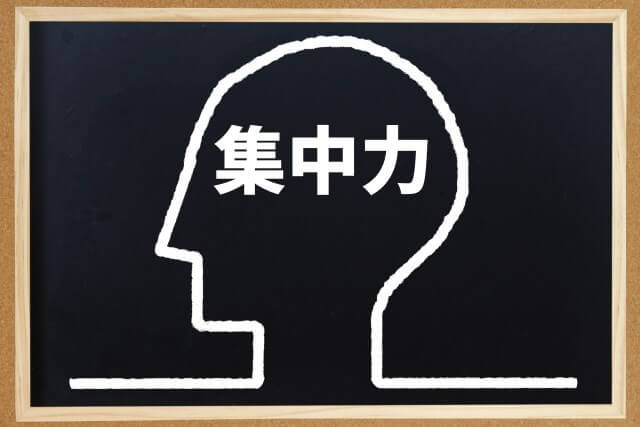
ADHDのお子さまは、その特性上、どうしても集中力が保ちづらい傾向にあります。
ADHDのお子さまに「集中力を切らすな」と言っても限界があるため、「集中力を切らさないように対策すること」「集中力が切れた時に、切り替えられるやり方を見つけること」が大切です。
「集中力を切らさないように対策すること」については、
などが具体的な方法として挙げられます。
スマートフォンを視界に入らない場所に置いたり、5分以上考えて分からない問題は印をつけておいて、後で先生に解き方を聞いたりするようにすると良いでしょう。
5分以上考えて初めて解き方が分かるレベルの問題は、受験でもそう多くは出題されません。
難しい問題にずっと取り組んでいるとどうしても集中力が落ちてしまいますし、受験対策としての優先度も低いため、「後で先生に聞く」という方法はぜひ積極的に取り入れていただければと思います。
集中力が切れた時の切り替え方は、人それぞれ異なります。
例えば、「眠気が強い場合はタイマーをセットして5〜10分の仮眠をとる」という方法が効果的な方もいらっしゃいます。また、好きな科目やサクサク解ける簡単な問題に取り組むと集中力が回復するという方もいらっしゃいます。
リフレッシュについては様々な方法を試しながら、自分に合った方法を見つけていただければと思います。
>>ケアレスミス対策には発達障害専門のプロ家庭教師がおすすめ
⑤慣れない環境で緊張する

「中学生に上がって環境が変わる」など、周囲の環境が変わったときにケアレスミスが増えるADHDのお子さまは多いです。
進級や進学によって周囲の環境が変わると、新しい情報がたくさん入ってきます。ADHDのお子さまは頭の中の交通整理が苦手なため、パンク状態になって集中力が下がり、結果としてケアレスミスが増えると考えられます。
また、ケアレスミスに限らず、環境の変化自体がストレスになり、さまざまな困りごとが増えるケースもあります。
解決策としては、早い段階で学校に慣れるために、信頼できるお友達と学校を探検してみるなどが挙げられます。また、「自分は緊張している」「不安を感じやすい性質だ」ということを自分自身で把握しておくのも大切です。
自分が万全の状態ではないという自覚があれば、その分ミスの無いよう注意しようという意識が働きますし、ミスをしてしまったときにも「緊張しているせいだ」と原因を分析できるため、過度に落ち込むことを避けられます。
上記の延長で最も怖いものが、入試本番でのパニックです。
入試会場は環境や状況がこれまでと大きく変わるため、ADHDのお子さまでなくてもパニックになることがあります。
対策としては、できるだけ早くに試験会場に行き、その場の雰囲気に慣れておくことが挙げられます。また、オープンキャンパスや学園祭などで学校が開放される場合は、こまめに足を運び、試験会場が「行ったことのある場所」になるよう慣れておくことも大切です。
⑥不安や疑問があることで生まれるケアレスミス

気になることや不安なことがあると、ケアレスミスが増えてしまうことがあります。これは、脳内のキャパシティが不安や疑問に取られてしまい、意識がそちらに引っ張られるためです。
そのため、ケアレスミスを減らすためには、不安や疑問を解消することがとても大切です。
例えば、気になっていることを紙に書き出して発散することなどは効果的です。その後、さらに気になることを項目ごとに整理してみると、よりスッキリします。
また、信頼できる人にモヤモヤしていることを聞いてもらうことも有効です。
重要なのは、モヤモヤを途中で止めずにしっかりと出し切ることです。
モヤモヤした気持ちをアウトプットすると、気持ちがスッキリし、その結果、ケアレスミスも減らすことができます。
⑦ながら勉強や、気になるもの・好きなものを視界に入れることでのケアレスミス
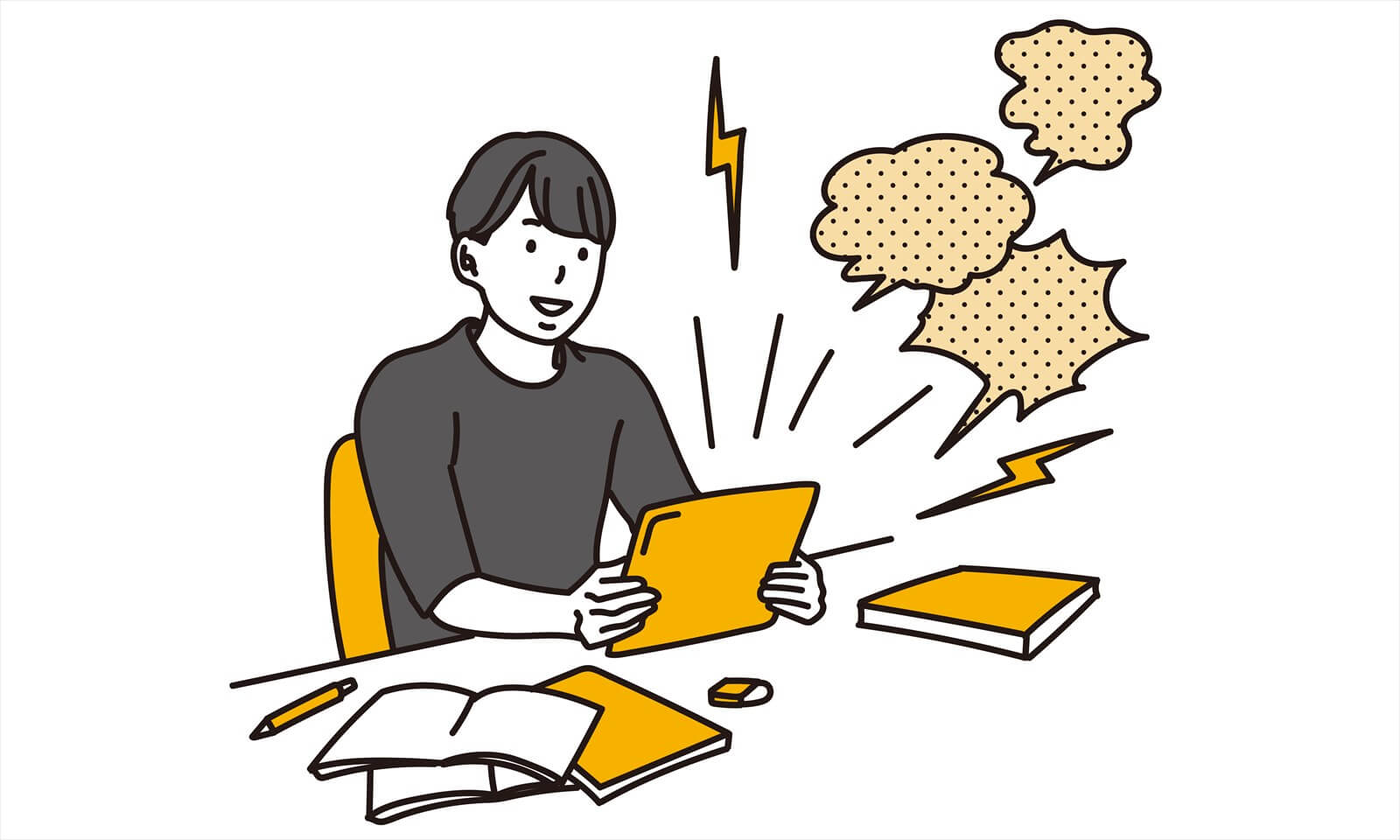
音楽を聴きながらの勉強や、テレビを見ながらの勉強など、いわゆる「ながら勉強」はケアレスミスを引き起こしやすいです。特に、ADHDのお子さまは集中を維持するのが難しいため、いつの間にか音楽やテレビに100%の意識が向かってしまうことがあります。
対策としては、「視界内に気になるものや興味があるものを入れないこと」が重要です。
例えば、漫画が好きなお子さまなら、勉強中には漫画の棚が視界に入らないようにしましょう。また、スマートフォンも視界から外しておくことが大切です。
さらに、原色は気を引きやすいため、勉強机の周りにはなるべく置かない方が良いでしょう。
気になる形や好きなキャラクターの文房具は机の周りに置かない、もしくは見えない場所にしまっておくことをオススメします。また、机や壁の色、柄をシンプルで淡い色にすることによっても、集中力を高められる可能性があります。
ADHDのケアレスミスのまとめ
ADHDのお子さまが学習において経験しやすい「ケアレスミス」。その原因と効果的な対策について、7つのポイントを紹介しました。お子さま一人一人の特性に合わせた方法を取り入れることで、ケアレスミスを減らし、学習の質を向上させることができます。
- ケアレスミスのよくある事例をチェックリストにまとめ、見直しを習慣化する
- 計算ミスは「丁寧に計算するメリット」を実感させる
- 気になることや不安を解消することで、ケアレスミスを減らす
- 適度に休憩を取り入れ、メリハリをつけて集中する
- 作業環境をシンプルにし、気が散るものを排除する
重要なのは、ただ「ミスを減らす」ことではなく、お子さまに合ったサポートと工夫をしながら、学習の自信を育むことです。
「うちの子、どうしてもケアレスミスが多い」とお悩みの保護者さまは、ぜひ一度私たちプロ家庭教師メガジュンのサポートをお試しください。お子さまの性質をしっかりと見極め、一人ひとりに合った学習方法やサポートをご提案いたします。
また、プロ家庭教師メガジュンでは、生活上の困りごとや進路相談など、学習面以外の相談も幅広く承っています。なかなか良い塾や家庭教師が見つからないという方は、ぜひ一度、プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
なお、初回のご相談や授業は無料で承っています。面談や授業を踏まえてじっくり検討いただくことができますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
授業や面談はオンラインでも行っており、これまで日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方にも多数ご利用をいただいてきました。「オンラインで授業を受けられるか不安」という方も、体験授業を受けてから入会について判断いただけますのでご安心ください。
お子さまが自らの力で未来を切り拓き、よりよい人生を歩めるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。