発達障害とメモの取り方|ADHD・ASDの人が苦手を克服するためのコツと工夫
- 発達障害の方がメモを取るのが難しい理由とその背景
- 発達障害の方がメモを取るときのコツや工夫方法
- メモを取るのが苦手な方への配慮方法
人の話を聞くときに、必ずメモを取るようにしている方は多いのではないでしょうか。
一方で、発達障害の方の場合はメモを取るのが苦手なことが多く、「後から見返すと意味が分からない」「メモを取るのに一杯一杯になり、話が頭に入らない」「メモした紙を失くしてしまう」といった悩みをお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。
実は、メモを取るという作業にはとても高度な脳の働きが必要です。
メモを取るときには、「話を聞きながら」「内容を整理し」「手を動かして文字を書く」というマルチタスクが必要であり、脳の機能の凹凸が大きい発達障害の方にとっては非常に難しいものになります。
とはいえ、メモを取らなければ言われたことを忘れてしまいますし、メモを取ること自体が話を聞くときのマナーのようになっている場面も多いため、メモを取ることは社会人として最低限のスキルとも言えます。
私は、発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として長年にわたり活動してきました。
これまで1500人以上のお子さまをサポートしてきましたが、お子さまの中にも「メモを取ること」に苦戦している方はたくさんいらっしゃいました。
お子さまの場合、大人に比べるとメモを取る機会は少ないものの、口頭だけの指示や板書以外の情報などは自分なりにメモを取ることが求められます。
メモを取るにはコツがいる一方、「慣れ」も非常に重要ですので、子どもの頃から意識的にメモを取る練習をしておくことも大切です。
この記事では、発達障害の方の困りごとが少しでも小さくなるよう、メモを取るときのコツやポイントを紹介していきます。
発達障害ご本人の方だけでなく、発達障害のお子さまをお持ちの保護者さまや支援者の方にも役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
この記事はこんな方におすすめ
- 発達障害を持つご本人
- 発達障害のお子さまをお持ちの保護者さま
- 発達障害のある方を支援している教育関係者や支援者
- メモを取る際に苦戦している方や、そのサポート方法を学びたい方
▼目次
- 1 発達障害がメモを取るのが苦手な理由
- 2 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選
- 2.1 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選①5W1Hを意識する
- 2.2 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選②きれいに書こうとしない
- 2.3 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選③メモは1冊にまとめる
- 2.4 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選④色ペンを使いすぎない
- 2.5 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑤伝言メモは書式を決める
- 2.6 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑥パターンを覚える
- 2.7 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑦ボイスメモを使う
- 2.8 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑧写真で撮っておく
- 2.9 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑨スマホやPCでメモする
- 2.10 発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑩文書で説明してもらう
- 3 発達障害の人のメモの取り方のまとめ
発達障害がメモを取るのが苦手な理由

発達障害の人がメモを取るのが苦手な理由は、実は一つだけではありません。
発達障害と一口に言っても持っている特性は人それぞれであり、そこから生じる困りごとも人によって異なります。そのため、メモを取るときのコツや工夫を考える際には、「自分にはどんな特性があるのか」「その特性がどのように影響しているのか」を理解することが大切です。
この章では、発達障害の特性と、なぜメモを取ることが苦手になるのかについて詳しく解説していきますので、ぜひご参考にしていただければと思います。
※メモを取るときの具体的なコツが知りたいという方は、「2.発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選」までお進みください。
発達障害がメモを取るのが苦手な理由①ADHDの場合
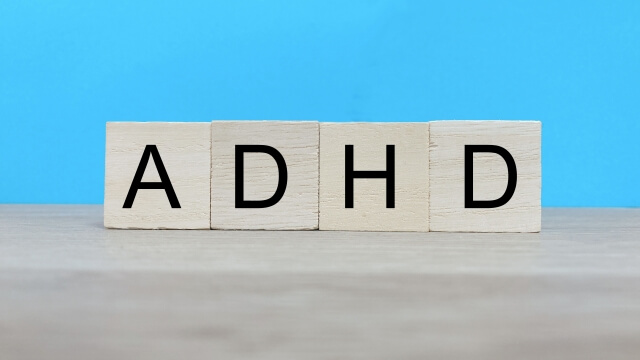
ADHD(注意欠如・多動症)の方の場合、「メモを後から見返してみると、自分でも何を書いてあるのかわからない」「メモしたこと自体を忘れる」「メモした紙を失くす」といった困りごとを抱えるケースが多くなっています。
これらの困りごとは、ADHDの方の特性である「不注意」や「多動性・衝動性」が原因になっていると考えられます。
- 不注意
- 一つの物事に集中し続けるのが難しく、注意散漫である。
- 多動性・衝動性
- 落ち着きが無くじっとしているのが苦手で、衝動的に行動してしまう。
これらの特性からADHDの方が抱えやすい困りごととしては、「整理整頓が苦手」「忘れ物や失くし物が多い」などが挙げられます。
メモしたこと自体を忘れたり、メモした紙を失くしてしまったりするのも、これらの特性が原因となります。
実は、メモを取るときの脳の働きと、物を整理整頓するときの脳の働きは非常によく似ています。
メモを取るということは、耳から入ってきた様々な情報を、全体を把握しながら要領よく整理し、メモという形に収納していく行為ですので、“メモを取る=情報を整理整頓する”と言い換えることもできます。
したがって、実際の物体を整理整頓するのが苦手なADHDの人が、耳から入ってくる情報を整理する(=メモを取る)ことを難しく感じるのは当然とも言えます。
また、ADHDの方が、「メモは取ったけれど、後から見返すと何が書いてあるのかわからない」という状況によくなってしまうのは、情報を整理するのが苦手で、聞こえてきた言葉を整理せずただ書いているだけになっていることが原因と考えられます。
発達障害がメモを取るのが苦手な理由②ASDの場合

ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)の方の場合、「必要な情報がメモできていない」「メモをするタイミングがわからない」という悩みを持つことが多い傾向にあります。
これは、ASDの特性である「コミュニケーションの困難」や「限定された興味・こだわり」が影響していると考えられます。
- コミュニケーションの困難
- 表情などから他人の感情を読み取るのが苦手で、言外のニュアンスなどが通じにくい。
- 限定された興味・こだわり
- 特定の物事や自分なりのルールに強いこだわりを持ち、融通が利かなかったり、イレギュラーな出来事を忌避したりする。
ASDの方は、相手の表情やその場の雰囲気から物事を察するのが苦手です。
そのため、相手の話の中で「重要な点とそうでない点」の区別が付きにくく、重要でないこともメモしようとしているうちに、重要なことを聞き逃してしまうなどのケースが考えられます。
また、相手がどのような意図で発言しているのかを理解するのも苦手で、電話の応対や引継ぎのメモなどでミスやトラブルを招いてしまうこともあります。
例えば、「○○さんはいらっしゃいますか?」と電話口で聞かれたとき、ただ居るかどうかを答えるだけでなく、
という判断が必要になります。
「○○さんはいらっしゃいますか?」という問いからは、これらの対応が必要になるとあらかじめ予想が付くからこそ、私たちはメモの準備をしたり、相手の予定を確認したりすることができます。
ASDの方は、こういった文脈の把握や「心の理論」の理解が苦手なため、とっさにメモを用意したり、必要な情報を確認・伝達するのが難しくなってしまいます。
発達障害がメモを取るのが苦手な理由③LDの場合
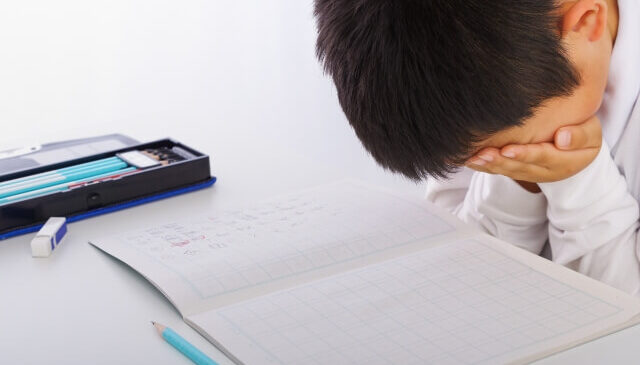
LDとは、知的な遅れや視覚・聴覚に問題が無いものの、読む・書く・計算するといった特定の技能に困難がある発達障害のことです。
このうち、読むことや書くことに困難があるタイプの方は、メモを取ることに困難を抱えやすくなります。(読みの困難のことを「読字障害/ディスレクシア」、書きの困難のことを「書字障害/ディスグラフィア」と言います。)
読みや書きに困難のある方は、文字と音を結びつける脳の機能(=音韻処理)が弱く、音として認識した情報を文字に変換することが苦手です。そのため、メモを取るのに時間が掛かってしまうなどの困りごとが生じます。
手書きでメモを取るのに時間が掛かる場合は、キーボードを利用したり、スマホのボイスメモを活用したりと、ツールの使用を積極的に検討すると良いでしょう。
発達障害がメモを取るのが苦手な理由④聴覚情報の処理不全
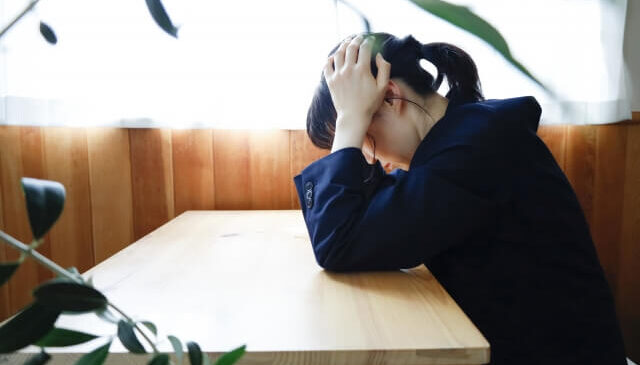
ADHD・ASD・LDに関わらず、発達障害の方は耳から聞いた情報を処理するのが苦手な傾向にあります。
そのため、口頭で説明されるよりも文章で説明した方がわかりやすかったり、テレビも字幕付きで見ている方がわかりやすいという方がいらっしゃったりします。
また、聴覚からの情報を処理するのが苦手なため、ザワザワした環境で話を聞くことも苦手です。
いろいろな音の中から必要な音だけを聞き取ることが難しいため、説明を受ける時などはできるだけ静かな環境を整えてもらうようにしましょう。
メモを取ることに限らず、学習全般のお悩みもお気軽にご相談ください。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選

発達障害でメモを取るのが苦手な方でも、コツを掴んだり、様々な工夫を行ったりすることで困りごとを軽減することができます。
持っている特性によって効果のある工夫やコツも違ってきますので、自分の特性をしっかりと見極めることが大切です。
この章では、発達障害の方がメモを取るときのコツや工夫について順に解説していきます。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選①5W1Hを意識する
メモを取るときの一つ目のコツは、「5W1H」を意識することです。「5W1H」とは、
- ① When(いつ)
- ② Where(どこで)
- ③ Who(だれが)
- ④ What(何を)
- ⑤ Why(なぜ)
- ⑥ How(どのように)
のことで、情報を伝達する際のポイントを端的に表しています。
発達障害の方がメモを取るときには、この5W1Hを意識するようにしましょう。
とはいえ、6つの点を全て意識しなければならないわけではありません。
電話の取次ぎであれば「③Who(誰が)」が一番重要ですし、作業の手順であれば「④What(何を)」「⑥How(どのように)」がポイントになるでしょう。
6つを全て均等に意識するのではなく、その時々によって重要な項目が違ってくるということを理解し、状況に応じて「今はWhoに注目しよう」など、5W1Hを元に何が大切な項目なのかを判断していくことが大切です。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選②きれいに書こうとしない
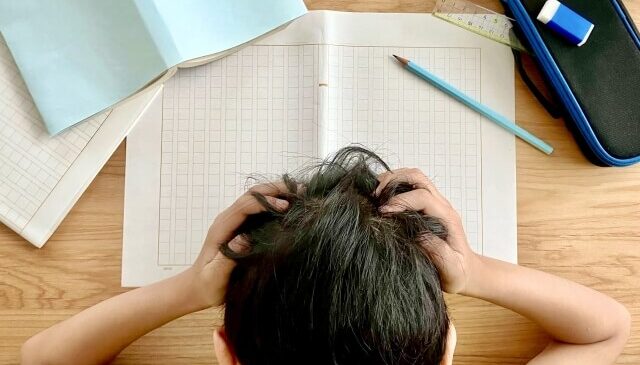
発達障害の方は、「きれいに書くこと」にこだわり過ぎてメモを取るスピードが追い付かない場合があります。
メモはあくまでメモですので、一字一句書き起こす必要はありませんし、漢字が思い出せなければ平仮名でも構いません。
後で読み返したときに読めないのが困るのであれば、一旦は大雑把にメモし、話がひと通り終わってから清書すると良いでしょう。
メモで助詞の省略ができない方も意外と多くいらっしゃいます。
「3時に駅前に集合する」という内容をメモするには、「3時 駅前 集合」とだけ書けばよく、“に”は省略して構わないのですが、そのことが分からず一字一句書いてしまうパターンです。
慣れの問題もありますので、助詞を省略した文章を敢えて書いてみるなどして、省略のコツをつかむのも良いでしょう。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選③メモは1冊にまとめる
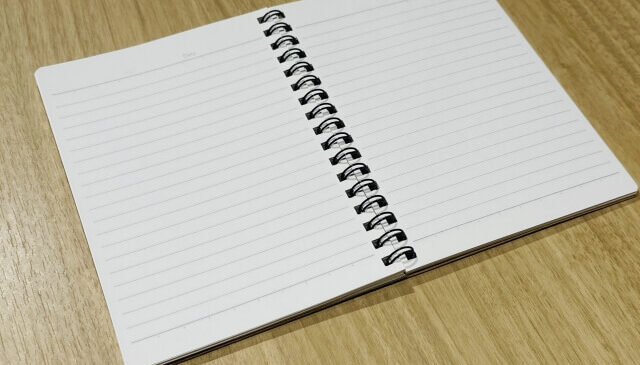
ADHDの方で非常に多いのが、書いたメモを失くしてしまうか、どこに書いたか分からなくなってしまうパターンです。
これを防ぐために、紙切れに書くのではなく、1冊のノートや手帳にメモすることを徹底しましょう。
ノートのどこに書いたのか分からなくなってしまう場合は、ノートのタイトル行に日付と概要を書いておくようにしましょう。
「○年○月○日 銀行の支払い」と書いておくだけで、かなり情報にアクセスしやすくなります。また、一つのページに複数の情報を書くのではなく、1ページにつき1つの内容だけを書き込むようにしましょう。
紙媒体の管理が苦手な人や、かさばるのが嫌な人は、スマホのメモアプリを使うのも良いでしょう。リマインダーと連携できるタイプもあるため、上手く活用できるとスケジュール管理にも役立ちます。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選④色ペンを使いすぎない

発達障害の方は、基本的に複数の情報を同時に処理することが苦手です。ですので、色ペンを使い分けながらメモを取ることはできるだけ避けましょう。
色ペンを複数使うと「どの色にしようかな」という判断が必要になるため、脳のキャパシティを圧迫してしまいます。
基本的には黒一色だけ、どうしても必要なときだけ赤を使うなど、色ペンの使用は最低限に留めましょう。色ペンを使わなくても、○や☆を付けるなどして目立たせることは十分可能です。
なお、メモを取りながら色を使い分けるのではなく、後から見直す際に蛍光ペンなどで色付けするのは問題ありません。
どうしても色を使い分けたい場合は、メモを取りながらではなく、後から装飾するようにしましょう。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑤伝言メモは書式を決める

電話の応対などで伝言メモを作る場合は、書式を決めておきましょう。
- 【日時】
- ○月○日○時○分
- 【誰から】
- (所属)○○株式会社 (名前)○○さま
- 【誰あて】
- (所属)○○部○○課 (名前)○○さま
- 【必要な対応】
- ・折り返しが必要 → 電話番号(xx-xxxx-xxxx)
- ・掛け直してもらえる → ○時○分ごろ
- ・伝言がある → 内容
- 【誰が応対したか】
- ・自分の名前
インターネットで「電話 伝言メモ」と検索すると、テンプレートを見つけることができます。
自分が使いやすいテンプレートを見つけ、電話の傍に常備しておくと良いでしょう。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑥パターンを覚える

発達障害の方は、その時々に応じて臨機応変に対応するのが苦手な傾向にあります。
特に、イレギュラーな出来事が起こったり、複数のタスクが重なったりすると、パニックに近い状態になることも少なくありません。
ただし、発達障害の人が「イレギュラーな出来事」であると捉えていることでも、実は一般化できるケースがあります。
例えば、知らない人から電話が掛かってきた場合、「知らない人=イレギュラーである」と捉えるのではなく、「株式会社を名乗っている→取引先である可能性が高い→他の取引先と同様の対応をする(=イレギュラーではない)」といったケースです。
知っている人であれ知らない人であれ、取引先としての対応は変わりません。
発達障害の人はこうした「抽象化・一般化」が苦手なことが多いため、「外線電話が掛かってきたら相手の名前をまず確認する」など、パターンとして覚えてしまうのが良いでしょう。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑦ボイスメモを使う
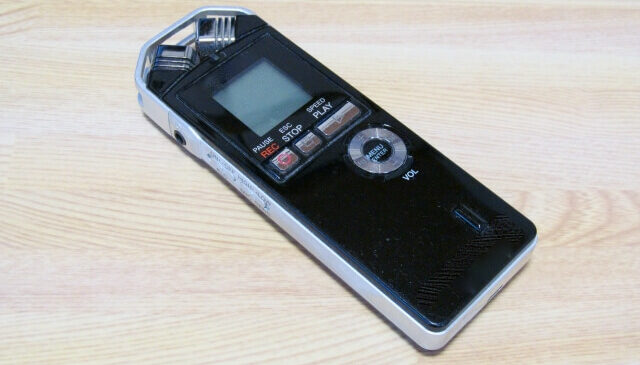
発達障害の方は、ワーキングメモリー(情報を一時的に保持しながら処理する能力)が低く、「聞きながら書く」というマルチタスクがそもそも苦手な場合があります。
そういった方は、手書きのメモにこだわらず、ボイスメモなどのツールを活用すると良いでしょう。
最近では、スマホの機能としてボイスメモが入っている場合も多いため、ICレコーダーをわざわざ用意しなくてよい点もメリットです。「あとで聞き返すために録音させてください」と伝えるのも良いですし、伝えづらい場合はポケットにスマホを入れて録音しておく形でも問題ありません。
ただし、個人情報や企業機密などが含まれる内容を録音する場合は、データの取扱いに注意しましょう。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑧写真で撮っておく

会議で使ったホワイトボードや授業の板書の内容は、スマホで撮影しておくのも一つの方法です。
メモを取ろうとすると「話を聞きながら」「前に書かれた内容を見て」「手元のメモに書き写す」という3つのタスクが重なるため、発達障害の人にとって難しいだけでなく、定型発達の人にとっても話を聞き漏らす原因となっている可能性があります。
会議のルールとして「書かれた内容は後ほどデータで共有するため、書き写しは不要」という形にできれば、参加者全員にとってメリットがあります。組織の雰囲気によっては言い出すのが難しい場合もありますが、一度提案してみる価値はあります。
また、自分から率先してホワイトボードや黒板の内容を消しに行き、「写しきれていない人のために写真で撮りますね」と言ってみるのも良いかもしれません。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑨スマホやPCでメモする

発達障害の方の中には、手先が極端に不器用なため文字が書きづらく、メモを取るのが難しいという方がいらっしゃいます。
特に、LD(学習障害)のうち書字障害の方に多く見られる症状ですが、ADHDやASDといった他の発達障害の方でも、こういった特性を持っている方がいらっしゃいます。
手先の極端な不器用さや運動能力の低さは、「発達性協調運動障害」と呼ばれ、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の「五感」と、自分の身体に対する感覚である「固有感覚」、身体の傾きやスピード・回転に対する感覚である「前庭感覚」が上手く連携しないことが原因となっています。
幼少期からの療育によって症状を軽減することはできますが、改善には時間を要します。
発達性協調運動障害によってメモを取るのが難しくなっている場合は、手書きにこだわらず、スマホのフリック入力やPCのキーボード入力など、自分が扱いやすいツールでメモを取ることも検討しましょう。
発達障害の人のメモの取り方のコツ・工夫10選⑩文書で説明してもらう
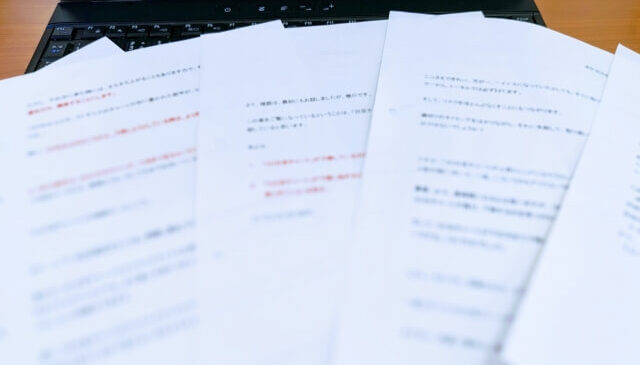
説明する人がメモを見ながら話して、さらに聞き手がメモを取るというのは、ある意味では非効率と言えます。メモをそのまま渡してもらった方が、メモを取る手間が省略できますし、聞き漏らしを防ぐこともできます。
「自分でメモを取った方が頭に入りやすい」と主張する人もいますが、知識の定着しやすさは人それぞれ違いますし、マルチタスクが苦手な発達障害の方にとっては、多くの場合、自分でメモを取ることは知識の定着につながりません。
伝達事項はメールやチャットなど文章で伝えてもらえるよう、周囲にもできる限りの配慮を求めましょう。
適切な配慮を行うことは周りの人の義務(※)でもありますし、「言った/言わない」のトラブルを避けるためにも、文書による伝達には大きなメリットがあります。
豊富な経験を持つプロの講師が、お子さまの特性を細かく分析し、それぞれに合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成。受験対策から日々の学習サポートまで、お子さまのペースに寄り添い丁寧にサポートいたします。
メモを取ることに限らず、学習に関するお悩みがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
発達障害の人のメモの取り方のまとめ
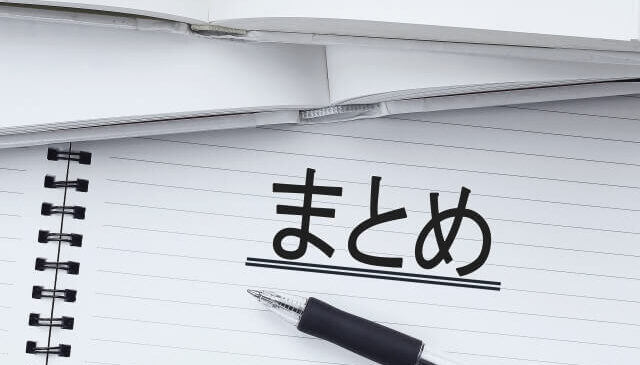
この記事では、発達障害の方がメモの取るときのコツや工夫について詳しく説明してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 発達障害の人がメモを取るのが苦手な理由は様々であり、自分の特性がどのように影響しているのかを見極めることが重要
- ADHDの場合は、情報を整理するのが苦手で、後から見返したときにメモの内容がわかりづらかったり、メモ自体を失くしてしまったりすることがある
- ASDの場合は、話のポイントがどこかわからなかったり、メモすべきかどうかを判断するのが苦手な傾向にある
- LDの場合は、書くことが苦手でメモを取るのに時間が掛かってしまうことがある
- 人の話を聞く時は、5W1Hのうち何が重要かを意識する
- ボイスメモを使ったり、黒板の内容を撮影したりするなど、ツールを活用するのも効果的
- 口頭での説明ではなく、チャットやメールで伝えてもらうよう配慮を求めることも必要
メモを取るという行為は、「話を聞きながら要約して、文字で記録する」というとても高度なマルチタスクです。
そのため、発達障害の方は苦手を感じやすいのですが、要点に集中したり、自分なりのテンプレートを作ったりすることで、苦手を軽減することができます。
メモを取るスキルが身に付けられると、仕事や勉強の効率も大きく向上しますので、少しずつコツを掴んでいただきたいと思います。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり多くの発達障害のお子さまを支援してきました。受験の指導だけでなく、勉強のやり方から生活上の困りごとまで、幅広くサポートを行っています。
発達障害のお子さまのことでお悩みの方は、ぜひプロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
また、指導や面談はオンラインでも承っています。遠方にお住まいの方や海外在住の方、帰国子女の方からもこれまでご利用いただき、たくさんのご好評の声をいただいてきました。
初回授業や初回ご相談は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか不安なお子さまでもお気軽にお試しいただけます。
1人でも多くのお子さまが、自分らしく社会で活躍できるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。




