無気力型不登校とは?原因と対応方法をプロ家庭教師が解説
不登校は、原因や背景の違いから7つのタイプに分類され、その中でも特に対応が難しいのが「無気力型」の不登校であると言われています。
無気力型不登校の大きな特徴は、「本人の罪悪感が少ないこと」と「原因が特定できないこと」の2つです。
特に「原因が特定できないこと」については、原因が分からないゆえに周りもどのようにアプローチして良いか分からず、結果として見守るだけになってしまうことも多いです。
ですが、無気力型不登校において見守るだけの対応を取ってしまうと、長期化してしまうケースが多く、原因が分からないこそ早めに対応策を考え、適切にアプローチすることが大切です。
この記事では、無気力型不登校の具体的な対応策について、不登校専門のプロ家庭教師ならではの視点で詳しく解説していきます。
保護者さまや学校の先生の参考になる内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
▼目次
不登校の7タイプと無気力型について

この章では、不登校の7タイプについてそれぞれの概要を解説していきます。無気力型不登校について詳しく知りたい方は、「2.無気力型不登校の特徴3つ」までお進みください。
不登校の7つのタイプとは、以下のとおりです。
1.分離不安型
2.人間関係型
3.息切れ型
4.無気力型
5.甘え型
6.ストレス型
7.発達特性型
※この7タイプは、特定非営利活動法人教育研究所の監修のもと、キズキ家学が作成したものを参考にしています。
それぞれについて、以下で順に解説していきます。
不登校の7タイプ①分離不安型
母親から離れることや学校生活に不安や恐怖を感じやすいタイプで、小学校低学年に多いケースです。
- 一人になることや集団の中に入ることに強い不安や恐怖を感じ、行動できないことがある。
- 自分がうまくできないことで周囲から見捨てられることへの不安がある。
- 同世代と比べて自信を持つことができない。劣等感を抱いている。
不登校の7タイプ②人間関係型
友達や教師などの人間関係によるトラブルや環境に馴染めないなど、人間関係に問題を抱えているタイプです。
- 嫌がらせやいじめを受けていたり、友達や教師とのトラブルがあったり、クラスに馴染めなかったりするなど、人間関係に問題を抱えている。
- 自分で解決できないほど大きな問題を抱えているため、登校できなくなる。
- ストレスが積み重なっていくと体調を崩し、頭痛や腹痛などの症状を訴えることがある。
不登校の7タイプ③息切れ型
勉強やスポーツなどで周囲の期待に応えようとしてきた結果、息切れを起こして気分の落ち込みや身体症状が現れるタイプです。
- 不登校前は優秀で、「真面目」「几帳面」「向上心が強い」など完璧思考で自分に厳しい傾向がある。
- 登校できないことに罪悪感が強く、自分を責める気持ちが強い。
- 自分の失敗を受け止めることができず、問題を隠したり、原因を外的要因に求めたりする場合もある。
不登校の7タイプ④無気力型
「登校しなければならない」という気持ちがほとんどなく、何事にも無気力である場合が多いタイプです。
- 心因性の身体症状がほとんど現れない。
- 家ではゲームや動画など、自分の好きなことをしてだらだら過ごしている。
- 強く催促すると登校できることもあるが、長続きしない。
不登校の7タイプ⑤甘え型
精神的に幼く、年齢相応の適度な負荷を我慢する力や、「自分で何とかする」という自立の意識が十分に育っていないタイプです。
- 年齢よりも考え方が幼く、我慢したり、自立したりしようとする意識が低い。
- 逃げ癖(=嫌なことや出来ないことがあると、立ち向かわずに逃げる)傾向があり、物事を最後までやり遂げた経験がほとんどない。
- 落ち込んでいることもあるが、好きなことや楽しいことは自ら積極的にする。
不登校の7タイプ⑥ストレス型
ストレスを感じやすく、神経症性の症状(頭痛・腹痛・吐き気・発熱等の身体症状や強迫観念など)を伴うタイプです。
- こだわりが強く、自分の世界にひきこもりがちである。
- ストレスによる身体症状のほか、不安障害(強迫観念)や摂食障害、自傷行為を伴うことがある。また、精神疾患の初期症状である場合もある。
- ストレスを感じやすい性質があり、その他の精神疾患のリスクも高いことから、専門医への受診が推奨される。
不登校の7タイプ⑦発達特性型
不登校の原因に発達障害などの特性が大きく関わっているタイプです。不登校がきっかけで気づくことも多いです。
また、②人間関係型や⑥ストレス型の背景に、発達障害の特性が関わっていることもあります。
- できないことや苦手なことを注意されたり、叱責されたりすることが多く、自信を失くしている。
- コミュニケーションが上手く取れず、クラスで孤立している(→1-2.不登校の7タイプ②人間関係型)。
- 勉強が極端に不得意で、苦手意識が強い。
- 怒りや不安などの感情をうまく処理できず、パニックや癇癪を起こすことがある。
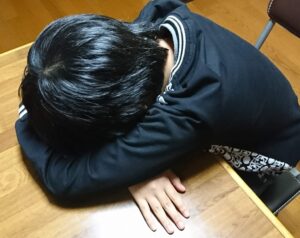
無気力型不登校の3つの特徴

無気力型不登校の特徴は、「1-4.不登校の7タイプ④無気力型」でも触れたとおり、「登校しなければならない」という気持ちがほとんどなく、何事にも無気力であるという点が挙げられます。
登校できないことへの罪悪感が少ないため、ストレスによる心因性の身体症状が現れることは稀です。
また、他の不登校のタイプに比べると、はっきりとした原因が分かりづらく、アプローチの方法が見出しにくいという困難さがあります。
この章では、無気力型不登校の特徴について、以下の3つの観点からさらに詳しく解説していきます。
1.登校できないことへの罪悪感が少ない
2.何事にも無気力で面倒くさがる
3.原因がはっきりとしない
無気力型不登校の3つの特徴①登校できないことへの罪悪感が少ない
無気力型不登校のお子さまは、何事に対しても興味や関心が持てないという心の状態に陥っています。
そのため、登校できていない現状に対して心が動くことがほとんど無く、焦りや罪悪感を持つことも少ないです。
ストレスも比較的少なく、心因性の身体症状(頭痛・腹痛・吐き気など)が生じることは稀です。
また、学校に対して明らかな苦手意識や拒否感があるわけではないため、友だちから誘われれば登校したり、学校行事だけ参加したりすることはできる場合があります。
ただし、自ら積極的に学校に行こうとしているのではないため長続きせず、段々と気力が無くなって元通りになってしまうケースがほとんどです。
無気力型不登校の3つの特徴②何事にも無気力で面倒くさがる

「何事にも無気力で面倒くさがる」のは、無気力型不登校の大きな特徴の一つです。
他のタイプの不登校のお子さまの場合、保護者さまに極端に甘えたり、イライラをぶつけたり、癇癪を起こしたりといった特徴が見られますが、無気力型のお子さまの場合、こうした行動を起こすことは稀です。
無気力型不登校のお子さまは、一見すると気分的には安定しているように見えますが、一方で「面倒くさい」「だるい」と口に出すことが多く、何かに積極的に取り組むことがありません。
スマホやゲームなどを楽しんでいるように見えても、惰性でだらだらと触っているだけで、本人が積極的に「○○したい」と思っていない点が大きな特徴となります。
スマホやゲームを惰性で触ってるのか、それとも積極的に楽しめているのかは判断に迷うところですが、例えば一緒にゲームで遊んでみたり、話題に出してみたりして、お子さまが積極的に楽しんでいるかどうかを確認するなどの方法があります。
無気力型不登校の3つの特徴③原因がはっきりとしない
原因がはっきりとしないことも、無気力型不登校の特徴の一つです。
人間関係でトラブルがあったり、勉強についていけなかったりといった明確な理由やきっかけがなく、ただ何となく面倒臭かったり、気分が乗らなかったりというのが無気力型不登校の特徴です。
また、不登校になる前からサボり癖があったり、主体性が無かったりするわけではありません。
不登校になる前はクラスメイトともほどほどに付き合い、勉強もそれなりにできていた子でも、急に「面倒くさい」という無気力感から学校に通えなくなることもあります。
周りからは単にサボっているだけと見られやすく、保護者さまとしては周りの目が気になることもあるかもしれません。
ですが、一見明確な理由が無いように思われる無気力型不登校にも、必ず原因はあります。
お子さまがなぜ「面倒くさい」という気分に陥ってしまうのかを分析し理解することが、無気力型不登校の解決への第一歩となります。
次章では、この「面倒くさい」の背景に何があるのかについて、詳しく解説していきます。

無気力型不登校の原因|「面倒くさい」の背景とは

無気力型不登校のお子さまは、「面倒くさい」「だるい」とよく口にします。
「面倒くさいって何?怠けてるだけ?」と理解に苦しんでしまいますが、実は、この「面倒くさい」という言葉には様々なメッセージが隠れています。
「面倒くさい」の背景にあるお子さまの気持ちをよく分析することで、解決が難しいとされている無気力型不登校でも、改善に向けた一歩を踏み出すことが可能になります。
以下では、面倒くさいという言葉の裏側にあるメッセージについて、詳しく解説していきます。
無気力型不登校の原因①悩みを言語化できていない
本当はいろいろな思いや悩みがあるけれど、上手く言葉にできず、「面倒くさい」という言葉になってしまっているケースがあります。
心の中にモヤモヤした気持ちがあるとき、それを上手く言葉にして相手に伝えるのは大人であってもなかなか難しいものです。
お子さまは言葉にして伝える力(言語化力)が未発達なので、なおさら「面倒くさい」という言葉でしか伝えられないことがあります。
ですので、何が面倒くさくて何がだるいのか、一つずつ聞き取っていくことが大切です。
また、学校では様々な理不尽に直面することがあります。
- 計算ができる子もできない子も、同じだけ練習問題を解かなければならない。
- 授業中に隣の子が質問をした。自分も気になっていたことだったので答えを聞きたかったのに、先生は「今は関係無いでしょ」と一蹴した。
- クラスメイトのAくんはみんなによく揶揄われている。いじめじゃないかなと思ったけれど、止めることができなかった。
一つ一つの出来事は大したことではないかもしれませんが、こうした小さな違和感や辛さ、しんどさが蓄積し、ぼんやりとした行きづらさにつながることは多いです。
このぼんやりとした行きづらさが言葉では上手く表現できず、「面倒くさい」という言葉となって表われる場合があります。
無気力型不登校の原因②大人を信用できていない

お子さまが相手を信用できておらず、悩みを打ち明けても無駄だと思っているため、「面倒くさい」という言葉を使っているケースもあります。
このようなケースにおいては、不登校の状態になる前に何らかのサインが発されていたものの、その際に適切な対応が取られなかったために、お子さまが心を閉ざしてしまった可能性があります。
例えば、お子さまが「明日の部活、しんどいなあ」とふと漏らしたときに、「自分でやりたいと言ったんでしょ」と返すようなケースです。
もちろん、このやり取り自体はごく普通のものであり、たった1回で信頼が崩れてしまうものではありません。
ですが、お子さまが本当にしんどいと感じていて、「たまには休みたいな」もしくは「頑張っていることをお母さん/お父さんに認めてもらいたいな」と思っているタイミングで淡々とした答えが返ってくると、お子さまは大きなショックを受けることがあります。
他にも、将来の進路について相談したときに、あまりお子さまの意見を聞かなかったり、逆に「好きにすれば良いんじゃない」と関心が無いように聞こえる答えをしてしまったりすると、「この人に打ち明けても意味が無い」と感じてしまうことがあります。
特に中学生のお子さまは、自立したいという気持ちと、まだ甘えたいという気持ちがちょうどせめぎ合っている段階にあります。
そのため、ちょっとした会話の積み重ねが、大人を信頼できない気持ちにつながることもあります。
対応が非常に難しいところではありますが、お子さまの表情や様子をよく見て、日頃から丁寧に対応するよう心掛けることが大切です。
無気力型不登校の原因③何をやっても無駄だと思っている
本当に何もかもにやる気が起きず、面倒くさいという状態に陥っているケースもあります。
お子さまがやる気を失ってしまう原因として最もよくあるのが「自己効力感の低下」です。
自己効力感とは、自分はやればできるという実感のことであり、自己効力感があることで、人間は物事に積極的に取り組むことができるようになります。
逆に、自己効力感が乏しいと「何をやっても無駄だ」という感覚になり、やる気が湧いてきません。
お子さまの場合、以下のような出来事がきっかけとなり、自己効力感が低下してしまうことがあります。
- 勉強しても成績が上がらない
- 学校に行く意味を見出せない(楽しみや成長を感じられない)
- 自分で自分の人生をコントロールしている実感が持てない
- (家庭環境などにより)明るい将来を描けない
これらの要因を取り除くことにより、お子さまの自己効力感を取り戻し、やる気を引き出すことが無気力感の解消につながります。
学力不振であればお子さまの性質に合わせた学習支援が、学校に行く意味を見出せない場合は認知の偏りにアプローチできるカウンセリングなどが効果的です。
自己効力感が低下している要因は複数にまたがることもありますが、丁寧に分析し、一つずつ着実にアプローチしていくことが大切です。

無気力型不登校の4つの段階

一般的に、不登校は「前駆期」「進行期」「混乱期」「回復期」の4つの段階を経て回復していきます。
この章では、無気力型不登校がどのようなステップで回復していくのか、具体的に解説していきます。
無気力型不登校の4つの段階①前駆期
無気力型不登校の前駆期では、以下のような特徴が見られます。
- 「面倒くさい」「だるい」とよく言うようになる。
- 何事にもやる気が起きず、やや元気が無い。
- 学校を休みたいと訴えるが、はっきりとした理由が無い。
- 友だちが誘うと登校でき、先生の電話や訪問には応じる。
- 「登校しなさい」と強く言わなければ、気分は比較的安定している。
- 学校を休んだ日は、スマホやゲームを触りながらだらだらしている。
無気力型不登校の前駆期では、お子さま自身も自分の無気力感に戸惑いを覚えています。
自分の気持ちを言語化できる段階ではないため、原因を根掘り葉掘り聞き出すことは避けましょう。
無気力感が強い中でも、本人が関心を持ちやすい話題(ゲームやYouTubeなどに関することで構いません)をきっかけに、お子さまが心を開きやすい関係性を築いていくことが重要です。
お子さまの心がある程度ほぐれてきたら、無気力感の背景にどんなものがあるのか、一緒に考えていきます(例:どんなことが面倒くさいと感じるのかな?)。
お子さまが上手く答えられない場合は決して追求せず、「言葉にするのは難しいよね。お母さん(お父さん、先生)も一緒に考えてみるね」と寄り添う姿勢を示すことが大切です。
また、ついつい大人としてアドバイスしたくなることもあるかもしれませんが、考えを押し付けられるようで嫌だと感じるお子さまも多いです。
なので、大人目線のアドバイスではなく、若いころの失敗談や悩みなどを話し、「お母さん(お父さん、先生)も自分と同じなんだな」とお子さまが思い、より心を開きやすくなるように接することが大切です。
無気力型不登校の4つの段階②進行期

無気力型不登校の進行期では、以下のような特徴が見られます。
- 学校に行かなくなる。「行かない」と宣言し、強固な姿勢を見せることもある。
- 生活のリズムが崩れ、昼夜逆転する。
- 家族との会話が少なくなり、表情も暗くなる。
- クラスメイトや先生とも顔を合わせたがらなくなる。
無気力型不登校の進行期は、「無気力であること」が本人にも強く自覚され、自分の考えであるとして強く主張するようになります。
すなわち、「学校に行くことには意味が無い」という結論に達し、どんな言葉を掛けられても考えを曲げないかのように振る舞います。
ですが、ここで周りの大人が強い声掛けをしてしまうと、ますます自分の考えにこだわってしまうため、注意が必要です。
一方で、「勝手にしなさい」というように突き放してしまうのも禁物です。
お子さまは強硬な態度を取りつつも、内心では「このままではいけない」と気付いており、人生の行き詰まり感まで感じていることがあります。
「勝手にしなさい」と突き放すと、誰も助けてくれないのだという絶望感につながり、不登校からひきこもりへと長期化してしまう可能性が非常に高くなります。
ですので、進行期になりお子さまの態度が硬化したとしても、背景には「言葉にできない無気力感がある」ということを忘れず、そのサポートに努めるようにしましょう。
具体的には、「○○しなさい」「○○したら?」など指示するような声掛けは避け、学校の話題に触れることも避けましょう。
本人が話しやすい話題を見つけ、まずは普通の会話ができるように関係性を構築し直すことが非常に重要です。
また、もしお子さまが本心を話してくれる機会があれば、内容や口調はどうであっても、まずは必ず共感するようにしましょう。
「そんな風に思っていたんだね」「話してくれてありがとう、嬉しいよ」「一緒に考えるからね」といった声掛けをし、お子さまの心に寄り添う姿勢を見せていただければと思います。
無気力型不登校の4つの段階③混乱期
無気力型不登校の混乱期では、以下のような特徴が見られます。
- 家族との会話が戻り始め、表情が少し明るくなる。
- 進級や進学のことを気にするようになり、自分から学校の話題に触れることがある。
- 自分なりに転編入や進学、就職について調べることもある。
- 「一人暮らしがしたい」「アルバイトしてみたい」など独立心を見せることがある。
混乱期では、強硬な態度が落ち着き始め、状況を改善しようとする前向きな意欲が現れ始めます。
ですが、この時に周りが過度に後押ししてしまうと、ようやく見え始めていた意欲を削いでしまうことがあるため注意が必要です。
混乱期においても、先回りして「○○したら?」と言うことは避け、本人の意思を確認しながら一緒に考えるという姿勢を維持しましょう。
本人の意向は非現実的なものも含まれているかもしれませんが、頭ごなしに否定せず、
「そういう風に考えているんだね、話してくれてありがとう。この案だと○○の部分が難しそうだけど、ほかの方法が無いか一緒に考えよう」
といったように、寄り添う姿勢で対応していただければと思います。
無気力型不登校の4つの段階④回復期

無気力型不登校の回復期では、以下のような特徴が見られます。
- 無気力感が解消され、心から前向きに物事に取り組めるようになる。
- 自分の考えを冷静に家族や先生に話せるようになる。
- 自分の決めた進路で、自分の決めた学び方ができるようになる。
回復期では、無気力感がほとんど解消され、自分の意志で生きていくという実感が持てるようになります。
不登校であった期間の長さによっては、通信制高校への進学や、高卒認定試験からの資格取得・就職など、必ずしも全日制高校→大学進学といった一般的な進路にはならないかもしれません。
ですが、お子さま自身が自分で決めた進路なのであれば、全力で応援してあげることが何よりも大切です。
お子さまの人生が幸せなものであるかどうかと、進路選択がメジャーなものであるかどうかは関係がありません。お子さまが悩んだ末に選び抜いた進路なのであれば、自信を持って送り出していただければと思います。
また、無気力感から回復したからといっても、まだまだ社会的に未熟な部分は多いです。必要に応じてサポートしつつも、口出しし過ぎないことを心掛けましょう。

無気力型不登校の特徴・原因・対応方法のまとめ

この記事では、無気力型不登校の特徴や原因、対応方法について詳しく解説してきました。改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 無気力型不登校は、学校生活全般や日々の生活にやりがいを感じられず不登校になってしまうタイプで、「面倒くさい」「だるい」とよく言うのが特徴。
- 無気力型不登校に明確な理由はないものの、自己効力感が低いことによる無気力感がベースにあることが多い。
- 不登校のステップには、「前駆期」「進行期」「休息期」「回復期」の4つがある。対応を誤ると長期化の恐れがあるため、それぞれのタイミングに合った対応をすることが大切。
- 無気力型不登校の対応のポイントは、根本的な原因である無気力感の解消に努めること。そのためには、子どもの本心を尊重し、「自分の人生は自分でコントロールできる」という自己効力感を育むことが大切。
不登校には色々なタイプがありますが、子どもならではの元気さや積極性が感じられなくなる「無気力型」は、明確な理由が見当たらず、不登校の中でも特に解決が難しいタイプであるとされています。
ですが、根本的な原因である無気力感の背景にあるものをきちんと分析し、一つ一つ対応していけば必ず解決できます。
また、初期にきちんと対応できれば、長期化を免れることも可能です。
お子さまがなぜ無気力感を持っているのかについて、日頃の会話や関わりをとおし、ご家庭や学校でも丁寧に分析していただければと思います。
一方で、不登校の問題をご家庭だけで解決するのは非常に困難です。
不登校の原因は複数の要因が複合的に重なっていることも多く、要因を一つずつ分析し、地道に解決していく必要がありますが、そのためには専門的な知見や経験を持った人のサポートが欠かせません。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり不登校のお子さまのサポートを行ってきました。
無気力型不登校においても、学力不振が原因の一つであるケースは多いです。
たくさん勉強しても成績が上がらないことが自己効力感の低下を招き、ひいては無気力感につながってしまうケースがあります。
そこで、プロ家庭教師メガジュンでは、お子さまのペースや性質に合わせた授業を行い、勉強に対する自己効力感を取り戻せるようアプローチを行います。
こうしたアプローチの結果、学校に復帰できたというお子さまはこれまでたくさんいらっしゃいます。
また、学習支援だけでなく、お子さまの性質に合わせたコミュニケーション支援など、幅広いサポートを承っています。
不登校に関する相談先が見つからずお困りの方や、お子さま一人ひとりに合わせたサポートを受けたいとお考えの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問合わせください。
また、授業や面談はオンラインでも承っています。全国各地からご利用いただけるほか、海外にお住まいの方や帰国子女の方にもこれまでご利用いただき、多数のご好評の声をいただいてきました。
初回の授業・面談は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか不安な方もお気軽にお問合せください。

一人でも多くのお子さまが、心身とも健やかに成長していけるよう一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。





