ADHDの子育てが楽になる!親ができる接し方・育て方の工夫
- ADHDのお子さまと上手に関わるための接し方のコツ
- 叱り方・褒め方のポイントと環境調整の工夫
- 家庭でできる育て方の工夫やサポート方法
- 保護者さま自身の心の負担を軽くする考え方
「注意しても聞いていないようで、どう接したらいいのか分からない…」
ADHD(注意欠如・多動症)のお子さまを育てる保護者さまの中には、日々の子育てに悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
ADHDの特性は「努力不足」や「しつけの問題」ではなく、お子さまの生まれ持った脳の働きによるものです。具体的には、以下のような特徴があります。
- 注意欠如(不注意):集中しづらく、忘れ物が多い
- 多動性:落ち着きがなく、じっとしていられない
- 衝動性:考える前に行動し、感情をコントロールしにくい
そのため、親が「もっと厳しくしつけよう」「言い聞かせよう」と考えてもうまくいかず、ストレスを感じてしまうこともあります。
本記事では、ADHDのお子さまとの関わり方について、具体的な接し方や育て方のポイントを解説します。日々の関わり方を工夫することで、お子さまの成長をサポートし、親子ともに穏やかな毎日を過ごせるようになるヒントをお伝えします。

・個別指導塾の経営・運営でお子さまの性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▶ご相談・お問合せはこちらから
▼目次
ADHD(注意欠如・多動症)のお子さまの子育て|6つのポイント

ADHDのお子さまは、特性上「努力が足りない」「わがまま」と誤解されることもあります。しかし、適切な関わり方をすることで、お子さまの良い部分を伸ばしながら、親子ともにストレスを減らすことができます。
ここでは、ADHDのお子さまを育てる上で大切な6つのポイントを解説します。
①とにかく褒める
ADHDのお子さまは、褒められる機会が他のお子さまと比べて少ない傾向にあります。
落ち着きが無かったり、集中力が無かったり、衝動的であったりと、行動の理由を周りに理解してもらえることが少なく、結果として怒られてしまう場合が圧倒的に多いでしょう。
そのため、ADHDのお子さまは、「褒められたい、認められたい」という欲求を持っていることが多いです。
こういった承認欲求が満たされない状況が続くと、大人の気を引くためにわざと反抗的な態度や反社会的な行動をとったり、精神的なストレスが溜まって不安障害や気分障害を発症してしまう場合があります。
ですので、ADHDのお子さまを褒めることは非常に重要です。
ただし、褒めるといっても、ただやみくもに根拠なく褒めるのでは意味がありません。
褒める際のポイントは以下のとおりであり、順に詳しく紹介していきます。
先に褒めて、改善点を後から伝える
例えば、お子さまが宿題の漢字ドリルを約束どおりできたとしましょう。
しかし、早くゲームがしたかったためか、字が雑だったり、正しくない書き順で書いてしまった部分があるようです。さてこの時、皆さんは次の①②のどちらの褒め方をしますか?
- ① ゲームより先に宿題ができて偉いね。次はもっと丁寧にできるとより良いね。
- ② ちょっと雑なところがあるけど、ゲームより先にできたのは偉いね。
より好ましい褒め方は①です。
まず良い点を先に伝えることで、お子さまは保護者さまの意見を受け入れる姿勢になります。
何もかも完璧にできることはほとんどありませんし、逆に言えば何もかも駄目なこともほとんどありません。
お子さまの行動一つ一つをできるだけ細かに分析し、良いところを見つけてまずは褒めることが大切です。
その次に改善してほしい点を伝えると、お子さまも保護者さまの言うことを素直に聞いてくれる場合が多いです。
一つずつ褒める
あれもこれもと、まとめて褒めてもあまり効果がありません。
というのも、ADHDのお子さまは一度に処理できる情報の量が少ない(=ワーキングメモリーが低い)ため、いっぺんにたくさんのことを伝えてもほとんど頭に残らないからです。
お子さまが何か行動したら、こまめに(できればその都度)声を掛けましょう。
「今の行動の○○が良かったね」という声掛けの積み重ねが、お子さまの自信や良い行動パターンの定着につながります。
注意する時も同じで、一度に2つ、3つと注意するのではなく、その都度伝えることがポイントです。
叱っているとついついあれもこれも言いたくなってしまいますが、お互いストレスになり、効果もあまりないので、できるだけ避けましょう。
親のアンガーマネジメント
日頃から突拍子もない行動が続くADHDのお子さまを育てていると、保護者さまもどうしてもストレスがたまります。
褒めるのが大切だとわかっていても、「それどころではない!」と感じる方も多いのではないでしょうか。
人の感情は完全にコントロールできるものではありませんので、イライラしてしまう保護者さまがご自身を責める必要はありません。
そもそも、ADHDは脳の機能的な問題ですので、きつく怒ったからといって解決できる問題ではありません。このことを心に留めていただきつつ、自然体で過ごしていただければと思います。(→2.1 ADHDの脳の特性|注意欠如・多動性・衝動性のメカニズム)
また、怒りやイライラを溜めこみすぎると、保護者さまの方が心身の調子を崩しかねません。
もし怒りやイライラが溜まってしまったときは、お子さまに怒りをぶつけるのではなく、できる限り、配偶者やカウンセラーといった大人に対して悩みを話すようにしましょう。
仲の良い保護者さまでも学校や塾の先生でも、今の率直な気持ちを話せる大人が1人でもいると、大きな支えとなり保護者さまの気持ちも安定しやすいため、ぜひ意識していただければと思います。
②規則正しい生活を送る

最も基本的なことであるがゆえに見逃されがちですが、ADHDのお子さまにとって規則正しい生活を送ることはとても重要です。
ADHDのお子さまはワーキングメモリーと言われる脳の働きが低いことが多いため、いわゆる「段取りを考える」という作業が苦手です。(参考:ADHDはワーキングメモリーが低い?受験対策・勉強法・鍛え方を紹介!)
朝の準備一つをとっても、何から手を付けてよいのかわからず混乱してしまい、はたから見るとぼーっとしているだけというケースも少なくありません。
色々な選択肢を頭に思い浮かべて、その中から取捨選択するというプロセスは、ワーキングメモリーの低いADHDのお子さまにとってはかなり負担が大きいものです。
そこでご家庭においては、日々のタスクをきっちりと習慣化することをオススメします。
選択肢を最小限にとどめることで、お子さまのワーキングメモリーの負担を軽減することができます。
具体的には、
- 朝の準備の手順
- 宿題の時間
- テレビやゲームの時間
- 就寝時間
などが挙げられます。
これらのタスクを分単位でしっかり決め、家族全員で守るようにしましょう。家庭内でそれが当たり前になると、お子さまも自然と規則正しい生活リズムを身につけることができるようになります。
③視覚で伝え、体で覚える

言葉だけの情報を処理することは、実はとても高度な脳の働きが必要です。
言葉を聞き取り、その概念を理解し、具体的な行動として処理するというプロセスは、脳のワーキングメモリーの多くを使うことになります。
そこで、ADHDのお子さまに指示を伝えたいときは、イラストを使ったり、実際に目の前で手本を見せたりするようにしましょう。
視覚的に伝えることで、言葉を理解するというプロセスを省略することができ、お子さまの負担を少なくすることができます。
さらにプロセスを省略するために、お子さま自身に身体で覚えてもらう方法もあります。
家から帰ったら手を洗うという習慣も、意識せずとも勝手に洗面所に身体が向かう人も多いのではないでしょうか。
ADHDのお子さまは、いろいろなことが気になりだすと行動が止まってしまうことが多いため、考えなくても勝手に体が動くまで習慣化することがポイントです。
「帰ったら手を洗う」という情報以外はお子さまができるだけインプットしないよう、玄関や洗面台の周りをできるだけスッキリと片付けておくなども効果的です。
④タスクを小分けにする

「部屋の掃除をしなさい」と言われたときに、頭の中には複数の選択肢が浮かびます。
例えば、掃除機をかけるのか、物を片付けるのか、机の上を整理するのか……あれもこれも気になってしまうADHDのお子さまは、どれから手を付けてよいかわからず、いつまで経っても掃除が終わりません(終わらないどころか、始まらないこともよくあります)。
こうしたお悩みを解決するポイントは、タスクを小分けにして伝えることです。
掃除をするには、まずは床に散らかっているものを片付ける必要がありますが、できるだけ具体的に「本を本棚にしまってね」と1つだけ伝え、それができたら褒めます(→1.1.2 一つずつ褒める)。
次に「服はタンスにしまってね」と伝え、できたら褒めて…を繰り返していきます。
「掃除してね」と一言いえば掃除ができるお子さまに比べて、確かに手はかかるかもしれません。
ですが、なかなか掃除が終わらず「いつまでかかっているの!」と怒ってしまい親子ともどもストレスを感じるよりは、タスクを切り分けてこまめに指示する方が、結果として掃除は早く終わりますし、お子さまも褒められる機会が増えて楽しく掃除することができます。
また、最初のうちはかなり細かい指示が必要かもしれませんが、やがてルーティン化でき、保護者さまが付きっきりでなくても掃除できるようになるかもしれません。
お子さまが「できた!」と感じる経験を増やすことが何より大切ですので、根気よく取り組んでいただければと思います。
⑤お子さまの集中を引き出す

ADHDのお子さまは、集中することが苦手です。
何か気になることがあると、すぐに集中が途切れてしまいます。ですので、話を聞いてほしいときは、できるだけ静かで外的な刺激が少ない環境を用意しましょう。
また、お子さまが何かに集中しているときは、口出しせず見守ることを心がけましょう。
話を聞いてほしかったり、注意しなければならないときに、ついつい大きな声を出してしまうことがあると思います。ですが、大きな声はあまり効果的ではありません。
というのも、「怖い」「怒らせてしまった」という感情が先行し、お子さまが話の内容を受け入れる態勢になりづらいためです。伝えたいことがあるときは、お子さまと目を合わせ、できるだけ落ち着いた口調で話すようにしましょう。
お子さまの集中を引き出す方法として、軽い運動や簡単なクイズ、ゲームなども効果的です。
じっと座って話を聞いてばかりいるよりも、「AかB、どっちだと思う?」という問いかけを挟んだり、体を動かすためにキャッチボールをしてみたりといった工夫をすることで、お子さまの注意を引くことができるケースもあります。
特に、ADHDのお子さまの中には、じっとしているよりも体を動かしながらの方が集中しやすいタイプもいます。
そのため、お子さまによっては手遊びをしたり、ソファでゴロゴロしたりしながらの方が話をよく聞けることがあります。
「一緒に歩きながら話す」「軽く体を動かしながら説明する」など、少し動きを取り入れるだけでもお子さまの話への集中力が変わることがありますので、ぜひ試してみていただければと思います。
⑥教育方針を一貫する

ADHDのお子さまだけでなく子育て全般に言えることですが、お子さまに注意や指導をするときは、一貫性を保つことが重要です。
気分によって言うことが変わったり、昨日は怒られたのに今日は怒られなかったという状態では、お子さまは何を信じればよいのかわからなくなり、正しい習慣も身に付きません。
また、ADHDのお子さまの場合は、学校の教育方針との整合性にも注意しましょう。
お子さまの特性に理解がある家庭内では、単に立ち歩くだけで他人に迷惑を掛けない限りは注意をしないという場合もあるでしょう。大雑把な指示で伝わりづらいときは、具体的な内容を伝えるというフォローもできます。
しかし、学校では必ずしも同じ対応ができるとは限りません。
「周りに迷惑を掛けない範囲で自由にさせてほしい」「指示が抽象的でわかりづらいときは、具体的にかみ砕いて説明してほしい」と面談などで伝えることはできますが、先生1人で30人以上を指導しなければいけない学校と、保護者さまがお子さま1人だけを見ていられる家庭とでは、そもそもの環境が違います。
こちらの希望はしっかり伝えた上で、できることとできないことを明確にし、ご家庭と学校が共通の認識を持つことが大切です。
もし学校の指導によってお子さまの心が傷ついている場合は速やかに相談する必要がありますが、それ以外で気になることがある場合は、その都度丁寧に話し合うことで解決を目指すようにしましょう。
ADHDとは?注意欠如・多動性・衝動性の特徴を解説
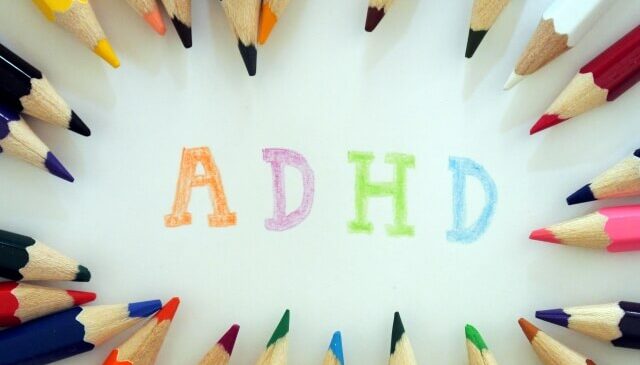
以下からは、ADHDの特性について詳しく解説します。
ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder、注意欠如・多動症)は、脳の働きに関わる発達特性の一つで、以下のような特徴が見られます。
- 注意欠如(不注意): 集中しづらい、気が散りやすい
- 多動性: 落ち着きがない、じっとしていられない
- 衝動性: 考える前に行動してしまう、感情のコントロールが難しい
また、お子さまの場合は以下のような行動が見られることがあります。
- 授業中に立ち歩く
- 友人関係のトラブル(短気、衝動的な行動)
- 先生の指示が頭に入りにくく、同じ注意を何度も受ける
- 年齢に比べて整理整頓が苦手
幼児期の検診では問題が指摘されなかった場合でも、小学校入学後に学習環境の変化により特性が目立ち始め、検査を受けるケースもあります。
ADHDの脳の特性|注意欠如・多動性・衝動性のメカニズム
かつては、ADHDのお子さまに落ち着きがないのはしつけの問題と考えられることが多かったのですが、現在では脳の機能の違いが関係していることが分かっています。
「特性を理解したけど、実際のサポートはどうすれば?」
ADHDのお子さまの学習・生活サポートに精通した専門のプロ家庭教師が、お子さまに合わせたアドバイスを提供します。
研究によると、ADHDのあるお子さまは以下のような脳の特徴を持つことが報告されています。
- 大脳基底核が小さい
- 筋肉の動きを制御する働きがあり、必要な時に活動し、休むべきときに休ませる役割を持ちます。ADHDのお子さまはこの働きが弱いため、じっとしていることが難しくなります。
- 前頭前野の機能低下
- 衝動のコントロールや注意の維持に関与する部分です。この働きが弱いと、思いついたことをすぐに行動に移してしまう傾向があります。
ADHDの特性や、それに伴い生じる苦手や困りごとが、脳の働きの問題であることを理解するのはとても大切です。
理解するだけで状況がすぐに改善するわけではありませんが、「この子(あるいは私の育て方)が悪いわけではないのだ」と気持ちが楽になる保護者さまは多くいらっしゃいますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。
ADHDによる二次的な障害|不安・うつ・行為障害との関連
ADHD自体は精神疾患ではありませんが、周囲の環境や対応次第で、以下のような二次的な問題が生じることがあります。
- 双極性障害やうつ病(約20%)
- 行為障害(非行・反社会的行動)(約30%)
- その他、不安障害や学習面での困難を抱えるケースも多数
ただし、「ADHDのお子さまが必ずうつ病や非行につながる」というわけではありません。これらは、ADHDの本質的な理解が不足している環境において、適切なサポートを受けられなかった場合に生じやすくなります。
例えば、
- いつも教室でみんなの前で叱責される
- 勉強についていけないのを「努力不足」と言われる
- 周囲の人から否定的な言葉をかけられ続ける
こうした経験が続くと、自己肯定感が低下し、精神的な負担が大きくなってしまいます。
適切な支援の重要性
ADHDの特性によって生じる二次的な障害は、周囲の理解と適切な支援によって予防することができます。
- 学校や家庭での環境調整
- できるだけ成功体験を積ませる
- 叱責ではなく改善に向けた工夫や提案を心がける
- 学習面でのサポート
- 適切な目標設定(スモールステップ)
- 一人ひとりの性質に合わせた個別指導
- 専門機関への相談
- ADHDの診断や支援に詳しい医療機関や教育機関の活用
ADHDと薬の活用
ADHDへの対処法として、投薬治療を行う場合もあります。これは、
- お子さまの生活の質を向上させるため
- 学校生活をスムーズにするため
に用いられることが多く、適切な管理のもとで服用することで大きな助けとなる場合があります。ただし、副作用や他の薬との飲み合わせを考慮しながら、慎重に進めることが大切です。
ADHDのお子さまが社会の中でスムーズに生活していくためには、適切な理解とサポートが欠かせません。
目が悪い人が眼鏡をかけたり、耳が悪い人が補聴器を付けたりするのと同じように、ADHDのお子さまも特性に応じた支援が必要です。
「努力で何とかするもの」ではなく、特性に合ったサポートを受けることは当然のことであり、おかしなことではありません。
お互いの特性を受け入れ、支え合える社会になることを願いつつ、私たちもプロ家庭教師としてできることを続けていきたいと考えています。
ADHD(注意欠如・多動症)のお子さまの子育てのまとめ
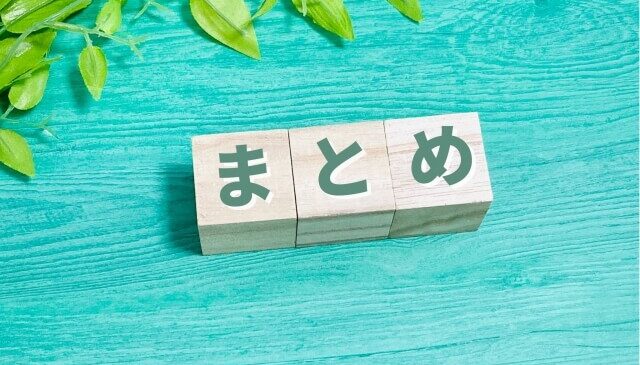
この記事では、ADHDのお子さまの育て方のポイントについてお伝えしてきました。
改めて内容をまとめると以下のとおりです。
- ADHDのお子さまは、とにかく褒めることが大切
- ADHDのお子さまの子育てにおいて、規則正しい生活は基本中の基本
- ADHDのお子さまには、言葉よりも視覚的に伝える方が効果的
- ADHDのお子さまに指示する時は、できるだけ具体的に伝える
- ADHDは脳の仕組みの問題であり、育て方や本人の努力とは無関係
ADHDのお子さまが持っている特性は、一人一人違います。
これらのポイントを参考にしながら、ご家庭においてはお子さまそれぞれにあった子育てに取り組んでいただければと思います。
また、お子さまの育て方や学力面でお悩みの方は、学校だけでなく、各市町村が設置している教育相談センターや医療機関、あるいは専門的な知識を持つプロ家庭教師などに相談することをオススメします。
一般的にADHD向きだとされている支援方法も、お子さまには相性が悪い場合もありますし、プロの目からお子さまの特性を分析することは非常に重要です。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、お子さま一人ひとりに寄り添った指導をモットーにしています。
長年の指導経験で培ったノウハウを生かしたサポートにより、これまで数多くのお子さまを第一志望合格へと導いてきました。また、学習指導だけでなく、日常生活やコミュニケーションに関する困りごとについてもサポートが可能です。
- 発達障害について相談しても、一般的なことしか答えてもらえず困っている
- 悩みや困りごとを聴いてもらうだけでなく、具体的な改善策を教えてもらいたい
などのお悩みがある方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
さらに、面談や指導はオンラインでも承っています。
近隣の塾や大学生による家庭教師では満足のいくサポートが受けられないとお悩みの方でも、日本全国・海外からでもご相談いただくことが可能です。
オンラインでの授業が不安な場合でも、初回は無料で受講可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
1人でも多くのお子さまが、自らの力で未来を切り拓き、よりよい人生を歩んでいけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。



