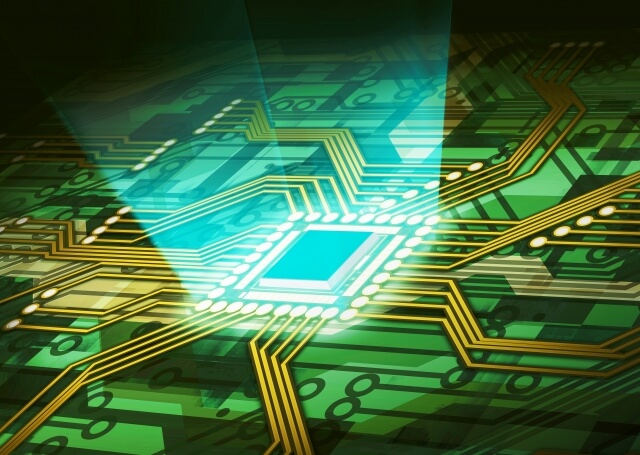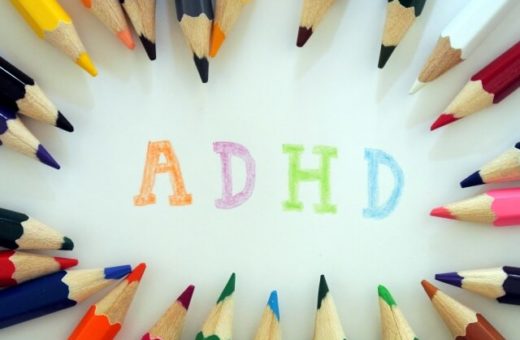ADHDはワーキングメモリーが低い?受験対策・勉強法・鍛え方を紹介!
- ADHDの集中力が低いのは、ワーキングメモリーが低いから?
- ワーキングメモリーって鍛えられるの?
- 検査を受けたら「ワーキングメモリーが低い」と言われたけど、どういうこと?
ADHDと診断を受けた方やグレーゾーンの方、あるいは、ご自身やお子さまにADHDの特性があるのではないかとお悩みの方にとって、“ワーキングメモリー”は知っておいていただきたい重要な概念です。
この記事では、発達障害を専門に1500人以上を指導してきたプロ家庭教師が、ADHDを理解する際の重要なポイントである“ワーキングメモリー”について徹底的に解説していきますので、最後までお読みいただけますと幸いです。

発達障害専門のプロ家庭教師・キャリアアドバイザー
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
近年、発達障害への理解は広まってきており、ADHDやASDといった分類を知っている人も増えています。
また、認知度の高まりに伴って学校や公的機関における支援や配慮も進んでいます。
そこでこの記事では、改めて発達障害とは何か、ADHDとは何かをお伝えするとともに、ADHDを理解する際に欠かせない「ワーキングメモリー」の概念について詳しく説明していきます。
- 発達障害やADHDについて詳しく知りたい
- お子さまのADHDの特性について理解を深め、サポートしたい
- 学校の先生や周りの人に特性を上手く説明し、適切な配慮につなげたい
- WISC-IVによりADHDの診断を受けたが、診断結果の見方を知りたい
ADHDと診断された方でも、周りのサポートや適切な配慮によって、ほとんど困難無く過ごしている方もたくさんいらっしゃいます。
この記事が、少しでも発達障害やADHDの方にとって参考になれば幸いです。
▼目次
発達障害とは概要(WISC-IV検査とADHD、ワーキングメモリー)
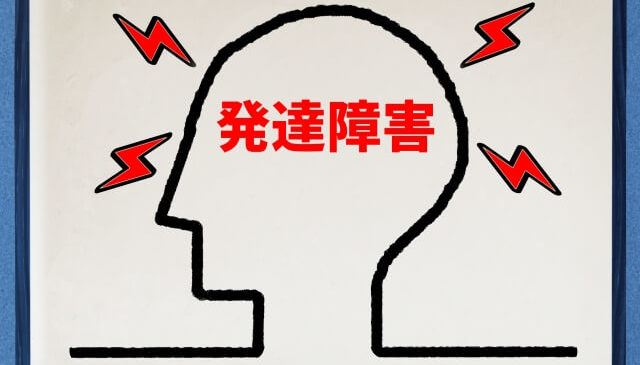
この章では、発達障害やその診断の際に用いられる知能検査「WISC-IV」について説明していきます。
というのも、「ワーキングメモリー」とはWISC-IV検査で測ることのできる指標のうちの一つであり、ADHDの方はこの指標が低くなりやすいと言われています。ADHDとワーキングメモリーの関係を理解するためには、まずはWISC-IV検査の概要を知ることが大切ですので、この章ではWISC-IVについて詳しく解説していきます。
なお、発達障害やWISC-IVについて既に十分な知識をお持ちの方は、「2.ADHDとワーキングメモリー」までお進みください。
お子さまの発達障害を診断する際には、「WISC-IV」という知能検査が広く用いられています。
学校から「お子さまの様子が気になるので、一度発達検査を受けてみてはどうか?」と言われたような場合、多くはこのWISC-IV検査を受けることになります。
ただし、WISC-IV検査を受けたからといって、すぐにADHDであるかどうかが分かるものではありません。ADHDをはじめ、発達障害の診断は知能検査の結果だけではなく、日常の様子や本人の行動パターンなどから総合的に判断されるものであり、検査を受けたその日に診断が出ることはむしろ少ないです。
加えて、ADHDの場合は「多動性」「衝動性」が特性とされています。ですが、ADHDの特性の本質は「集中力のコントロールの苦手さ」であり、単に落ち着きが無いだけではADHDであると診断することはできません。学校から落ち着きの無さを指摘され、WISC-IV検査を受けることになったとしても、落ち着きの無さの原因が集中力のコントロールの苦手さ以外であった場合(ストレスや環境によるものであった場合)はADHDには該当しません。
お子さまの落ち着きの無さの原因が「生まれつきの集中力のコントロールの苦手さ」であるかどうかを見極めるには、WISC-IV検査のほか、成育歴の聞き取りや普段の様子の観察など、丁寧な診察が必要となります。また、落ち着きの無さの原因が集中力のコントロールの苦手さ以外であった場合は、それらの原因を取り除くための支援方法を考えていかなければなりません。
いずれにせよ、WISC-IVなどの発達検査や知能検査は、お子さまがより良い日常生活・学校生活を送れるように対策を考えるために受けるものですので、気になることがある場合は学校や専門機関、医師などに積極的に相談するようにしましょう。

WISC-IV検査では、以下の4つの指標とFSIQ(全検査IQ)と呼ばれる数値を測ることができます。
また、これらの4つの指標とFSIQは平均からどれくらい離れているかという数値(平均100、標準偏差15)で表されます。
- 言語理解指標(VCI)
- 知覚推理指標(PRI)
- 処理速度指標(PSI)
- ワーキングメモリー指標(WMI)
ADHDの方は、このうち「ワーキングメモリー指標(WMI)」の数値が低くなることが多いとされています。ワーキングメモリーとは情報を一時的に記憶しながら処理する能力のことで、集中力に大きく関わる能力であると言われています。
ADHDの根本的な性質は「集中力のコントロールの苦手さ」ですので、ワーキングメモリーの数値は必然的に低くなる傾向にあると考えられています。
ただし、前述したように、WISC-IV検査の結果だけでADHDかどうかを診断できるわけではありません。ワーキングメモリーが低くなっている原因が、集中力のコントロールの苦手さ以外である可能性もありますし、全体的に数値が低く、知的境界域(FSIQが75~84程度)に該当する場合などは、ADHDとは違ったアプローチが必要になるかもしれません。
ですので、WISC-IV検査の結果の数値だけを参照するのではなく、日ごろの様子や成育歴などを丁寧に分析し、お子さまの困りごとの原因を見極め、適切にサポートしていくことが何よりも大切になります。
一昔前は、知能検査によって測られたIQが医療的な診断や福祉的な支援において重視されていたこともありました。(例:障碍者手帳の取得や障害等級の区分など)
ですが、近年ではIQだけに注目するのではなく、一人一人が持っている特性や困りごとの度合いを総合的に判断して、診断や福祉的支援を行うという方針が取られることが増えてきています。
例えば、アメリカの精神医学会では、IQによって自閉症の重症度を判断するのでは無く、「どれくらい支援が必要か?」という観点で重症度を判断する方針になりつつあるようです。
また、日本の福祉制度においても、特別児童扶養手当などについては、これまではIQだけで支給の認否を判断していましたが、最近は、援助を必要とする度合いや困り感の程度を判断基準とする傾向にあります。
さらに、学校現場でもIQだけで判断する傾向は少なくなりつつあります。
WISC-IVなどの発達テストの結果と学校の成績は必ずしも相関するわけではないという知見が共有され、IQだけを見て教育方針を決定するというケースはほぼ無くなっています。
IQが高い子どもだけを入学させたとしても、そのうち3割程度は必ず学習困難者が含まれる、という実例もあるようです。
福祉の現場、あるいは教育の現場でも、IQではなく支援が必要な度合いが重視されています。
ですので、WISC-IVの結果、IQが低かったり、分野ごとの数値に偏りがあったとしても、それだけで焦ったり、落ち込んだりする必要はありません。
検査の結果を参考にしつつ、「何に困っているのか」「どんな支援が必要か」という視点で受け止める必要があります。
とりわけ、ADHDのお子さまは注意散漫や多動といった特性を持っていますので、
- いろいろなことが気になり、集中できない、意思を強く保てない
- 計画を立てるのが苦手
- 計画どおりに進めるのが苦手
- 熱中するとやめられない
などの困りごとを抱えることになります。
学校では、先生の指示どおりに動いたり、授業の間ずっと集中を続けたりすることが求められますので、授業に集中できていないと、その度に先生から「ちゃんと話を聴くように」と注意を受けることになるでしょう。
授業に集中できないのは、決してお子さまが怠けていたり、努力が足りなかったりするわけではありません。
本人の特性によるものであることを踏まえて、「どうすれば解決できるのか?」を本人と周りが一緒に考えていく必要があります。
声かけだけで集中を取り戻せる場合もあれば、何か興味を引く話題などで徐々に誘導する、一度完全に集中を解除する、などが有効なケースもあります。
「サボっている」「わがままである」と叱責することはほとんど意味がありません。
それどころか、お子さま本人ができない自分を責めてしまい、自信を無くして成長を妨げる原因にもなりますし、そのことが本人の生きづらさにつながることさえあります。
周りから叱責されるなどのストレスにより、適応障害や鬱を発症する方もいらっしゃいます(二次障害)。
本人の特性を周りが理解することも重要ですが、同時にお子さま自身が自分の特性を把握することも重要です。自分が苦手なことを知り、どうすれば困りごとを減らすことができるのかを自分で考えられるようになることは、発達障害のお子さまにとって最も大切なことです。
お子さまはいずれ大人になり、社会の一員として生きていくことになります。いつまでも保護者さまや先生の支援が受けられるわけではありません。
なぜできないのか?と聞かれたときに、自分の言葉で説明し、「だからこんな助けが必要です」と伝えられるスキルは、たとえ発達障害やADHDでなかったとしても、生きていく上でとても重要な力です。
私たち家庭教師メガジュンは、単に勉強を教えるだけでなく、お子さまの“生きる力”につながる指導をモットーにしています。
勉強のことや生活のこと、進路のことなど、お困りの方はぜひ一度ご相談ください。誠心誠意、サポートしてまいります。
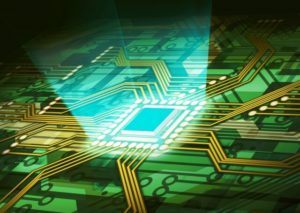
ADHD(注意欠陥・多動性障害)とワーキングメモリー
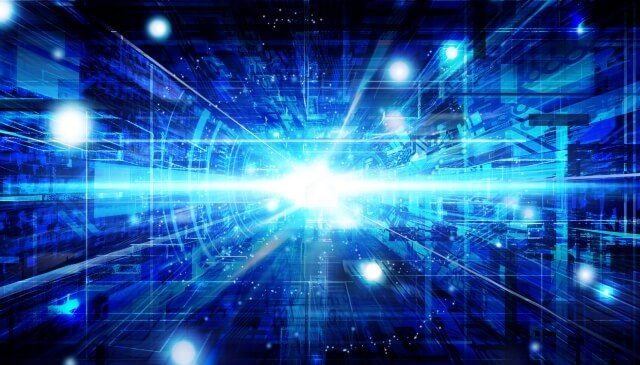
ADHD(注意欠陥・多動性障害)でワーキングメモリーが低いとどうなる?
ADHDの特性である注意欠如や多動は、ワーキングメモリー(作業記憶)の能力が影響していると言われています。
ワーキングメモリーとは、「これからすること/しなければいけないこと」を一時的に記憶しておく能力のことですが、この能力が低いことにより、すぐに気が逸れてしまって集中できない、そわそわしてしまうといった特性が出ると考えられます。
ワーキングメモリーは、「1.発達障害とは」でお伝えしたとおり、WISC-IVという知能検査で測定することができます。
情報を一時的に記憶しながら処理する能力なので、集中力だけで無く、読み書きや計算といった、学習における基礎的な能力にも大きく関わるとされています。
情報を一時的に記憶しながら処理するということは、複数の情報を同時に処理したり、順序立てて処理したりする能力(マルチタスク)につながります。
先生の指示を聞いてすぐに行動できたり、板書したりできるお子さまはワーキングメモリーが高いと言えるでしょう。
また、料理のように複数の手順を順序よく組み立てる作業も、ワーキングメモリーが重要な役割を果たしています。
「先生の指示を聞く」「板書する」といった動作は学校生活で頻繁に求められるものであり、これらが苦手なお子さまは劣等感を抱いたり、学校が苦手になったりしてしまうかもしれません。
そこで周りができるサポートとしては、
- 簡潔にまとめて話す
- 口頭だけでなく資料やメモを使いながら話す
- 話し手に注意を向けさせてから(聞く態勢ができてから)話す
などが挙げられます。
これらの工夫は、ADHDでないお子さまにとってもより分かりやすくなるものであり、クラス全体にもメリットが生まれるものです。
お子さまがワーキングメモリーが低いことで困難を感じている場合は、学校の先生やスクールカウンセラーなどに配慮について相談してみると良いでしょう。

ADHD(注意欠陥・多動性障害)のワーキングメモリーは鍛えられる?

ワーキングメモリーを鍛えれば、マルチタスクがこなせるようになり、頭の回転も早くなりそう!と期待してしまいますよね。
しかし、ワーキングメモリーそのものを鍛えることは難しいと考えられています。
例えば、数桁の数字の羅列(電話番号など)を記憶するという場面を思い浮かべてください。
その数字を心の中で言い続けている限り、数字を忘れることはありません。この「心の中で言い続けている限りは覚えられる」という能力は“短期記憶”と呼ばれます。
では、心の中で数字を唱え続けている最中に、突然話しかけられたらどうでしょうか。
話しかけてきた人物への対応に追われ、心の中で唱えていたはずの数字は徐々に忘れていってしまうはずです。それでも何とか覚えられていた数字の桁数が“ワーキングメモリー”と言われるものになります。
成人の場合、数字であれば5〜7桁、言葉であれば2〜4語がワーキングメモリーの平均と言われています。
ワーキングメモリーは年齢によって異なり、7歳で1語、11歳で2語、20歳で3語と成長していき、20歳以降は徐々に低下していくと考えられています。
「数字や単語の羅列を記憶する」ということだけに特化したトレーニングをすれば、7歳でも3語以上を記憶できるかもしれませんし、60歳になっても4語以上を記憶することは可能かもしれません。
ですが、このトレーニングはどちらかといえば短期記憶のテクニックを磨いているに過ぎず、純粋なワーキングメモリーの働きを伸ばしているとは言えません。
さらに、親の裕福さとIQは相関していることが複数の研究で明らかになっていますが、ワーキングメモリーは親の裕福さとは相関しないと言われています。
つまり、ワーキングメモリーそのものを鍛えることはできないものの、個々のワーキングメモリーの特性に応じた教育を受けることによって、その人の能力を伸ばすことは十分に可能ということになります。
100mを10秒で走れと言われても、全員が走れるわけではありません。
7桁の数字を覚えて!と言われて易々と覚えられる人もいれば、そうでない人もいます。
同じように、板書が苦手、じっと座って先生の話を聞くのが辛いというのも、生まれ持った能力の差に過ぎません。
その能力の差をいかに埋めるか、それとも代わりに他の能力を伸ばすか——教育の意義はまさにそこにあります。
本人が将来、どんな風に生きていきたいのかを見据え、いま伸ばすべき力を逆算して積み上げていく、そのサポートをするのが私たち周りの大人の役目です。
教育の目的は、平均に追いつくことではなく、自分に必要な力を自分で身につけられるようになることです。
お子さま自身が、自分の成長を期待し、自信を持って物事に取り組んでいけるよう、プロ家庭教師メガジュンは一人一人に寄り添った最適なサポートを提供しています。
ADHDの特性でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
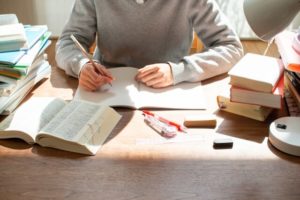
ワーキングメモリーが低いADHD(注意欠陥・多動性障害)のお子さまへの支援策

ワーキングメモリーは様々な動作に関連する指標であり、ワーキングメモリーが低いことによって生じる困りごとも多岐にわたります。
以下はほんの一例になりますが、WISC-IV検査を受けてないお子さまでも当てはまるものが多い場合は、検査を受検したり、この章で紹介する支援策を参考にしていただければと思います。
ワーキングメモリーが低い場合の困りごとの例
- 指示されたことをすぐに忘れる
- 周りの話についていけない
- 少しの雑音でも集中が途切れる
- 聞き間違いが多い
- 板書が苦手、遅い
- アナログ式の時計が読めない(読むのに時間がかかる)
- 地図を読むのが苦手
- 音読が苦手、ミスが多い
- 長文の読解が苦手
- 作文が苦手
- 「っ」や「ゃ・ゅ・ょ」などの特殊音をよく間違える
- 順序立てて説明するのが苦手
- 九九が覚えられない
- 文章題が苦手
- 図形の性質や定義を理解するのが苦手
- 図形の展開図の問題が苦手
- 理科の実験や料理など、複数の工程を一度に処理するのが苦手
- ダンスなど一連の動作を覚えるのが苦手
- ラジオ体操など、簡単な動きでもついていけない
- 初めての単語を理解するのに時間がかかる
ワーキングメモリーは、脳の中に記憶を一時的に保ちながら、同時に作業や動作を行う能力です。
この能力が低いことによって、上述のような困難が生じるわけですが、解決策としては「記憶を一時的に保ちながら」という部分に注目することがポイントです。
脳の中に記憶を保つことで脳全体のキャパシティが圧迫され、やるべき作業が追いつかなくなってしまうのであれば、記憶を「脳の外」に置いてしまえば良いのです。
つまり、メモを取ったり、やることリストを作成することで、脳内に留めるべき情報を外に出し、目の前のことに集中できるように工夫をします。メモややることリストのほかにも、
- 絵や図で説明する
- 計算の過程をリスト化する
- 大事な部分に線を引きながら文章を読む
といったことも、一時的な記憶を外に出すことの一環です。
ワーキングメモリーが低いと言われたADHDのお子さまの支援については、こういった視点で工夫を重ねていくと良いでしょう。
- 簡単な言葉でシンプルに伝える
- 伝わりづらいときは、何回か指示を繰り返す
- 全体への指示で伝わらないときは、個別に指示する
- 落ち着いた環境で話す
- 文字だけでなく、音声やイラスト、図などを組み合わせて説明する
- 計算の過程を細かく紙に書く
- こまめにメモを取るようにする
- 丸暗記できるものは身体に馴染むまで練習する
もう少し具体的な例を紹介するために、算数の文章題で考えてみましょう。
例えば、
という文章題があったとします。
この場合、脳に一時的にストックしなければいけない情報は、①ボール、②35個、③赤いカゴ、④9つ、⑤同じ数、⑥余り、⑦青いカゴ、⑧4つ、⑨同じ数といった9個の要素になります。
まずは①〜⑤を処理することで35÷9を計算しますが、同時にさらに余りを処理するための⑥余り、⑦青いカゴ、⑧4つ、⑨同じ数といった要素も覚えていなければなりません。
年齢によって記憶に留められる要素の数は違い、小学3年生で2つ程度と言われています。
ですので、小学校低学年のお子さまの中には、上述の問題が解けないお子さまもある程度いらっしゃいます。
そこで先生は、
- 大事なところに線を引いてみよう
- 問題文を2つに分けてみよう
- 絵に描いてみよう
といったアドバイスをします。
こうすることで、全てを頭の中でいっぺんに処理するのではなく、一つ一つ情報を整理しながら順番に解くことが可能になります。
こういった「解き方」を身に付けていくことが、私たちが「勉強」と呼んでいるものの本質的な意味と言えます。
自分の持っている能力でいかに対処していくか、ということは身近な学校の勉強とも深く結びついていますので、ぜひ知っておいていただきたいと思います。
お子さまの中には、目で見た情報を理解しやすい視覚優位のお子さまや、音で聞いた情報を処理しやすい聴覚優位のお子さまがいます。
問題文に線を引くのが良いのか、声に出して読むのが良いのかはお子さまによって違いますので、お子さまそれぞれの特性に合った方法を見つけることも大切です。
ADHDのお子さまの中には、ASD(自閉スペクトラム、アスペルガー症候群)の傾向を併せ持った方がいらっしゃいます。
ASDのお子さまは独自のこだわりを持つことが多く、「教科書に書き込みたくない。だから線を引きたくない」といったこだわりから問題が解けない場合などがあります。
また、「なぜ赤いカゴに先に分けるのか?」といったことが気になってしまい、問題の内容が上手く頭に入らないといった場合もあります。
違うことを考えているうちに、必要な情報を忘れてしまったり、あるいは字が汚くなってしまうというお子さまもいらっしゃいます。
お子さまに合った方法を見つけ、それを自分のものにしていく過程が教育であり成長です。
ワーキングメモリーそのものが後天的に伸びることはありませんが、短期記憶の使い方を工夫し、さらに短期記憶の使い方のコツを長期記憶として定着させていくというのが心理学的な面から捉えた「学習」ということになります。
お子さまの特性を見極め、より適切な方法で伸ばしていくことが指導者に求められるスキルなのです。
塾やプロ家庭教師は世の中にたくさん存在しますが、教育や学習について本質を理解し、さらに一人一人に寄り添った指導ができる人材はごくわずかです。
お子さまの成長にとって指導者選びはとても重要になりますので、塾選びの際はこちらの記事などを参考にしていただくとともに、プロ家庭教師メガジュンについても選択肢の一つにしていただけますと幸いです。

ADHD(注意欠陥・多動性障害)とワーキングメモリー:まとめ

この記事では、ADHDとワーキングメモリーの関係についてご説明してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- ワーキングメモリーとは、「これからすること/しなければいけないこと」を一時的に記憶しておく能力のこと
- ワーキングメモリーが低いことにより、すぐに気が逸れてしまって集中できない、そわそわしてしまうといったADHDの特性が出ると考えられている
- ワーキングメモリーは読み書きや計算など、学習の基本的な能力にも影響する
- ワーキングメモリーそのものを鍛えることはできないが、対処法を身に付けることはできる
- どんな支援策が効果的か、お子さま一人一人の特性を見極めることが重要
私たちプロ家庭教師メガジュンは、発達障害専門のプロ家庭教師として、数多くのお子さまを指導し、ノウハウを蓄積してきました。
オンラインでの指導により、遠隔地からもご相談いただけますし、海外在住の方や帰国子女のお子さまにも、数多くこれまでご利用をいただいてきました。

なかなか相性の良い塾や家庭教師を見つけられないとお悩みの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
初回相談は無料で承っていますので、お気軽にご連絡いただければと思います。
お子さまがより良い人生を歩んでいけるよう、全力でサポートしてまいります。