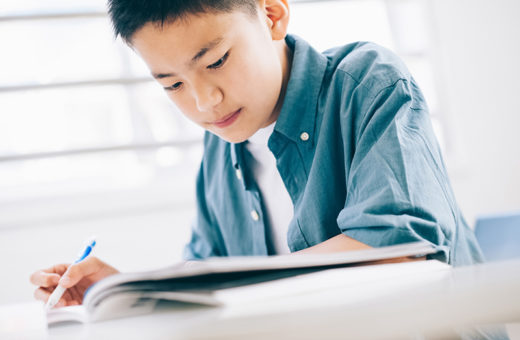【ADHD治療薬】コンサータとストラテラの違いって?効果・副作用・依存性などを解説
- ADHDの治療薬にはどんなものがあるの?副作用は大丈夫?
- コンサータとストラテラの違いって何?
- ADHDの治療で服薬を勧められたが、抵抗感がある
ADHDの治療薬について、このような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
ADHDの方に処方される薬は現在4種類ありますが、効果や特徴はそれぞれ異なるため、一人一人に合わせた処方が必要となります。
私は発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として、長年にわたりADHDのお子さまのサポートに携わってきました。
ADHDのお子さまの場合は、基本的には療育や生活環境の調整によって困りごとに対処していきますが、薬を服用しながら上手く特性と付き合っているお子さまもいらっしゃったことから、ADHDの薬物療法についても強い関心を持つようになりました。
例えば、不注意の特性によりぼーっとしてしまうことが多い方には、脳の覚醒度を上げる効果のあるコンサータ(メチルフェニデート徐放錠)を、衝動性が強く悩んでいる方には、気分や情動を安定させるためにインチュニブ(グアンファシン徐放錠)を処方するなど、どのような困りごとがあるかによって処方される薬は異なります。
※薬品名は代表的な商品名で記載し、()内には一般名を記載しています。
「集中できない」と一言で言っても、脳の覚醒度が低くぼんやりしてしまっているのか、それともソワソワして気分が落ち着かないために集中できないのか等、人によって状況は異なります。
状況や体質によって処方すべき薬の種類は変わりますので、薬物治療を行う際には丁寧な聞き取りが欠かせません。
また、ADHDの治療のために処方される薬は、脳内の神経伝達の機能を改善する効果があります。言い換えれば、脳そのものに作用する薬であり、服用することに抵抗感を感じる方もいらっしゃいます。
薬のことで気になることや心配なことがある場合は、主治医に相談し、自分が納得した上で服薬することが大切です。
ADHDやASDといった発達障害の治療は、薬物治療だけではなく、生活環境を調整したり、療育や行動療法、カウンセリングを組み合わせながら行われます。
薬物療法は治療全体の一部ですので、薬だけに頼るのではなく、様々なアプローチで困りごとを改善していくという意識を持つと良いでしょう。
- ADHDの薬の種類について詳しく知りたい
- ADHDで薬物治療を検討している
- ADHDの薬の効果や副作用を学びたい
この記事では、ADHDの方や、ADHDのお子さまのことでお悩みの保護者さまに向けて、コンサータやストラテラ、インチュニブといった薬について詳しく説明していきます。ADHDの治療薬について関心のある方は、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
▼目次
ADHD(注意欠如・多動症)の薬物治療とは?

ADHD(注意欠如・多動性障害)の特性である「注意散漫」や「多動性・衝動性」は、脳内の神経伝達物質であるドーパミンやノルアドレナリンの不足、あるいは神経伝達の調節異常によって現れると考えられています。
そのため、脳の中の細胞間の伝達を助ける薬を使用することで、特性の発現が穏やかになるとされています。薬によって一時的に状態を改善することはできますが、ADHDは生まれつきの脳の働きの性質であり、性質そのものが無くなるわけではない点は押さえておきましょう。
薬による治療は、ADHDの困りごとへの対処法の一部です。
薬のほかに、生活環境を調整したり、行動療法に取り組んだり、お子さまの場合は療育を受けたりと、様々なアプローチによって困りごとの改善を目指していく必要があります。
薬には副作用や依存性といったマイナスの面もあることから、一般的には生活環境の調整や行動療法などの「心理社会的治療」を優先し、それでも改善が見られない場合に薬物療法を検討することになります。
困りごとの度合いについては、「GAF(機能の全体評定)」と呼ばれる尺度が用いられることがあります。
GAFとは、精神障害や知的障害のある人が社会生活を送る能力を評価するためのツールで、ADHDの薬物治療の要否のほか、精神科訪問看護の評点評価の際などにも使用されます。(参考:GAF(機能の全体的評定)尺度|厚生労働省)
数値が高いほど精神が良好な状態にあるとされ、心理社会的治療を行った上でなお評点が60以下である場合には、薬物療法が検討されます。
評点60以下の具体的な症状としては、
- 友人がほとんどいない
- 同僚と人間関係が築けない
- 仕事が続かない
- 希死念慮がある
などが挙げられます。
これらは健全な日常生活・社会生活を送るために改善すべき症状であり、積極的な治療が必要であると判断されます。
薬物療法が必要であると判断された場合、ADHDの方に処方される主な薬は以下の4種類です。
- コンサータ(メチルフェニデート徐放錠)
…「不注意」の特性を抑える効果 - ストラテラ(アトモキセチン塩酸塩)
…ADHDの特性全体を抑える効果 - インチュニブ(グアンファシン徐放錠)
…「衝動性・多動性」を抑える効果 - ビバンセ(リスデキサンフェタミンメシル酸塩)
…ADHDの特性全体を抑える効果 ※18歳未満のみ処方可能
これらの薬の詳しい効果や特徴について、次の章で解説していきます。

ADHD(注意欠如・多動症)に使われる4つの治療薬|コンサータ・ストラテラ・インチュニブ・ビバンセ

ADHD(注意欠如・多動症)に使われる薬は、
- コンサータ(メチルフェニデート徐放錠)
- ストラテラ(アトモキセチン塩酸塩)
- インチュニブ(グアンファシン徐放錠)
- ビバンセ(リスデキサンフェタミンメシル酸塩)
の4つがあります。以下では、それぞれの特徴について解説していきます。
ADHD(注意欠如・多動症)に使われる4つの治療薬①コンサータ(メチルフェニデート徐放錠)
ADHDの治療薬として、コンサータの名称を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
よく名前を耳にする薬なので、ADHDのあらゆる特性に効果があるのでは?という印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。ですが、コンサータは、ADHDの特性のうち、「不注意」の特性の治療を中心としたお薬です。
コンサータは、脳内のドーパミンを増やす効果があります。これにより脳の覚醒度が上がるため、頭の中をすっきりさせ、不注意や注意散漫、頭の中のモヤモヤした感じを軽減することができます。
強い効果がある一方、脳の興奮が高まるため、不眠や不安感の増強、万能感などを伴う躁状態、お子さまの場合は食欲減退などを引き起こす場合があります。
ADHDでも衝動性が強い方の場合は、コンサータによってさらに衝動性が強まり、衝動買いに走ってしまう方などもいらっしゃるようです。ですので、双極性障害や不安障害を併発している場合は処方は避けるべきと考えられています。
お子さまの場合で食欲減退が見られる場合は、服用前にしっかり朝食を取ったり、薬の効果が切れた後に夕食を取ったり、栄養補助食品を活用したりするなど、成長期に必要な栄養をしっかりと摂取できるように工夫する必要があります。お子さまは体や脳が成長する大切な成長期にありますので、栄養面でのフォローは非常に重要です。
コンサータの一般名は「メチルフェニデート徐放錠」です。徐放錠とは、服用した後、成分がゆっくりと体の中に放出されるよう設計された薬のことで、コンサータの場合は服用直後から効果が表れ、それが12時間続くとされています。
上述したように脳を興奮状態にする薬のため、午後に飲むと夜に眠れないケースが多く、朝に飲むよう指示されるのはこのためです。また、仕事の日だけ服用し、休みの日は服用しないなどの使用方法も可能です。
用量については、まず少量から服用を始め、適量となるよう徐々に増量していきます。体重1kgあたり1mg/日程度が最適な用量とされていますが、個人差があるため服用しながら調整していく必要があります。
また、1日に最大で服用できる量は、小児で54mg/日、成人で72mg/日と定められています。
ADHDに処方される薬は4種類ありますが、このうち「コンサータ」と「ビバンセ」は中枢神経刺激剤に分類されます。
中枢神経刺激剤とは、脳の報酬系(欲望や幸福感を司る神経回路のグループ)を刺激する効果を持つ薬剤のことで、モチベーションをコントロールする強い作用を持つ一方、依存性のリスクを伴います。
コンサータの主成分であるメチルフェニデートは覚醒剤や麻薬と同じ成分が含まれており、服用後に尿検査をすれば覚せい剤反応が出ることもあります。さらに副作用としてめまいや眠気、視覚障害等が発現するおそれがあることから、自動車の運転などは控えるように指示されます。(参考:自動車運転に注意が必要な薬剤リスト|鳥取大学医学部附属病院薬剤部)
そのため、認可された医療機関でしか処方できず、処方の際には必ず記録をつけなければならないなど、流通には厳しい規制が敷かれています。
中枢神経を刺激するという強い作用がある一方で、コンサータは徐放錠であり成分がゆっくりと体に行きわたることから、血中濃度の変化は穏やかです。そのため、成分が同じくメチルフェニデート塩酸塩であるリタリン(※)に比べると、依存のリスクは最小限にとどまります。
また、ADHDの方はもともと報酬系の働きが低いため、依存のリスクはかなり低いと考えられています。
ADHD(注意欠如・多動症)に使われる4つの治療薬②ストラテラ(アトモキセチン塩酸塩)

ストラテラ(アトモキセチン塩酸塩)は、脳内の神経伝達物質を調節し、シグナルの伝達を改善する作用があります。
このため、注意散漫や衝動性・多動性といったADHDの特性全般を改善する効果が期待できます。特に、過集中(※)の改善においては大きな効果があるとされています。
- 例1:ゲームに熱中して寝食を忘れてしまう
- 例2:同時並行で進めなければならない仕事なのに、一つの仕事にだけ集中してしまい、結果として他の仕事が進まず納期に遅れてしまう
コンサータは、ADHDの不注意の特性の改善に大きな効果が期待できる一方、脳の興奮を高める作用を持つことから、不安障害や双極性障害を併発している場合は処方が避けられます。
一方、ストラテラは不安症状を軽減する作用が認められており、双極性障害やうつ病を併発している方にも処方することができます。また、コンサータと異なり、ストラテラは脳の報酬系を刺激しない非中枢神経刺激剤であるため、依存性はありません。
コンサータは服用したその日に効果が現れますが、ストラテラの効果が表れるのは服用を始めて1~2週間程度経ってからになります。徐々に効果が現れるようになり、安定した効果が実感できるのは、服用から6~8週間後とされています。
すぐに効果が現れるわけではないため不安を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、穏やかに効果が現れるのがストラテラの特徴ですので、それを踏まえた上で服用を続けましょう。薬の効果が現れるようになってからは、終日効果が実感できます。
重大な副作用として肝不全や肝機能障害が挙げられますが、発現率はそれほど高くありません。重要ではないものの起きやすい副作用としては、頭痛や吐き気、腹痛などが挙げられます。
これらの副作用は飲み始めの時期に起きることが多いため、心配なことがあれば医師に相談するようにしましょう。
ストラテラを服用すると感情が無くなる?
「ストラテラを服用すると感情が無くなってしまう」という言説もインターネット上では見られます。
これは、ストラテラが気分を落ち着ける作用を持つためであり、人によっては「何の感情も湧いてこない」という状態になることがあるようです。
気分の浮き沈みが激しかったり、不安が強かったりする場合はこうした効果がプラスに働きますが、効きすぎると「やる気が出ない」「何をしても楽しくない」などマイナスの面も生じることになります。
マイナス面が大きいと感じる場合は、医師と相談して薬の量を調整するなどしましょう。
ADHD(注意欠如・多動症)に使われる4つの治療薬③インチュニブ(グアンファシン徐放錠)

インチュニブ(グアンファシン徐放錠)は、α2Aアドレナリン受容体を刺激し前頭葉の働きをよくするほか、情動を安定させる働きがあります。そのため、ADHDの多動性や衝動性を改善する効果が期待できます。
せっかちでイライラしてしまったり、癇癪を起こしてしまったり、ルールが守れないなどの困りごとがある場合に優先して処方されます。
インチュニブは、もともと高血圧の薬として開発されました。そのため、飲み初めには眠気や低血圧といった副作用が生じる可能性があることから、少量から服薬を始め、少しずつ増量しながら適量を検討します。(ちなみに、高血圧についてはより効果的な薬が開発されたため、現在はADHDの薬としてのみ処方されています)
服用後すぐに効果が現れるほか、不安障害などを併発していても服用可能であるなど、相性が良い場合は非常に大きな効果を発揮する一方で、ジェネリックが無く薬価が高いというデメリットがあります。
さらに、現在は小児期のADHDしか保険適応されないため、18歳以上の場合は自費での使用となります。そのため、医療費の助成制度を利用するなど、費用面においては検討が必要です。
ADHD(注意欠如・多動症)に使われる4つの治療薬④ビバンセ(リスデキサンフェタミンメシル酸塩)

ビバンセ(リスデキサンフェタミンメシル酸塩)は、脳の神経細胞間でやりとりされるノルアドレナリンとドーパミンの量を増やす作用があります。
その結果、より多くの情報が伝達できるようになるため、ADHDの不注意などを改善する効果が期待できます。
ビバンセは、コンサータと同様に中枢神経を刺激する作用があるため、依存のリスクがあります。
ビバンセの成分であるリスデキサンフェタミンは、覚せい剤の原料として指定されており、流通には厳しい規制が敷かれているほか、ビバンセを処方しない方針のクリニックもあるようです。
欧米ではADHDの治療薬として優先的に処方されていますが、日本では乱用・依存性について評価中という位置づけであり、他のADHD治療薬で効果が見られない場合のみ使用することとされています。
また、コンサータ・ストラテラ・インチュニブは18歳以上への処方が認められていますが、ビバンセは18歳未満のみに使用が認められています。
ADHD(注意欠如・多動症)が処方を受けるまでの流れ

メンタルクリニックを受診したとしても、すぐに薬物治療を受けることになるわけではありません。
例えば、
- 同じミスを繰り返す
- ケアレスミスが多い
- 時間の管理が苦手
- 整理整頓が苦手
- 指示通りに動くのが苦手
- 早とちりや思い込みが多い
- せっかちでイライラしてしまう
- 人間関係のトラブルが多い
といった困りごとを抱えていたとします。
これらは一見するとADHD特有の困りごとのように思われますが、ASDや別の精神疾患が根本的な原因となっているケースもあります。
例えば、時間の管理が苦手な場合、「一つのことにこだわり過ぎてしまう」といったASDの特性が関係しているなどのケースがあります。(ADHDとASDの併発については、こちらの記事をご覧ください。)

お子さまの場合は、年齢に不相応な注意散漫さや落ち着きの無さから、ADHDではないかと受診される場合がほとんどです。
周りと比べて極端に落ち着きが無い、順番を待てない、話を聞けない、ケアレスミスが多いなどが具体的な困りごとになりますが、大人の場合と同様、ADHDの特性のように見えて、実はASDも併発しているケースは少なくありません。
また、成長とともに多動性や衝動性は落ち着くことが多い一方、不注意の特性は大人になってからも持続することが多いとされています。
大人の場合でも子どもの場合でも、表面上の困りごとだけを見て判断するのではなく、丁寧な聞き取りによって困りごとの根本的な原因を明らかにし、その上で薬物治療に取り組む必要があります。
以下では、ADHDの方が薬物治療を受けるまでの具体的な流れについて解説していきます。
ADHD(注意欠如・多動症)が処方を受けるまでの流れ①症状の聞き取り
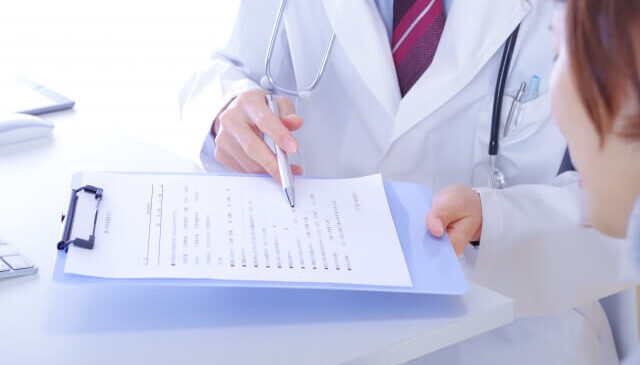
症状の聞き取りにおいては、
- どんな状況で困りごとがあるか
- 何がきっかけになっているか
- 似たような困りごとはあるか
といった点が重視されます。
そのため、受診する際には、いつ・どこで・どんな困りごとがあるか、それはいつからか(子どもの頃から/成人してから/最近になって 等)などを話せるようにしておきましょう。
発達障害は生まれつきの性質であるため、子どもの頃から特性が現れていたどうかが非常に重要です。子どもの頃の様子がわかる通信簿や、可能であれば親に付き添ってもらうなどし、幼少期からの成育歴を詳しく医師に伝えられるようにしましょう。
具体的に症状を伝えることで、ADHDなのか、それともASDや他の精神疾患なのか、ADHDでもどの特性が強く出ているのかなどを正しく判断することができます。
医師に正しく説明できるよう、あらかじめノートやメモを作っておくのもおすすめです。

ADHD(注意欠如・多動症)が処方を受けるまでの流れ②ADHDのタイプの分類
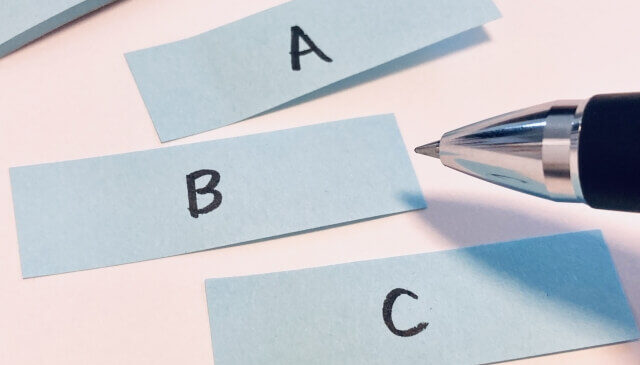
ADHDの特性には「不注意」と「衝動性・多動性」がありますが、さらに細かくタイプを分類することができます。
特に不注意の特性については、大人になってからも特性が持続することが多く、より細かい観点で分類することが症状改善につながります。
- 他集中タイプ
- 低覚醒タイプ
- 思考過多タイプ
- 過集中タイプ
多集中タイプ
いろいろなことに注意が向き、一つのことに集中できないタイプです。ですので、優先して取り組むべき仕事や勉強など、今まさに必要なことに集中できるよう処方を行います。
ソワソワした感じやイライラが強い場合はインチュニブで情動の安定を図りますが、イライラがあまりない場合はコンサータを使用することもあります。
低覚醒タイプ
ミスや見落としが多い、ボーっとする、何かを始めるのに時間がかかるなど、脳の覚醒度合いが低いタイプです。
集中力を高め、考えたことを実行する脳の働きを高めるため、コンサータを使用することが多いタイプです。
思考過多タイプ
頭の中に次々に考えが浮かんできて、目の前のことに集中できないタイプです。興味の無いことに直面すると他のことを考えてしまったり、空想にふけってしまいがちなこともあります。
思考を落ち着けるためにストラテラが処方されるほか、自分の興味をコントロールする方法を行動療法によって身につける場合もあります。
過集中タイプ
一つのことに極端に集中し、周りのことが全く見えなくなったり、優先順位が滅茶苦茶になってしまったりするタイプです。
視野を広げるために、ストラテラが使用されることがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)が処方を受けるまでの流れ③薬の選択と調整

ADHDのタイプに応じて薬が処方されますが、実際に服用する中で、薬の種類を変えたり、用法・用量を調整したりすることがあります。
薬の種類を変えても効果が見られない場合は薬物治療そのものが中止されることもあるほか、ADHD以外の治療薬の使用が検討される場合もあります。
ADHDの治療薬以外で処方が検討される薬には、気分の浮き沈みを穏やかにする感情調整薬や、脳の興奮を抑える抗精神病薬などが挙げられます。
薬が処方されたら、必ず指示された用法・用量を守って服用するようにしましょう。
ADHDの治療薬は症状を抑えることはできますが、ADHDそのものを無くすことはできません。そのため、長く飲み続けるケースも多く、副作用や依存性、耐性とも上手く付き合っていく必要があります。
もし体調や薬の作用について気になることがある場合は、医師とよく相談し、自分が納得した上で服用するようにしましょう。また、自分の判断で服用を中止したり、定められた用法・用量以外で服用したりすることは避け、必ず医師の判断を仰ぐようにしましょう。

ADHD(注意欠如・多動症)の薬物治療の注意点
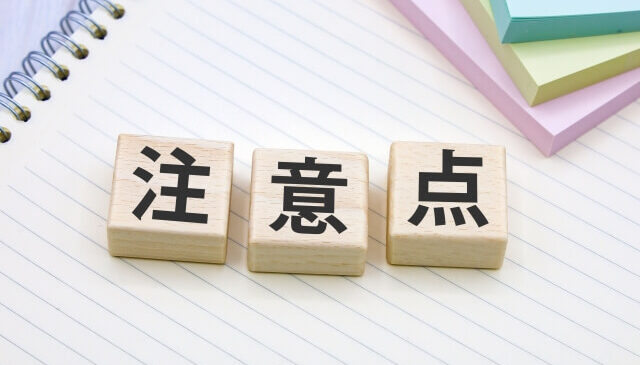
ADHDの方は、コンサータやストラテラといったADHDの症状を緩和する薬のほかにも、うつ症状や不安障害などの二次障害を軽減するために、リスパダール(リスペリドン)、エピリファイ(アリピプラゾール)、パキシル(パロキセチン)を併用する場合があります。
これらの薬は精神を安定させ、気持ちを落ち着ける作用があります。ADHDによる困りごとが多く、気持ちが落ち込んでいたり、ストレスによってうつ病や双極性障害を発症している場合に処方されることが多くなっています。
不眠の症状がある場合は睡眠導入剤が、てんかん発作がある場合は抗てんかん薬が処方されるなど、併存している症状によって様々な薬が組み合わせられますが、薬の組み合わせによっては症状が悪化したり、危険な反応が生じることもあります。
薬の種類や量が変わったときは、自分の体調の変化について、いつも以上に気にかけるようにしましょう。また、別の病院で処方されている薬がある場合は、必ず医師に伝えるようにしましょう。
特に精神科の薬は、依存性ができるだけ発現しないように配合し、十分に安全性を確かめながら慎重に服薬量が調整されます。心配なことがあれば医師に相談し、薬の内容に疑問がある場合は説明を求めるようにしましょう。
ところで、皆さんは「服薬アドヒアランス」という概念をご存じでしょうか?
「服薬アドヒアランス」とは、服薬する本人が、薬がなぜ必要なのかを正しく理解し、意志を持って服用しているかどうかを表す概念です。
服薬アドヒアランスが低いと、薬を飲み忘れたり、指示通りではない用法・用量で服用することが増える傾向にあることが統計的に明らかになっています。
飲み忘れや用法・用量に従わない服用は、薬の効果が減ってしまうだけでなく、副作用などのリスクも高まります。そのため、何のために薬を飲むのか、どんな状態を目指すのかを服用者本人が理解し、医師と服用者が共通理解を持って薬物治療に挑むことが大切です。
例えば、ADHDで最もよく処方される薬のひとつがコンサータですが、「依存性があるため服用には注意が必要だ」といった言説をインターネットなどで目にすることがあるかもしれません。
ですが、コンサータは徐々に成分が行き渡る徐放錠であり、依存性は最低限に抑えられています。ですので、薬を飲まなくなるとイライラや震えといった身体依存が出るというような可能性はほとんどありません。
もし「コンサータに依存してしまった」というケースがあるとすれば、コンサータの服用によって頭がすっきりし、ADHDの困りごとを軽減できたゆえに「コンサート無しで生活するのが怖い」「コンサータの服用をやめたくない」といった精神的なものになるでしょう。
現時点では、コンサータを長期間服用することのリスクは報告されていませんので、このように「コンサータがよく効くから、服用をやめたくない」という状態になったとしても大きなデメリットはありません。また、コンサータへの精神的な依存は、服用休止後に徐々に消失することが分かっています。
ですので、もしコンサータを処方された場合に「依存性が心配だな」と感じたときは、正しい知識を身につけるとともに、医師や薬剤師に「依存性が心配である」ということを率直に伝えて相談するようにしましょう。
「仕事が休みの日は服用しない(休薬日を設ける)」「ほかの薬から試してみる」など、自分が一番納得できる形で処方してもらえるよう、医師とよく話し合うことが大切です。
また、依存性が心配だからといって、勝手に飲む量を減らしたり飲むのをやめたりすると、想定された効果が表れずどんどん薬の量が増えてしまったり、医師との信頼関係が崩れてしまったりするかもしれません。
発達障害の治療は、特性そのものが無くなるわけではないことから、主治医とも長く付き合っていくことになります。主治医と良好な関係を築くことも、発達障害の治療においては大切ですので、ぜひ意識していただければと思います。

ADHD(注意欠如・多動症)の治療薬(コンサータ・ストラテラ・インチュニブ・ビバンセ)のまとめ
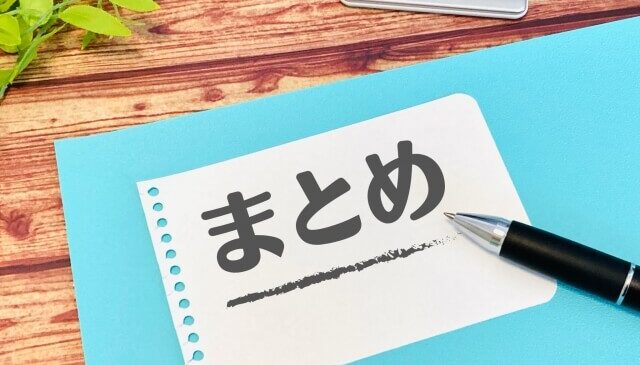
この記事では、ADHDの治療薬(コンサータ・ストラテラ・インチュニブ・ビバンセ)や薬物治療の流れについて詳しく説明してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- ADHDの特性が生じるのは、脳の神経伝達の異常が原因であると考えられている
- ADHDは薬によって一時的に症状を軽減することができるが、ADHDの特性そのものを解消することはできない
- ADHDの治療の基本は、行動療法や生活環境の調整であり、薬物治療は補助的なもの
- ADHDの治療薬は「コンサータ」「ストラテラ」「インチュニブ」「ビバンセ」の4種類
- 薬によって効果が異なるため、特性に合わせた処方が重要
ADHDと一口に言っても、その特性は様々です。
大人の方は不注意型が多いとされていますが、衝動性や多動性でお悩みの方ももちろんいらっしゃいますし、学生時代と社会人になってからで困りごとが変わることもあります。
行動療法でも薬物療法でも、本人の困りごとを具体的に聞き取り、原因を見極めながら問題の解消に向けてアプローチすることがとても重要です。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年の指導経験の中で培ったノウハウを元に、ADHDなど発達障害のお子さまに向けて幅広いサポートを行っています。
学習指導のほか、生活上の困りごとやキャリアプランのご提案なども承っていますので、塾や家庭教師をお探しの方や、ADHDのことで相談先が見つからずお困りの方などは、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでご連絡ください。
また、指導や面談はオンラインでも承っています。全国各地からご利用をいただいているほか、海外の方や帰国子女の方にもご利用いただき、これまでたくさんのご好評の声をいただいていきました。
初回の指導は無料で承っていますので、オンラインでの受講が不安な方もお気軽にお試しいただけます。
1人でも多くのお子さまが、自分らしく社会で活躍できるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
- ADHDの治療薬の種類から使い分け、処方までの流れを解説。 – あらたまこころのクリニック | 名古屋市瑞穂区の心療内科・精神科 (mentalclinic.com)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)治療薬の解説|日経メディカル処方薬事典 (nikkeibp.co.jp)
- 注意欠陥・多動性障害(ADHD)治療薬 – 解説(効能効果・副作用・薬理作用など) | MEDLEY(メドレー)
- ADHDの症状、原因と治療薬|心療内科|ひだまりこころクリニック栄院 (nagoyasakae-hidamarikokoro.or.jp)
- ADHDと薬~効果や副作用を理解しよう – 児童向けコラム | 障害者ドットコム (shohgaisha.com)
- ハイパー薬事典 (jah.ne.jp)