発達障害のスマホ依存の対処法!子どものルールの作り方はどうする?
- 発達障害の子どもがスマホばかり触っている
- スマホが気になって勉強に集中できない
- スマホを取り上げると癇癪を起こしてしまう
発達障害のお子さまの保護者さまで、このようなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
スマホは私たちの生活に欠かせないものであり、お子さまにとっても身近なアイテムとなっている一方、スマホに夢中になり依存してしまうリスクもあります。
視力や体力の低下など身体的な影響のほか、スマホが気になって勉強が手に付かなくなるなど、学力面や生活面で心配されている保護者さまも多いのではないでしょうか。
特に、発達障害のお子さまは脳への強い刺激を求めたり、衝動性が強かったり、こだわりが強かったりと、スマホ依存になりやすい性質を持っています。
無理にスマホを取り上げるとパニックや癇癪を起こしてしまうこともあるため、スマホの使用を制限する場合には丁寧な対応が必要です。
私は発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として長年にわたり活動し、1500人以上のお子さまを支援してきました。
スマホやゲームが止められないとお困りのお子さまも多く、私たちプロ家庭教師と保護者さまが連携しながら、スマホへの依存を改善したケースもこれまで数多くあります。
そこでこの記事では、発達障害のお子さまのスマホ依存でお悩みの保護者さまに向けて、スマホ依存の原因や対処法を詳しくお伝えしていきます。
現場で奮闘してきたプロ家庭教師ならではの視点で解説していきますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
- 発達障害の子どもがスマホに依存してしまう原因は?
- スマホを長時間使用すると、どんな影響がある?
- スマホと上手く付き合うコツを知りたい!
発達障害がスマホ依存になりやすい4つの理由

発達障害の方がスマホ依存になりやすいとされている理由には、次のようなものがあります。
②不注意や衝動性などの特性によって、ついついスマホを触ってしまう(ADHD)
③過集中やこだわりの強さから、没頭したり癖になったりする(特にASD)
④ストレス解消や現実逃避の手段として使っている(ADHD・ASD)
発達障害がスマホ依存になりやすい4つの理由①脳への強い刺激を求める(特にADHD)

スマホ依存に限らず、多くの依存症はドーパミンなどの脳内物質の過剰な分泌が原因となっています。
スマホやゲーム、ギャンブルなどではこれらの脳内物質が大量に分泌されるため、脳に強い快感をもたらします。
その結果、「もっとやりたい!」「もっと強い刺激が欲しい!」という衝動がどんどん強くなり、スマホを触らずにはいられない、触れないとイライラしてしまうという依存症状が現れます。
一方、発達障害の中でもADHD(注意欠如・多動症)の方は、ドーパミンやノルアドレナリンといった脳を活性化させる脳内物質のはたらきが弱いとされています。
定型発達の人もドーパミンの効果によってスマホに依存してしまうことがありますが、ADHDの方は普段からドーパミンが不足している分、より刺激が癖になりやすく、依存にも陥りやすいと考えられます。
発達障害がスマホ依存になりやすい4つの理由②不注意や衝動性の特性で、ついついスマホを触ってしまう(ADHD)

ADHDの方の特性には、「不注意」と「多動性・衝動性」の2つがあります。
不注意特性の強い方は、一つの物事に集中し続けることが難しく、色々なものに注意が移っていってしまいます。
そのため、勉強をしていてもふとした拍子にスマホが気になって触ってしまったり、複数のアプリをあれこれと使い、何時間もスマホを見てしまうなどのケースがあります。
衝動性については、“やりたい”と思った気持ちにブレーキが掛けられず、「今はスマホを触るべきではない」と頭ではわかっていても、ついついスマホを触ってしまうなどのケースがあります。
いずれの場合も、スマホを触りすぎていることには本人も自覚があるものの、特性ゆえに行動を制御することができていない状態です。
そのため、ADHDのお子さまがスマホを触りすぎているときは、頭ごなしに叱るのではなく、「スマホを目に付かないところに置く」「時間が来たらアラームを鳴らす」など、本人の特性を上手くコントロールすることがポイントとなります。
発達障害がスマホ依存になりやすい4つの理由③過集中やこだわりの強さから、没頭したり癖になったりする(ADHD・ASD)

発達障害の人は、寝食を忘れて何時間も一つのことに没頭してしまう「過集中」と呼ばれる状態になることがあります。
過集中の原因には、切り替えが苦手であることや、優先順位が付けられず目の前のことだけに集中してしまうこと、衝動性が抑えられないことなどが挙げられます。
定型発達の人の場合、1時間もスマホを触っていれば、目が疲れたり集中力が切れたりして、スマホを触るのを止めてしまうでしょう。ですが、過集中の状態にある発達障害の人は「疲れた」という感覚が無く、何時間でもスマホを触り続けることができてしまいます。
過集中自体はADHD・ASDの両方に見られる特性ですが、特にASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)の方は「強いこだわり」や「ルーティンを好む性質」を併せ持っていることが多く、相手を論破するまでSNSを使い続けたり、レベルが上限に達するまでゲームを続けたりすることがあります。
発達障害はスマホ依存になりやすい4つの理由④ストレス解消や現実逃避の手段として使っている(ADHD・ASD)

発達障害のお子さまは、特性ゆえに注意を受けたり、集団生活に馴染みにくかったりと、日常生活でのストレスが多く、自己肯定感も低い傾向にあります。
スマホを触ること自体がストレス解消になるほか、スマホに没頭すれば日常の嫌なことを忘れられるため、現実逃避としてスマホにのめり込むお子さまも多くいらっしゃいます。
学校やご家庭では苦手なことが多いお子さまも、ゲームの世界では活躍できるなど、ある意味でスマホが“安心できる居場所”になっていることがあります。

スマホ依存症のチェックリスト

発達障害かどうかに関わらず、スマホが止められない人はたくさんいます。
ついついスマホを触ってしまうだけでなく、トイレやお風呂でもスマホを手放せなかったり、スマホが無いとイライラしてしまったりするなど、日常生活に支障がある場合は「スマホ依存症」に該当します。
2021年に行われた調査によると、自分がスマホ依存だと思う人は全体の17.6%に上り、特に10代女性では29.8%の人がスマホ依存の自覚があると回答していました。
その他の調査でも、思春期や青年期の年代で特に依存傾向が高いことが分かっています。(参考:2021年スマホ依存と歩きスマホに関する定点調査 (mmdlabo.jp))
以下では簡単なチェックリストをお示していますので、該当する項目が多い場合はスマホ依存の傾向があると考え、使用時間を制限するなど適切に対応していきましょう。
- スマホが使えないと、イライラしたり不安になったりする
- 目的が無くても漫然とスマホを触ってしまう
- 時間を忘れて何時間でもスマホを触ってしまう
- 食事中でもスマホを触る
- トイレやお風呂にもスマホを持ち込む
- スマホ以外での人とのつながりが極端に少ない
- SNSの反応が常に気になっている
- すぐに返信しなければならないという強迫観念がある
- スマホに夢中になり、家族との会話が減っている
- スマホの触りすぎで、仕事や勉強などに支障が出ている
- 夜遅くまでスマホを触ってしまい、睡眠不足になっている
- 昼夜が逆転している
- 朝、起きられなくなった
- キレやすくなった
- イライラして人や物に当たるようになった
- 何事にもやる気が起きない
- 感情が乏しくなった
- 記憶力や集中力が低下した
- 視力が落ちた
- 肩こりや頭痛、腰痛、めまいなどの症状がある
- 体重が増えた/減った

スマホ依存症と「スマホ脳過労」

スマホ依存症になると、スマホが止められないだけでなく、「イライラする」「キレやすくなる」「集中力が低下する」などの精神的な症状や、「頭痛」「めまい」「肥満」「不眠」「視力低下」など、身体的な症状が現れることがあります。
特に、イライラや集中力の低下といった精神的な症状は、スマホを使いすぎることで脳が疲弊し、一部の機能が衰えてしまう「スマホ脳過労」であることが指摘されています。
スマホを使用すると、視覚や聴覚をとおし、脳には膨大な情報が流れ込んできます。これらの刺激や情報を処理するため、脳は一部の機能だけを極端に働かせることになります。
その結果、脳の一部だけに負荷が集中し、逆に他の部分はほとんど使われない状態となります。
人間の身体は、使わない部分はどんどん衰えていく仕組みになっているため、スマホを使う際に使われない脳の機能については、段々と衰えてしまいます。
スマホ依存症の人の脳では、自分や相手の感情を読み取ったりコントロールしたりする機能や、集中力や記憶力などの認知機能をつかさどる部分が委縮する傾向にあることが分かっています。
この傾向は、脳の機能が発達途上にある子どもや若い人において特に顕著であるとされています。
発達障害のスマホ依存症への5つの対処法

では、発達障害のお子さまがスマホ依存になってしまっているときには、どのように対応するのが良いのでしょうか。
口頭で禁止してもついつい触ってしまうお子さまは多く、無理に取り上げることは依存症への対応としてはタブーとされています。
全く触らせないのではなく、少しずつスマホに触れない時間を伸ばしていったり、スマホ以外で楽しいものを見つけたりと、発達障害のお子さまのスマホ依存への対処法にはいくつかのポイントがありますので、順にご紹介していきます。
発達障害のスマホ依存症への5つの対処法①ルールの作り方の工夫

スマホを使うルールとして、「1日○時間まで」というように時間制限を設けるご家庭は多いと思います。
時間制限を設ける場合、まずは現実的な目標から設定するようにしましょう。
毎日3時間スマホを使ってしまうお子さまの場合は、いきなり1時間まで減らすのではなく、2時間30~40分くらいの目標を設定しましょう。20~30分だけスマホの使用を我慢すれば良いので、多くのお子さまはルールを守ることができます。
また、使う時間の総量を制限せず、「夜ごはんの後は使わない」「夜8時以降は使わない」など、時間帯で制限するのも効果的です。約束の時間になったら、保護者さまはお子さまのスマホを預かり、目の届かないところに保管しておきましょう。
時間帯で使用を制限する場合は、家族全員でルールを守ると良いでしょう。
お子さまの使用を禁止しているにもかかわらず、保護者さまがスマホを触っていては、お子さまはスマホを使いたいという気持ちが刺激されてしまいますし、大人に対して「ずるい」とも感じてしまいます。
どうしてもスマホの使用が必要なときは、お子さまの目の届かないところで使用するか、「仕事の連絡が来たときだけ使うね」と大人のスマホ使用についても約束事を設けると良いでしょう。
発達障害のスマホ依存症への5つの対処法②家族の会話を増やす

スマホに極端に依存してしまうお子さまは、居場所の無さを感じているケースが多くなっています。
学校でも注意を受けることが多かったり、友達が少なかったりして寂しさを感じているほか、家庭でも宿題や勉強に追われて安らげていない場合があります。
実際に、家族の会話が活発な家庭ではスマホ依存になりにくく、家族の会話が少ない場合はスマホ依存になりやすいことが分かっています。
「自分の話を一番聞いてもらえるのはSNS」という状態のお子さまからスマホを取り上げると、いよいよ居場所がどこにも無くなってしまいます。
そういったお子さまの場合、まずはスマホ以外の居場所を作ってあげることが必要です。
具体的には、家庭での会話や交流の在り方を見直していきましょう。保護者さまはお子さまのことを気にかけて話しているつもりでも、お子さまにとってはプレッシャーになっているかもしれません。
学校や勉強のことばかりを話題にせず、お子さまの好きなアニメやゲーム、アイドルの話をしても良いですし、保護者さまが「今日の嬉しかったこと」をお子さまに伝えるのも良いでしょう。
以前に私がサポートさせていただいたご家庭では、お子さまがあまり学校に馴染めない傾向にあったことから、保護者さまはいつも「嫌なことは無かった?」とお子さまに話しかけていました。
そうした声掛けを毎日続けていると、お子さまもいつの間にか「学校での嫌なこと」を探してしまうようになります。
そこで保護者さまには、「嫌なことは無かった?」ではなく、「楽しいことはあった?」と声掛けしていただくようにしました。
最初のうちはお子さまも戸惑っていましたが、徐々に「算数の授業はつまらなかったけど、理科の観察は楽しかった!」など、楽しかったことについても話せるようになってきました。
親子の会話も徐々に増え、結果的にスマホを使う時間も減らしていくことができました。
発達障害のスマホ依存症への5つの対処法③デジタル・デトックス

デジタル・デトックスとは、一定の期間スマホを完全に手放すことを指します。
急にスマホを取り上げるのではなく、「今度キャンプに行くから、その間はスマホの電源を切っておこうね」というように、目的を持って自発的にスマホを断つことがポイントです。
「4-1.発達障害のスマホ依存症への5つの対処法①ルールの作り方の工夫」と同様、デジタル・デトックスを行う際は、できる限り家族全員で取り組むようにしましょう。
スマホ断ちは大人でもなかなか難しいものですが、1日だけでもスマホを手放してみると、何とも言えない解放感を得ることができます。
また、iPhoneのスクリーンタイムやAndroidのデジタル・ウェルビーイングのように、各スマホには使い過ぎを防ぐために使用時間を制限する機能が搭載されています。
1日単位のデジタル・デトックスが難しい場合は、こうした機能も活用しながら、少しずつスマホを使わない時間を作っていくことが大切です。
発達障害のスマホ依存症への5つの対処法④スマホ以外の趣味を持つ

スマホ以外に熱中できる趣味があることや、複数のコミュニティに所属していることによって、依存症のリスクが下がることも分かっています。
ネットやゲーム以外の趣味を持つことで自然とコミュニティも広がりますので、お子さまには様々な体験をさせてあげると良いでしょう。
習い事をするのが金銭的に難しい場合でも、市町村が運営する博物館や資料館、科学センターなどでは子ども向けのイベントがたくさん開催されていますし、比較的安価で参加できる科学教室や体験活動などもありますので、お金を掛けずに楽しめるものを探していくと良いでしょう。
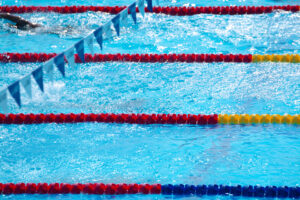
発達障害のスマホ依存症への5つの対処法⑤専門機関に相談する

スマホ依存が長引き重度のものになると、スマホ以外には全く興味が湧かず、引きこもりになってしまうケースもあります。
引きこもりによる精神的・身体的・社会的な影響は非常に大きいため、引きこもりの兆候が現れたときには速やかな対応が必要です。
重度の依存症や引きこもりの問題を家庭だけで解決することは難しいため、専門機関に相談し、治療などのサポートを受けるようにしましょう。
スマホ依存の背景に発達障害がある場合は、依存症の治療のほか、発達障害への対応やサポートも同時に受けることが望ましいでしょう。
相談先としては、児童精神科や心療内科のほか、地域の発達障害者支援センターなどが挙げられます。
どこに相談してよいかわからない場合は、市町村が設置する子育ての相談窓口などに連絡してみましょう。
ご家庭だけで抱え込まず、まずは相談することが大切です。
⚫️発達障害者支援センター
– 発達障害者支援センターは、発達障害のある子どもから大人までを総合的にサポートすることを目的に設置された公的な施設です。
関係機関との連携体制も整えられているため、発達障害に関する困りごとがある場合は、まずは各地域の発達障害者支援センターに相談すると良いでしょう。(参考:発達障害者支援センター・一覧 | 国立障害者リハビリテーションセンター (rehab.go.jp))
⚫️精神保健福祉センター
– 精神保健福祉センターは、精神疾患など関する問題をサポートするための施設です。
精神障害を持つ方の社会復帰などもサポートしているため、依存症状が強い場合や引きこもりの状態にある場合は、精神保健福祉センターに相談するのも良いでしょう。(参考:全国精神保健福祉センター一覧│全国精神保健福祉センター長会 (zmhwc.jp))
⚫️教育支援センター
– 教育支援センターは各教育委員会が設置する機関であり、保護者向けの相談や教員向けの研修などを行っています。
お子さまの教育に関する様々な相談を行うことができ、電話相談が可能な施設も多くなっています。
特に、学力や不登校など、学習面や学校に関して困りごとがある場合に相談すると良いでしょう。

発達障害のスマホ依存に関するまとめ
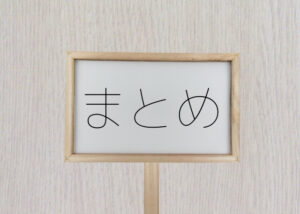
この記事では、発達障害のお子さまのスマホ依存について詳しく解説してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 発達障害のお子さまは、スマホ依存になりやすい性質を持っている
- 発達障害のお子さまは「強い刺激を求める」「物事に集中しづらい」「切り替えが苦手」「日常生活でストレスを溜めやすい」ことなどから、スマホ依存になりやすいと考えられる
- スマホ依存は、脳の快感がクセになるために生じる
- スマホ依存の特徴には、「スマホを手放すのが不安」「食事や入浴の際もスマホを手放せない」「スマホに熱中して寝不足になる」などがある
- スマホ依存によって、「イライラする」「集中力や記憶力が低下する」などの症状が現れることがある
- スマホ依存への対処法には、「ルールを決める」「SNS以外の居場所を作る」「デジタル・デトックスを行う」などがある
- 重度のスマホ依存で引きこもりになった場合は、速やかに専門機関に相談する
誰しもついついスマホを触ってしまうことはあり、使用を一切禁止するのは難しいものです。
少しずつルールを作ったり、家族全員でスマホを離れる機会を作ってみたりと、お子さま本人が納得しながら使用時間を減らしていけるような工夫が必要です。
また、ご家庭だけで問題を解決するのが難しく、困りごとが大きい場合は学校や専門機関に相談することも大切です。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、受験に向けた学習指導のほか、お子さまの勉強習慣の定着や日常生活の困りごとのご相談まで幅広く承っています。
長年の経験に基づく確かなノウハウと、一人一人に寄り添う丁寧な姿勢を強みに、全力でお子さまをサポートしてまいります。
発達障害のお子さまの勉強のことや、学校やご家庭での過ごし方についてお悩みの方は、ぜひプロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。

指導や面談はオンラインでも承っています。
遠隔地からもご利用いただけるほか、これまで海外にお住まいの方や帰国子女の方からもご利用いただき、ご好評をいただいてきました。
オンラインで授業を受けられるか心配な方も、初回のご相談や授業は無料でお試しいただけますので、気軽にご相談ください。

1人でも多くのお子さまが、心身とも健やかに成長していけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。





