【小学生・10歳保護者必見】発達障害チェックリスト保存版|診断前のサインを年齢・特性別30項目で解説
- 発達障害の種類にはどんなものがある?
- 発達障害の子どもの特徴は?
- 子どもが発達障害かどうか、チェックリストで確かめたい
周りの子どもと比べて苦手なことが多かったり、変わった行動が目立ったりするため、「もしかしてこの子は発達障害なのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。
↓ すぐにチェックリストを見たい方はこちらから ↓
発達障害とは、生まれつきの脳の性質であり、保護者さまの育て方は関係が無いことが分かっています。
また、お子さま本人の努力不足やわがままによるものでも無いため、叱ったり、単純な反復練習を繰り返したりしても、特性そのものを改善することはできません。
発達障害の特性そのものを無くすことはできませんが、発達障害に伴う困りごとについては、お子さまの特性を正しく見極め適切なサポートを行うことで小さくすることができます。
療育を行うことによって、お子さまそれぞれに応じた特性への向き合い方や対処方法を学ぶことができますし、周りの環境を調整することによっても困りごとを軽減することができます。
私は、発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として、長年にわたり活動してきました。
1500人以上のお子さまをサポートする中で、誰一人として同じ特性を持ったお子さまはおらず、一人ひとりに合わせた支援を行うことの重要性を実感しています。
発達障害だからといって、将来を悲観する必要はありません。
発達障害の診断を受けた方で、社会で大きく活躍されている方はたくさんいらっしゃいますし、小中学生の6.5%が発達障害であるという調査結果もある現代において、発達障害は特別なものではなく、当然に想定されるものとして付き合っていく必要があると考えています。(参考:通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について:文部科学省 (mext.go.jp))
私が支援してきたお子さまの多くも、無事に第一志望の学校に合格し、社会へと羽ばたいていきました。
無理に特性を無くそうとするのではなく、特性と上手く付き合いながら、お子さまが健やかに成長していくためのサポートや育て方のコツなどについて、この記事では詳しくご紹介していきます。
この記事はこんな方におすすめ
- 発達障害の子どもへの接し方を知りたい
- 発達障害の子どもが学力面で伸び悩んでおり心配
- 発達障害の子どもの中学受験、高校受験、大学受験にはどう対策すればよい?
▼目次
発達障害の「困り感」とは?診断前の保護者の悩み
この章では、発達障害の概要と種類を解説していきます。また、発達障害の種類ごとに簡単なチェックリストも作成しました。
「もしかして発達障害かも?」と感じておられる方は、ぜひご活用いただければと思います。
発達障害の種類と特徴
主な発達障害の種類としては、「ADHD」「ASD」「LD」の3つが挙げられますが、さらに「チック症」「吃音」「発達性協調運動障害」なども発達障害に分類されることがあります。
以下では、それぞれの特徴について説明していきます。
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDの特性は、「不注意」と「多動性・衝動性」の2つです。
不注意と多動性・衝動性の両方が顕著に現れるお子さまもいれば、不注意だけ、多動性・衝動性だけ、といった現れ方の場合もあります。
不注意の特性がある場合には、物事に集中しづらかったり、ケアレスミスが多かったりといった行動が見られます。
多動性・衝動性による行動としては、同年代の子どもと比べて著しく落ち着きが無かったり、待つのが苦手で順番抜かしをしてしまうなどの行動が見られます。
ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)
ASDの特性は、「コミュニケーションの困難」と「限定された興味・こだわり」です。併せて、感覚の過敏さが見られるケースもあります。
コミュニケーションの困難については、微妙なニュアンスを読み取るのが苦手で場違いな発言をしてしまったり、相手の表情から感情を読み取ることが苦手などの特徴が見られます。
限定された興味・こだわりについては、特定の物事に強い関心を持ち、膨大な知識を蓄えるなどの行動のほか、自分なりのこだわりが強く、こだわりが実現できないと癇癪を起こしてしまう等の場合もあります。
LD(学習障害、限局性学習症)
学習障害(LD)とは、知的な遅れや、視覚・聴覚に障害が無いにもかかわらず、「読み」「書き」「計算」など特定の学習技能だけが困難となる症状のことを指します。
吃音
吃音とは、言葉をスムーズに発することが難しい状態を指します。話し始めの音を繰り返したり、音が伸びたり、音を発するのが難しいなどの症状が見られます。
チック症
チック症とは、本人が意図していないにも関わらず、発声や素早い身体の動きを繰り返してしまう症状のことです。
咳払いやまばたきなど、一時的な音声チック・運動チックが子どもの頃に現れることはよくあるため、経過観察で問題が無い場合も多いです。
様々な種類の音声チックや運動チックが強い程度で1年以上続き、日常生活に支障がある場合は「トゥレット症候群」と呼ばれ、治療を検討していくことになります。
発達性協調運動障害(DCD)
発達性協調運動障害とは、手先を細かく動かす作業や、全身を動かす運動など、身体を動かすこと全般が極端に苦手な状態を指します。
運動機能自体には問題が無いものの、それぞれの動きを統制する脳の働きが弱いことが原因と考えられており、ADHDやLDとの併発が多いことも注目されています。
【全体概要】発達障害チェックリストの正しい活用法
発達障害の分類は「1.1 発達障害の種類と特徴」で述べたとおりですが、それぞれの発達障害の特性から見られる行動について、以下のチェックリストにまとめました。
医師や専門機関を受診する際の目安として活用していただくほか、医師や心理士に日頃の困りごとや成育歴を伝える際のガイドラインとしても利用していただけます。
「いざ受診しても、何を伝えれば良いのか困ってしまう」という声も保護者さまから多くお聞きしますので、以下のチェックリストを参考に、医師に伝えたいことをリストアップし、メモしておくことなどをおすすめします。
なお、発達障害の診断は、日頃の様子や成育歴、知能検査(WISC-IVなど)の結果を医師が総合的に診て判断するものですので、安易な自己診断は避けていただければと思います。
ADHD(注意欠如・多動症)
- 食事の時や授業中など、椅子にずっと座っていられずに立ち歩いてしまう
- 貧乏ゆすりや爪噛みなど、いつも身体のどこかを動かしている
- 気になるものがあると衝動的に動いてしまい、道路への飛び出しなど危険な場面が多い
- 忘れ物や失くし物が多い
- 整理整頓が極端に苦手
- 宿題をしていても、いつの間にか別のことをしている
- 空想に耽り、ぼーっとしてしまうことがある
- 話の内容があちこちに飛ぶ、思いついたままにおしゃべりしてしまう
ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)
- 後追いや指さしが少ない
- 一人遊びを好み、周りの子どもに興味を示さない
- いつもと同じであることへのこだわりが強い(服やおもちゃ、通学路など)
- スケジュールが急に変わるとイライラしたり、パニックになったりする
- 数字に強い興味があり、時刻表や車のナンバーに注目する
- 言外に含まれたニュアンスが受け取れず、見当外れの受け答えをする
- 自分の好きな話を一方的にする
- 大きな音や強い光が苦手
- 特定の質感の服を嫌がる
- 偏食が激しい
LD(学習障害、限局性学習症)
- 音読すると、年齢不相応にたどたどしい
- 文字を指でなぞりながら読む
- 形の似た文字(「る」「ろ」、「ぬ」「め」など)を書き間違える
- 枠の中に文字を収めることができない
- 学年が上がっても指を使って計算している
- 繰り上がり、繰り下がりの計算ができない
- 九九が覚えられない
吃音
- 言葉の繰り返し、引き伸ばし、つまりがある
- 発音が苦手な音がある
- 顔をしかめながら話す
- 話すのを嫌がる、人前で話す場面を避ける
チック症
- 頻繁にまばたきや咳ばらいをする
- 急に頭を振ったり、手足を伸ばしたりする動きがある
- 唐突な発声を何度も繰り返す
- 急な動きや発声を繰り返す症状が1年以上続いている
発達性協調運動障害(DCD)
- 何もないところで躓いたり、転んだりする
- 人や物によくぶつかる
- 筆圧が強すぎるか、弱すぎる
- はさみを使うのが苦手
- 箸、スプーン、フォーク、コップなどが上手く扱えず、よく食べこぼす
- 片足立ちができない
- ボールを投げるとき、上半身だけで投げる(逆足を踏み出さない)
👉 年齢・学年から気になる行動をチェックしたい方は、こちらをご覧ください。
【保存版】年齢別 発達障害チェックリスト(6歳〜15歳)
「発達障害かもしれない」と感じた時、年齢によって気になる行動の現れ方は変わってきます。
この章では、ADHD・ASD・LDなどの発達特性に基づき、年齢や学年別に「よく見られる行動例」を整理しました。
※いずれも診断を確定するものではなく、相談のきっかけや情報整理の参考としてご活用ください。
▼ 気になる年齢をクリックしてください
小学1〜2年生(6〜7歳):多動・衝動のピークと特性の見極め
- 授業中、椅子にじっと座っていられない(ADHD)
- 先生の話を聞いていないように見える(ADHD)
- 一人遊びばかりで、友達と遊ぼうとしない(ASD)
- 音読が極端にたどたどしい(LD)
- 急な予定変更でパニックになる(ASD)
- 食事中に頻繁に食べこぼす、箸がうまく使えない(DCD)
小学2〜4年生(8〜10歳)
- 忘れ物や落とし物が多い(ADHD)
- 集団行動のルールが理解できず、トラブルが増える(ASD)
- スケジュールや持ち物の変化に過敏(ASD)
- 形の似た文字(ぬ・め等)を間違える(LD)
- 授業の指示が伝わりにくく、的外れな行動をする(ASD)
- 体育や図工などでの不器用さが目立つ(DCD)
小学5〜6年生(10〜12歳):複雑な指示・集団行動でつまずく子への対応
- 友人関係がうまくいかず孤立しがち(ASD)
- 計算問題はできるが、文章題になると解けない(LD)
- 話が飛びがちで、会話がかみ合わない(ADHD/ASD)
- こだわりが強く、納得できないと感情的になる(ASD)
- 体育の評価が著しく低い、不器用でよく転ぶ(DCD)
- 「読んで考える」問題になると著しく苦手意識を示す(LD)
中学生(12〜15歳)
- 定型的な会話が成立せず、誤解を招く(ASD)
- 自己管理が苦手で、宿題や提出物を忘れがち(ADHD)
- 周囲とのトラブルが続き、学校への不安が強くなる(ASD)
- 音読や書字に顕著な困難があるが、知的には問題ない(LD)
- チック症状が目立ち始め、周囲の注目を気にする(チック)
- 手先の不器用さで技術・家庭科の課題が苦手(DCD)
【専門家の視点】特性別に見る「困りごと」と「今すぐできる接し方」
この章では、それぞれの発達障害に伴う困りごとと支援方法について説明していきます。
お子さまに当てはまる症状や関心のある項目からご覧ください。
①ADHD(注意欠如・多動症)
ADHDのお子さまは、「集中できない」「落ち着きがない」といった特性から、学校生活や家庭で困りごとが現れやすくなります。
この章では、ADHDに伴う代表的な悩みと、その対応方法について解説します。
困りごと
ADHDのお子さまの困りごととしては、多動性・衝動性が要因となって、授業中の立ち歩きやおしゃべりが止められない、順番抜かしをしてしまうなどがあります。
学校ではルールを守って集団生活を送ることが求められますので、これらの行動は問題行動として叱責されてしまう場合があります。
ただし、ADHDの多動性・衝動性の特性は、年齢とともに落ち着いていく傾向にあります。
道路への飛び出しや衝動的な暴言・暴力など、自分や他人を傷つける可能性のある行為は抑えていく必要がありますが、貧乏ゆすりや立ち歩きなど日常生活への支障がそれほど大きくないものについては、過度に叱らず見守る方が良い場合もあります。
ADHDの特性のうち、不注意特性については大人になっても継続しやすく、仕事や日常生活で困りごとを伴うケースが多くなっています。
子どもの頃の困りごととしては、勉強に集中できない、整理整頓が苦手、忘れ物や失くし物が多いといったことになりますが、先生や保護者のサポートがあればある程度解消できるものが多く、「学生時代はそれなりに過ごせた」という人も一定いらっしゃいます。
大人になると、子どもの頃に比べて周りのサポートが受けられなくなるほか、自分で段取りを立てて問題を解決することが求められます。
ADHDの不注意特性を持つ人はあちらこちらに注意が散漫としてしまうため、「何から手を付けて良いかわからない」「最後までやり抜けない」といった状態になり、仕事や家事が上手くこなせず、挫折を感じる人が多くなっています。
気分の落ち込みや不安感、双極性障害などの精神的な不調を伴うことがあるほか、仕事や日常生活が上手くいかないストレスから、うつ病や適応障害などの二次障害を抱えることもあります。
子どもの頃に診断を受け療育などに取り組んでいれば、自分の特性を上手くコントロールする方法を身につけた状態で社会に出ることができます。
大人になってからでも診断を受けることはできますが、できる限り早い段階から特性を把握し、自分なりに対処する方法を身につけることが望ましいでしょう。
支援方法
ADHDのお子さまに接する際には、「あれはダメ」「それはしないで」とダメな行動を指摘して減らすのではなく、「○○してほしいな」「○○できたね、すごい!」など、褒めながらしてほしい行動を増やしていくことがポイントです。
やってはいけないことだと理解していても、立ち歩きやおしゃべりをコントロールできないのがADHDの特性です。
過度に叱責しても自信を無くしたり、信頼関係が崩れてしまったりするだけですので、「どうしてできないの!」など、本人を否定するような言い方はできるだけ避けましょう。
勉強に集中してほしいときは、本人が集中しやすい環境を整えてあげましょう。
一緒に部屋を片付けたり、テレビを消したり、話し声もできるだけ小さくするなどが効果的です。
また、一度に長時間集中させるのではなく、時間を決める場合は短時間に、課題の量を決める場合は少なめに設定し、休憩をこまめに挟むのもポイントです。
やることが複数あり、何から手を付けていいかわからなくなっている時は、大人が一緒にTo Doリストを作ってあげると良いでしょう。
頭の中だけでやるべきことを整理するのが苦手なお子さまでも、リスト化することで視覚的に把握でき、優先順位をつけて取り組むことができます。
ADHDのお子さまに対して、ついつい否定的な言葉で怒ってしまったりすることもあると思います。
「褒めながら伸ばす」というのは非常に難しいものであり、意識していても簡単にできるものではありません。
ADHDに関する知識を身につけ、日々少しずつ慣れていくことが必要ですが、ADHDのお子さまを持つ保護者同士で交流したり、ペアレント・トレーニングを受けたりすることにより、さらに効果的にお子さまへの対応スキルを身につけていくことができます。
また、ご家庭だけで悩みを抱えず、担任の先生やスクールカウンセラー、療育の先生や主治医など、多くの人と協力しながらお子さまをサポートしていくことを心掛けましょう。
これらのサポートを行っても日常生活での困りごとが大きい場合は、並行して薬物療法に取り組むことがあります。
ただし、薬物療法は症状を緩和するだけで、特性そのものが根本的に無くなるわけではありませんので、効果と副作用のバランスを見ながら慎重に取り組む必要があります。
👉 ADHDの薬物療法について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
②ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)
ASDのお子さまは、コミュニケーションのズレや強いこだわりから、集団生活でのトラブルが起きやすい傾向があります。
ここでは、ASDの特性に起因する困りごとと、日常でできる支援方法を紹介します。
困りごと
ASDのお子さまは、幼い頃から「目線が合わない」「笑わない」「指さしや後追いをしない」といった特徴が見られることが多くなっています。
幼稚園や保育所に入ってからも、他の子どもに興味を示さず一人遊びが多いこと、癇癪をよく起こすことなどから、小学校入学前にASDであると診断されるケースもあります。
言葉の遅れについては個人差があり、言葉の遅れが全く見られないケースもあります。ですが、自分の興味のあることだけを一方的に話し、会話がキャッチボールにならないなどの傾向は、ASDのお子さまの多くに見られます。
「いつもと同じであること」へのこだわりが強く、通学路が変わっただけでパニックになってしまったり、新しい服を着ることを嫌がり、ボロボロになっても同じ服を着るなどの行動が見られます。
事あるごとに癇癪を起こしてしまうお子さまもおり、保護者さまが疲弊するケースも多くなっています。
また、新しい環境に馴染むのが苦手で、幼稚園から小学校、小学校から中学校に上がるタイミングでの登校渋りなどが見られることもあります。
小学校低学年くらいまでは、こだわりの強さに伴う精神面の不安定さや集団生活への馴染みづらさが主な困りごとになりますが、小学校高学年くらいからは、コミュニケーションの困難に伴う人間関係での悩み事が多くなっていきます。
クラスメイトとの会話が噛み合わず友達ができづらかったり、冗談や皮肉が伝わらず関係がぎくしゃくしてしまったりするほか、ASDのお子さまは言われたことをそのまま受け取ってしまう傾向にあることから、「お金をくれたら友達になってあげる」という言葉を鵜吞みにし、金銭的な被害を受けるケースもあります。
臨機応変さや高いコミュニケーション能力を求められる職種はASDの方には不向きなため、自分のペースで淡々と取り組める職業を早いうちから検討していくことが望ましいでしょう。
進路選択においても、経理やエンジニアなど、コミュニケーションがあまり必要とされない仕事に就くことを想定して進学先を検討すると良いでしょう。
支援方法
ASDのお子さまは、幼少期から個別や少人数での療育を行い、少しずつ対人スキルを身につけていくことになります。
例えば、会話はキャッチボールであるということを知るために、実際にボールを受け渡ししながら「ボールを持っている人がしゃべる番」というルールで先生とお話をします。このトレーニングを繰り返すことで、徐々にボールが無くても交互に発言しながら会話できるようになります。
定型発達の人は、“人と会話するときは交互に発言する”というルールを自然と身につけることができますが、ASDの方の場合はしっかりと視覚化・言語化して伝えることが必要です。
また、イレギュラーな出来事に対する苦手さも、イラストなどを用いて視覚的に説明し、先の見通しが持てるようにすることで、「普段と違うことが起きても、説明してもらえれば大丈夫」という状態を目指します。
ASDのお子さまの子育てにおいては、「指示が通りにくい」というのも大きな困りごとの一つです。これは、ASDのお子さまが言外の意味を読み取ることが苦手なことに起因します。
例えば、「ちゃんと片付けて」と保護者さまが指示しても、ASDのお子さまは意図を汲み取ることができません。ASDのお子さまに指示する時は、「床の絵本を本棚にしまって」など、具体的に伝える必要があります。
ASDのお子さまは、コミュニケーションの困難や激しい癇癪を伴う場合があることから、保護者さまも精神的に大きな負担を感じる場合があります(カサンドラ症候群※)。我が子と心が通じていないのでは?という不安がある場合は、主治医や心理士に相談するようにしましょう。
ご家庭だけで抱え込むことなく、医師や学校の先生などを上手く巻き込みながらお子さまを支えていくようにしましょう。
また、ASDそのものを治療する薬はありませんが、ASDに伴う不安障害やうつ症状、てんかん、睡眠障害を改善するための薬が処方されることがあります。
療育や環境の調整によってもなかなか改善が見られない場合は、医師とも相談しながら服薬を検討するのも良いでしょう。
③LD(学習障害、限局性学習症)
読み書きや計算など、特定の学習面でつまずきが出るのがLDの特性です。
この章では、学習面の具体的な困りごとと、それに合わせた支援方法をお伝えします。
困りごと
LDは、知的な遅れが無いにもかかわらず、読み・書き・計算のいずれか又は複数に著しい困難が見られる発達障害のことです。
読むことや書くことに困難がある場合は、学校の勉強が全般的に苦手になり、学力が伸び悩むことになります。
ただし、小学校2年生くらいまでは記憶力でカバーするお子さまも多く、また、周りのサポートも手厚いために特性が目立たないケースがあります。
例えば、音読するのが苦手なお子さまでも、文章を丸暗記することでスラスラと読んでいるように見えることがあります。計算が苦手で繰り上がり・繰り下がりができない場合も、計算式を暗記して対処するお子さまなどがいらっしゃいます。
ですが、小学校高学年以降になると、記憶力だけでカバーすることが難しくなります。
問題文を読んで自分で考えることが必要になるため、学習障害のお子さまは「問題文を読む」という時点でつまずいてしまうほか、算数の文章題などは太刀打ちできないという状態になります。
学習障害のお子さまは、知的な遅れがあるわけではありません。
そのため、問題文を大人が読み上げてあげれば理解できたり、算数以外の教科は全く問題無かったりといったケースがほとんどです。
学習障害は症例が少なく、支援方法も確立されたものがありません。一般的な認知度も低いため、「本人の努力不足」「練習すればできる」といった誤った指導が行われることもしばしばあります。
やみくもな反復練習は、ますます勉強を嫌いになってしまうだけですので、本人に合わせた適切なサポートを行う必要があります。
支援方法
読みの困難がある場合は、文字を大きくしたり行間を広くしたりして、まずは文字を視認しやすくする工夫を行います。
視覚的な問題とともに、音韻処理(文字と音を結びつける脳の働き)に問題がある場合は、文節ごとに線を入れながら読むなどのトレーニングを重ねることで、単語や文章をまとまりとして捉えることに慣れていきます。(※)
書きの困難がある場合は、大きなマス目のノートを使い、なぞり書きから始めます。
書きの困難には、「視覚認知の弱さ」「手先の不器用さ」「音韻処理の問題」が関係していると考えられることから、まずは「書く」という感覚に慣れていきます。
なぞり書きの次は、手本を見ながら書き写す「模写」の練習を行います。
この時、まだ書く感覚に慣れきっていない場合は、紙の下にやすりやサンドペーパーなどざらざらした質感のものを敷くなどして、さらに書く感覚を馴染ませていきます。
模写の次に、音で聞いた文字を書く「聴写」を行います。聴写が問題無くできれば、書きの困難は概ね解消できたと言えます。
ただし、大人になってからは手書きで文字を書く機会は非常に少なくなるため、無理に書きの困難を解消する必要性は低いとも考えられます。お子さまの負担感が大きい場合は、無理に書く練習はせず、将来を見据えてキーボードのタッチタイピングの練習をするなども検討していきましょう。
計算に困難がある場合は、量よりも質を重視した練習が必要です。
たくさんの問題を解くのではなく、簡単な問題を一つ一つ丁寧に解説し、本人が納得できるまでじっくり取り組むようにしましょう。時間はかかるかもしれませんが、根気よくサポートするとともに、本人が「できた!」と感じる感覚を大切にしましょう。
計算についても、大人になれば電卓を使うことができますし、日常生活においては簡単な繰り上がり・繰り下がりさえできれば問題ありません。
こちらも本人の負担感を鑑みて、無理の無いように取り組むことが大切です。
④吃音
吃音は、言葉が詰まったり繰り返されたりすることで、対人関係や自己肯定感に影響を及ぼすことがあります。
ここでは、吃音のあるお子さまへの理解と、家庭でできるサポートの工夫についてまとめます。
困りごと
吃音は、言葉に詰まったり繰り返したりといった特徴から、いじめやからかいの対象となってしまうケースがあります。
いじめやからかいについては、周りの子どもたちへの適切な指導によって改善することができますが、中には先生自身が吃音に対して誤った認識を持っている場合があります。
吃音は体質的な要素が大きく、本人の努力不足や精神的な弱さ、親の育て方に起因するものではありません。
ですが、理解の無い指導者の場合は、「たくさん音読すれば治る」「自信を持てば良い」といった誤った指導を行うケースがあります。
学校には、担任の先生だけでなく、吃音について正しい知識を持っている先生(養護教諭やスクールカウンセラー)がいますので、指導に疑問を感じたときは他の先生に相談したり、地域の発達支援センターや教育委員会に相談するようにしましょう。
また、本人が吃音を気にして孤立したり、人前で話したりする機会を避けてしまうケースもあります。
無理して人と話す必要はありませんが、自分を責める必要は無いこと、引け目を感じることではないことについては、保護者さまからしっかりと伝えてあげていただければと思います。
吃音の支援方法
就学前のお子さまの吃音は、時間の経過とともに改善する場合が大半です。
ですので、幼い頃はあまり神経質にならず、なかなか改善されないようであれば健診の際に相談したり、発達支援センターに問い合わせたりして、治療を検討すればよいでしょう。
吃音の治療については、言語聴覚療法や認知行動療法を行うことになります。例えば、お子さまの場合は「リッカムプログラム」と呼ばれる療法を取り入れるクリニックが増えてきています。
リッカムプログラムとは、スラスラと言葉が発せた場合に褒め、言葉に詰まったら中立的に指摘することを1日15分、褒めるのと指摘するのとを概ね「5:1」の割合で行うトレーニングです。
指摘よりも褒める頻度を増やすことがポイントであり、言語聴覚士が保護者さまに定期的に助言しながら進めていきます。
⑤チック症
意図しない発声や身体の動きが繰り返されるチック症は、本人にも周囲にも誤解を生みやすい特性です。
この章では、チック症による困りごとと、学校や家庭での関わり方について解説します。
困りごと
チック症は、本人の意志とは関係なく、突発的な運動や発声が反復して起こります。
そのため、静かにしなければならない場面でも声を出してしまったり、顔をしかめる反復行動によって相手に誤解を与えてしまったりといった困りごとが生じます。
また、手先が震えるようなチックの場合は、物をよく落としてしまうといった物理的な困りごとがあるほか、頭を振るチックの場合は頭痛や肩こりで悩むケースもあります。
支援方法
子どものチック症は一過性の場合が多く、経過観察で問題が無いケースも多くなっています。
10~15歳くらいで症状が一番強くなり、成人するまでに落ち着くことが多い一方、大人になってからも症状が続く場合があり、長期的に続く場合は「トゥレット症候群」と呼ばれます。
トゥレット症候群は体質的なものであり、本人の意志で制御することはできません。まずは、周りの人がそれを理解することが大切です。
行動療法としては、チックが現れそうになった時に、拮抗する動きを取る方法(ハビットリバーサル)などがあります。
また、薬物療法としては、トゥレット症候群に有効性が認められた薬は無いものの、統合失調症の薬が効果的であることが知られています。
⑥発達性協調運動障害(DCD)
DCDのお子さまは、運動や手先の作業が極端に苦手で、「不器用」と言われやすい傾向があります。
ここでは、身体の動かし方に困りごとがあるお子さまへの配慮と支援の視点をまとめます。
困りごと
発達性協調運動障害のお子さまは、手先を動かす細かい作業や全身を大きく使う運動など、身体を動かすことが全般的に苦手です。
そのため、よく転んだり躓いたり、物にぶつかったりするなど、ケガの危険が大きいほか、体育の授業に付いていけず成績が下がってしまったり、「不器用」「鈍くさい」と言われて自己肯定感が下がってしまう等の困りごとを抱えることがあります。
また、手先が不器用なことから、文字が上手く書けず、書字障害の症状が出たり、塗り絵や工作といった作業も苦手で自信を無くしてしまうケースがあります。
不器用であることは、勉強面でも生活面でも大きなコンプレックスとなる場合があり、本人の自己肯定感については丁寧に見守る必要があります。
支援方法
学校現場では、字がきれいに書けなかったり、縄跳びが飛べなかったりするお子さまに対して、「練習が足りないからだ」「もっと練習しなさい」と単純な反復練習を強いる指導が多く行われています。
ですが、発達性協調運動障害は、その他の発達障害と同様に生まれつきの特性であり、反復練習によって改善されることはありません。
強く叱責したり、出来るまで居残りさせたりするような指導は、本人に挫折感を与え、自尊感情を傷つけるだけです。
身体を動かすことが嫌いなお子さまはいませんので、まずは身体を動かすことを楽しみながら、手足や目線の動かし方などを一つずつ丁寧に伝えていき、少しずつできることを増やしていくことを目指しましょう。
診断の考え方と学校・外部機関への相談ロードマップ
この記事では、発達障害に関するチェックリストをさまざまな角度からご紹介してきました。
チェックリストを活用する際は、単に当てはまる項目の数を気にするのではなく、「困っていることがあるかどうか」を基準に考えることが大切です。
たとえ複数の項目に当てはまっていたとしても、日常生活や学校生活に支障がなければ、すぐに診断や支援が必要というわけではありません。
一方で、学校でのトラブルが続いていたり、ご家庭での関わりにお悩みがあったりする場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
- 発達支援センターや子ども家庭支援センター
- かかりつけの小児科、児童精神科などの医療機関
- スクールカウンセラーや特別支援教育コーディネーター
- 教育委員会の就学相談窓口
- 発達障害に詳しい家庭教師・学習支援サービス
「誰に相談したらいいか分からない」「どの支援が合っているのか分からない」と迷われる保護者さまも少なくありません。
一人で抱え込まず、まずは信頼できる大人や専門家に一歩踏み出して相談することが、最初の大切なステップになります。
プロ家庭教師メガジュンでは、無料のご相談も承っております。チェックリストを通して気になることがあれば、ぜひお気軽にお話しください。
発達障害の子どもチェックリスト(特性別・年齢別)のまとめ
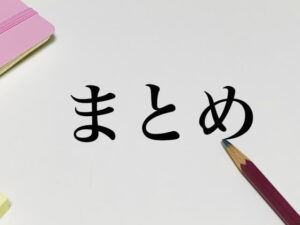
この記事では、発達障害の子どもの特徴や支援方法について詳しくお伝えしてきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 主な発達障害はADHD、ASD、LDの3つであり、吃音やチック症も発達障害に含まれる
- 発達障害には発達性協調運動障害を伴うことが多い
- ADHDの特性は「不注意」と「多動性・衝動性」であり、大人になってからは不注意特性で悩む人が多くなっている
- ASDの特性は「コミュニケーションの困難」と「限定された興味・こだわり」であり、幼い頃から療育に取り組むことで困りごとを改善することができる
- LD、吃音、チック症、発達性協調運動障害については、周りの人が特性をきちんと理解し、適切にサポートすることが大切
発達障害と一口に言っても、様々な分類があり、持っている特性も一人ひとり違います。
ですので、基本的な知識を持ちながらも、目の前のお子さまをしっかりと見て、それぞれに合った支援を行うことが大切です。
私たちプロ家庭教師メガジュンは、長年にわたり発達障害のお子さまのサポートを行ってきました。
16年以上の指導経験をとおし積み上げてきたノウハウと、一人ひとりに寄り添う丁寧な姿勢をモットーに、これまで1500人以上のお子さまを支援し、90%以上のお子さまを第一志望合格へと導いてきました。
発達障害のお子さまのサポートには、専門的な知識のある指導者の存在が欠かせません。お子さまの発達障害のことでお悩みの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
また、指導や面談はオンラインでも承っています。関西だけでなく全国各地からご利用をいただけるほか、海外にお住まいの方や帰国子女の方からもこれまでご利用をいただき、たくさんのご好評の声をいただいてきました。
初回のご相談や授業は無料で承っていますので、オンラインで授業が受けられるか不安なお子さまもお気軽にお試しいただくことができます。
1人でも多くのお子さまが、自身の特性と上手く付き合いながら、未来へ大きく羽ばたいていけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。




