アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の中学生の特徴と接し方とは?親ができる支援を解説
- ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生に見られる特徴や特性
- 思春期に差し掛かる中学生のASDのお子さまが抱えやすい困りごと(人間関係、勉強、学校への行き渋りなど)
- 親ができる支援方法や対応策(家庭内サポート、勉強法、進路選びのポイントなど)
- ASDのお子さまに適した学習法や進学に向けたアドバイス
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生のお子さまにおかれては、思春期に差し掛かると人間関係や学校生活において新たな困りごとが現れることがよくあります。
特に、コミュニケーションや集団生活でのストレスが増すため、親としてのサポートがますます重要になります。
私は発達障害専門のプロ家庭教師として活動している中で、多くのASDのお子さまが学校生活に適応するのに苦労している場面に出会いました。特に、中学校進学を機に「勉強についていけない」「友達と上手くコミュニケーションが取れない」「学校に行きたくない」といった悩みを持たれる方はたくさんいらっしゃいます。
この記事では、ASDのお子さまへの支援方法や、家庭でできるサポートを具体的に解説していきますので、ぜひ最後までお読みいただければと幸いです。
この記事はこんな方におすすめ
- ASDの中学生を持つ保護者さま
- 思春期に差し掛かったASDのお子さまの困りごとや支援方法に悩んでいる方
- 中学生のお子さまが学校に行きづらくなっている、または勉強に苦労していると感じている保護者さま
- 高校進学や将来の進路について考え、早めに対策を立てたいと考えている方

発達障害専門の受験プロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▼目次
- 1 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生の特徴
- 2 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生の困りごと
- 3 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生への支援のポイント10選
- 3.1 ASDの中学生への支援のポイント①家族は味方だと伝える
- 3.2 ASDの中学生への支援のポイント②家庭だけで抱え込まない
- 3.3 ASDの中学生への支援のポイント③柔軟性を身につける
- 3.4 ASDの中学生への支援のポイント④ルールを統一する
- 3.5 ASDの中学生への支援のポイント⑤「断り方」と「絶対にしてはいけないこと」を知る
- 3.6 ASDの中学生への支援のポイント⑥進路を早めに調べる・決める
- 3.7 ASDの中学生への支援のポイント⑦勉強をルーティン化する
- 3.8 ASDの中学生への支援のポイント⑧学校に行きたがらないとき
- 3.9 ASDの中学生への支援のポイント⑨性の正しい知識を知る
- 3.10 ASDの中学生への支援のポイント⑩保護者さま自身が知識を身につける
- 4 アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の中学生の特徴と接し方のまとめ
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生の特徴
この章では、ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の定義や特徴について説明していきます。
既に十分な知識をお持ちの方は、「2.ASDの中学生の困りごと」までお進みください。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)とは
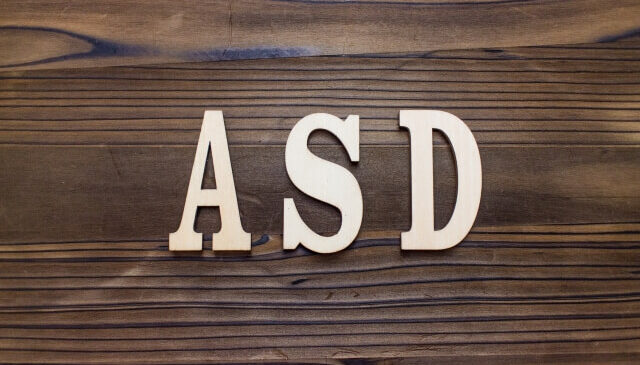
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)とは、発達障害の一つであり、
- 対人関係やコミュニケーションが苦手
- こだわりが強く、興味が極端に限定されている
といった特性があります。
アスペルガー症候群という名称は、「自閉スペクトラム症(ASD, Autism Spectrum Disorder)」に統一されたため、正式な診断名としては現在ではほとんど使われていません。
一方で、アスペルガー症候群という名称は一般に広く浸透しているため、両方の名称が併記されている場合も多いです。
自閉スペクトラム症の「スペクトラム」とは「連続している」という意味で、自閉症や高機能自閉症、アスペルガー症候群などはすべて自閉スペクトラム症(ASD)に含まれます。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の診断とグレーゾーン

ASDの診断の際には、こだわりの強さや興味の限定性といった条件が診断基準となります。
例えば、アメリカ精神医学会の「DSM-5」による診断基準では、
- コミュニケーションや対人関係の持続的な困難
- 限定された興味や反復行動
- 発達早期の段階で特性が出現する
- 社会生活において重大な困難が引き起こされている
といった条件が挙げられています。
知能検査や発達検査、日常の行動についての質疑応答などを行い、医師がASDかどうか総合的に判断し、確定診断を行いますが、ASDの特性には連続性(グラデーション)があり、すべての条件に100%当てはまるケースは多くありません。
そのため、確定診断には至らず、いわゆる“グレーゾーン”が多いのもASDの特徴の一つです。
人間関係やコミュニケーションで困りごとが多く、「もしかしてASDかも?」と思った場合は、以下のチェックリストなどを参考にしていただき、当てはまる項目が多いときは受診を検討すると良いでしょう。
- 曖昧な言葉(「適当に」「もう少し」など)が理解できない
- 言外に含まれている意味が読み取れない(=行間が読めない)
- 表情や雰囲気から相手の気持ちを読み取れない(=空気が読めない)
- 言い方が失礼だと指摘されることがある
- 物事には一人で取り組むのが好き
- 同じ方法を繰り返す方が好き(違う方法には挑戦したくない)
- 没頭すると周りが見えなくなる
- 小さな物音でも気が散ってしまう
- 車のナンバーや時刻表など、数字の羅列に惹かれる
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生の困りごと

この章では、ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生の困りごとについて具体的に解説していききます。
ASDの中学生の困りごと①思春期に差し掛かる
ASDのお子さまは、コミュニケーションや対人関係が苦手です。
保護者さまであれば、お子さまの特性を理解した上で対応することができますが、同年代のクラスメイトとの会話ではかみ合わなかったり、悪気なく相手を傷つけてしまう発言をしてしまったりと、友達付き合いが上手くいかないケースも少なくありません。
小学校3年生くらいまでは本人が気にしない(気付かない)こともありますが、小学校高学年になり思春期に差し掛かると、周りから「あの子はちょっと変だ」と認識されたりすることも増え始め、本人がそのことを気に病む場面も増えます。
さらに、中学校に進学すると環境やクラスメイトの面子もがらりと変わるため、小学校までは何となく周囲から受け入れられていたことでも、途端にからかわれたり、距離を取られたりといった対応に変わってしまうことがあります。
加えて、ASDのお子さまは感覚過敏や感覚鈍麻の特性を持っていることがあります。
ちょっとした音や匂い、触り心地などの変化にも敏感なお子さまは、ただでさえ疲れやすいことに加え、思春期においては二次性徴といった身体的な変化や性への関心といった内面の変化など、意識することが格段に増えます。
このため、ASDのお子さまは人一倍ストレスを感じることになります。
協調性や友達づくりは大切だと言われますが、一人の方が気楽であるという人もたくさんいます。
ASDのお子さまは、無理に人付き合いするよりも、思春期という時期を心穏やかに過ごすことを優先し、自分が安心して過ごせる時間を作ることを大切にすると良いでしょう。
ASDの中学生の困りごと②勉強が難しくなる

中学生に上がると勉強の内容がかなり難しくなるため、「好きな教科しか勉強したくない」というこだわりが強いASDのお子さまの場合、得意な教科と苦手な教科の差がどんどん開いてしまいます。
また、先生との相性も重要です。嫌いな先生が教える教科は勉強したくないという状態になると、先生が変わったとしても苦手意識が払拭できなかったり、英語などの積み上げ型の教科の場合は、基礎が定着していないために内容が理解できないといった問題が生じることになります。
中学校の定期テストは小学校の単元ごとのテストと違い、範囲も広く難易度も上がります。
不得意な教科で赤点を取ってしまうと、お子さまにとっては精神的なショックがかなり大きく、「自分には無理なんだ」と自信を失ってしまうケースも少なくありません。
自己評価が下がってしまうことは、お子さまの今後の人生にとって大きな影響を与えてしまいますので、まずは勉強に前向きに取り組み、本人が楽しく学べる環境を作ることが大切です。
認知能力の問題で、どうしても国語の読解が苦手であったり、数学の図形の問題が苦手である場合もあります。その際は、無理に点数を伸ばそうとするのではなく、本人の能力の範囲の中でできたことを褒めるようにしましょう。
あるいは、不得意な教科に注目するのではなく、得意な教科を伸ばすことによって、本人の自信につなげることも大切です。
お子さま一人ひとりの性質に合わせて、得意を活かして苦手をカバーする指導を行うことは、学校や塾などの集団指導では難しい面があります。
ですので、できる限り発達障害やASDの特性に知見のある塾やプロ家庭教師に指導してもらうようにしましょう。
ASDの中学生の困りごと③周囲からの見られ方が変わる

お子さまに対して、「中学生なんだからしっかりしなさい」という言葉はついついかけてしまうものです。
ですが、ASDのお子さまにとっては、中学生になった途端にルールが変わったように感じて混乱してしまいます。
例えば、ご近所さんに挨拶をしないなど、小学生までは大目に見られていたことも、中学生になると厳しい目で見られるようになります。
お子さまが周囲の人々と上手に付き合い、社会に出てからも問題無く生きていくためにも、自立した人間としての態度を中学生段階で身につけることはとても大切です。
ASDのお子さまに対しては、「中学生なんだから」といった表現ではなく、どういった態度が望ましいのかを具体的に伝えるようにしましょう。
また、食べ物の好き嫌いや、表情や雰囲気で察することなどは、ASDの特性からどうしても解消できない場合もあります。
中学生になったからといって急に厳しくするのではなく、どうすればできるようになるのか、どうしてもできないときの代替策などを一緒に考えていくことが大切です。
ASDの中学生の困りごと④慣習やマナーの理解が求められる

ASDのお子さまは、慣習やマナーの理解が難しい場合があります。
例えば「身だしなみ」について、私たちは明文化されたルールを持っているわけではありません。「清潔感のある服装」といった表現も、爪を切る・髪を整えるなど、皆が何となく共通理解を持っているだけに過ぎません。
このような、いわゆる“暗黙の了解”を理解することが、ASDのお子さまは苦手です。
制服を着るなど校則のようにはっきりと決まっていることを守ることはできる一方、私服ではTPOに合わせた服装がどのようなものかわからず、小学生の頃に来ていた服をずっと着ていたり、体を動かすアクティビティだからと体操服を着てしまったりといったことが起こります。
中学生になったとしても、「何となくわかるでしょ」はASDのお子さまにとって禁物です。
人前では着替えない、爪は短く切る、髪は朝起きたら梳かすなど、当たり前のことでも一つ一つ具体的に伝えることを心がけましょう。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の中学生への支援のポイント10選

ASDと一口に言っても、お子さまによって持っている特性やその強度、そして困りごとは違います。
思春期に差し掛かり自分と周りの違いを感じて悩んでしまうお子さまもいれば、中学生になっても他人と自分の違いが気にならず、ずっとマイペースなお子さまもいらっしゃいます。
私たち周囲の大人ができることは、やがてお子さまが独り立ちするときに、自分自身の特性を認め、自分の力で対処できる力を身につけられるようサポートすることです。
そのためには、お子さま自身が「自分はきっとできる」という自信と自己肯定感を持つことが何よりも重要です。
また、中学生段階になると、脳の機能そのものを改善するよりも、困りごとの要因を探し、環境の改善や対処法を検討する視点の方が重要になってきます。
例えば、幼児期であれば作業療法やビジョントレーニング(※)を通して、脳の機能そのものの向上を目指すことが療育の中心となります。
しかし、中学生になって脳や体の機能が完成してくると、機能そのものを鍛えることの効果は児童期までと比べて期待しにくくなります。
そのため、中学生段階においては、周囲の環境整備やソーシャルスキルの習得など、社会的なアプローチが重要になります。
こういった観点を踏まえながら、以下ではASDの中学生お子さまをサポートする際のポイントを順にご紹介していきます。
ASDの中学生への支援のポイント①家族は味方だと伝える

「2.ASDの中学生の困りごと」でお伝えしたとおり、思春期に差し掛かったASDのお子さまは大きなストレスを感じるとともに、周りとの違いを感じて孤独感や自己否定に陥りがちです。
ですので、
を伝え続けることが何よりも大切です。
家族だからといって、テレパシーを使うことはできません。
「態度で分かるだろう」「親が子どもを大切に思うのは当たり前だから、わざわざ言わなくても良いだろう」と考えず、具体的に言葉にすることを心がけましょう。
また、日頃からお子さまとの会話を大切にし、ちょっとした変化を見逃さないことが重要です。
ASDの中学生への支援のポイント②家庭だけで抱え込まない

お子さまの困りごとを家庭の中だけで抱え込む必要はありません。
家庭で抱え込むと、保護者さま自身もストレスが溜まり、心身に不調をきたしたり、家庭内の雰囲気が悪くなったりします。
お子さまは一日のうち、多くの時間を学校で過ごします。ですので、学校には積極的にお子さまの状態を伝え、一緒に困りごとを解決していくようにしましょう。担任の先生だけでなく、スクールカウンセラーなども交えて、学校全体で支援することが大切です。
特に、中学校では教科ごとに先生が変わるため、先生間での情報共有が重要です。学校によっては、特別支援教育コーディネーターが配置され、通級指導など特別な配慮が受けられることもあります。
地域の教育支援センターや教育委員会に問い合わせるなど、積極的に情報収集することも大切です。
また、メンタル面で心配なことがあれば、専門の医師や心理士に相談するようにしましょう。
加えて、学力面の心配から塾やプロ家庭教師を利用する場合は、お子さまの特性を踏まえた指導ができる家庭教師や塾を選ぶことが重要です。
講師の中には、お子さまの特性を単なる怠けだと捉えて厳しく指導してしまう人もいるため、初回の面談でお子さまの性質を詳しく伝えるとともに、お子さまの特性を踏まえて指導してくれるかどうかをしっかりと確認して選んでいただければと思います。
ASDの中学生への支援のポイント③柔軟性を身につける

ASDのお子さまは「これくらいは大丈夫だろう」という感覚が乏しく、指示されたルールを徹底的に守る傾向があります。
例えば、先生が1学期の最初に「制服のボタンは第1ボタンまで閉めるように」と指示すると、ASDのお子さまは夏場でもずっとそのルールを守っている、といった状態です。
一方、定型発達のお子さまは、先輩の服装などを見て「第1ボタンを閉める必要は無さそうだ」と察し、式典の時だけ閉める、あるいは厳しい先生の前だけ閉めるといった要領の良さを身につけます。
もちろん、決められたルールを守ることも大切ですが、いつも杓子定規でいる必要はなく、肩の力を抜くことが必要な場面もあります。
ASDのお子さまにケースバイケースの感覚を伝えるのは難しいかもしれませんが、「暑いときはボタンを外しても大丈夫だよ」など具体例を示しながら柔軟性を身につけられるようにしましょう。
ASDの中学生への支援のポイント④ルールを統一する
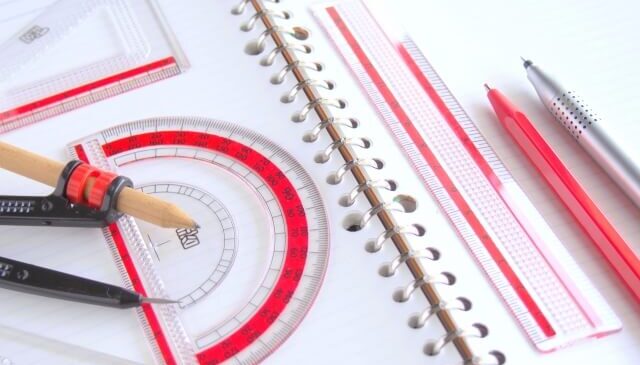
明確なルールがあるほど行動しやすいのがASDのお子さまの特性です。
お父さまとお母さまで注意する基準が違っていると、ASDのお子さまは混乱しストレスになってしまいます。どんな場面で褒め、どの基準で注意するのかを家庭内で統一するようにしましょう。
学校ともルールを統一することが望ましいですが、保護者さまがお子さま1人だけを見ていられるご家庭と異なり、先生1人で30人以上を見ている学校では、対応に限界がある場合もあります。
お子さまが強いストレスを感じたり、癇癪を起こしてしまうような状況は避けなければなりませんが、そうでない場合は、場所や場面によってルールが変わることをお子さま自身に実感してもらう機会として捉えることも大切です。
ASDの中学生への支援のポイント⑤「断り方」と「絶対にしてはいけないこと」を知る
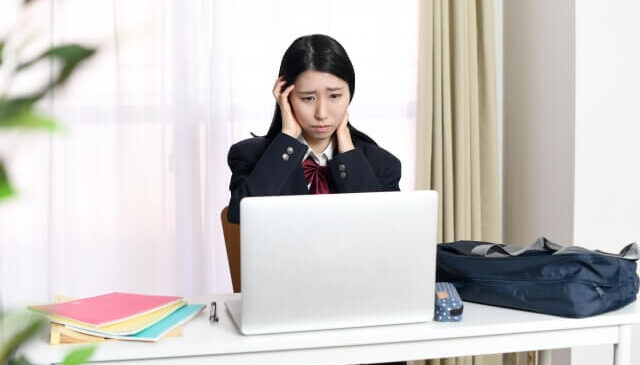
ASDのお子さまは、言葉を額面通りに受け取ってしまうことがあります。
友達付き合いで悩んでいるASDの中学生のお子さまが、「おごってくれたら友達にしてあげるよ」と声を掛けられた場合、言われたままにお金を払ってしまうなどのケースが考えられます。「親や先生に言ったら仲間外れにするからな」と言われ、被害がわからないという最悪のケースさえあり得ます。
こういった誤ったルールを信じてしまう前に、ご家庭では「むやみに金銭のやり取りをしない」「おかしいと思ったらすぐに大人に言う」といったことを徹底して伝えましょう。
併せて、ASDのお子さまの場合は上手な断り方を身につけることも大切です。
あまりにもストレートに断ってしまうと逆にトラブルを招くことがありますので、「今日は財布を忘れてしまった」「○時までに帰らなければならない」など、上手く断る方法を身に付けるようにしましょう。
療育で行われるソーシャルスキルトレーニングでは、こういった上手な断り方などを学ぶことができます。
ASDの中学生への支援のポイント⑥進路を早めに調べる・決める

ASDのお子さまは、こだわりの強さの特性が原因となり、学力面で伸び悩んだり、得意な教科と不得意な教科の差が激しくなったりすることがあります。
公立高校の入試では、どの分野も満遍なく得点でき、出席数や提出物・授業態度などの内申点も優秀であることが求められるため、高校進学に不安を感じている保護者さまもいらっしゃるかもしれません。
高校進学に不安を感じている場合は、できるだけ早く情報を集め、戦略を考えるようにしましょう。
不得意な教科があっても早い段階であれば苦手を克服できるかもしれませんし、飛び抜けて得意な科目がある場合は私立高校の受験を検討するのも良いでしょう。
私立高校の場合は当日の試験結果だけで合否が決まることが多く、得意な教科での得点だけで合格を目指せる可能性があります。ですので、出席日数などで内申点に不安がある場合も同様に、私立高校の受験を検討してみると良いでしょう。
ASDのお子さまの高校進学においては、得意不得意や現在の成績や内申点の状況を踏まえた適切な学校選びが欠かせません。
また、志望校合格に向けては、お子さまの性質をしっかりと見極め、特性に合わせた学習サポートを受けることがとても大切です。ASDのお子さまの高校進学や進路指導でお悩みの方は、ぜひ発達障害専門のプロ家庭教師をご検討ください。
ASDの中学生への支援のポイント⑦勉強をルーティン化する

ASDのお子さまは、イレギュラーな出来事に対応するのが苦手な一方で、決められたルーティンをこなすことは得意な傾向にあります。
中学生に上がると勉強面でつまずきがちですが、勉強時間をきっちり決めて取り組むことで、定期テストなどもうまく乗り越えることができます。
時間だけでなく、場所を決めることもポイントです。
自分の部屋や自習室など、お子さまが落ち着いて勉強できる環境を整えましょう。学校と同様に、家でも帰宅後の時間割(ルーティーン)を作ることで、より勉強に取り組みやすくなります。
>>ASDのお子さまの勉強の工夫・第一志望合格へのポイントはこちら
ASDの中学生への支援のポイント⑧学校に行きたがらないとき

ASDのお子さまが学校に行きたくないと感じる理由には、以下のようなものが挙げられます。
ASDのお子さまは感覚過敏である場合も多く、周囲が気付かない些細な変化が登校渋りの要因になっているケースもあります。ですので、まずはお子さまの話をよく聞き、学校に行きたくない理由を分析しましょう。
学校に行きたくない理由が人間関係によるものの場合は、すぐにクラス替えや担任替えができるとは限らないため、解決が難しい場合があります。
一方、勉強への苦手意識が行き渋りの原因であれば、塾やプロ家庭教師などでフォローすることが可能です。
また、どうしても朝起きるのがしんどい場合は、起立性調節障害の可能性があります。まずは規則正しい生活を心がけるとともに、症状が重い場合は医療機関への受診を検討しましょう。
最近では、フリースクールやオンラインで完結するプログレッシブスクール(N中等部 | N中等部 (n-jr.jp))などもあり、無理をして学校に行かないという選択肢を採ることもできます。
とはいえ、フリースクールやオンラインスクールでは自学自習が求められる側面もありますので、学校ともよく相談しながら、最適な答えを見つけていただければと思います。
ASDの中学生への支援のポイント⑨性の正しい知識を知る
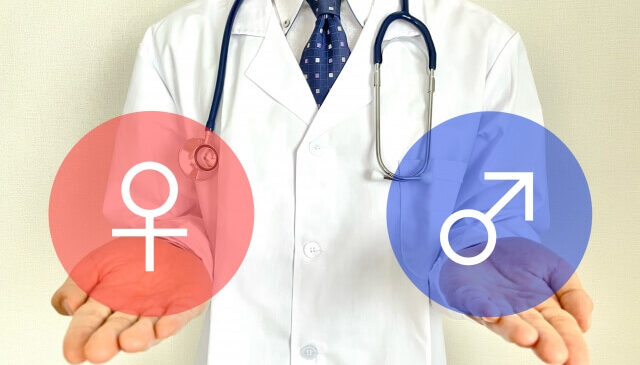
中学生という発達段階は、性への関心が高まる時期でもあります。
他者との距離感を測るのが苦手なASDのお子さまは、一方的な好意のままに行動して相手を傷つけてしまったり、逆に言葉巧みに好意に付け込まれて被害を受けてしまう可能性があります。
性に関するマナーは暗黙の了解になっている部分も多いので、「許可なく相手の体に触らない」「好きだからといって何でも許して良いわけではない」といったことを具体的に教えるようにしましょう。
漫画やアニメの行動をそのまま現実で行ってしまうお子さまもいらっしゃいますので、「今のキャラの行動は、相手の尊厳を傷つける行為に当たる」といったことを具体的に伝えるようにしましょう。
性に関する正しい知識を身につけることが、自分自身を守ることにつながります。
ASDの中学生への支援のポイント⑩保護者さま自身が知識を身につける

この記事を読んでいただいている方には釈迦に説法かと思いますが、保護者さま自身がASDについて正しい知識を身につけることはとても大切です。
単に空気を読まないだけに見える行動も、ASDのお子さまの中ではきちんとした理由があるかもしれません。お子さまがその行動に至った背景を理解することで、頭ごなしに怒らずにすみ、保護者さまのアンガーマネジメントにつながります。
ASDについて十分知識のある方も、新しい情報についてときどき調べてみるのも良いでしょう。あるいは、保護者同士のコミュニティに参加してみるなど、困りごとを共有することがガス抜きにつながることもあります。
とはいえ、頭でっかちになるのは禁物です。
本や論文の知識ももちろん大切ですが、ASDのお子さま一人ひとりの特性の現れ方や強度は違いますので、目の前のお子さまのことを丁寧に見守り、お子さまにあったサポートを考えることが何よりも重要です。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の中学生の特徴と接し方のまとめ

この記事では、ASDの中学生のお子さまの困りごとや支援方法について詳しくお伝えしてきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- ASDには「コミュニケーションが苦手」「こだわりが強い」といった特性がある
- ASDの特性には連続性があり、グレーゾーンと診断される場合も多い
- ASDの中学生のお子さまは、思春期ならではの難しさがある
- ASDのお子さまが中学生になると、周りの目が厳しくなる
- ASDの中学生のお子さまにおいては、脳の機能そのものの向上よりも、対処法を身につけることが大切
- ASDのお子さまには、ルールを明確にし、具体的に伝えることが効果的
中学生のお子さまは多感な時期であることに加え、ASDのお子さまの場合は、定型発達のお子さまと比べて環境の変化や身体的な変化から感じるストレスも大きくなります。
ストレスからついつい保護者さまに反抗的な態度を取ってしまうなど、保護者さまがご苦労を感じる場面も多いかもしれません。
ご家庭だけで解決するのが難しいときは、学校の先生やスクールカウンセラーなどに相談するほか、発達障害専門のプロ家庭教師などの利用も検討すると良いでしょう。
プロ家庭教師メガジュンでは、生活上の困りごとや進路相談など、学習面以外の相談も幅広く承っています。なかなか良い塾や家庭教師が見つからないという方は、ぜひ一度、プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
また、初回のご相談や授業は無料で承っています。面談や授業を踏まえてじっくり検討いただくことができますので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
授業や面談はオンラインでも行っており、これまで日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方にも多数ご利用をいただいてきました。「オンラインで授業を受けられるか不安」という方も、体験授業を受けてから入会について判断いただけますのでご安心ください。
お子さまが自らの力で未来を切り拓き、よりよい人生を歩めるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



