ASD(アスペルガー)の受験対策|勉強の工夫と第一志望合格へのポイントを徹底解説
ASD(アスペルガー)の特性があるお子さまは、人間関係での困難に注目されがちです。
ですが、「こだわりが強い」「神経質」といった特性から、勉強面でも困り事を抱える場合があります。
例えばASDのお子さまで、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 塾や学校の先生との相性が気になる、成績が上がらない
- 一つのことにこだわりすぎるせいで勉強が苦手
- ASD(アスペルガー)の特性を上手く使った勉強法を見つけたい
- 大学進学できるか不安
この記事では、ASDを含め、発達障害を持つお子さまに特化した指導を行うプロ家庭教師として、16年にわたる活動歴の中で培ってきたノウハウをお伝えします。
これまで指導してきた1500人以上のうち、第一志望合格率は90%以上を誇っており、発達障害のお子さまの指導には今も現役で携わっています。
ASDだからといって、勉強面で諦める必要は全くありません。
この記事の内容を実践していただければ、ASDのお子さまでも得意を活かしながら、第一志望に合格することが可能です。
この記事が、少しでもASD(アスペルガー)のお子さまの勉強のお役に立てれば幸いです。

発達障害専門の受験プロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▼目次
- 1 ASD (自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)とは
- 2 ASD(アスペルガー)と勉強や受験との相性
- 3 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選
- 3.1 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選①曖昧な言い方を避け、指示をはっきり伝える
- 3.2 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選②関係性の構築(信頼してもらう)
- 3.3 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選③本人のこだわりを尊重する
- 3.4 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選④本人に適した話し方をする
- 3.5 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選⑤細かい疑問にも丁寧に答える
- 3.6 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選⑥予定をはっきり示す
- 3.7 ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選⑦勉強の計画の立て方を工夫する
- 4 ASD(アスペルガー)の受験勉強のポイント
- 5 ASD(アスペルガー)の受験勉強の肝は「志望校選び」
- 6 ASD(アスペルガー)の勉強や受験対策のまとめ
ASD (自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)とは

ASDとはAutism Spectrum Disorderの略で、日本語に訳すと「自閉スペクトラム症」となります。
また、厳密に言うと定義が異なりますが、ASD=アスペルガー症候群とされる場合もあります。
ASD(アスペルガー)の方には、人間関係が苦手であったり、興味や関心に偏りがあるといった特性があります。
以下の特徴に多く当てはまり、社会生活上の困難や生きづらさを抱えている場合は、病院で診断を受けてみましょう。
ASDと診断された際は、療育やソーシャルスキルトレーニングなどにより、状態の改善を目指すことになります。

- 人の気持ちを読み取るのが苦手
- その場の雰囲気や空気が読めない
- (子どもの場合)ひとりで遊ぶことが多い
- こだわりが強い
- 想定外の出来事に対応できない
- 光や音、においや触った感じなど、外部の刺激に極度に敏感か鈍感
ASD(アスペルガー)と勉強や受験との相性
この章では、ASD(アスペルガー)のお子さまと勉強や受験の相性について解説していきます。
ASD(アスペルガー)のお子さまが勉強が苦手になってしまう理由

ASD(アスペルガー)の特性によって、お子さまが学校や家庭で以下のような困難を抱えることがあります。
定型発達のお子さまではこれらの困難は生じにくいので、結果として勉強しづらい、集中できないといったことにつながります。
- 授業中に空気を読まずに発言し怒られ、学校が嫌いになる
- 視線が合いにくく表情が乏しいため、友達と上手くコミュニケーションできない
- 手先が不器用で、作業などで周りについていけなかったり、字が汚かったりする
- マルチタスクが苦手(例:ノートを取りながら話を聴けない)
- 急な授業変更や教室移動でパニックになる
- 自分独自のルールややり方にこだわり、集団生活ができない
- 休み時間などのうるさい状況が苦手で、イライラしてしまいケンカになる
- 細かいことが気になり、時間内にやるべきことが終わらない
- 過去にあった嫌なことを思い出してイライラしやすい
これらの困難のために、学校や勉強に苦手意識を持ってしまい、不登校になるケースもあります。
特に日本の学校教育は画一的で同調圧力も強いため、独特のこだわりを持つASD(アスペルガー)のお子さまは周りに理解されず、辛い思いをされることもあります。
ご家庭ではお子さまの様子をしっかり見ていただくとともに、「どんな配慮が必要か」を学校や塾に対して丁寧に説明することで、お子さまの生きづらさを軽くすることができます。
筆者にご連絡・ご相談いただく際も、お子さまの様子をできるだけ詳細にお伝えいただくようお願いしています。
お子さまの特性はそれぞれ異なります。ご相談の際には、一人一人に合わせた支援を行うためにも、ぜひご協力をお願いできれば幸いです。

ASD(アスペルガー)ならではの勉強や受験における強み
一方で、ASD(アスペルガー)のお子さまは「興味のあることには集中して取り組める」といった長所もあります。また、ある分野で突出した才能を発揮するギフテッド(2E型)である場合もあります。
苦手なことや困り事に注目してしまいがちですが、お子さまの得意なことにも目を向けましょう。
「4.ASD(アスペルガー)の受験勉強のポイント」で詳しくご説明しますが、お子さまの得意分野に特化した志望校選びをすることで、ASDでも第一志望合格は十分可能です。
生きづらさや困難を解消することと同時に、お子さまの長所や得意分野を見つけることにも取り組んでいただければと思います。(参考:東大・京大合格者は発達障害の性質を持つ人が多い!? 個性を活かした勉強法で難関を突破 | キャリコネニュース (careerconnection.jp))
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選

この章では、ASD(アスペルガー)のお子さまが勉強や受験対策に取り組む際のコツについて詳しく解説していきます。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選①曖昧な言い方を避け、指示をはっきり伝える
ASD(アスペルガー)の特性を持つお子さまは、言外に含まれた意図を察するのが苦手です。
ですので、指示はできる限り具体的に伝えましょう。
- NGな例…「漢字練習を頑張ろう」
- OKな例…「○○、××、△△という漢字をノートに5回ずつ書こう」
また、勉強に関する指示だけでなく、日常生活においてもできる限り具体的な言い回しを使いましょう。
ちょっとしたことがストレスになり、お子さまが心身を消耗してしまう場合もあるため、勉強以外の負担を取り除くことも重要です。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選②関係性の構築(信頼してもらう)

ASD(アスペルガー)のお子さまは、環境の変化が苦手です。
新しい先生に勉強を教えてもらうとなると、見知らぬ人だと警戒してお子さま本人が心を閉ざしてしまうこともあります。
ですので、私が家庭教師でASDのお子さまの指導に当たるときは、まずは関係性を築くことから始めます。
「この人は信頼できる人だ」「自分のことをわかってくれる」とお子さま本人が思ってくれて始めて、勉強のコーチングに取りかかることができます。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選③本人のこだわりを尊重する
ASD(アスペルガー)のお子さまは、それぞれ独自のこだわりや世界観を持っています。
「変わった子」とレッテルを貼るのではなく、本人の個性として受け入れてあげることが大切です。
本人が触れてほしくない事柄であったり、「このシャープペンシルじゃないと勉強したくない」など、周りから見ると些細なことでも、本人にとっては大問題の場合があります。
こだわりを蔑ろにされることは、本人にとって大きなストレスです。親や指導に当たる大人は本人のこだわりを最大限尊重しましょう。
また、本人のこだわりポイントについては、ご家庭のお母さま・お父さまがいちばん把握しています。
学校や塾、家庭教師に対しては、本人のこだわりを十分共有するようにしてください。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選④本人に適した話し方をする

ASD(アスペルガー)のお子さまは、雰囲気やイントネーションから察することが苦手です。
「①曖昧な言い方を避け、指示をはっきり伝える」とも共通しますが、どちらとも取れる言葉は使わず、語尾も曖昧にせずはっきり言い切りましょう。
耳から聞いた言葉を理解するのが苦手なお子さまもいらっしゃいます。
また、大きな声が苦手なお子さまもいますので、「ゆっくり話す」「大き過ぎない声で話す」など、お子さまの様子をしっかり観察しながら、お子さま一人一人に応じた話し方の工夫をする必要があります。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選⑤細かい疑問にも丁寧に答える
ASD(アスペルガー)のお子さまは、普通の人なら気にならないような細かい「なぜ?」が気になることがあります。
「なぜ?」に対して明確な答えが無いまま先に進めるのが苦痛で、イライラや不安が募った状態になります。結果として、勉強そのものが嫌いになるケースも少なくありません。
先生にすぐ質問できる場合は、その都度丁寧に答えてあげましょう。
宿題や自習などで今すぐに質問できない場合は、「問題に○をつける」「わからなかったことをメモしておく」などして、後で先生に答えてもらうようにしましょう。
後で答えがわかると思えば、安心して他の問題に進むことができます。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選⑥予定をはっきり示す
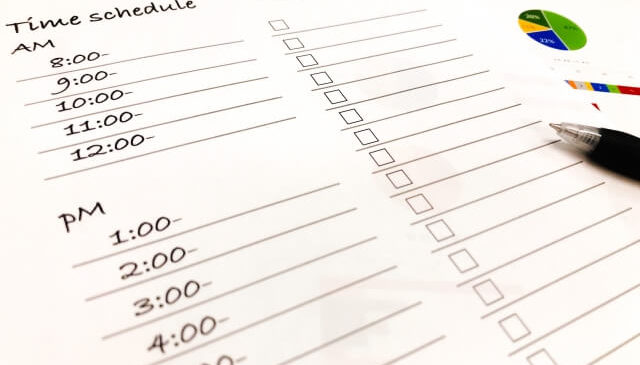
ASD(アスペルガー)のお子さまは、想定外の出来事への対応が苦手です。
その日に取り組む勉強は明確に決めておきましょう。
また、曜日で内容を決めてしまっても良いでしょう。
想定外の出来事をできるだけ減らし、ルーティン化することで、ストレス無く勉強に取り組むことが出来ます。
一度予定した内容は、大人側の都合で変更しないようにしましょう。
子ども自身にやる気が無かったり、予定を変更したいと言っている場合は対応して構いませんが、「思ったより進みが悪かった」などで大人の側から予定を変更してしまうと、ASD(アスペルガー)のお子さまにとっては大きなストレスになってしまいます。
ASD(アスペルガー)のお子さまの受検勉強のコツ7選⑦勉強の計画の立て方を工夫する
「得意な科目から始めることで気分を上げる」「苦手な科目は気力と体力に余裕のある週初めに取り組む」など、お子さまの性質に適した勉強の計画を立てましょう。
本人と相談し、お子さま自身が納得できる勉強計画にすることで、学習習慣の定着につながります。
また、「⑤細かい疑問にも丁寧に答える」でお伝えしたとおり、難易度の高い問題はお子さま一人で取り組むとその先に進めず、勉強が嫌いになってしまうこともあります。
できれば宿題などの内容はあらかじめ大人がチェックし、難易度の高い問題には○をつけて「あとで一緒に解く問題」とし、お子さま一人で解くことを避けるようにしましょう。


ASD(アスペルガー)の受験勉強のポイント

入学試験は、普段の勉強の総まとめとして、お子さまの学力を測るものです。ですので、受験だからといって特別に身構える必要は無く、普段通りの勉強をコツコツ進めるのが良いでしょう。
特に、ASD(アスペルガー)のお子さまは変化が苦手であり、普段通りのルーティンの方が落ち着く傾向にあります。
そのため、急に勉強量を増やしたりプレッシャーをかけたりするのは望ましくありません。
とはいえ、受験を前に不安を感じるのはお子さまも保護者さまも同じです。では、受験勉強と普段の勉強の大きな違いはどこにあるのでしょうか。
受験勉強と普段の勉強の違いは、以下の2点しかありません。
- 難関校を受験する場合はそのための対策が必要
- これまで習ったこと全てが出題される
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
ASD(アスペルガー)の受験勉強のポイント①難関校を受験する場合はそのための対策が必要

難関校の場合は、学校で習う以上の内容が出題される場合があります。
特に中学校受験の場合は、出題の50~90%が学校で習う範囲を超えた内容であると言われています。そのため、学校の教科書に沿った内容に加えて、受験のための内容をプラスして勉強しなければなりません。
大学受験でも、教科書の範囲を超えた出題がされる場合があります。例えば、歴史の問題で、教科書に載っていないマニアックな人名や専門用語が出題されるケースなどです。
公立高校の受験では、それほど高難度の問題は出題されません。ですが、私立難関校であれば、高難易度で特別な対策が必要となる問題が出る場合も稀にありますので、出題傾向をチェックしましょう。
高難易度の問題への対策が必要という点においては、ASD(アスペルガー)の方だけが不利ということではなく、ASDではない人もみんな同じ条件です。
教科書の範囲を超えた内容についても、日頃からコツコツと取り組むようにしましょう。
ASD(アスペルガー)の受験勉強のポイント②これまで習ったこと全てが出題される
学校の定期テストであれば、出題範囲は直近に習った内容に限定されています。
ですが、受験ではこれまでに習った全ての内容から出題されます。
例えば日本史であれば、「2学期の期末テストでは江戸時代からしか出題されない」などの条件があり対策もしやすいのですが、受験は全ての時代から出題されます。縄文時代から近現代まで、全ての範囲を網羅的に勉強しなければならず、記憶の定着が重要になります。
また、英語など積み上げが必要な科目であれば、それぞれの単元が別の単元とどのように結びつくのか、関連性を考えながら勉強することが重要です。
ASD(アスペルガー)のお子さまは、一度学習習慣を確立してしまえばコツコツと取り組むことが出来ますので、早いうちに勉強を生活の一部にして受験に備えるようにしましょう。
ASD(アスペルガー)の受験勉強の肝は「志望校選び」

ASD(アスペルガー)のお子さまが受験を上手く乗り越えるには、志望校選びが最も重要なポイントになります。
というのも、ASDのお子さまは特定の分野には強い関心を持つため、その科目であれば満点近く取れるケースもあります。
また、得意な科目が無くても、自分の得意と苦手の凸凹を上手くコントロールすることで、第一志望に合格することが可能です。
志望校選びのコツについて、以下で詳しくお伝えします。
得意科目の配点が高い学校を選ぶ
試験科目の配点について、事前に調べておきましょう。
自分の得意な科目の配点が高い学校であれば、それだけ周りと差をつけることが出来ます。
また、単元や分野ごとの出題傾向にも注目しましょう。
世界史であっても、中世が多く出題されるのか、近現代が多く出題されるのかで、点数は大きく変わってきます。
細かい出題傾向については、学校や塾の進路担当の先生の力も借りながらリサーチしましょう(ちなみに、日本史も世界史も近現代からの出題が多いケースがほとんどです).
科目ごとの難易度に注目
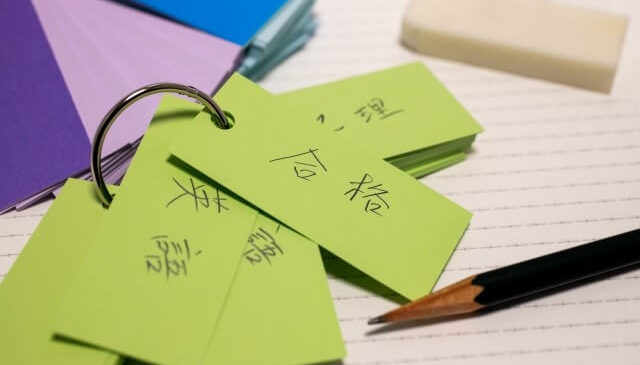
学校の偏差値イコール試験の難易度とは限りません。教科や単元ごとに難易度が異なる場合も多くあります。
例えば、日本史の難易度は非常に高いものの、数学はそれほどでもない、といったケースです。
上のケースであれば、日本史の得意なお子さまは有利に受験を進められますし、逆に数学が得意なお子さまは、周りも点が取れるために差が付かず、苦しい戦いになります。
「点差が付いているのはどの科目で、どのラインで合否が分かれるのか」についてしっかり分析することが、受験を有利に進めるポイントになります。
出題傾向や合否ラインの分析には専門的な知識が必要ですので、入試についてしっかりとした知識のある先生や家庭教師などと相談しましょう。
記述式orマーク式?
ケアレスミスの多いお子さまであれば、計算ミスがあっても部分点がもらえる記述式の出題形式がオススメです。
逆に、どうしても苦手な科目があり白紙回答になりかねない場合は、とにかく回答欄を埋めれば点がもらえる可能性がある、マーク式中心の学校を選ぶのも一つの方法となります。
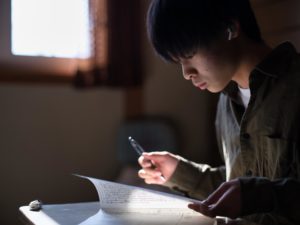

ASD(アスペルガー)の勉強や受験対策のまとめ

この記事では、ASD(アスペルガー)のお子さまの勉強方法や受験対策について詳しく解説してきました。
日常でも困難を抱えがちなASDのお子さまですが、以下のポイントを実践していただき、少しでも勉強に前向きに取り組んでいただければと思います。
- ASD(アスペルガー)は「人間関係が苦手」「興味や関心に偏りがある」といった特性がある
- ASD(アスペルガー)の特性から、学校や家庭で困りごとを抱えるケースがある
- 様々な困難が原因で、勉強に集中できなかったり苦手意識をもってしまったりする
- 本人のこだわりや思いを尊重することが大切
- 曖昧な言葉をさけ、わかりやすい言葉で伝える
- 勉強の計画を立て、学習の習慣化を目指す
- 得意を活かせる志望校選びをする
発達障害と一言でいっても、お子さまによって性質や個性はさまざまであるため、一人ひとりに合わせたカリキュラムの作成や授業の組み立て、日々の声掛けなどが必要です。
そのため、ASDなど発達障害のあるお子さまの勉強や受験をサポートにおいては、確かな知見やノウハウのある講師の指導を受けることが非常におすすめとなります。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり発達障害のお子さまの支援を行ってきました。
「発達障害だから~」と決めつけるのではなく、また、知識だけに頼り切るのではなく、目の前のお子さまと真摯に向き合い、一人ひとりの状態を丁寧に把握しサポートしてまいります。
- 発達障害について相談しても、一般的なことしか答えてもらえず困っている
- 悩みや困りごとを聴いてもらうだけでなく、具体的な改善策を教えてもらいたい
などのお悩みがある方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問合わせください。
また、授業や面談はオンラインでも承っています。全国各地からご利用いただけるほか、海外にお住まいの方や帰国子女の方にもこれまでご利用いただき、多数のご好評の声をいただいてきました。
初回の授業・面談は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか不安な方もお気軽にお問合せください。

一人でも多くのお子さまが、心身とも健やかに成長していけるよう一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。




