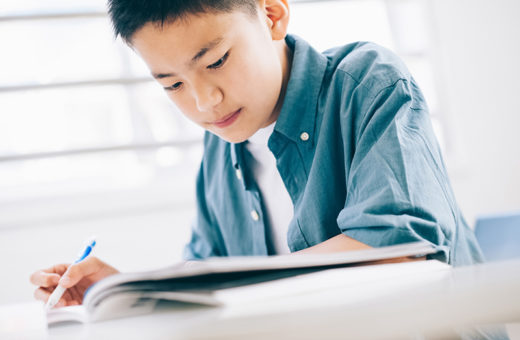【チェックリスト付】ASD・アスペルガーのグレーゾーンの特徴とは?対処法も合わせて紹介!
以下のようなことで日常生活に支障がある方は、もしかしたらASD(アスペルガー症候群)かもしれません。
- 人の気持ちを読み取れず、コミュニケーションが苦手
- 人間関係を上手く築けない
- 「適当に」「もう少し」など曖昧な指示を受けると混乱する
- 一つのことにこだわってしまう
「自分はコミュニケーションが苦手だ」と感じている人は多くいますが、周囲からよく孤立してしまったり、高い頻度でトラブルを起こしてしまう人は、発達障害(ASD、アスペルガー症候群)の可能性があります。
また、はっきりと診断できるレベルではなくても、その傾向がある「グレーゾーン」として医師に判断されることもあります。
「もしかして自分はASDかもしれない…」とお悩みの皆さまのために、この記事では、ASDの特性やグレーゾーン、困りごとへの対処方法についてご紹介していきます。

発達障害専門の受験プロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中

▼目次
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の特徴とは【チェックリスト
14問】

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)とは、
- コミュニケーションや対人関係が苦手
- 強いこだわりがあり、興味が限定されている
といった特性がある発達障害です。
「スペクトラム」は「連続している」という意味であり、自閉症や高機能自閉症、アスペルガー症候群などがASDに含まれています。
文部科学省では高機能自閉症やアスペルガー症候群について以下のように定義しています。
高機能自閉症とは、3歳位までに現れ、
- 他人との社会的関係の形成の困難さ
- 言葉の発達の遅れ
- 興味や関心が狭く特定のものにこだわること
を特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものをいう。
(中略)
アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものをいう。
つまり、ASD(自閉スペクトラム症)は、
- 知的発達の遅れがあるものを「自閉症」
- 知的発達の遅れはないが、言葉の遅れがあるものを「高機能自閉症」
- 知的発達の遅れや言葉の遅れを伴わないものを「アスペルガー症候群」
といった形で分類されています。
私たちはテレパシーが使えるわけではありませんので、日常生活でコミュニケーションが上手くいかなかったり、ちょっとした言葉の取り違えがあったりすることはどんな人でもあり得ます。また、どうしても捨てられない自分なりのこだわりがある人もたくさんいます。
「コミュニケーションが苦手だと感じる」「物事に強いこだわりがある」からといって、必ずしもASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)であるというわけではありません。
ですが、それらの特性の度合いが強く、困りごとが大きい場合にはASDと診断されたり、グレーゾーンと診断されたりすることになります。
以下では、お子さまから大人の方まで使っていただけるASDのチェックリストをお示ししていますので、気になることがある方は簡易な診断テストとして利用いただき、多くのチェック項目に当てはまる場合は医療機関への受診を検討していただければと思います。
- 他人の表情から気持ちを読み取るのが苦手(空気が読めない)
- 言外に含まれている意味を読み取るのが苦手(行間が読めない)
- ジェスチャーを読み取ったり、使ったりするのが苦手
- 「適当に」「もう少し」など曖昧な指示が理解できない
- 人の話を遮り、自分の話ばかりしてしまうときがある
- 言い方が失礼だと指摘されることがある
- 物事には一人で取り組みたい
- 同じやり方を繰り返す方が良い(違うやり方には挑戦したくない)
- 何かに没頭すると周りが全く見えなくなる
- 少しの物音でも気が散る
- 特定の味やにおい、感触などが苦手
- 急に予定が変更されると、イライラしたりパニックになったりする
- 物事を大まかに把握するより、細部に注目することが好き
- 時刻表や車のナンバーなど、数字の羅列に注目することがある
また、当てはまる項目が多くなかったとしても、こういった特性が原因で大きなストレスを感じている場合は医師への相談を検討しましょう。放っておくとストレスによって、うつや不安障害などの二次障害を引き起こしてしまう可能性があります。
気になることがある場合は、早めに医療機関や専門機関に相談することが大切です。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)のグレーゾーンの特徴とは

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)のうち、特性や困難の程度がそれほど大きくないものを「グレーゾーン」と呼ぶことがあります。
「グレーゾーン」とは正式な診断名称ではありませんが、現時点ではASDかどうかの診断が付きづらく、また、支援を必要とする程度がそれほど大きくないと判断される場合などに「ASDのグレーゾーンかもしれない」といった表現がされることがあります。
ASDグレーゾーンの方が困難の度合いが大きい場合も
病院を受診すると、「基準を満たしていないが傾向はある=グレーゾーン」と診断されることがあります。グレーゾーンとは、発達障害の度合いが小さいことを指すのでしょうか?
答えは「No」です。
発達障害の診断は、診察する医師によって判断が異なる場合があり、困りごとの度合いが重視される場合や、自閉スペクトラムの特性の強さが重視される場合など、医師の見解は様々に分かれます。
例えば上述のチェックリスト(実際に医療機関で用いられる診断基準とは異なります)で、
- Aさんの場合
①~⑨まで全ての項目に当てはまるが、それぞれの困り具合は30%で、日常生活に支障は無い。 - Bさんの場合
②③⑦の3項目にしか当てはまらないが、それぞれの困り具合は100%で、日常生活に困難がある。
というケースの場合、医師によっては日常生活での困難はBさんの方が大きいにも関わらず、発達障害と診断するのはAさんで、Bさんはグレーゾーンとされる場合もあります。
すなわち、特性の強さが重視される場合、「それほど特性は強くないから」と確定診断にはいたらないグレーゾーンであると判断する医師もいます。
ただし、特性が強くない場合でも、今の職場や環境が自分に合っておらず、困りごとを抱えている場合には対処が必要です。
職場に理解を求めたり、休職するために診断書が必要な場合は、その旨を医師にも伝えるとともに、自分の目的に沿ったアドバイスをくれる医師を探すことも大切です。
ASD(グレーゾーン)の正確な診断を受けるには

いくら基準を満たさないとはいえ、日常生活での困難は解消したいものです。
また、学校や職場へ説明する際も、グレーゾーンよりは確定診断が出ている方が説明しやすく、投薬治療も受けやすいでしょう。
自分の困り度合いに応じた正確な診断を受けるための方法としては、次のようなものが挙げられます。
- 複数回診断を受ける
- 病院を変える(セカンド・オピニオン)
- 客観的な検査を受ける(QEEG、WAIS-IV、WISC-IV)
- 正確な情報を伝える
- 自己診断はNG
以下では、それぞれについて解説していきます。
ASD(グレーゾーン)の正確な診断を受ける方法①複数回診断を受ける
グレーゾーンの方は、診断基準のボーダーラインにいます。
体調によって基準を満たしたり満たさなかったりするので、日を変えて受診することで確定診断となる場合があります。
ASD(グレーゾーン)の正確な診断を受ける方法②病院を変える(セカンド・オピニオン)
最終的に診断するのは、医師の主観です。同じ症状や検査結果でも、グレーゾーンと診断する医師もいれば、確定診断とする医師もいます。
ですので、別の病院を受診することで確定診断につながることがあります。
ASD(グレーゾーン)の正確な診断を受ける方法③客観的な検査を受ける(QEEG、WAIS-IV、WISC-IV)
医師の主観のみの診断では、診断結果にブレが出ます。脳波を検査する「QEEG」や知能検査「WAIS-IV」「WISC-IV」を受けることで、発達障害の特性を数値化することができます。
客観的な根拠に基づいた診断は信用できますし、こういった検査を受けられる医院を探しましょう。
WISC-IV知能検査について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

ASD(グレーゾーン)の正確な診断を受ける方法④正確な情報を伝える
発達障害の診断には、幼少期の情報や自分の普段の様子を正確に伝える必要があります。気になった症状はメモしておくほか、親や配偶者など、自分の普段の様子をよく知る方に付き添ってもらうのが良いでしょう。
また、幼少期の情報は本人が忘れてしまっていることもあります。通信簿や母子手帳など、幼少期の様子がわかる資料もできる限り準備しましょう。
ASD(グレーゾーン)の正確な診断を受ける方法⑤自己診断はNG
インターネット上には、さまざまなチェックリストがあります。参考にしても構いませんが、安易な自己診断は避けましょう。
この記事でもチェックリストを掲載していますが、あくまで病院や専門機関に相談するための目安として利用していただくものであり、それだけでASDかどうかを判断できるものではない点には十分ご注意ください。
発達障害の特性の現れ方は、先入観やその日の体調などにも左右されるため、自分で客観的な判断をするのは非常に難しいです。少しでも困っていることがあれば、まずは病院や専門機関に相談するようにしましょう。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の特徴と困りごとへの対処法

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の困りごとに対処する際のポイントは、次のとおりです。
- 二次障害の有無を確認する
- 確定診断でもグレーゾーンでも対処法は同じ
- 周囲の配慮
それぞれについて、以下で解説していきます。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の困りごとへの対処法①二次障害の有無を確認する
グレーゾーンであると診断された場合、確定診断と比べて以下のような困りごとが生じます。
- 周囲に配慮が求めづらい
- 保険治療が受けられないことがある(自由診療であれば可)
- 障害者手帳の交付が受けられない
グレーゾーンの方は、まずは二次障害の有無を確認しましょう。二次障害とは、発達障害の特性による生きづらさから、うつ病や不安障害、適応障害などの精神疾患を発症することを言います。
こういった二次障害がある場合は、その治療を保険診療内で受けることができますし、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けられる場合があります。困りごとが多く心がつらいときは、迷わずメンタルクリニックを受診しましょう。
発達障害についてはグレーゾーンでも、精神疾患の診断書があれば、周囲への配慮も求めやすくなるはずです。
お子さまであれば勉強面や生活面の配慮について、大人であれば休職や職務上の配慮について、診断書を準備した上で学校や職場に相談してみましょう。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の困りごとへの対処法②確定診断でもグレーゾーンでも、対処法は同じ
二次障害が出ていなくても、生きづらさや日常の困難はできる限り解消したいものです。
グレーゾーンであっても、ASDの特性への対処法は確定診断を受けた場合と変わりません。
- 指示は具体的に出してもらい、わからなければ聞き返す
- 集中しすぎを防ぐため、アラームを使う
- 耳栓やイヤホンを使って、静かな環境を作る
- 気が散らないよう、作業環境をいつも同じにする
以上のことは、ASDの特性への対処法としてとても有効です。
また、お子さまであれば、環境が変わることでパニックになってしまったり、細かいことが気になって勉強に集中できなかったりといった困りごとがあります。
成績が伸び悩んでおり、その原因が発達障害の特性によるものである場合は、ASDのお子さまの学習支援について専門的な知識を持った人のサポートが必要です。
市町村の教育相談センターや発達支援センターのほか、発達障害に特化した塾やプロ家庭教師などを利用するのも効果的ですので、お子さまの学習面でお悩みの場合はぜひご検討ください。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の困りごとへの対処法③周囲の配慮

ASDの人は、「コミュニケーションが苦手」「融通が利かない」などの特性があります。
本人に悪気があるわけではありませんが、周囲から誤解を受けてしまい、ストレスや生きづらさから、うつ病などの精神疾患(二次障害)になることがあります。
周りの人たちに配慮を求めることが難しいケースもありますが、身近な人には自分の困りごとをきちんと説明しておきましょう。
曖昧な表現を避けてもらったり、先の見通しが立つように予定を立てることは、ASDの方だけでなく定型発達の方にとっても「より仕事がスムーズに進められる」などのメリットがあるはずです。
お子さまが発達障害の場合は、育て方が悪いのでは?と考えてしまう方も多いようです。ですが、発達障害は生まれ持った特性であり、育て方によるものではありません。
また、幼いころから特性に気づき適切なサポートを受けることで、発達障害のあるお子さまであっても社会の一員として問題なく生きていくことができます。中には個性を存分に伸ばすことで、定型発達には無い才能を発揮するお子さまもいらっしゃいます。
実際に、東大や京大などの難関校においては、発達障害の性質を持つ学生が多いということも言われています。
ASDの方のこだわりの強さは、一方で「好きなことにとことん打ち込める」という強みにもなります。ですので、苦手なことや困っていることだけに注目するのではなく、お子さまが持っている強みにもぜひ注目していただければと思います。
(参考記事:東大・京大合格者は発達障害の性質を持つ人が多い!? 個性を活かした勉強法で難関を突破 | キャリコネニュース)

ASD(アスペルガー・自閉スペクトラム症)のお子さまを持つ保護者の方へ

これまでお伝えしてきたとおり、人の気持ちを読み取ることが苦手だったり、強いこだわりがあったりするのは、決してお子さまがわがままということではありませんし、親のしつけや愛情の注ぎ方の問題でもありません。
発達障害は脳の特性であり、脳の機能の偏りです。遺伝などの要因も指摘されていますが、発達障害の遺伝に関してはまだよく解明されていません。
お子さまに発達障害の可能性があると分かると、「なぜうちの子に限って…」「育て方が悪かったのだろうか」と心配や不安な気持ちでいっぱいになってしまうことも多いと思います。
ですが、世の中には発達障害の特性を持ちながらも充実した人生を送っている方はたくさんいますので、お子さまの性質と上手に向き合いながら、お子さまにとってより良い人生は何か?という視点で前向きにサポートしていくことが大切です。
周りの大人が以下のような点に気を付けながらお子さまと関わっていくことによって、お子さまは発達障害と上手く付き合い、自分らしく人生を歩めるようになっていきます。
- 本人が落ち着けるように環境を整える
- 公的機関に相談し、療育を受ける
- お子さまの個性を褒め、伸ばしてあげる
例えば、お子さまがソワソワと落ち着かず勉強に集中できないようなときには、「どうして集中できないのだろう?」とその原因を考えるようにし、
- テレビの音がうるさいのであれば、テレビを消す
- 勉強が終わる見通しが立たないのが不安なのであれば、「この問題を解いたら終わりだよ」と声を掛けたり、やるべき問題を一覧にして示す
- ゲームや動画をやりたい気持ちで頭が一杯になってしまっているときは、一度思い切りやりたいことをさせて、気持ちを発散させる
など、状況に応じて対応していくことが大切です。
お子さまに対して、ただ「勉強しなさい」「集中しなさい」「ソワソワしないで」と伝えるだけでは、なかなか状況は改善しません。
お子さまも「勉強しなくていいや」と本当に思っているわけではなく、生まれつきの脳の性質(=発達障害の特性)によってどうしても落ち着かなかったり、イライラ・ソワソワしているという状態にあります。ですので、「なぜイライラ・ソワソワするのか?」と考え、その根本的な原因となっている要因を解消していくことが大切です。
また、お子さまが「発達障害かもしれない」と思ったら、早めに学校や地域の教育相談センター・発達支援センターなどに相談するようにしましょう。
発達障害の診断はすぐにできるものではなく、専門の医師であっても診断まで数か月かかることもあります。また、児童精神科は数も少ないため、予約が半年後まで埋まってしまっているようなケースも多いです。
ですので、お子さまのことで気になることがある場合は、早めに学校や専門機関に相談するようにしましょう。早く支援につながることができれば、それだけ早く困りごとを解消していくことができますので、困ったときはまずは相談することが大切です。
なお、どこに相談してよいかわからない場合は、各市町村の子育てに関する総合窓口に問い合わせると良いでしょう。相談の内容に応じて、適切な機関につないでもらうことができます。
また、インターネットや親の会などを通じて、同じ悩みを抱えている保護者の方同士で情報交換するのも、当事者ならではの共感が得られ、保護者さま自身の気分の安定につながることが多いためおすすめとなります。

【ASDチェックリスト】ASD・アスペルガーのグレーゾーンの特徴のまとめ

この記事では、ASDやグレーゾーンの特徴や対処方法について解説してきました。改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
POINT
- ASDの特性=コミュニケーションが苦手、こだわりが強い
- グレーゾーンだからといって、日常の困難が少ないとは限らない
- 正確な診断を受けるためには、複数回の受診やセカンド・オピニオンが必要
- ASDのお子さまには、専門家のサポートがおすすめ
発達障害には生きづらさを伴うこともありますが、自分の特性をきちんと理解し対処することで、生き生きと充実した人生を歩んでおられる方もたくさんいらっしゃいます。
発達障害やASD(アスペルガー)の方がより良く人生を歩んでいくためには、自分の特性について正しい知識を身につけ、「困りごとの原因は何か?」について一つずつ確認しながら解消していくことが大切です。
そしてそのためには、医師や心理士、療育施設の先生など、「こんなときどうすれば良いか?」を考えるための知識や経験が豊富な人とつながることが重要です。
ですので、発達障害に関わる悩みや困りごとについては、ご家庭だけで抱え込まず、学校や医療機関・専門機関に積極的に相談し、いろいろなつながりを作っていくようにしましょう。
また、発達障害のあるお子さまが勉強のことで悩んでいる場合には、発達障害やASDの特性を理解し、その子に合わせた指導ができる先生に見てもらうことが最も効果的です。
ただし、学校の先生で発達障害の特性を踏まえた指導ができる先生はまだまだ数が少なく、一般的な塾や家庭教師の場合も(特に学生が講師を務めている場合などは)発達障害の特性を踏まえた授業をできる先生を見つけることは非常に困難です。
ですので、発達障害のお子さまの学力を伸ばしたい場合は、発達障害を専門としている塾や家庭教師を選ぶことをお勧めします。
また、発達障害専門の塾や家庭教師の中でも、指導経験が豊富で、お子さまの特性を丁寧に分析し、それぞれに合った対応ができる先生を選ぶようにしましょう。
残念ながら発達障害を専門とする塾や家庭教師の中にも、「ASDだから○○に違いない」などと決めつけて指導してしまう先生がいます。
「発達障害だから」「ASDだから」といった固定観念ではなく、目の前のお子さまはどうなのか?をフラットに分析し、一人一人に合った指導ができる先生こそが、お子さまにとって本当に良い先生であると言えます。
ですので、塾や家庭教師を検討する際には初回の面談などで先生の指導方針をよく確認し、お子さまに合った指導をしてくれそうか、お子さまと相性は良さそうかをしっかりと見ていきましょう。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、お子さま一人一人に丁寧に寄り添った指導をモットーに、長年にわたり発達障害やギフテッドのお子さまの学習支援を行ってきました。
発達障害のお子さまは、特性ゆえに学力が伸びづらいことも多く、勉強に対して強い苦手意識を持っていることがあります。
そんなお子さまが学力を伸ばしていくためには、まずはお子さまが「勉強がわかる、できる、楽しい!」と学習意欲を持つことが大切です。
プロ家庭教師メガジュンでは、そんなお子さまの前向きな気持ちを呼び起こせるよう、一人一人に合わせたスモールステップを設け、お子さまが自信を持てるようにサポートしていきます。
ASDのお子さまの学力面でお悩みの方や、ASDゆえになかなか相性の良い先生が見つからないとお困りの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。これまでの経験とノウハウを生かし、確実に効果のあるサポートをお約束します。
また、授業や面談はオンラインでも承っています。全国各地からご利用いただけるほか、これまで海外にお住まいの方や帰国子女の方にもご利用いただき、多数のご好評の声をいただいてきました。
初回の授業と面談は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか心配な方もお気軽にお試しいただけます。

一人でも多くのお子さまが、自分らしく伸び伸びと人生を歩んでいけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。