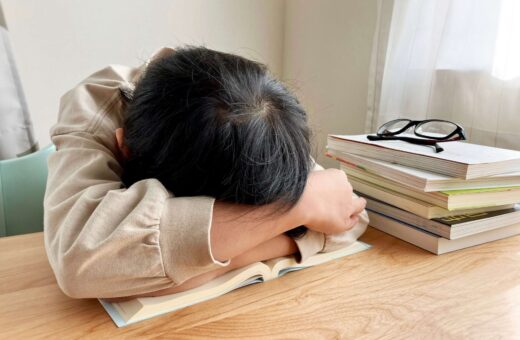発達障害の子は字が汚いのはなぜ?大人でも練習すれば改善できる?書字障害や発達性協調運動障害との関連も解説
発達障害のお子さまをお持ちの保護者さまで、「どうしてうちの子はこんなに字が汚いの?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
発達障害のお子さまの字が汚くなってしまう原因には、
- 集中力が続かない
- 指先を動かすのが苦手である(=発達性協調運動障害)
- 文字と音を結びつける能力が低い(=音韻処理不全)
- 文字の形をイメージする力が弱い
といったものが挙げられます。
現代ではパソコンやスマホで文字を入力することも多いため、文字を綺麗に書けることが絶対に必要であるとは言えませんが、字が綺麗だと「賢そう」「礼儀正しそう」というイメージを与えることができ、学校だけでなく社会に出てからもメリットを得ることができます。
ただし、お子さまに綺麗に字を書いてほしいからと言って、何度も反復練習をさせたり、本人が乗り気でないのに書道教室に通わせたりするのは逆効果です。無理をさせるとますます書くことが嫌いになり、苦手意識も強まってしまいます。
字の汚さを改善するためには、字が汚くなってしまっている原因を明らかにし、お子さまに合った方法でトレーニングを行うことが大切です。また、少しでもきれいに書けたときはしっかりと褒めてあげることも大切です。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、書字障害(=書くことが苦手な発達障害)のお子さまを含め、これまでたくさんのお子さまをサポートしてきました。
これまで指導させていただいたお子さまの中には、字がきれいに書けるようになることで自信が付き、成績もアップしたお子さまがたくさんいらっしゃいます。
そこでこの記事では、発達障害のお子さまの字が汚くなってしまう原因とその改善方法について詳しく説明していきます。
お子さまに字をきれいに書けるようになってほしいと思っている保護者さまや、大人の方で字をきれいに書けるようになりたいと思っている方にもおすすめの内容となっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
<この記事で分かること>
- 発達障害の人が字が汚くなってしまう理由
- 発達障害の人が字をきれいに書くためのポイント
- どうしても字を書くのが苦手な人への配慮方法
発達障害の子どもの字が汚い理由
発達障害のお子さまの字が汚い理由には様々なものがあります。
手先が極端に不器用で筆圧が調節できないお子さまもいれば、文字と音の結びつきが弱く、言葉をまとまりとして捉えることが苦手なお子さまもいらっしゃいます。
生まれつきの要因によって字が上手く書けない場合は、LD(学習障害、SLD)の一つである「書字障害(ディスレクシア)」に該当します。
書字障害自体は生まれつきの性質ですので、性質そのものを解消することはできません。
ですが、字が汚くなってしまう原因を明らかにし、適切なトレーニングを行うことで、苦手さを少しずつ改善していくことはできます。
以下では、発達障害のお子さまの字が汚くなってしまう理由を紹介していきます。
複数の原因が重なっている場合もありますので、お子さまの様子をしっかりと観察し、丁寧に要因を見極めていただければと思います。
発達障害の子どもの字が汚い理由①集中力が続かない

発達障害のお子さまの字が汚い理由の一つに、「集中力が続かない」ということがあります。
勉強に対するモチベーションを保てないことから集中力が続かず、「丁寧に書くのが面倒」と感じることで字が汚くなってしまいます。この傾向は、ADHDのお子さまに多く見られます。
このようなケースでは、絵や図形など字以外のものを描くことには問題が無い場合が多く、「字を書くことは楽しい」「丁寧に書くと褒めてもらえる」という経験を積み重ね、字を書くことに対するモチベーションを上げてあげると、字の汚さを解消できることが多くなっています。
また、手先の不器用さや言葉の処理の苦手さが原因となって集中力が続かない場合もあります。手先の不器用さが関係している場合は字以外の絵や図形を描き写すことも苦手になりますし、言葉の処理が苦手な場合は、読むことにも苦手が生じる場合がほとんどです。
集中力が続かない背景に、他の原因が隠れていないか確認することも大切です。
発達障害の子どもの字が汚い理由②手先の不器用さ(発達性協調運動障害)

発達障害のお子さまは、「発達性協調運動障害」を併発する場合が多いとされています。
発達性協調運動障害とは、指先を動かす細かい運動(微細運動)と全身を大きく動かす運動(粗大運動)の両方の発達が年齢不相応で、極端に不器用だったり運動神経が悪かったりする状態のことを指します。
文字を書く際には、マス目の中に納まるように書いたり、線や点をそろえて書いたり、筆圧を調整したりと、手先の細かい運動が必要になります。また、手先の運動だけでなく、正しい姿勢で椅子に座り、それを長時間保つという全身の運動も必要です。
そのため、発達障害のお子さまで、字が上手く書けなかったり、姿勢がすぐに崩れてしまったりするお子さまは、発達性協調運動障害が関係している可能性があります。
発達性協調運動障害のお子さまの場合は、字を書くこと以外にも、
- 紐を結ぶ
- はさみを使う
- 服に袖をとおす
- 食べ物をこぼさず口に運ぶ
といった日常の動作にもぎこちなさが見られる場合が多いです。
発達性協調運動障害が疑われる場合は、字の汚さ以外の身体の動かし方にも注目してみると良いでしょう。
発達障害の子どもの字が汚い理由③文字と音の結びつきが弱い

文字と音を結びつける脳の働きが弱いことから、言葉自体を認識するのが難しく、書くことが苦手になる場合があります。
文字と音を結びつける脳の働きは「音韻処理」と呼ばれます。例えば、「りんご」という言葉を目で見たとき、私たちは頭の中で「り・ん・ご」と発音すると同意に、赤くて丸い果物をイメージします。
音韻処理の働きが低い人は、この処理に時間が掛かります。そのため、文章を読むのに時間が掛かったり、言葉を文字で表すのが難しくなったりします。
音韻処理不全のあるお子さまは、書くことだけでなく読むことも苦手である場合がほとんどです。読むことの苦手さは「読字障害(ディスレクシア)」、書くことの苦手さは「書字障害(ディスグラフィア)」とそれぞれ呼ばれますが、両方を合わせて「発達性読み書き障害(発達性ディスレクシア)」とする場合もあります。
なお、読字障害と書字障害は、いずれもLD(学習障害)に含まれます。
<学習障害の分類図>

書くことの困難の背景に音韻処理不全がある場合は、文字と音の結びつきを強化するためのトレーニングを行います。
いきなり文字を書く練習をするのではなく、まずは読むことからトレーニングを始め、「文字」「音」「イメージ」の結びつきを少しずつ強化していきます。
音韻処理は、勉強だけでなく日常生活や脳の機能そのもの(ワーキングメモリー)にも大きく影響すると考えられています。
早めに対処することで少しずつ改善していくことができますので、お子さまに音韻処理の苦手さが見られるようであれば、早めにお近くの発達支援センターに相談し、言語聴覚士などによる療育を受けるようにしましょう。

発達障害の子どもの字が汚い理由④視覚イメージの操作が苦手

文字を書く時には、文字のバランスを考え、どの辺りから線を書き始めれば良いかを想定しながら筆を運ぶ必要があります。
そのため、字を書く際には常に頭の中で文字の全体像をイメージしておく必要があるのですが、この「文字の形を頭の中でイメージする」というプロセスが苦手なお子さまがいらっしゃいます。
視覚的なイメージを操作することが苦手なお子さまの場合、文字だけでなく絵や図形を描き写すことも苦手です。複雑な図形を描き写させてみると、「全体をとらえてから細部を書き込む」ということができず、バランスが悪かったり、図形同士の配置がバラバラになってしまったりするなどの傾向が見られます。
視覚イメージを扱うことが苦手なお子さまの場合は、全体から細部を捉えていくトレーニングを行います。具体的には、文字のパーツを色分けしたり、マス目を四分割したりして、どこにどのパーツが配置されているかを確認しながら文字を書いていきます。
文字を書くのが苦手なお子さまのために、1マスを空色、黄色、ピンク、緑色の4色のパステルカラーに分割した「カラーマスノート」などもありますので、学校の先生や言語聴覚士とも相談しながら活用してみると良いでしょう。(参考:小児科医と言語聴覚士が考えたノート。文字を正確に書き写せます。 | tobiraco(トビラコ))
発達障害で字が汚い場合の改善方法6選
発達障害で字が汚い場合は、単純な反復練習を繰り返すのではなく、なぜ字が汚くなっているのかを明らかにし、原因にアプローチしていく必要があります。
適切ではないトレーニングを繰り返しても字の汚さは改善できませんし、ますます字を書くことが嫌いになってしまう可能性もあります。「1.発達障害の子どもが字が汚い理由」で紹介したとおり、原因をしっかり見極めた上でトレーニングに取り組むようにしましょう。
また、書くことが苦手となっている原因を見極めるためには専門的な知識が必要です。発達支援センターや児童発達センターに相談し、言語聴覚士など専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。
発達障害で字が汚い場合の改善方法6選①音韻処理の向上

字の汚さの背景に音韻処理不全がある場合は、音韻処理機能を向上させるためのトレーニングに取り組みましょう。
音韻処理とは、文字と音の結びつきの処理ですので、文字を声に出して読みながら、同時に意味をイメージする練習を繰り返します。
一例として、分かち線を活用したトレーニング方法をご紹介します。
<分かち線を活用した音韻処理トレーニング>
※文章に目を通してもらうことが目的なので、読み方がたどたどしかったり、不自然に区切って読んだりしても指摘しない
② 先生が文章に分かち線を引く(例「私は/公園に/行きます」)
③ 先生が文章を音読し、子どもは分かち線を引いた文章を目で追う
④ 子どもに分かち線を引いた文章を音読してもらう
⑤ 子どもに分かち線を引いてもらう
このトレーニングを半年続けたところ、かなり強い読字障害があったお子さまも、周りの子どもたちと同程度にすらすらと音読できるようになりました。
このお子さまは書字障害もありましたが、読む力が付いたことで、書字障害についても少しずつ改善することができました。

また、「文字」「音」「イメージ」を一体的に捉えるために、机・いす・電話・冷蔵庫…など、身の回りの物にその名称を書いたシールを貼っておくことも効果的です。
併せて、それらの物が話題に出てきたときには、その物を指差しながら会話するのもおすすめです。
ほかにも、しりとりや言葉を逆さまから言ってみるなどの遊びを通して言葉に親しむのも良いでしょう。
発達障害で字が汚い場合の改善方法6選②姿勢の確認

発達性協調運動障害で身体を動かすことが苦手なお子さまの場合は、まず書く時の姿勢を確認してみましょう。
横から見たときに、耳-肩-骨盤が一直線になっていれば正しい姿勢です。姿勢を整えるだけで字がきれいになるお子さまもたくさんいらっしゃいます。
頭が前に出て猫背になり、骨盤が傾いてしまっている場合は要注意です。発達性協調運動障害だけでなく、身体を支える筋肉(体幹)が弱い可能性もありますので、体幹を鍛えるトレーニングなどにも取り組んでみましょう。
片足立ちやV字バランスなど、お子さまでも楽しく取り組めるトレーニングがありますので、YouTubeなどで調べてみると良いでしょう。
体幹が弱くすぐに転んでしまうような場合でも、決してお子さまのことを笑ったりからかったりせず、「難しいよね」「さっきよりはできたんじゃない?」など、お子さまが次も頑張ろうと思えるように声掛けすることが大切です。

発達障害で字が汚い場合の改善方法6選③書く行為に慣れる

「書く」という行為そのものに慣れることも大切です。まずはなぞり書きから始め、筆を運ぶという感覚をつかんでいきましょう。
サンドペーパーややすりなど、ざらざらしたものを紙の下に敷くと書きやすいというお子さまもいらっしゃいます。下敷きのようにつるつるした質感だと書きにくい場合もありますので、お子さまが書きやすい材質の物をそろえてあげると良いでしょう。
なぞり書きができたら、手本を見ながら書く「模写」に進みます。模写でバランスが崩れてしまう場合は、視覚イメージを扱うのが苦手な可能性がありますので、パーツごとに文字を色分けしたり、カラーマスノートを使ったりして、マス目のどこにどのパーツが配置されているかを意識しながら書く練習をすると良いでしょう。
模写ができるようになったら、耳で聞いた言葉を書く「聴写」に進みます。聴写ができれば書くことの困難はほぼ克服できたと言えますし、たとえ聴写まで進めなかったとしても、書くことには十分慣れることができているはずですので、お子さまの頑張りをしっかりと褒めてあげましょう。
発達障害で字が汚い場合の改善方法6選④鉛筆以外で書く

書くこと自体に抵抗感のあるお子さまは、鉛筆以外で文字を書くことから始めるのも良いでしょう。サインペンや筆を使っても良いですし、砂に指で字を書いてみるのも良いでしょう。
また、画用紙に大きく白抜きの文字を書いて色塗りするなど、文字の形そのものに親しむのもオススメです。
他にも、背中に指で文字を書き、何を書いているか当てるゲームなど、楽しみながら文字を書くことへの抵抗感を無くしていくと良いでしょう。
発達障害で字が汚い場合の改善方法6選⑤褒める

お子さまの字が汚いと、ついつい「きれいに書きなさい」と注意したくなってしまいます。
ですが、字を書くたびに注意を受けると、字を書くことがますます嫌いになってしまいますし、自分は丁寧に書いているつもりなのに「汚い」と指摘されることで自信を無くし、自己肯定感が下がってしまう場合もあります。
字が汚いお子さまに対して声掛けをする際には、良い部分を褒めるとともに、どうすればもっときれいに書けるかを具体的に教えてあげましょう。
発達障害のお子さまは、そもそもどうすればきれいに書けるかがわかっていない場合が多いため、
「(カラーマスノートを使って)水色の左上の方から書き始めると良いね」
「急がずゆっくり書いてみよう」
など、お子さまの特性に合わせた声掛けを行うことが大切です。
また、「マス目の中に書けている」「とめ・はねができている」など、ちょっとしたことでも構いませんので、こまめにしっかり褒めてあげることも意識しましょう。
発達障害で字が汚い場合の改善方法6選⑥キーボード入力の習得

字が綺麗に書けると、それだけで「賢そう」「礼儀正しそう」という印象を与えられるため、字が綺麗であるに越したことはありません。
ですが、最低限読めるレベルの字が書けていればテストで減点されることはないため、「お手本のようなきれいな字」を目指す必要は無いとも言えます。
ただ例外として、小学校の間はひらがなや漢字のとめ・はねでも減点される場合があります。お子さまの特性を学校の先生にも説明し、特性を踏まえた視点で採点してもらうようにしましょう。
先生によっては、「その子だけ甘く採点することはできない」と対応を断られる場合があるかもしれません。その場合は、減点はされていても、お子さまが一生懸命字が書けていることをご家庭でたっぷり褒めてあげるようにしましょう。
字を書くトレーニングに取り組む際には、お子さまのキャパシティを考え、どこまで綺麗に書くことを目指すかを考えておきましょう。
発達障害のお子さまの場合は、できることのキャパシティも限られていますし、字を綺麗に書くことに時間を割きすぎて、勉強やコミュニケーションなど、他のスキルのトレーニングが疎かになってしまっては本末転倒です。
また、大人になってからは手書きで文字を書く機会は非常に少なくなります。
どうしても書くことが苦手なお子さまの場合や、学年が上がって勉強の内容が高度になり、字を書く練習に時間を割くことが難しくなってきた場合は、キーボード入力に切り替え、タッチタイピングの練習をしていくことも大切です。
学校現場でも、LD(学習障害、SLD)に対する理解は徐々に広まりつつあり、合理的配慮としてキーボードやタブレット端末の使用が認められることも多くなっています。
大学共通試験でもこれらの配慮を受けることができますので、デジタル機器の活用を検討する場合は調べておくと良いでしょう。(参考:受験上の配慮 | 独立行政法人 大学入試センター (dnc.ac.jp))
また、公立学校だけでなく、私立学校でもデジタル機器を活用し、特性のある子どもたちへの配慮を行っている学校があります。
宿題の管理や家庭との連絡など、字を書くこと以外においてもデジタル機器は大きなメリットがありますので、私立学校を受験する場合は、デジタル機器の活用状況についてもチェックしておくと良いでしょう。

発達障害が字が汚い理由と解消法のまとめ

この記事では、発達障害の方が字が汚くなってしまう理由と、その改善方法について詳しく解説してきました。
改めてポイントをまとめると以下のとおりです。
<POINT>
- 生まれつきの要因で字が書くことが苦手な場合、LDの一つである「書字障害」に該当する
- 字が汚くなってしまう要因には、手先の不器用さ(発達性協調運動障害)や視覚イメージを扱うことの苦手さ、音韻処理の不全など様々なものがある
- 字が汚くなってしまう要因を明らかにし、適切なトレーニングを行うことが重要
- 字を書くことが嫌いになってしまわないよう、叱らず褒めることが大切
- 言葉遊びやゲームを使いながら、楽しく文字に親しむのも効果的
- 本人の負担感や大人になってからのことを踏まえ、キーボード入力を取り入れることも必要
発達障害のお子さまの字の汚さは、厳しく叱ったり、単純な反復練習を繰り返したりすることで改善できるものではありません。
なぜ字が汚くなってしまうのかをしっかりと分析し、原因に応じて適切なトレーニングに取り組む必要があります。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり発達障害のお子さまのサポートを行ってきました。
書くことに困難があるお子さまの指導もこれまでたくさん行ってきましたが、書くことへの苦手意識が解消できたことで、成績がぐんと伸びたお子さまはたくさんいらっしゃいます。
字が汚くなってしまう要因を分析し、改善に向けて適切なアプローチを行うためには、専門的な知識を持った指導者のサポートが欠かせません。
経験豊富な講師たちがお子さまをしっかりサポートいたしますので、お子さまの書字障害についてお悩みの方は、ぜひプロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。

また、指導や面談はオンラインでも承っています。
全国各地からご利用いただけるほか、これまで海外にお住まいの方や帰国子女の方にもご利用いただき、ご好評の声をいただいてきました。
初回授業・初回ご相談は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか心配なお子さまも、お気軽にお試しいただくことができます。

1人でも多くのお子さまが、自分らしく社会で活躍していけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。