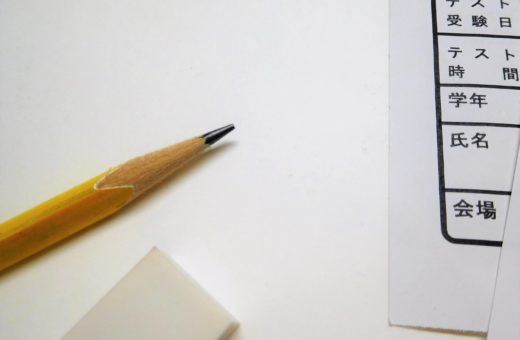【不登校の中・高校生へ】1学期中間テストが終わったタイミングでやるべきこと(期末テストに向けて)
●中間テストは受けてくれたものの、点数が悪く、不登校が加速した
●期末テストに向けて、どうすれば良いのでしょうか?
この時期、上記のことで本当にご不安な方が多くいらっしゃると思います。
だからこそ、期末テストに向けてどうすれば良いか。
不登校の小学生・中学生・高校生専門のプロ家庭教師が蓄積してきたノウハウを包み隠さずご紹介します。

不登校専門の受験プロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▼目次
中間テストを受けられなかった中学・高校生に向けて

経験則的に、不登校は真面目なお子様がなることが多いです。
成績下位で不真面目なお子様がなるのではなく、成績中上位の真面目なお子様がなることが多い実感です。
そのため、中間テストを受けられなかった事実を、一番重く受け止めているのは、お子様自身であることが多いです。
実際にお子様が真面目で完璧主義であれば、上述の事実を念頭に置いて接することが重要です。
具体的には、以下の3つを押さえておくことだと思います。
②:受けられなかったことを責めるような発言、期末テストを匂わせる発言は余計に追い詰めてしまうので、避けた方が良いこと
③:沈んでいる時期の良薬は時間。お子様が沈みきって、浮上するまで待ってあげること
不登校のそれぞれの時期により、最適なアプローチが異なるにあるように、気持ちが沈んでいる時の最適な対応は「家庭が居場所になること」「家族が本人以上に余裕を持って安心感を与えること」です。
さらに、重要なことは、「どう伝えたか」ではなく「どのようにお子様が感じ取るか」です。
お子様への言動や雰囲気などから醸しでる接し方で、お子様がどのように感じとりそうか。どう接すれば「家族は味方だ。自分のことを大丈夫だと思ってくれているんだ」と受け取ってくれそうか。
上記を考えた上で接することが何より重要だと思います。
「不登校のお子様が自宅で、どのようなことを考えていたか?」
登校に至ったお子様から聞き取った実際のお気持ちの記事もよろしければご参照ください。
不登校の保護者様は真面目で、きちんとされている方が多く、上記のような悠長な対応はご不安だと思います。ですが、急がば回れです。
是非、実践して頂き、お子様が少しでも早く浮上されることを心から願ってます。
浮上してからの対応、どうすれば良いか?
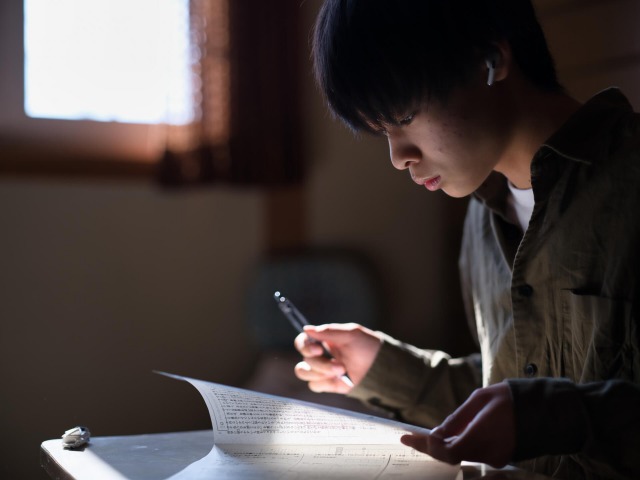
期末テストに間に合うなら、「学習面で余裕を持った状態で期末テストを受けること」が重要です。
なぜなら、期末テストも受けられなかった、もしくは受けたものの結果が散々であれば、お子様はさらに傷ついてしまうからです。そうなると、登校への気持ちは遠ざかります。
そうならないためにも、期末テストでは結果を出す必要があります。
以下では、期末テストで結果を出す具体的方法を記載します。
期末テストで成果を出す勉強方法
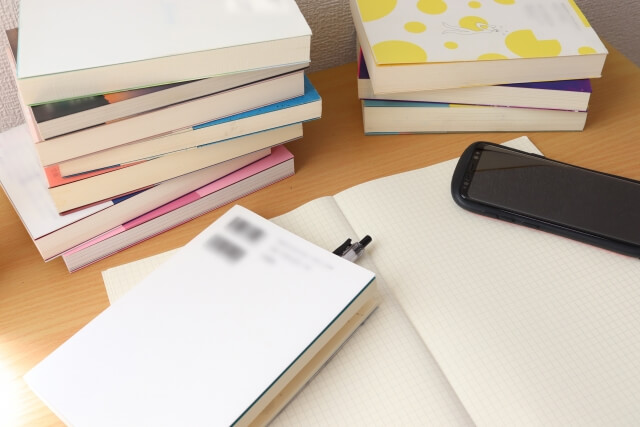
中学・高校では、中間テストから期末テストまで、1ヶ月ほどしかない学校が大半だと思います。
結論から申しますと、期末テストで全教科成果を出すことは、相当難しいと思います。
そのため、お勧めは「科目や分野を絞って対策すること」と「お子様が、勉強ついていけそうと希望を持てること」の2つです。
どちらも、具体的な対策をご紹介します。
科目や分野を絞って対策すること
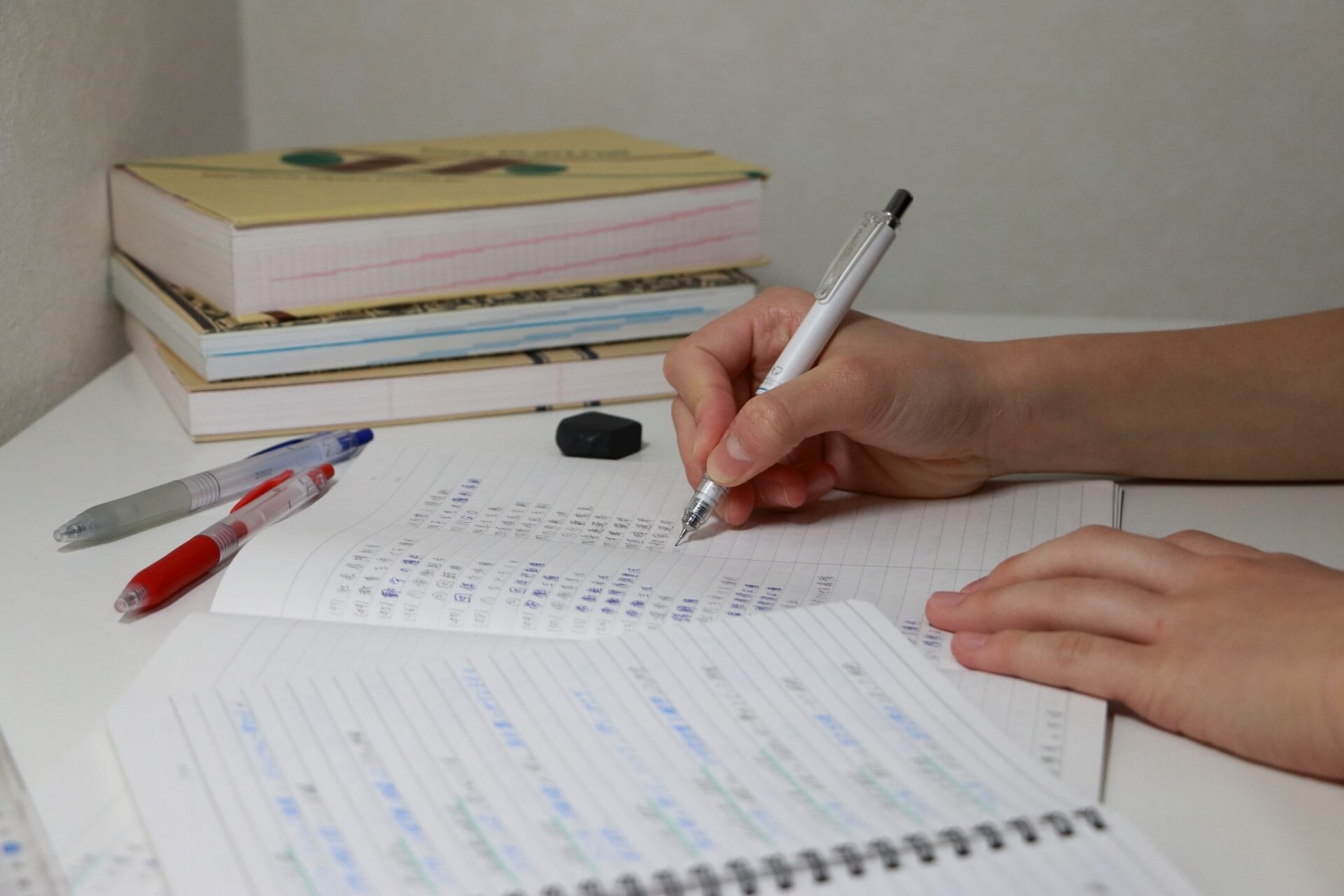
公立中学生でしたらテストは5教科、私立中学生や高校生であれば5教科10科目に加えて、期末テストは副教科も入ることが多いです。
どの科目を重点的に対策することが重要か?
登校を目標とするなら、「お子様が学習で期待が持てる科目で対策する」が重要です。
お子様の性格や価値観によりますが、個人的には以下の対策をお勧めします。
公立高校志望の受験生の場合
副教科を重点的に対策することをお勧めします。
都道府県ごとに内心点上の特典は異なりますが、理由は以下の3つです。
②副教科は期末テストのみであることが多く、この1回のテストで内申点を大きく左右すること
③副教科の対策に力を入れる受験生が少なく、成果が出やすいこと
私立高校志望の受験生の場合、または受験生ではない中学生の場合

苦手科目でも十分に点数を伸ばせそうなら苦手科目。
苦手科目が十分に点数を伸ばせなさそうなら、得意科目を重点的に対策することをお勧めします。
苦手科目を優先した理由は、苦手科目で点数が伸びれば、お子様が大きく自信や希望を持てるからです。
だからこそ、苦手科目で点数が伸びそうにないなら、自信や希望が持てません。
その場合、得意科目で対策をして成果を出すことをお勧めします。
苦手科目で点数を伸ばすよりも実感値は下がりますが、通用するものがあると自信や期待を持てるお子様は多いです。
高校生の場合
高校生は大学受験を意識した勉強方法をお勧めします。
特に学年が1年生、次に2年生であれば、受験で使用しない科目が定期テストに入っていることが多いです。
そのため、受験で使用する科目を勉強することをお勧めします。
受験で使用する科目の中の優先順位は、上記の「私立高校志望の受験生の場合〜」と同じです。
お子様が、勉強でついていけそうと希望を持てること

最後に、大切なことは期末テスト前後で「勉強でついていけそうという希望」をお子様が強く持てることです。
例えば、以下は指導の場面で私が言うことが多いものです。
②:夏休みや冬休みなど、長期休暇でまとまった時間を勉強すれば、同年代の友達に追いつける可能性が高いこと
③:勉強はやり方次第で大きく効率的、効果的に成果を出せること
「本当のことを言うこと」が重要ですが、上記に限らず、「お子様が勉強をついていけそうと希望を持てる」なら、他のものでも良いです。
上記が、不登校のお子様が少しでも登校に至るきっかけになれば、何よりです。