アスペルガー(ASD)の子育てはどうする?子どもの特徴と接し方を解説
・何度も同じことで注意するので、親も子どももストレスを感じている
・友達付き合いや集団行動に関わるトラブルが多い
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)のお子さまのことで、このようなお悩みをお持ちの保護者さまはいらっしゃいませんか?
アスペルガーのお子さまは、表情やニュアンスから相手の気持ちを読み取るのが苦手なため、保護者さまの思いが伝わりづらく、もどかしく感じている方も多いと思います。
私は、発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として、長年にわたり活動してきました。
1500人以上のお子さまをサポートする中で、アスペルガーのお子さま特有の難しさを実感する場面も多くありましたが、お子さまの特性を正しく理解し真摯に向き合うことが、困りごとの解決につながると感じています。
アスペルガーの最も特徴的な特性は、「社会性・コミュニケーションの困難」と「パターン化された興味・行動」の2つです。これらは生まれつきの脳の性質によるものであり、保護者さまの子育ての方法などは関係ありません。
また、お子さまの性格の問題や、努力不足が原因であるというわけでもありません。
周りの人には理解できないような行動も、お子さま本人の中では筋の通った理由がある場合もあります。頭ごなしに叱ることはできるだけ避け、なぜその行動を取ったのかを聞いてみることが大切です。
「何度言っても伝わらない」というのも、アスペルガーのお子さまの子育てでありがちな困りごとです。
多くの場合、お子さまの中で指示に納得できない理由がありますので、視点を変えて伝えてみたり、なぜそうしてほしいのかを具体的に伝えてみたりするなど、アスペルガーのお子さまでも指示の意図を理解できるよう工夫してみると良いでしょう。
・アスペルガーの子どもへの接し方のポイントを知りたい
・アスペルガーの子どもの特性について理解したい
この記事では、アスペルガーのお子さまをお持ちの保護者さまに向けて、アスペルガーの特徴や接し方について詳しく解説していきます。
ご関心のある方は、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
▼目次
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと子どもの特徴

アスペルガー症候群とは、ASD(自閉スペクトラム症、Autism Spectrum Disorder)に分類される発達障害の一つで、知的障害や言葉の遅れは無いものの、「コミュニケーションの困難」や「パターン化された興味・行動」といった特性があります。
ASDのうち、知的障害と言葉の遅れがある場合は自閉症、知的障害が無く言葉の遅れがある場合は高機能自閉症に分類されますが、自閉スペクトラム症の名称にもあるとおり、それぞれの特性には連続性=スペクトラムがあり、厳密に区分することが難しい面もあります。
そのため、医師が診断する際には、「アスペルガー症候群」という名称はほとんど使われず、多くの場合、診断名は「ASD(自閉スペクトラム症)」となります。
(参考:子どもの発達障害 「自閉スペクトラム症(ASD)」とは?アスペルガー症候群などとの違い | NHK健康チャンネル)
アスペルガーのお子さまの特徴には、
・自分の好きなこと(例:電車やバス、国旗など)に関して大人顔負けの知識を持つ
などが挙げられます。
自分だけの強いこだわりを持つことも多く、「相手の気持ちが分からない」「協調性が無い」という評価を受けてしまうこともありますが、お子さまの行動の背景にはアスペルガーの特性が深く関係していますので、特性をきちんと理解し対処することが大切です。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと子どもの特徴①コミュニケーションや社会性の困難

アスペルガーの最も特徴的な特性の一つが、「コミュニケーションや社会性の困難」です。
アスペルガーの人は表情や雰囲気から他者の気持ちを読み取ったりするのが苦手です。
一方、社会生活においては、その場の空気を読んだり、明文化されていないルールや常識を感じ取って行動したりすることが求められる場面が多くあります。
アスペルガーのお子さまはこういった「察する力」が乏しいため、学校や家庭生活で以下のような困りごとを抱える場合があります。
・空気を読まない発言をしてしまう
・悪気無く相手を傷つける発言をする
・表情やジェスチャーがぎこちなく、感情が読み取りづらい
・自分の話ばかりを一方的にしてしまう
・複数人で行動するよりも一人が好きで、協調性に乏しい
・堅苦しい言い回しなど、独特で距離感のある話し方をする
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと子どもの特徴②パターン化された興味・行動

コミュニケーションや社会性の困難とともに、「パターン化された興味・行動」もアスペルガーの特性の一つになります。
アスペルガーのお子さまは、未来のことを想像するのが苦手で、いつもと同じであることに安心する傾向にあります。
そのため、「いつもと同じルーティンで過ごしたい」という行動のパターン化や、「新しい物事には挑戦したくない」という興味の限定などの特性が現れます。
自分が興味のあることについてはとことん追求できるため、幼い頃には“電車博士”や“バス博士”として注目を浴びる一方、成長に従い柔軟性の無さが目立つようになる場合もあります。
急な予定の変更によるパニックや、臨機応変な対応の苦手さなど、パターン化された興味・行動という特性からは以下のような困りごとが生じやすくなります。
・自分の決めたルールに極端に固執する
・一つの物事に過剰に熱中し、その他の物事には関心を持たない
・ルーティンを好み、イレギュラーや新たな挑戦を避ける
・急に予定が変更されるとパニックになる
・臨機応変な対応が苦手、融通が利かない

アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと発達段階

アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)のお子さまは、知的障害や言葉の遅れが無いため、幼児期には特性に気付きにくいと言われていました。
ですが、最近の研究結果から、アスペルガーのお子さまは幼児期においても以下のような特徴が見られることが分かっています。
・同じ遊びを繰り返すことが多い
・パターン化した行動が見られる
・融通が利かない
・一人遊びが多い
・同年代の子どもにあまり関心が無い
早い段階からアスペルガーの特性に気付くことができれば、それだけ早く適切なサポートを受けることができます。
アスペルガーのお子さまは、幼稚園や保育所の集団生活の中で大きなストレスを感じている可能性もありますので、早めに対処することが非常に重要です。
また、早いうちにお子さまの特性を理解することは、お子さま自身の持っている力や可能性を伸ばすことにもつながります。
以下では発達段階ごとのアスペルガーのお子さまの特徴をご紹介しますので、気になることがある場合は医療機関や保健師、幼稚園・保育所・学校の先生などに相談するようにしましょう。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと発達段階①乳児期(0~1歳)

乳児においては、言語・認知・学習などの領域は未発達ですので、この時期にアスペルガーの診断はできません。
発達障害の赤ちゃんの特徴として、
・よく泣く(あるいは泣かない)
・人見知りしない(あるいは極端に人見知りする)
・音や光に敏感
といった特徴が挙げられることもありますが、赤ちゃんの発達は個人差が大きいため、これらに当てはまるからと言って必ずしも発達障害であるとは限りません。
いずれにせよ、この段階で診断することはできず、ましてや療育に取り組むこともできませんので、目の前の赤ちゃんにしっかり愛情を注ぎ、今しかない“赤ちゃんが可愛い時期”を堪能すると良いのではないでしょうか。
どうしても気になることがある場合には、かかりつけの医師や地域の保健師などに相談してみると良いでしょう。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと発達段階②幼児期(1~6歳)
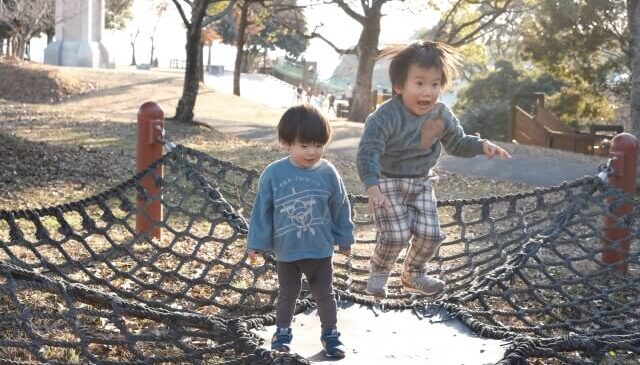
幼児期になると、言葉を覚え会話ができるようになります。
「言われたことをそのまま受け取ってしまう」というのは幼い子どもにはよく見られる言動ですが、そのほかにも、
・相手の気持ちを気にせず、思ったことをそのまま口に出してしまう(「嫌い」「太っている」など)
・一人遊びを好む
・同年代の子どもたちと交流せず、関心を持たない
・関心のあることに熱中し、大人以上に知識を蓄える
など複数の特徴が見られる場合は、アスペルガーの可能性があります。
気になる行動がある場合や、保育所や幼稚園で本人がストレスを感じていたり、保護者さまが子育てで困っていたりする場合は、早めに医師や地域の発達支援センターなどに相談するようにしましょう。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てと発達段階③児童期(6~12歳)
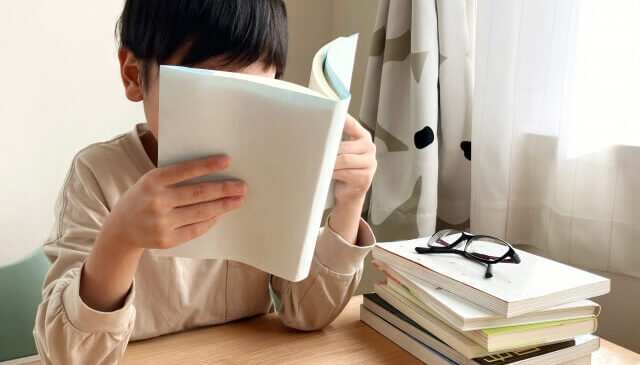
集団生活が本格化するとともに、周りのコミュニケーションのレベルがぐっと上がります。
協調性が求められる場面も増えるため、学校に馴染めないなどの困りごとが増える時期になります。
勉強面でも、小学校3年生くらいまでは問題無いケースが多いものの、高学年になって複雑な文章を理解したり、登場人物の心情を理解する問題が増えてくると、勉強でつまずくようになるお子さまもいらっしゃいます。
学校の先生とも協力しながら、本人の特性に合わせたサポートを行うことがポイントです。
特に、
・音や光など感覚過敏に関する対処
・「何となくわかるだろう」を避け、一つ一つ言葉にして伝えること
などは、アスペルガーのお子さまのサポートにおいて非常に重要ですので、スクールカウンセラーなども交えながら学校全体で対応してもらうようにしましょう。
ただし、お子さま一人だけを見ていられるご家庭と、1人の先生で30人以上の子どもたちを見なければならない学校とでは、環境に大きな違いがあります。
どこまで対応可能かを家庭と学校でしっかり擦り合わせることも、学校と家庭の連携においては非常に重要なポイントです。

アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのポイント5選

アスペルガーのお子さまは、言外のニュアンスや表情を読み取ることが苦手なので、保護者さまが注意しても意図が伝わらず、何度も同じ注意を繰り返すことになってしまう場合があります。
また、保護者さまであっても、お子さま独自のこだわりに付いていけず、「我が子と分かり合えない、我が子が理解できない」とお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
子育てにおいて、不安を感じたりイライラしたりすることは当然あると思います。ストレスを溜めすぎると、保護者さま自身が心身の調子を崩してしまいますので、ご家庭だけで抱え込まず、学校や地域の発達支援センター、医療機関などを頼りながら、焦らず対処するようにしましょう。
ただ1点だけ注意していただきたいのは、お子さまに対してイライラを直接ぶつけることは避ける、ということです。
「皆と同じようにしなさい」
といった言葉は、大人が思っている以上にお子さまの自己肯定感を傷つけてしまいます。
どうしてできないのか?と問うても、自分ではどうしようもない「脳の特性」による言動ですので、アスペルガーのお子さまには答えることができない状態であることがほとんどです。
こういった叱責を受けると、お子さまは、
・自分の親でさえ、自分の存在を否定するんだ
・自分ではどうしようもないことを責めるなんて、親は自分をわかってくれない
といった自己否定的な思考に陥ってしまい、大人になってからも生きづらさに悩むことにつながります。
アスペルガーの特性そのものを無くすことはできませんが、「どんな言葉が人を不快にさせるのか」「この場面ではどのように対応するのが適切か」といったことを一つずつパターンとして習得することで、アスペルガーのお子さまは社会性を身につけていくことができます。
発達支援センターなどで行われる療育では、遊びやロールプレイングを通して、社会性を身につけるためのソーシャルスキルトレーニングを受けることができます。
また、発達支援センターにおける療育だけではなく、ご家庭の中で経験を積み重ねていくことも非常に重要ですので、以下ではアスペルガーのお子さまに保護者さまが接する際のポイントを順に解説していきます。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのポイント①はっきり伝える

アスペルガーのお子さまは、言葉の行間を読むことが苦手です。
「言わずもがな」は通じませんので、叱ったり指示を出したりするときは、一つずつ言語化して伝えることを意識しましょう。
「なぜダメだと思う?」とお子さま自身に考えさせる手法も、アスペルガーのお子さまには不向きです。自力で考えて理解できることはほぼありませんので、ダメな理由を保護者さまからはっきりと伝えるようにしましょう。
同様に、単に「ダメでしょ!」と伝えるのも効果がありません。
なぜ叱られているのかが分からず、理由なく怒られたと感じて自己肯定感が下がってしまうか、大人は理不尽であると感じて、ますます指示を聞かなくなってしまう可能性があります。
例えば、アスペルガーのお子さまがお友達に対して、「○○ちゃんは太っているね!」と発言したとします。
このような場合には、
②なぜなら、太っていることを指摘されると傷つくから
ということをまずははっきりと伝えましょう。
さらに理解力があるお子さまの場合には、①②に加えて、
④なぜなら、その人がコンプレックスに感じている場合、指摘されると傷つくから
といったように、一般化した形で伝えてみましょう。
なぜダメなのかがお子さまの中で納得できれば、次から同じような失敗を避けることができます。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのポイント②曖昧な表現を避ける

アスペルガーのお子さまは曖昧な表現が苦手なため、「あれ・それ・これ」などの指示語が理解できないケースがあります。
「それを取って」と言わずに、「赤色のボールペンを取って」など具体的に伝えるようにしましょう。
同様に、アスペルガーのお子さまは省略された表現も苦手です。
「座って」と伝えれば椅子に座るものと大人が思っていても、床なのか、椅子なのか、はたまたベッドなのか、アスペルガーのお子さまには全てが選択肢に入ってしまいます。
ですので、「自分の椅子に座ってね」など具体的に伝えるようにしましょう。
とはいえ、指示語や省略された表現などはついつい使ってしまうものです。
指示が分からないと思ったら、「それってどれ?」「どこに座ればいい?」と聞き返すスキルも重要ですので、お子さまには、わからなかったら聞き返していいんだよと伝えておくことも大切です。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのポイント③急な予定変更を避ける
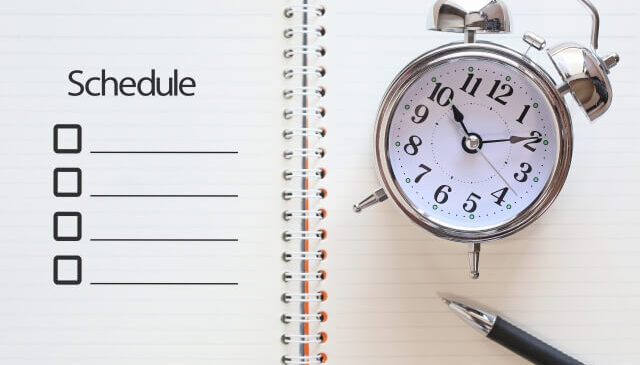
アスペルガーのお子さまの中には、急な予定の変化が苦手でパニックになってしまう方がいらっしゃいます。
いつもと同じルーティンを好む傾向にありますので、毎日の朝の準備や学校から帰った後にやることなどは、時間割を作ってその通りに進めるのがオススメです。
どうしてもいつもと違うことをしなければならないときは、できる限り事前に伝えるようにしましょう。
「来週の○日は遠方の祖父母の家に行くから、いつもより1時間早く起きるよ」など、できるだけ早めに、予定変更の理由も含めて伝えておくことがポイントです。
時間割や教室の変更など、学校でもイレギュラーなことは日々起こります。
その都度パニックになってしまってはお子さま自身も辛いので、できるだけ事前に連絡してほしい旨を学校に伝えておくとよいでしょう。
ただ、急な変更がどうしても避けられない状況もありますので、パニックになったときの対応を考えておくことも大切です。
静かな場所に移動する、お気に入りのハンカチを持っておくなど、いざとなった時に心を落ち着ける方法を想定しておきましょう。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのポイント④感覚過敏への対応

アスペルガーのお子さまは、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚などの感覚が非常に敏感な場合があります。
大きい音や激しい光が苦手というだけでなく、特定の音・におい・味などが苦手な場合もありますので、苦手な刺激についてはできるだけ遠ざけてあげるようにしましょう。
にぎやかな場所ではノイズキャンセラーやイヤーマフなど、道具を使う方法もあります。
パーカーのフードを被るだけで安心できるというお子さまもいらっしゃいますので、個々に合わせて工夫してみると良いでしょう。
味覚の過敏さについては、好き嫌いや偏食のように見えるかもしれません。ですが、アスペルガーのお子さまにとってはどうしても受け入れられない刺激かもしれませんので、無理させることは避けましょう。
栄養失調になるほどの偏食であれば問題ですが、味覚過敏や偏食は成長とともに収まることも多く、よほどの場合以外は様子見で構いません。
身体に触られることが苦手なお子さまもいらっしゃいます。
手をつなぐ、抱っこする、お風呂で体を洗ってあげるなどを嫌がる場合も、無理は禁物です。安全上手をつなぐ必要がある場合は、お子さま用のハーネスの利用などを検討してみましょう。
お風呂については、お子さまの機嫌が良いタイミングを見計らってみたり、「今からお腹を触るね」など声を掛けながら洗ったりすると良いでしょう。
アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのポイント⑤否定しない

アスペルガーのお子さまは、人を傷つける発言をしてしまうことが多い一方、自分自身も傷つきやすい傾向にあります。
お子さまのことを思っての注意であっても、アスペルガーのお子さまの場合はその真意を汲み取ることが苦手なので、「大きな声を出されて怖かった」「怒られている意味が分からない。お父さん/お母さんは自分のことが嫌いなのかな…」と受け止めてしまうことがあります。
厳しい言い方を避けるとともに、「○○してほしいから言っただけで、あなたのことが嫌いなわけじゃないよ」と丁寧に伝えることを意識しましょう。
保護者さまがお子さまを大切に思っていることは、大人にとっては当然かもしれませんが、お子さまにとっては言わなければ伝わらないことがあります。
また、アスペルガーのお子さまは、自分の好きなことには夢中になれる一方、自分の興味の無いものには関心を持ちづらい傾向にあります。
そのため、得意と苦手もはっきりと分かれやすいのですが、苦手なことだけに注目するのではなく、得意なことを伸ばす視点を大切にしましょう。
「同じ本ばかり読んでいないで、別の本も読んでほしい」など、保護者さまとしては色々なものに興味を持ってほしいと思うかもしれませんが、同じものにこだわることでお子さま自身は安心感を得ていたり、特定の分野を究めることで自信につながっていたりします。
対人関係や日常生活に支障の無い範囲であれば、こだわりを無理にやめさせることは避け、思いっきり集中させてあげる方が良いでしょう。

アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)の子育てのまとめ
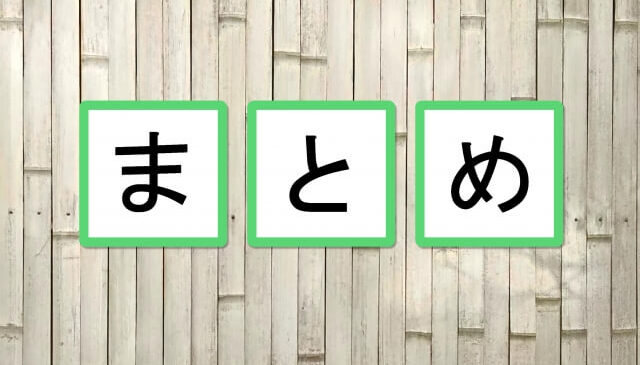
この記事では、アスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)のお子さまの子育てについて詳しく説明してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
・アスペルガーのお子さまの困りごとには、「集団行動が苦手」「相手の気持ちを察せない」などがある
・アスペルガーの特性に早くから気付き、早めに対処することが重要
・どの場面で、どのような言動が適切かを一つ一つ学んでいくことで、社会性を身につけることができる
・頭ごなしに叱らず、「なぜダメなのか」を言葉で伝えることが大切
・興味のあることやこだわりを尊重し、得意なことを伸ばす視点も重要
アスペルガーをはじめ、発達障害のお子さまは、学校でも叱られたりすることが多く、自己肯定感が下がってしまいがちです。
ご家庭においては、お子さまの特性をしっかり理解し、寄り添いながらサポートしていただければと思います。
アスペルガーのお子さまの子育てにおいて、イライラや不安が募っている場合は、無理せず周りを頼るようにしましょう。
学校にはスクールカウンセラーが配置されていますし、地域の発達支援センターや医療機関などには、専門的な知識を持つスペシャリストがたくさんいますので、困ったときは積極的に相談するようにしましょう。
勉強のことでお悩みの場合は、プロ家庭教師を利用するのもオススメです。
アスペルガーについて理解のある講師であれば、特性を上手くカバーしつつ教えてもらうことができます。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年の指導経験に基づく確かなノウハウと、お子さま一人一人に寄り添った指導をモットーに、これまで多くのお子さまのサポートに取り組んできました。
学習の指導だけでなく、日頃の勉強のフォローや進路のご提案など、様々なサポートを行っていますので、なかなか良い塾や家庭教師に出会えずお困りの方は、ぜひ一度お問い合わせください。

また、授業や面談はオンラインでも承っています。
日本国内だけでなく、海外にお住まいの方や帰国子女の方からもこれまでご利用いただき、ご好評の声をいただいてきました。
初回相談・授業は無料で承っていますので、オンラインでの授業が不安な方もお気軽にお試しいただけます。
1人でも多くのお子さまが、個性を生かしながら自分らしく人生を歩んでいけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。







