東大にはアスペルガー(ASD)が多くプライドが高い?高学歴な発達障害の特徴とは
高学歴とアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)に関して、次のような疑問をお持ちの方はいらっしゃいませんか?
- 東大生の4人に1人はアスペルガーって本当?
- 高学歴の人にアスペルガーは多いの?
- アスペルガーは突出した才能を持っている?
また、アスペルガー以外の発達障害(ADHD)でも、高学歴な人が多いというイメージを持っている方もいらっしゃるかもしれません。
実際に、筆者の知り合いの東大生や京大生も「同じサークルやゼミの学生に、発達障害らしい特性を持っている人がいる」という話をよくしています。
私は、発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として長年にわたり活動してきました。
1500人以上のお子さまをサポートする中で、難関校に合格したアスペルガーのお子さまもたくさんいらっしゃいましたが、一方で、アスペルガーだからと言って全員が難関校を目指したり、志望校に合格したりしているわけではありません。
アスペルガーのお子さまは、一つのことにこだわり、どこまでも追求できるという特性を持っています。
一度ハマるとずっと熱中できるため、受験においても「数学にハマった!」「歴史が面白くてたまらない!」というお子さまは、学校の先生を遥かに上回る知識を身に付け、受験も易々とクリアしてしまう場合があります。
また、受験はある意味では点数を稼ぐゲームとも言えるため、アスペルガーのお子さまの中には、“受験そのもの”にハマる方もいらっしゃいます。「点数が伸びていくのが楽しい」「C判定からB判定、A判定へと上がっていくのがゲームのレベルアップみたい」と楽しみながら受験を乗り越えるお子さまも少なくありません。
統計的にはアスペルガーや発達障害の方の平均的なIQは定型発達の人と変わらないと言われている一方で、高学歴のアスペルガーの方が多いように感じるのは、こういった特定の科目や受験そのものにのめり込むタイプのお子さまが一定数いることが理由の一つとして考えられます。
この記事では、大学受験を控えているアスペルガーご本人の方や、その保護者さまに向けて、アスペルガーの方が難関大学を受験するときのポイントや、就職までを見据えた進路の考え方について詳しく説明していきます。
少しでもご関心のある方は、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
- アスペルガーの特性を活かして難関校に合格したい
- アスペルガーに適した勉強方法を知りたい
- アスペルガーならではの強みを伸ばしたい
▼目次
- 1 アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由
- 1.1 アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由①ルーティンワークが得意で、学習習慣が確立しやすい
- 1.2 アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由②熱中すると、とことん追求できること
- 1.3 アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由③理系科目に強く、暗記も得意
- 1.4 アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由④感覚ではなく論理で思考できる
- 1.5 アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由⑤難関校では、互いの個性を尊重できる人同士で過ごせる
- 2 東大卒など高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方の困りごとの3つの例
- 3 東大生や高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害のまとめ
アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由

東大生にはアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方が多いという説は時々耳にしますが、正確な統計があるわけではありません。
また、知能指数(IQ)の分布を参照してみても、定型発達とアスペルガーや発達障害でIQの分布に違いは無く、アスペルガーだからといって必ずしもIQが高いというわけではありません。
- IQ70未満…知的障害に該当〔2.2%〕
- IQ70~80…境界知能(知的障害とのグレーゾーン)〔5.8%〕
- IQ81~89…平均を下回る〔14%〕
- IQ90~109…平均〔47%〕
- IQ110~119…平均を上回る〔15%〕
- IQ120~129…優れている〔6.4%〕
- IQ130以上…非常に優れている(ギフテッド)〔2.7%〕
したがって、「アスペルガーには知能が高い人が多いため、難関校の学生にはアスペルガーが多い」という説は成り立ちません。
しかし、東大や京大などの難関大学の学生にアスペルガーや発達障害を持つ人が多いということは、学生や大学関係者の間では実感を伴って語られていることであり、一概に否定することも難しいと言えます。
ではなぜ、東大や京大などの難関校にはアスペルガーや発達障害の学生が多いと感じられるのでしょうか。
それには、以下の5つの理由が考えられます。
- ルーティンワークが得意で、学習習慣が確立しやすいこと
- 熱中すると、とことん追求できること
- 数の処理が得意で、理系科目に強いこと
- 感覚ではなく論理で思考できること
- 難関校では、互いの個性を尊重できる人同士で過ごせること
アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由①ルーティンワークが得意で、学習習慣が確立しやすい

発達障害の中でも、特にアスペルガーの方は、新しいことに挑戦するよりも、いつもと同じ方法を繰り返すルーティンを好む傾向にあります。
そのため、毎日のルーティンに勉強を組み込むことでストレスなく学習習慣を身につけることができます。これによってコツコツと知識を積み上げることができるため、長期戦となる難関校受験においては圧倒的な強みを得ることができます。
私が指導してきたアスペルガーのお子さまの多くは、学習習慣の定着が定型発達のお子さまと比べて遥かに早く、「夜7時半から9時までは勉強タイムにしよう」などと伝えると、しっかり机に向かってくれる方がほとんどでした。
アスペルガーの方は言葉をそのまま受け止める真面目さも持っており、信頼できる先生の指示には素直に従ってくれるという点においても学習習慣が定着しやすいと言えます。
また、アスペルガーの方は未来のことを想像するのが苦手なため、「頑張れば何とかなる」といった曖昧な言い方よりも、「毎日勉強すると点数が○点ずつ伸びていき、1月の受験までには合格点に届く」というように、先のことを具体的に示すことも大事なポイントです。
見通しが持てることで、本人の中でさらに納得感を持って勉強に取り組めるようになります。
アスペルガーのお子さまは、適切に声掛けやサポートしてあげることで勉強の効率が飛躍的にアップすることも多いです。
アスペルガーの特性を踏まえた学習指導ができる講師をお探しの方は、ぜひ発達障害・ギフテッド専門のプロ家庭教師メガジュンまでご相談ください。
アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由②熱中すると、とことん追求できること
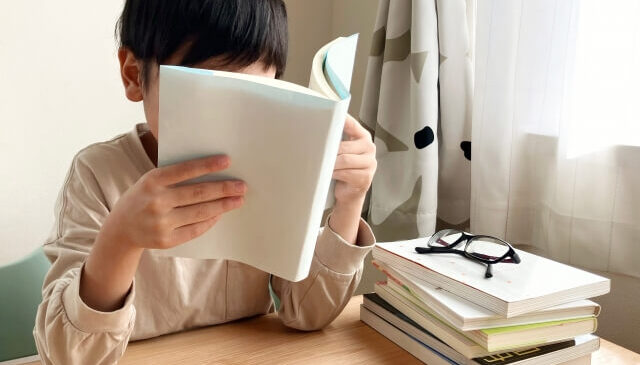
「一度ハマると、徹底的にやり続ける」というのはアスペルガーや発達障害の方の大きな特徴の一つです。
電車やアイドル、アニメやゲームなど、特定のものが大好きで、膨大な知識を蓄えていたり、話し始めると止まらなかったりするなど、アスペルガーの方が何かにハマっている様子を見たことがある方も多いのではないでしょうか。
ハマる対象が勉強に関係するもの(数学、物理学、歴史など)であれば、それだけで受験において大きな強みになります。
東大・京大レベルですと文理問わず得点することが必要になりますが、一部の私立大学であれば、「数学だけ」「歴史だけ」でも受験を突破できる場合があります。
さらに、受験そのものにハマるタイプの方もいらっしゃいます。
ある意味では受験は得点を競うゲームであり、オンラインゲームに熱中するような感覚で、模試の順位争いに熱を上げるタイプのお子さまもいらっしゃいます。
また、「難しい試験に受かること」や「勉強することそのもの」に喜びを感じるタイプの方は、大人になってからも資格マニアとして、様々な難関資格の取得を目指すことがあります。
資格を取得すると就職で有利にはなりますが、使わない資格をたくさん持っているよりも実際に働いた経験を重視する企業も多いため、本当に必要な資格を優先的に取得し、それ以外のものはあくまで趣味としてチャレンジすると良いでしょう。
なお、「一つの物事に熱中する」という性質は、アスペルガーだけでなくADHDの方にも見られます。
ADHDの方は集中力や興味・関心をコントロールするのが生まれつき苦手なため、一度物事に熱中すると、そのことにばかり気を取られて寝食さえ忘れてしまうことがあります。
この状態は「過集中」と呼ばれますが、受験においても「志望校に合格しなければならない」という考えで頭が一杯になり、寝る間を惜しんで勉強してしまうADHDの方もいらっしゃいます。
極端な過集中は健康を損ないかねないため、周りが声掛けなどをして過集中の状態から離脱させてあげる必要がありますが、過集中だからこそ定型発達の人には真似できないほどの努力ができ、結果として難関大学に合格できることもあります。
ADHDの方の過集中にはデメリットもありますので、周りの人のサポートを得ながら、上手く特性を生かしていくようにしましょう。

アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由③理系科目に強く、暗記も得意
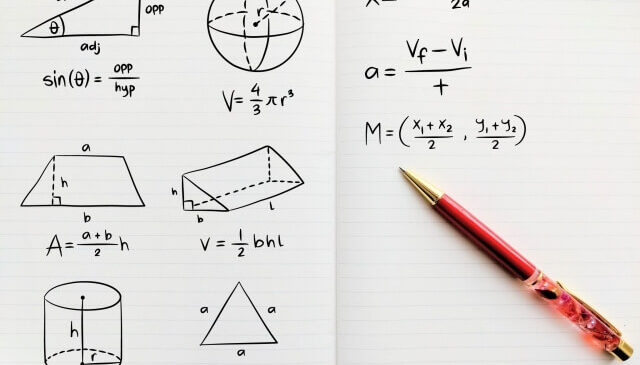
アスペルガーのお子さまは、幼いころから数字に強い興味を持つことがあります。
筆者が受け持ったお子さまの中には、文字よりも先に数字を覚えたり、円周率を覚えるのが特技という方がいらっしゃいました。
難関大学の受験においては、数学などの理系科目が合否を分けるパターンが非常に多いのですが、アスペルガーの方は幼い頃から数字に親しみを持ち、文系科目よりも理系科目が得意な傾向にあるため、受験を有利に進められる場合が多いです。
以前に私が教えていたあるお子さまは、数字の羅列に強く惹かれる性質を持っており、幼稚園の頃から電車の時刻表を覚えるのが好きでした。
時刻表をひと通り覚えた後は円周率を覚えることに没頭し、その後、小学校の高学年になってからは毎日の気温と気圧を記録するのが日々のルーティンになりました(ご家庭で購読していた新聞の天気予報がたまたま目に入ったことがきっかけだったそうです)。
毎日の気温の記録は、夏休みの自由研究として学校で賞を取ることができ、お子さまの自信につながりました。
気象学者になるのがそのお子さまの夢になり、夢への第一歩として現在は受験勉強に励んでおられます。もともと数学や物理が非常に得意なお子さまなので、強みを生かしながら受験に挑めるよう、私たちもサポートを続けています。
また、東大では、教授が講義で話したことを一字一句書き起こす「書き起こし文化」が他大学と比べてとても盛んです。これは、アスペルガーの方は耳で聞いた情報を処理するよりも、文字で読んだ方が分かりやすいという特性を持っている場合が多いためと考えられます。
アスペルガーの方の中には、視覚的な情報を一瞬で記憶できるカメラアイを持っている人もいますが、これもアスペルガー特有の「視覚優位」の特性によるものです。
加えてアスペルガーの方は、情報の全体ではなく、一部だけを集中して見るという特性(トンネルビジョン/シングルフォーカス)を持っていることがあります。
定型発達の人が気付かないようなことにも気付けるという点においては、研究者向きの特性と言えるでしょう。
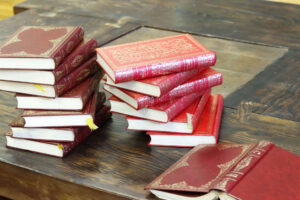
アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由④感覚ではなく論理で思考できる
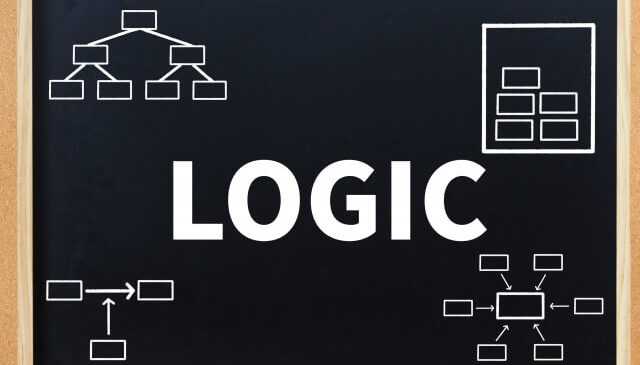
アスペルガーの方は、言葉の裏に隠されたニュアンスや行間を読むことが苦手です。
コミュニケーションにおいてはデメリットになる一方、「書かれていることだけで判断する」という考え方は、共通テストの国語の問題などでは非常に有利な思考パターンとなります。
いわゆる論理的な思考が得意なので、共通テストの国語の問題だけでなく、数学の論理の問題や生物の実験問題も得意な傾向にあります。
二次試験における物語文の読解などは苦手な傾向にありますが、東大では物語文が出題されず、“書かれていることから判断する”という解法がメインになるため、アスペルガーの方と東大国語は非常に相性が良いと言われています。
また、東大の英語は、膨大な量の英文をひたすら読み解いていくという問題構成になっていおり、長時間にわたり英文を読み続ける必要があります。
そのため、定型発達の人は集中が途切れてしまうことも多いのですが、ルーティンワークが得意なアスペルガーの方は淡々と問題を解き続けられるという強みを持っています。

アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)や発達障害が東大や高学歴に多い5つの理由⑤難関校では、互いの個性を尊重できる人同士で過ごせる

偏差値が高い学校であるほど、お互いの多様性を受け入れる風潮があります。
私が数年前に指導したAさんは、アスペルガーの特性を持っていました。地元の公立中学校に通っていたのですが、友達とのコミュニケーションが上手くいかず、やや不登校の傾向にありました。
Aさんは勉強が得意だったため、プロ家庭教師のサポートを受けながら高校受験に向けて勉強し、県内で有数の進学校に合格することができました。高校に進学してからは、Aさんは見違えるように生き生きとした様子で、不登校の傾向も全く無くなくなりました。
Aさんによると、中学校のときは「空気が読めない」「話についていけない」といった理由で友達の輪に入れないことがよくあったそうですが、高校に入ってからは、場にそぐわない発言をしてしまったり、曖昧な表現に戸惑っていたりすると、クラスメイトが自然とフォローしてくれるようになったそうです。
また、Aさんは小さい頃からパソコンに興味があり、プログラミングや自作PCのことを話せる友達が欲しいと感じていました。
中学生の頃は、パソコンの話をすると「オタク」とからかわれる場面もあったそうですが、高校のクラスメイトは関心を持って話を聞いてくれるため、それがとても楽しいと仰っていました。
大学でも同様に、偏差値の高い大学であるほど、アスペルガーの方への理解度や受容度も高くなる傾向があります。また、学部や専攻では同じ興味・関心を持った学生が集まるため、高校よりも一層話の合う仲間を見つけやすいでしょう。
さらに、国公立の難関校においては、発達障害の学生に対し手厚いフォロー体制が整えられています。
例えば東京大学では、発達障害の学生をサポートする専門機関「コミュニケーション・サポートルーム」が2010年から設置されています。コミュニケーション・サポートルームでは、
- 他者とのコミュニケーションが上手くいかない
- 注意力が散漫であると感じる(ADHDの傾向)
- 他人と感じ方や考え方が違うため、孤独感がある
といった悩みを相談することができます。
東大は日本のトップ大学ですので、配置されている医師や心理士もトップレベルです。
丁寧なカウンセリングを受けられるほか、同じ悩みを持つ人たちが集まるコミュニティを紹介してもらえるなど、非常に手厚いサポートを受けることができます。
話をうかがい、必要な場合には心理検査などを実施することで、自己理解を深め、どのような方策が良いのかを一緒に考えます。たとえば、苦手な領域を単純に克服していこうとするのではなく、他の方法でカバーできないかを探るといったやり方です。解決策が直ぐに見つからない場合もありますが、関係する機関に紹介するなど可能な範囲でお手伝い致します。
(引用元:コミュニケーション・サポートルーム | Communication Support Room (u-tokyo.ac.jp))
東大だけでなく京大でも、発達障害を含めた障害を持つ学生のための支援機構(DRC Kyoto Univ. | 学生総合支援機構 障害学生支援部門 (kyoto-u.ac.jp)))が設置されています。あらゆる社会的障壁を持つ人に対する支援のスペシャリストたちが関わる組織であり、こちらも手厚いサポートが期待できます。
アスペルガーのお子さまの「過ごしやすさ」の観点から言えば、難関大学は非常に適切な環境が整えられていると言えます。
そのため、スクールカウンセラーの中には、アスペルガーの特性を持つ高校生に対して、敢えてレベルの高い大学の受験を勧める方もいるようです。
東大卒など高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方の困りごとの3つの例

東大や難関大学とのアスペルガーとの相性は「1.アスペルガー(ASD、自閉症スペクトラム)が東大や高学歴に多い5つの理由」で述べてきたとおりです。しかし、アスペルガーの方が高学歴である場合、困りごとが生じることもあります。
高学歴で損をすることがあるの?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、周囲からの過度な期待やプレッシャー、本人のプライドなど、高学歴ならではの悩みは実際に存在します。
以下では、高学歴のアスペルガーの方が抱えがちな困りごとをご紹介するとともに、その解決方法も併せてお伝えしていきます。
東大卒など高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方の困りごとの3つの例①社会人では求められることが変わる

大学生までは、勉強ができていれば基本的に褒められます。
「何をすべきか」を自分で考える機会もほとんどなく、先生や親などの言うことを聞いていれば問題無いという状況が多いでしょう。
また、高学歴である場合は、アスペルガーの特性を受け入れてくれる人たちが周りに多くいるため、コミュニケーションの困難さに直面する機会も比較的少なくなります。
ですが、社会人になると「自分で考えて行動すること」が求められます。また、勉強のように「これだけやっていればOK」というものもなく、様々なタスクを同時進行で、周りの様子を見て優先順位を考えながらこなしていかなければなりません。
さらに、コミュニケーションにおいても、自分と同じ属性(年齢、性別、出身、学校など)の人たちだけではなく、様々な生い立ちや性格の人と付き合っていかなければなりません。
目上の人に対する振る舞いや、暗黙の了解に基づくコミュニケーションなどはアスペルガーの人が最も苦手とする分野であり、社会人になってからつまずいてしまう大きな要因となっています。
筆者は現役のキャリアアドバイザーでもあるため、日々多くの新卒・転職志望者の相談にお応えしています。
その中で新卒・転職志望者の皆さまには、「アメリカなどではプログラマーはプログラミングを、デザイナーはデザインをできれば良いといったように、企業内での分業制やスペシャリスト的な志向が主流である一方、日本の企業においては、オールマイティなジェネラリストが評価される傾向にあり、たとえ専門職であっても、ある程度のコミュニケーション能力が求められる」ということをお伝えしています。
- アメリカなどの外資系企業
- – 企業内での分業制やスペシャリスト的な志向が強い。専門職であれば、コミュニケーション力はそれほど重視されない。
- 日本の伝統的な企業
- – オールマイティなジェネラリストが評価される。専門職でもコミュニケーション力が重視される。
したがって、日本の伝統的な企業に就職する場合は、「たとえ専門職であっても一定のコミュニケーションが必要なことを覚悟してください」といつもお伝えしています。
つまり、「商品開発だけしたい!」と思って日本の大企業に就職しても、上司や同僚との付き合いは必ず付いてきます。
ですので、人間関係がどうしても苦手な場合は、社員同士であまりコミュニケーションを取らないドライな社風の企業や、スペシャリスト志向の強い外資系の企業など、コミュニケーションの負担が少ない企業を選ぶことをおすすめしています。
東大卒など高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方の困りごとの3つの例②周囲から過度に期待される

「東大卒の新入社員」と聞けば、誰しも期待をしてしまうものです。
もちろん、東大に入れる学力があるからといって、必ずしも仕事をこなす能力が高いとは限りませんが、日本はまだまだ学歴社会ですし、相応の期待をしてしまうのは仕方が無い面もあります。
東大卒をこれまで多く採用している企業であれば、「東大生でもコミュニケーションが苦手な人はいる」という前提の上で採用しているかもしれませんが、東大生や高学歴な人材を採用した経験が少ない企業の場合、「高学歴だから即戦力になるに違いない」という過度な期待をしてしまっている可能性があります。
そのため、本人なりに頑張って働いていても、「期待外れ」「高学歴なのに大したことがない」などとマイナスな印象を持たれてしまうケースがあります。
採用したのは企業の側ですので自分を責める必要はありませんが、メンタルが辛いときは休職や転職を検討しましょう。
また、就職の際には、学歴だけに注目する企業ではなく、自分の人となりやこれまで頑張ってきたことを踏まえて「あなたと一緒に働きたい」と伝えてくれる企業を選びましょう。発達障害の特性を受け入れてくれる雰囲気がありそうかどうかも重要なポイントです。
東大卒など高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方の困りごとの3つの例③プライドが高くなってしまう

学生時代までは、勉強ができるだけでとにかく褒めてもらうことができます。東大や難関大学に合格しようものなら、保護者さまや先生は諸手を挙げて喜んでくれるでしょう。
高い学力を持っていることや、厳しい受験を乗り越えられたことは素晴らしいことですし、自信を持って構いません。ですが、世の中には学力以外にも様々なスキルが存在しており、そのどれもが生きていく上では大切な能力と言えます。
勉強ができる人が偉くて、できない人は偉くない……と、ここまで極端な考え方の人は少ないと思いますが、学生時代に勉強が全てであった人ほど、自分にも苦手なことがあることを“分かっていても認めたくない”と思ってしまう傾向にあります。
つまり、高学歴かつアスペルガーや発達障害である方は、プライドが高く自分の非を認めたくないタイプの人が多いとも言えます(もちろん、全員がそうではなく、高学歴かつ発達障害であっても、自分を適切に客観視できる方はたくさんいらっしゃいます)。
プライドが高くなってしまった結果、悩みを周りに打ち明けられず一人で抱え込んでしまい、誰にも相談せずに会社をやめてしまうなどして、中には引きこもりになってしまう方もいらっしゃいます。
誰にでも苦手なことはありますので、辛いときは誰かに相談するように、できれば子どもの頃から習慣づけておくと良いでしょう。
特にアスペルガーの方は、気持ちを言葉にすること(=言語化)が苦手な場合があります。
自分でもわからないうちにストレスを溜めてしまうこともありますので、「何に困っているか」「どんなことが心配か」など、頭の中だけで考えず、誰かに話したり、ノートに書いたりして整理することをおすすめします。

東大生や高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害のまとめ
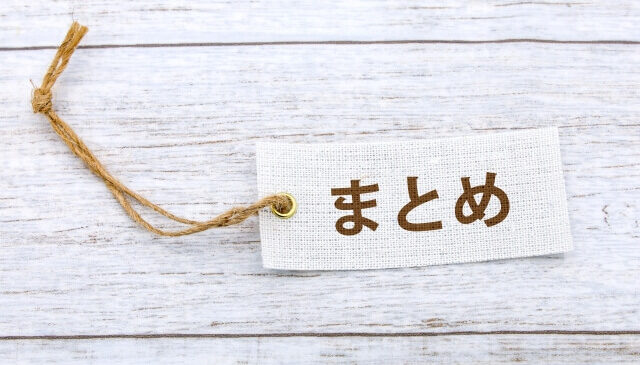
この記事では、東大生など高学歴のアスペルガー(ASD、自閉スペクトラム症)や発達障害の方の特徴や困りごと、その解決方法について詳しく説明してきました。
改めてポイントをまとめると以下のとおりです。
- アスペルガーは学習習慣が身に付きやすく、受験と相性が良い
- アスペルガーは熱中するととことんやり込むことができる
- アスペルガーは理系科目が得意な傾向にある
- アスペルガーは東大国語と相性が良い
- 東大や京大はアスペルガーへのフォローが手厚い
- 高学歴のアスペルガーならではの困りごとがある
アスペルガーの方は難関大学の受験においては強みが多く、高学歴の方もたくさんいらっしゃいます。一方で、学生時代と社会人になってからのギャップに悩み、就職してから困りごとを抱えるケースも見られます。
東大卒だから、高学歴だからといって、有名な大手企業への就職にこだわる必要はありません。
高い学力と厳しい受験を乗り越えた精神力は、社会人になってからも必ずどこかで活かせますので、視野を広く持ち、自分の強みや軸をしっかりと見極めながら就職活動に挑んでいただきたいと思います。
また、変化の激しい現代社会において、自分に合った生き方を見つけることはどんな人にとっても重要であり、早いうちからキャリアプランについて考えておくことが大きなポイントになります。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、アスペルガーや発達障害のお子さまに向けて、学習指導のほか、将来のキャリアを見据えた進路のご提案などを行っています。
代表は現役のキャリアアドバイザーでもありますので、お子さまの将来について確かな知見に基づいたアドバイスが可能です。
目の前の受験だけではなくお子さまの将来全体を見通したサポートをご希望の方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
また、授業や面談はオンラインでも承っています。
全国各地からご利用いただけるほか、海外や帰国子女の方からもこれまでご利用いただき、ご好評の声を多数いただいてきました。オンラインでの授業が不安な方も、初回は無料でお試しいただけますのでお気軽にご相談ください。

1人でも多くのお子さまが、自分らしくより良い人生が歩めるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。





