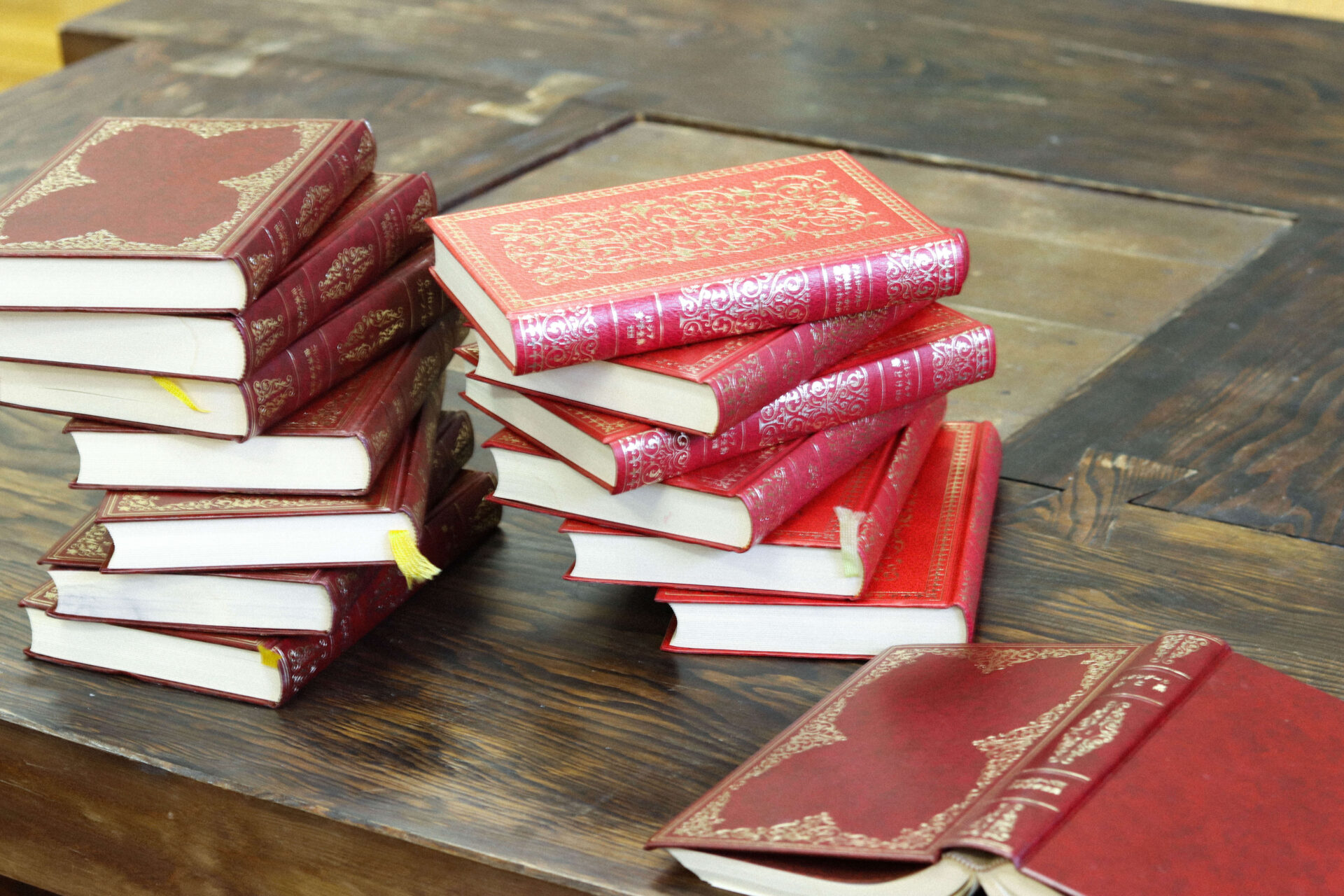ASD(アスペルガー)は記憶力が良い?悪い?勉強や就職で個性を生かす方法とは?
・ASD(アスペルガー)だから暗記科目が苦手なの?
・勉強は得意なのに、人の名前が全く覚えられない
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力について、このようなお悩みをお持ちではありませんか?
私は、発達障害専門のプロ家庭教師や塾経営者として、長年にわたりASDやADHDのお子さまの学習指導を行ってきました。
1500人以上を指導してきた中で、記憶力で悩まれているお子さまをサポートする機会も数多くありましたが、「ASDは記憶力が良いか、悪いか」といった問いは、簡単に答えられるものではないと感じています。
ASDの認知特性(脳の働きの傾向)は、ADHDやLDといった他の発達障害と比べて個人によるばらつきが大きいと言われています。
そのため、記憶力についても人によって様々で、非常に高い記憶力を持っている人、特定のことだけ覚えられる人、全体的に忘れっぽい人などがいらっしゃいます。
一方で、ASDの特性の一つに「限定された興味・こだわり」があるため、自分の興味のあるものに関しては優れた記憶力を発揮するタイプの方は比較的多いと言えます。
記憶に関しても、覚えられるものとそうでないものの凸凹が激しいというイメージで捉えると分かりやすいでしょう。
また、ASDの方は、ワーキングメモリーや短期記憶よりも、長期記憶の方が優れている場合が多いです。
子どもの頃に読んだ本の内容や、数年前に行った旅行先の風景は詳細に覚えている一方で、さっき頼まれた買い物の内容は忘れてしまうなどの例がこれに当たります。
日常生活においては、長期記憶よりもワーキングメモリーや短期記憶の方が使う場面が多いため、ASDの方は自分の記憶力が悪いと感じやすいかもしれません。
ですが、ASDの場合は反復学習が得意であったり、視覚的な情報の処理に優れていたりするため、自分の特性を上手く活かすことでワーキングメモリーや短期記憶の低さをカバーすることができます。
・ASDが暗記に取り組むときのコツを知りたい
・ASDの特性を活かして進学や就職に挑みたい
この記事では、ASDの記憶力について詳しく説明するとともに、特性との付き合い方や活かし方を紹介していきます。
ASDの記憶力や暗記力に興味・関心のある方は、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
▼目次
- 1 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の特性と記憶力の関係
- 2 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い6つの理由
- 2.1 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由①ルーティンを好む
- 2.2 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由②感覚が過敏である
- 2.3 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由③過去への執着が強い
- 2.4 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由④視覚情報を処理するのが得意(視覚優位)
- 2.5 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由⑤情報を取捨選択せず、優先順位をつけない
- 2.6 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由⑥過去と未来の整理が曖昧
- 3 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力と「サヴァン症候群」「ギフテッド」
- 4 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法
- 5 ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力・暗記力のまとめ
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の特性と記憶力の関係

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の特性は、
・限定された興味・こだわり
の2つと言われています。
一見すると、これらの特性と記憶力はあまり関連が無いように思えますが、実はASDの特性と記憶の能力は本質的な部分で結びついています。
人間の記憶に関する能力は、「ワーキングメモリー」「短期記憶」「長期記憶」の3つに分けることができ、それぞれの働きは以下のとおりです。
短期記憶や長期記憶のように“記憶そのもの”を指すのではなく、処理能力のことを指します。
テスト勉強など、一時的に覚えてアウトプットするものは短期記憶に該当します。
短期記憶を繰り返し反復することで、長期記憶として定着します。
このうち、ASDの方は、言語に関するワーキングメモリーや短期記憶の働きが低い傾向にあると言われています。
言語性のワーキングメモリーや短期記憶の能力が低いと、「文章問題が苦手」「テンポの速い会話についていけない」といった困りごとが生じますが、これはASDの方が持つ「社会性・コミュニケーションの困難」に通じるものがあります。
ASDの方は、機械的に記憶することが得意な場合が多く、語学や地理・歴史、プログラミングなど、反復学習や単純なインプットが必要な分野では優れた能力を発揮することがあります。
一般的にASDの方は言語に関わる学習は苦手とされますが、女性でASDの場合は言語感覚が非常に優れているケースがあり、英語の成績が抜群に良かったり、数か国語をすぐにマスターしたりと、語学に突出した才能を発揮することもあります。
他者に関心を持ちづらく、人の名前を覚えにくいというのも、ASDの方の記憶に関する困りごとの一つです。
私が指導したお子さまの中にも、クラスメイトの顔と名前が覚えられずに困っているお子さまがいらっしゃいました。一方で、そのお子さまは数字に対する関心が非常に強く、円周率や年号はすぐに覚えることができました。
そこで私は、出席番号と人物を紐づけて覚えることを提案しました。もちろん、出席番号は数字ですので、その子はあっという間にクラスメイト全員の出席番号を覚えてしまいました。
最初のうちは「○番の○○くん」というように、出席番号が無いと名前が出てこないようでしたが、そのうちに出席番号が無くても名前を思い出せるようになりました。
ASDの方は、「限定された興味・こだわり」という特性があるため、興味や関心の無いものについては記憶しづらい傾向にあります。
ですが、関心のあるものと紐づけるなどの工夫により、興味の無いものでも覚えやすくすることが可能です。
ASDの方の中には、普通の人が覚えていないような細かいことまで覚えている方がいらっしゃいます。
お子さまの場合ですと、クラスメイトの出欠や服装、教室の机の配置や壁の落書きなどを正確に覚えていて、それを家に帰ってから毎日事細かに保護者さまに報告する、といったケースです。
ASDの方が物事を詳細に把握し記憶しようとするのは、「不確定な事象や変化が苦手」という特性が要因の一つになっていると考えられます。
予想外の状況をできるだけ避けたいという思いが、たくさんの情報を把握し記憶するという行動に表れていると言えます。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い6つの理由

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の特性は個人差が大きいため、記憶力についても高い人もいれば低い人もいます。
ASDの方の記憶力が高くなる理由としては、以下のようなものが挙げられます。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由①ルーティンを好む
ASDの方は、ルーティンワークが得意で、ルールに忠実であることを好みます。
臨機応変な対応が苦手とも言えますが、規則正しい生活を送れたり、時間を守って行動出来たりする点においては、社会生活上、大きなメリットがあります。
規則正しくルールに忠実な生活を送るためには、当然ですが規則やルールを記憶する必要があります。
ASDの方が電車の出発時刻やゴミ出しの曜日、校則や就業規則などを細かく覚えているのは、こういったルーティンを好むことに起因します。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由②感覚が過敏である

ASDの方は、定型発達の人と比べて視覚・聴覚・嗅覚・触覚・痛覚といった感覚が過敏または鈍麻である場合があります。
感覚過敏の場合は、より強い印象を伴って情報が脳にインプットされるため、覚えやすくなります。
この場合、覚えるのは単語や数式といった概念というよりは、その場の情景や音、においといったものになります。感覚過敏は多くの場合不快感を伴いますので、「あの場所はうるさくて嫌だった。
一緒にいたのは誰々だった」というような記憶の仕方になります。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由③過去への執着が強い
ASDの方は未来のことを考えたり想像したりするのが苦手な一方、過去に対しては強いこだわりを持つ傾向にあります。
そのため、感情の切り替えがしにくいなどの困りごともありますが、記憶力が高くなる要因の一つとも言えます。
過去へのこだわりは長期記憶として発揮されることが多く、幼少期の出来事を細かく覚えていたり、小学校時代のクラスメイトの顔と名前を全て覚えている場合などがあります。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由④視覚情報を処理するのが得意(視覚優位)
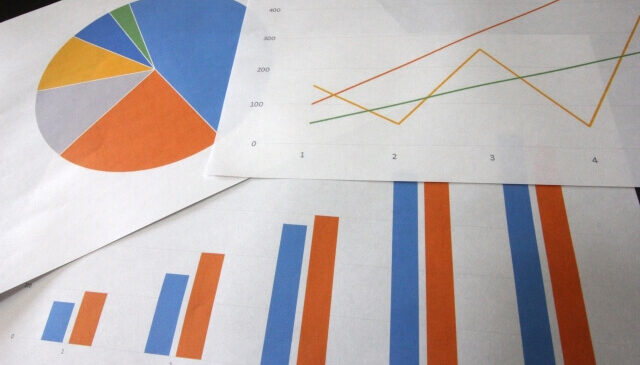
ASDの方は、目で見た情報を処理するのが得意な視覚優位である場合が多く、逆に耳で聞いた情報を処理するのは苦手な傾向にあります。
そのため、「○○と△△を買ってきて」と口頭で言われると覚えられなくても、メモに書いてあると一瞬で覚えられるなどの場合があります。
テスト勉強などでも、教科書をそのまま視覚情報として暗記して、「○ページの○行目に書いてあった」という覚え方をする方がいらっしゃいます。
単純な暗記テストであればカメラアイ(※)的な記憶でも問題ありませんが、内容の本質的な理解が求められる応用問題などでは、別の勉強方法が必要です。
※カメラアイ…目で見たものをそのまま画像で記憶することができる能力。瞬間記憶能力。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由⑤情報を取捨選択せず、優先順位をつけない
定型発達の人の場合は、必要な情報と不必要な情報を判別し、不必要な情報はインプットしないという選択を無意識で行っています。
にぎやかな場所でも話し相手の声や表情に集中できるのは、この取捨選択のはたらきによるものです。
一方、ASDの方は、目や耳から入ってくる情報を取捨選択する能力が低いため、話の内容だけでなく、周りの音も風景も、いったん全てが脳の中にインプットされてしまいます。
その結果、相手の話と周囲の様子をどちらも中途半端に記憶してしまったり、話の内容ではなく周囲の様子の方が記憶に残ってしまったりする場合があります。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い理由⑥過去と未来の整理が曖昧

ASDの方は、時間の流れの概念を捉えるのが苦手です。
そのため、今起きていることと過去に起きたことの区分が曖昧で、過去の記憶が今起こっているかのように不意に思い出されるといった場合があります。
楽しい記憶がよみがえる分にはそれほど問題がありませんが、嫌な記憶がよみがえるとストレスになりますし、加えてASDの方は過去に執着してしまう特性もあるため、一度嫌なことを思い出してしまうとそのことを考え続けてしまったり、パニックや不安感に襲われるなどの困りごとが生じることもあります。
いわゆるフラッシュバックやトラウマといった状態が見られる場合は、精神科を受診することも検討しましょう。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力と「サヴァン症候群」「ギフテッド」
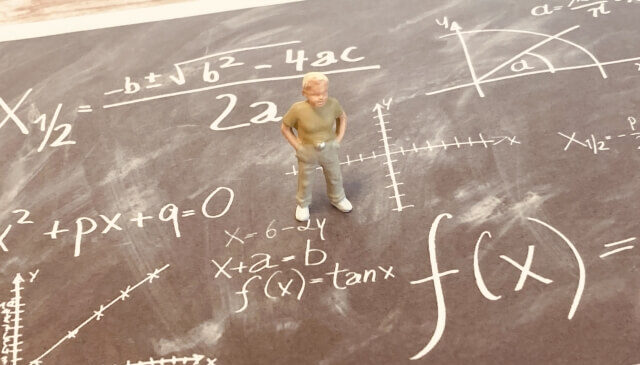
サヴァン症候群とは、記憶力や芸術・計算など、特定の分野に突出した才能がある一方で、知的障害や発達障害を併せ持っている状態を指します。
また、ギフテッドとはいわゆる天才のことで、高い知能や突出した才能を持っている人のことを指します。
発達障害を併せ持つ場合は、2E(twice-exceptional, 二重に例外)型ギフテッドと呼ばれる。
ASDの子どもの4人に1人はサヴァン症候群だとする研究がある一方で、サヴァン症候群は必ずしもASDの一部とは限らないという考え方もあります。
そもそもASDの特性には連続性や個人差がありますので、サヴァン症候群とASDの関連を明確に示すのは難しいでしょう。
ただ、「2.ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力が良い6つの理由」で紹介したように、記憶力が高かったり、視覚情報の処理に優れるといった点もあるため、ASDの特性を持つが故に人とは違う才能が発揮されやすいということは言えるかもしれません。
ギフテッドについては、基本的にはIQ130以上の人のことを指します。
IQは、お子さまの場合はWISC-IV、成人の場合はWAIS-IIIなどの知能検査を用いて計測しますが、ASDの方が比較的得意とする長期記憶は検査の項目に含まれません。
そのため、記憶力が高いだけでIQ130以上となる可能性は低く、ASDで2E型ギフテッドの方の場合は、知覚推理などの数学的処理が得意なケースが多いようです。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)だからといって、必ずしも記憶力が低かったり暗記が苦手というわけではありません。
むしろ、特定の感覚に鋭く、過去への志向性が高いASDの方は、記憶力に関して高いポテンシャルを持っていると言えます。
それにも関わらず、ASDの方が暗記が苦手だと感じたり、テストで点が伸びづらかったりするのは、記憶の整理の仕方や呼び起こし方に問題があると言えます。
学習方法や指導方法の工夫でASDの方の記憶力は格段に伸びますので、以下では勉強や暗記のコツについて紹介していきます。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法①ルーティンを作る
ASDの方は、ルーティンに従って行動するのが得意です。
「通勤・通学の電車の中では単語帳を見る」「○時~○時までは勉強タイム」というように、生活リズムの中に暗記や学習習慣を組み込むことで、毎日コツコツと取り組むことができます。
一度に多くのことを覚えるのではなく、少しずつ積み上げていくことが暗記のポイントです。ASDの方と非常に相性が良い方法ですので、ぜひ実践してみてください。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法②興味を持てる内容から始める
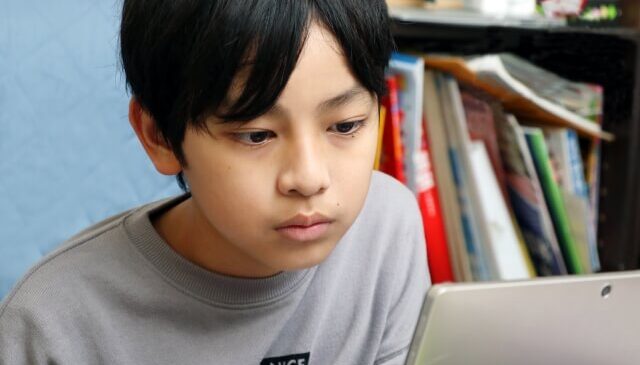
ASDの方は、自分の興味があることについてとことん追求することができます。
勉強は苦手でも、好きなアニメやゲーム、アイドルのことならいくらでも知識を吸収できる方も多いのではないでしょうか。
例えば、英語を勉強する場合、アニメが好きな方は英語版を視聴する、ゲームが好きな方は言語設定を英語表示にしてプレイする、アイドルが好きな方は歌詞を英訳したり海外のファンと交流してみるなど、好きな物や興味のある分野を入り口すると、単に英語の勉強をするよりも積極的に取り組むことができ、頭にも入りやすくなるためオススメです。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法③優先順位を付ける

受験までに英単語を覚えなければならないといった場合、単語帳の最初から順番に覚えていくと、後ろの方の単語を覚える前に時間切れになってしまうかもしれません。
どの単語が重要なのか、テストで出題される可能性が高いのかなど、覚える単語には優先順位を付ける必要がありますが、優先順位を付けることはASDの方が苦手とすることの一つです。
お子さまの場合は、保護者や先生など、周りの大人が優先順位を示してあげるようにしましょう。
「最初から順番に覚えたい」というこだわりがある子もいますが、お子さまとの間にしっかりとした信頼と尊敬関係があれば、指導者の提案を聞き入れてくれることがほとんどです。
どの単語を覚えればよいのか、また、いつまでに覚えればよいのかということをまずは明確にしましょう。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法④良い指導者を見つける

ASDの方が暗記や勉強に取り組む際には、ASDの特性に理解ある指導者や伴走者を見つけることも非常に重要です。
自分のこだわりを頭ごなしに否定せず、それぞれのやり方を尊重してくれる講師を探しましょう。
勉強の方法に絶対的な正解はありません。「先生の言った通りにやりなさい」と一方的に押し付けたり、自分のこだわりに耳を傾けてくれない指導者は避けるようにしましょう。
また、ASDの方は、疑問が残っているとずっと悩んでしまい、次の問題に進めないことがあります。わからないことや疑問があるときは、その都度先生に聞くようにしましょう。
曖昧な言葉を使わず、ご本人が理解できるほど具体的で丁寧に教えてくれる先生を見つけることがポイントです。
すぐに先生に聞ける状況でないときは、わからない問題に印をつけたり、メモしたりするなどのルールを作りましょう。
あとで聞けるという安心感があると、次の問題にもスムーズに進むことができます。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)が記憶力を高める5つの方法⑤自分の優位感覚を知る
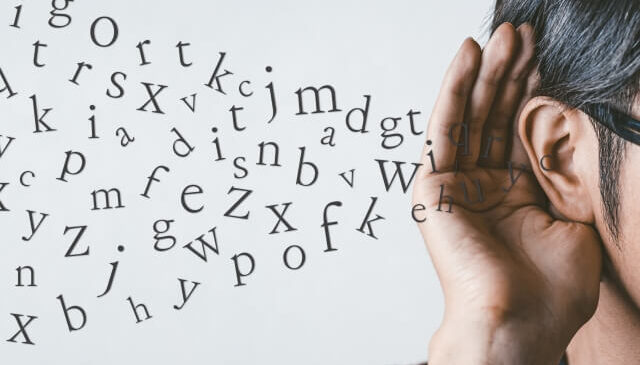
ASDの方は、目で見た情報を処理するのが得意(視覚優位)であることが多いとされています。
音で聞いたり文章で説明されるよりも、図やイラストの方が分かりやすく感じる場合は、視覚優位の性質があると言えます。
視覚優位の場合は、教科書の本文よりも、参考書や副読本の図表に注目するようにしましょう。
とにかく暗記が必要なときは、図をそのまま覚えて自分で書けるようにしてしまうことも一つの方法です。内容の理解が必要な場合も、まずは図表を見て、わかりづらいところだけ本文を参照する、といった方法が有効です。
聴覚優位の場合は、声に出したり、オーディオブックを活用するのが良いでしょう。
英語の教科書には、多くの場合本文を読み上げるCDが付いています。
以前に私が指導した聴覚優位のASDのお子さまは、英語の教科書のCDを流しっぱなし・聞きっぱなしにすることで、本文をほとんど覚えることができました。
そのため、英語のテストではいつも高得点を取ることができ、本人の自信につながっていました。自分の優位な感覚を知り、それに合わせた暗記方法を実践することは非常に重要であることがわかります。

ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力・暗記力のまとめ
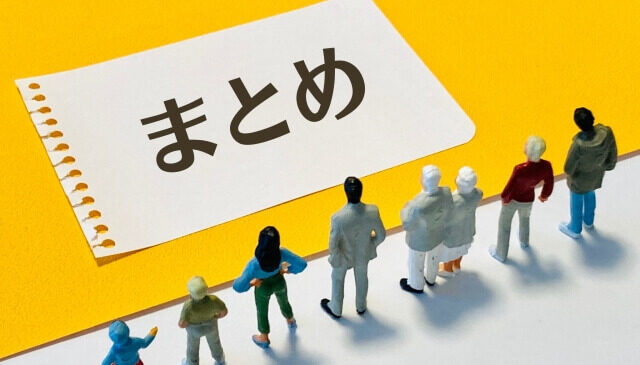
この記事では、ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の記憶力や暗記力について詳しく説明してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
・ASDは過去への志向性が強く、特定の感覚が敏感なため、記憶力に高いポテンシャルを持っている
・ASDは長期記憶に優れ、ワーキングメモリーや短期記憶は苦手な傾向にある
・ASDとサヴァン症候群の関係は、現在のところ明確には定義されていない
・学習方法や良い指導者を見つけることで、ASDの記憶力や暗記力は格段にアップする
ASDの方は、コツコツと積み上げる学習や、一つのことを追求する姿勢が強みです。
東大・京大といった難関校にはASDやADHDといった発達障害を持つ学生も多く、特性があるからといって社会で活躍できないということは全くありません。(弁護士の友人からは、弁護士にはASDの方が多いと思うとよく聞きます)
▼東大・京大合格者は発達障害の性質を持つ人が多い!? 個性を活かした勉強法で難関を突破
法律や医学など、膨大かつ専門的な知識が必要な士業や医療関係の職業に就いて活躍されている方もいらっしゃいますし、自分の好きな分野に関する研究職に就くのも良いでしょう。
また、敏感な感性を生かして、イラストレーターやデザイナーになる方もいらっしゃいます。
先を見通すことが難しい現代において、企業に就職するだけが正解とは限りません。
人生をより良いものにするためにも、特性を活かした職業選択は非常に重要であり、早いうちから人生全体を見通した進路やキャリアプランを考えることが大切なのは言うまでもありません。
私たち家庭教師メガジュンでは、お子さま一人一人に寄り添う丁寧な指導を強みにするとともに、代表が現役のキャリアアドバイザーでもあることから、お子さまの将来を見据えたサポートを行うことが可能です。
ASDのお子さまの学力や進路でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
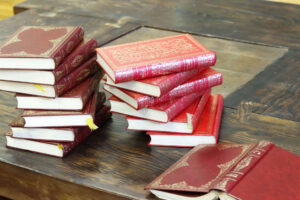
また、授業や面談はオンラインでも行っています。
全国各地からご利用をいただいているほか、海外にお住まいの方や帰国子女の方にもご利用いただき、ご好評の声をいただいています。
初回相談・初回授業は無料ですので、お気軽にご連絡いただければと思います。

1人でも多くのお子さまが、自分の力でより良い人生を切り拓いていけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。