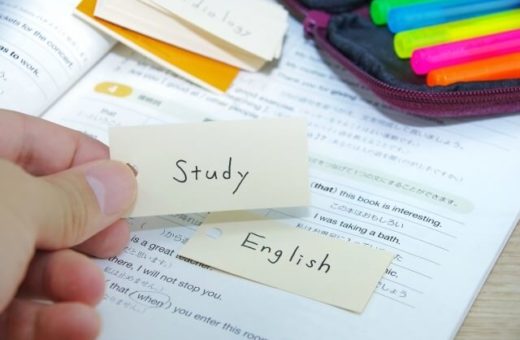ASD(アスペルガー)におすすめの英会話・受験英語学習法
・ASDの特性を活かして英語を勉強したい!
・英会話と受験英語、同時に効率よく勉強する方法は?
英語のスキルが重要であることは、皆さんがご存知のとおりです。
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)と診断された方やグレーゾーンの方であっても、仕事や受験で英語を学習しなければならない場面は多くあります。
この記事では、16年以上にわたる発達障害専門のプロ家庭教師としての経験の中で培ってきた、ASDの方に最適な英語学習方法をお伝えします。
これまで1500人以上を指導し、今も現役で発達障害のお子さまの指導に携わっています。
第一志望合格率は90%以上で、中でも英語学習については「苦手を克服できた」「コツがわかった」との声をたくさんいただいています。
国語や数学、物理などと違い、英語は発達障害の方でも学習しやすい科目です。
ポイントさえ押さえれば、受験英語も英会話も無理なく身に付けることが出来ますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

発達障害専門の受験プロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▼目次
ASD(アスペルガー症候群、自閉スペクトラム症)の性質と英語学習の相性
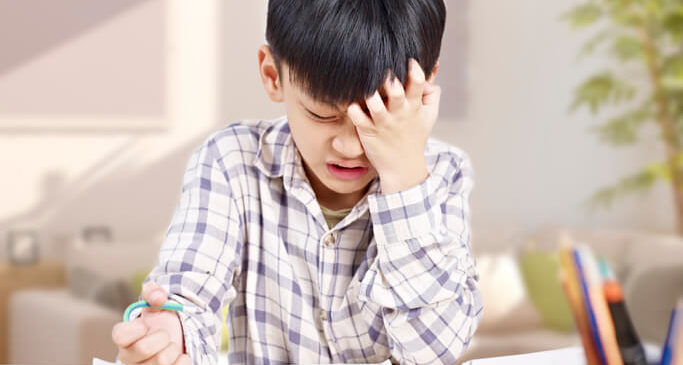
ASDの方は、以下のような特性を持っています。
・興味の対象が非常に限定的で、パターン化された行動をとる
病院で診断を受けた方以外でも、「会話が噛み合わないことが多い」「人の気持ちやその場の雰囲気が読めない」「一つのことに極端にこだわってしまう」などで困難を感じている方は、ASDの傾向にあり、グレーゾーンと言えるかもしれません。
「コミュニケーションが苦手であることから、英会話も苦手になってしまうのかな?」と不安に思われるかもしれませんが、ASDだから英会話ができないということは一切ありません。むしろ、ASDの方は英会話に向いています。
ASDの方がコミュニケーションを苦手と感じるのは、「行間が読むことが苦手」だからです。
日本語でのコミュニケーションは、日本人同士かつ日本的社会の中で行われます。文化や考え方が共有されているという前提条件のもとでコミュニケーションが行われるので、「言わなくてもわかるでしょ?」という場面が多く発生します。
しかし英会話は、異なる文化や社会的背景を持つ人同士のコミュニケーションで使われることがほとんどです。
日本人にとっては当たり前のことも、アメリカ人にとっては当たり前ではありません。なので、英会話においては、行間を省略せず、自分にとって当たり前のことでも言葉を尽くして説明するのが普通なのです。
つまり、英会話を使う場面では、ASDの方が苦手としている「行間を読む」「雰囲気で察する」ということはほぼ必要ありません。コミュニケーションに苦手意識があるからといって英会話に抵抗感を持つ必要は無く、むしろ「英語の方がコミュニケーションが取りやすいかも!」と前向きに捉えていただければと思います。
ASDにオススメの英語学習法

英語学習は、大きく2つのカテゴリに分けることが出来ます。
・受験英語
「1.ASDの性質と英語学習の相性」でお伝えしたように、ASDと英会話の相性は決して悪くありません。
また、受験英語についても、コツコツと継続的に取り組むことがポイントになりますので、ASDの特性を活かしながら効率的に勉強することができます。
それぞれについて、以下で詳しく説明していきます。
実用的な英会話

日本語でのコミュニケーションと違い、英語でのコミュニケーションは客観的な事実の積み重ねで行うことが多く、遠回しな表現や尊敬語、主語や目的語(誰が/何を)の省略もほとんどありません。
もし話し手の意図が理解できなかったら、その場で聞き返しましょう。日本であれば、聞き返してばかりいると嫌な顔をされることがあるかもしれませんが、英語によるコミュニケーションにおいて聞き返すことは普通ですので、相手に嫌がられることもありません。
また、よく使うフレーズも限られています。頻出フレーズについては暗記で乗り越える方法がオススメで、「毎日2フレーズ覚える」など目標を決めて取り組みましょう。
例えば、
2.昼休みに振り返る
3.帰りの電車でテスト
4.週末に、その週覚えたフレーズを復習
といったルーティンを決めてしまいましょう。ASDの方は自分で決めたルールを守ることがとても得意なので、一度習慣化してしまえば、継続的に続けることができます。
受験英語
単語、熟語、文法
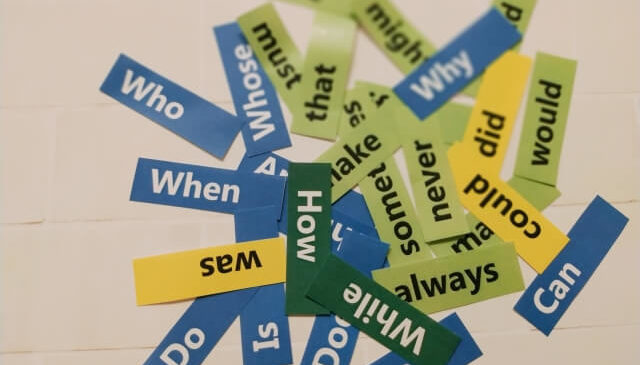
受験英語は、「単語・熟語・文法」「長文読解・英作文」「リスニング」の3つの分野に分けられます。
このうち、ASDの方が得意とする分野は「単語・熟語・文法」です。
単語や熟語は、シンプルな暗記です。毎日単語帳を開き、定期テストや小テストの範囲ごとに覚えていけばOKという、非常に単純な反復学習をこなしていくことになります。
ひたすら覚えるだけ、という勉強方法が苦手な方も多くいる中で、ASDの方はルーティンを行うのが得意であり、コツコツと覚えることが苦にならないという有利な面があります。
特に、英語における「単語・熟語」は、長文読解や英作文の土台になるとても重要な分野です。
単語や熟語の学習を有利に進められるということは、英語学習の土台作りが有利に進められるということであり、その上に積み上がる長文読解や英作文を勉強する際にも非常に役に立ちます。
単語や熟語を覚える際には、「2-1.実用的な英会話」で紹介した頻出フレーズを覚える方法と同様に、一日のルーティンの中に組み込んでしまうことをオススメします。
朝の電車の中や、夕食後の30分間など、「この時間は英単語の時間」と決めてしまうことで、学習を習慣づけることが出来ます。
自分の中でルール化し、よりストレス無く暗記学習に取り組めるようにしましょう。
長文読解、英作文
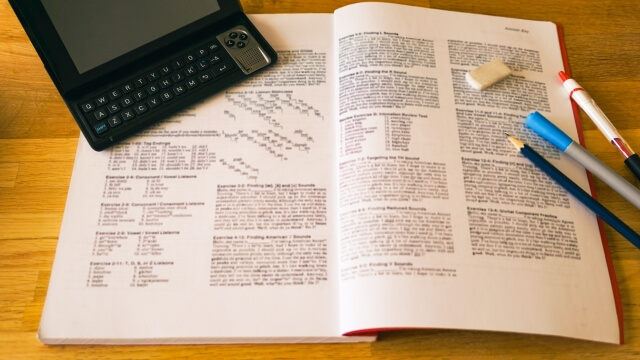
ASDの方には、「興味のあるものに、とことんこだわる」という特性があります。
長文読解や英作文については、この特性を上手く活かしましょう。
自分はこれが好きだ、と思えるジャンルはありますか?
アイドルやアニメ、鉄道、プログラミングなど、何でも構いません。自分の好きなジャンルに関する英文を、まずは読んでみましょう。
わからない単語はその都度調べてかまいません。また、文法的にわからないところは翻訳アプリなどを使っても大丈夫です。
英語は世界共通語です。日本語の文献でも知識は得られますが、英語も読めるようになるとさらに広い知識や情報を手に入れることが出来ます。
自分の興味のあるジャンルの英文を入り口にすることで、英語学習へのモチベーションを上げましょう。
もしくは、自分の興味のあるジャンルの海外での反応を英語で読むことも、面白いと思います。
また、長文や英作文においても、反復学習は有効です。
たくさん読み、たくさん書き、たくさん問題を解くことで、とにかく英文に慣れましょう。
ただし、何となく漫然と取り組むことは避けてください。
わからなかった問題は振り返り、解説を読んでもわからない場合は先生に聞くということを徹底しましょう。
一度にたくさん解くと、わからない問題もたくさん出現してしまい、振り返りが面倒になってしまいます。
1日に解く問題数は1~2問と決めておき、次の日までには振り返りを完了する、というルールを作ります。
単語の暗記と同様、長文読解でもコツコツと継続することを大切にし、学習の習慣化を心掛けましょう。
リスニング

リスニングも長文読解と同様に、自分の興味・関心があるジャンルの音声や動画、スピーチをまず聞いてみましょう。
今はYouTubeなどで簡単に海外の動画を見つけることが出来ますよ。
リスニングは英会話と違い、一方的に音声を聞くだけです。コミュニケーションの得手不得手はあまり関係ありません。ただ、長文読み上げの解釈問題などは、ASDの方にとっては少し苦手かもしれません。
やや長めの文章の解釈については、耳で英語を聞く能力のほか、論理的な読解力が必要になります。
それまでの内容で明かなことであれば、内容が省略されることもあり、ASDの方が苦手な「行間を読む」ことが求められるケースもあります。
長文読解や現代文の問題を解く際には論理構成を意識するなど、読解力も少しずつ身に付けるようにしていきましょう。

英会話と受験英語は両立できる?

英会話と受験英語を同時に対策できればいいのに……と誰しもが思うところですが、受験英語は「読むこと」「書くこと」がメインになるため、英会話と両立させながら学ぶのは効率が良いとは言えません。
ただし、海外在住経験があり、ネイティブレベルの英会話力がある場合は、受験英語にも英会話のスキルを活かすことが出来ます。ネイティブ並に英会話ができるのであれば、必然的に読む/書くといったスキルも付いてきますし、英語への抵抗感も少なくなるためです。
志望校選びについては、帰国子女枠のある学校を選ぶことが可能です。
他にも、英語の配点が高い国際系の学校や、英検やTOEICなどの資格試験で英語が免除となる学校、英語のみで受験できる学校などを選ぶと、受験を有利に進めることができます。
帰国子女などで高い英会話力がある場合を除いては、「単語→文法→長文」といった王道の勉強方法で、地道に積み上げていきましょう。ASDの方にオススメの勉強方法については、「2-2.受験英語」をご覧ください。
受験英語のうち、リスニングについては英会話のスキルと一部重複します。
ですが、英会話は「聞く」「話す」の両側面があり、リスニングにおいて「話す」ことはあまり関係がありません。
英会話ではわからなければ聞き返すことができますが、リスニングでは聞き返すことができないなどの違いもありますので、英会話をしているからといって、受験英語のリスニングの得点に直結するわけでは無いことは理解しておきましょう。
受験英語におけるリスニング
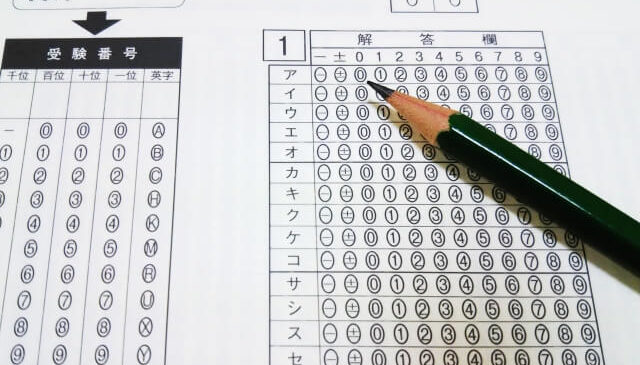
■中学受験
英語を受験科目とする学校は、中学受験では非常にまれでした。
しかし、2020年から新しい学習指導要領が小学校で実施され、小学校での英語教育が本格的に始まったことにより、中学受験でも科目に英語を設ける学校が増えてきました。
過去7年間で、英語を受験科目に導入する学校は約10倍に増加しています。
したがって、今後も中学受験で英語を受験科目とする学校は増えていくことが予想されます。一方で、現時点において中学受験で英語を導入している学校は少なく、難関校ではほとんど導入されていません。
英語が導入されている学校でも「読み書き」が中心で、リスニングがある学校はほぼありません。小学生のお子さまが英会話を習う場合は、受験のためではなく、英語に親しみ、抵抗感を無くすことを目的にすると良いでしょう。
■高校受験
高校受験におけるリスニングにおいて、配点は100点中15~35点程度です。
難易度はあまり高くなく、配点も少ないことから、受験において特にリスニングを意識する必要はありません。英語の勉強時間のうち、リスニング対策に費やすのは1/20程度で十分です。
■大学受験
私立大学でリスニング問題が出題されるのはまれです。国際系の大学や外国語大学以外では、リスニングは出題されず、対策も不要と考えて良いでしょう。
国公立大学を受験する場合は、共通テストの受験が必須であり、必然的にリスニング対策が必要になります。
リスニングの配点は大学によって異なりますが、二次試験でリスニングが出題されないなどの事情から、リスニングの配点が高い大学も多いため、国公立大学を受験する際には、しっかりとリスニング対策を行わなければなりません。
ASDの勉強法における8つのポイント
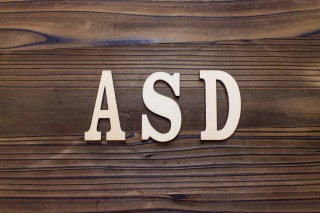
ASDの方の勉強において、重要なポイントは次の8つです。
②曖昧な表現を避け、はっきりと指示してもらう
③信頼できる人の指導を受ける(指導者との関係性の構築)
④自分のこだわりを否定しない
⑤聞きやすい話し方は何か、相手に伝える
⑥細かい疑問は早めに解消する
⑦予定をはっきりさせる
⑧勉強計画の立て方を工夫する
勉強を習慣化・ルール化し、反復学習に取り組む
ASDの方は、一度ルール化してしまうと根気よく反復学習に取り組めるため、受験勉強などの際には大きな強みになります。
単語や熟語の暗記は単調で苦手と言う人も多い中で、暗記にコツコツ取り組めるのは非常に有利ですし、英語であれば長文の基礎固めにもつながります。
学習習慣をルール化する際は、生活リズムの中に上手く組み込むようにして、よりストレス無くルーティン化するようにしましょう。一気にやるのではなく、コツコツと積み上げることがポイントです。
曖昧な表現を避け、はっきりと指示してもらう

ASDの方は、どうしても言外の意図を察したり、雰囲気から読み取ることが苦手です。
学校や塾の先生、家庭教師から指導を受ける際は、あいまいな言い方を避け、はっきりと指示してほしい旨を伝えましょう。
・悪いパターン…「問題集の○ページから○ページの問題を解きましょう」
発達障害の方の学習指導には、専門的なスキルが必要です。
先生との相性が合わないなどでお困りの方は、ぜひ発達障害専門の家庭教師を検討してみてください。

信頼できる人の指導を受ける(指導者との関係性の構築)
ASDの方は、環境の変化に敏感です。
先生が代わったりすると、無意識に抵抗感を覚え、勉強の内容が頭に入らないことがあります。
信頼できる先生を選ぶとともに、無理の無い範囲で構いませんので、自分の特性を理解してもらえるよう、説明やコミュニケーションに努めましょう。
お子さまの場合であれば、保護者からも先生に対し、できるだけお子さまの状況や特性について情報共有することを心掛けましょう。
自分のこだわりを否定しない

ASDの方は、独自の世界観やこだわりを持っています。学校や会社では「変わっている」とされてしまうこともありますが、本人の大切な個性ですので、否定する必要は全くありません。
「筆記用具はこのメーカーと決めている」など、周囲にとっては些細に思えても、本人にとっては大切なことです。ストレスなく勉強に取り組むことはとても重要ですので、無理にこだわりを捨てようとせず、実現できるこだわりは最大限尊重しましょう。
また、こだわりのポイントについては、本人や保護者が最も把握しています。学校や塾、家庭教師には、こだわりを細かく伝えるようにしましょう。
聞きやすい話し方は何か、相手に伝える
先生によっては「大きくはっきり話せば良い」とだけ考えている人もいます。ですが、発達障害の方の中には、聴覚過敏などで大きな声が苦手な場合もあります。
発達障害の方の特性はそれぞれ異なりますので、どんな話し方が聞きやすいのか、先生にきちんと伝えましょう。
ゆっくり話してほしい、音量は控えめにしてほしいなど、「3-2、曖昧な表現を避け、はっきりと指示してもらう」とあわせて伝えられると良いですね。
細かい疑問は早めに解消する

ASDの方は、普通の人ならあまり気にならないことでも、「なぜ?」と疑問に思うことがあります。
疑問に対して答えが無いまま次に進むことが苦痛で、ストレスや不安が募っていき、勉強に集中できないなどの悪影響が生じます。
個別指導の塾や家庭教師などであれば、その場ですぐ質問し答えてもらいましょう。
学校や集団指導塾の教室、あるいは宿題などですぐに質問できない場合は、わからなかった問題に○をつけたり、疑問点をメモしておいたりして、後で先生に聞けるようにしておきましょう。
後で答えてもらえると思えば、次の問題にスムーズに進めます。
予定をはっきりさせる
ASDの方は、イレギュラーな出来事が苦手です。勉強の計画は事前にはっきりと決めておきましょう。
曜日で勉強内容を決めておくなど、長期的かつルーティン的な計画の立て方がベストです。
一度予定した内容は、先生や親の都合で変更しないようにしましょう。
わがままではなくASDの特性によるものですし、きちんとした計画を見せれば、周りの大人も納得してくれるはずです。
勉強の計画の立て方を工夫する
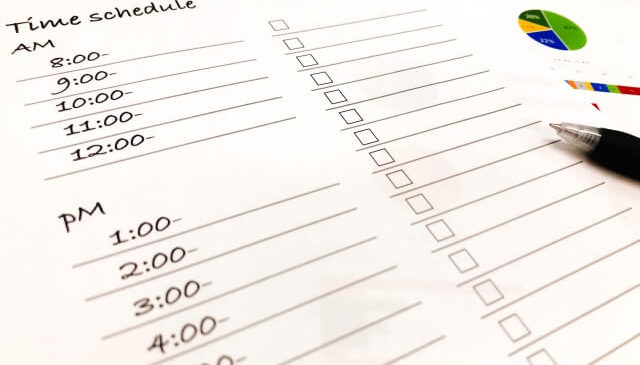
ASDの方でなくても、朝の方が勉強がはかどりやすい人もいれば、夜の方がやる気が出やすい人もいます。自分に合った生活リズムや勉強計画は何なのか、信頼できる先生と一緒に相談しながら決めていきましょう。
「3−1、勉強を習慣化・ルール化し、反復学習に取り組む」とも重複しますが、ASDの方は一度ルーティン化すれば根気よく続けられるという強みがあります。
最もストレスなく勉強に取り組めるリズムは何か、工夫しながら見定めていきましょう。



まとめ

この記事では、ASDの方におすすめの英語の学習方法や勉強のコツをお伝えしてきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
・ASDの方はコツコツ勉強するのが得意
・勉強を日々のルーティンに組み込み、学習の習慣化を目指す
・単語や熟語は、文法や長文読解の土台になる
・受験においてリスニングの重要度は低いが、国公立大学を受験する場合は対策が必要
・コミュニケーションが苦手なASDだからこそ、先生との意思疎通は綿密に
・自分のこだわりを無理に捨てず、ストレス無く勉強できることを大切に
発達障害の診断を受けたり、日々の生きづらさがあると、勉強に対しても自信を失ってしまうことがあるかもしれません。
ですが、特性と上手く付き合い、強みに変えることは可能です。
専門的な知識を持った先生の指導を受けることも大切なポイントですので、お悩みのある方は是非お気軽にお問い合わせください。