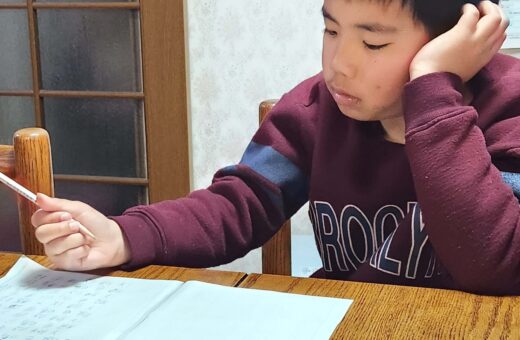発達障害の対処法とは?子供・大人・学校・職場、シチュエーションごとの対応例を紹介!
発達障害の方は、職場や学校で様々な困りごとを抱えています。
うっかりミスや人の話が理解できない、感情が抑えられないなど、発達障害の方が抱えることの多い困りごとの対処法について、この記事では具体的な実例を交えながら紹介していきます。
発達障害専門のプロ家庭教師とキャリアアドバイザーという二つの顔を持つ筆者ならではの視点で解説していきますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
▼目次
発達障害の特性と困りごと

この章では、発達障害の概要について解説していきます。発達障害について既にご存じの方は、「2.発達障害への対処法」までお進みください。
発達障害は、以下の3つに分類されます。
- ADHD(注意欠如・多動症)
- ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)
- LD(学習障害、限局性学習症(SLD))
このうち、LDは読み・書き・計算といった特定の学習スキルのみに困難が現れる発達障害であり、お子さまにおいては学力の伸び悩みが主な困りごととなります。
大人になってからもマニュアルを読むのに時間がかかる、暗算ができないなどの困りごとが生じることがありますが、基本的には補助ツール(PCの読み上げ機能や電卓)を使用することで解決することができます。
また、現代の日本においてLDは、ADHDやASDとの併発であると診断されるケースが多くなっており、LD単体での診断を受けるケースは稀です。
LD単体の場合は、「勉強が苦手なだけ」と周りが判断し、専門医につながれないケースも多いと考えられます。
この点については改善が必要であるものの、当記事での詳細な解説は割愛させていただきます。LD(学習障害、SLD(限局性学習症))についてご関心のある方は、以下の記事で詳しく解説していますので是非ご一読ください。
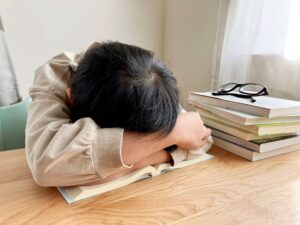
「発達障害」と聞いて、多くの方が思い浮かべるのはADHDとASDではないでしょうか。
いつもそそっかしく、頻繁に忘れ物やケアレスミスをしてしまう人や、段取りを立てるのが苦手な人、コミュニケーションがぎこちなかったり、会話が上手く成り立たなかったりする人……こういった特徴が人よりも顕著で、会社や学校で困り感が大きい人は「発達障害」の可能性があります。
人間には誰しも得意と不得意があり、忘れ物をすることや、ミスコミュニケーションが生じることはあります。ただ、その程度が大きく、本人の努力によって改善が難しい場合は発達障害かもしれません。
「ミスが多い=発達障害」という単純なものではありませんので、気になることがある場合は自己判断せず、まずは専門医を受診するようにしましょう。
また、発達障害が「生まれつきの性質」であることは非常に重要なポイントです。
発達障害の特性は、本人の努力不足や親の育て方が原因となって生じるものではありません。発達障害の特性は、生まれつきの脳の器質(性質、働き方)によるものであり、どんなに本人の努力があったとしても、根本的な性質自体を変えたり、解消したりすることはできません。
ただ、発達障害を疑って受診される方の中には、幼少期の経験が原因となって発達障害に似た困りごとが生じている場合があります。適切ではない親子関係による自己肯定感の低下やトラウマ経験により、集中力や感情のコントロールが難しくなっているケースが該当します。
生まれつきの発達障害か、それとも幼少期の経験による症状なのかを判断するのは非常に難しく、専門医でも誤診する場合があります。
病院を受診する際には、現在の困りごとだけでなく、幼少期からの成育歴についても細かく伝えるようにしましょう。
本人だけでは状況を客観的に伝えるのが難しい場合は、親やパートナーなど身近な人と一緒に受診するのが良いでしょう。
ADHD(注意欠如・多動症)の特徴と困りごと

ADHD(注意欠如・多動症)は、
- 集中力をコントロールしづらい
- 落ち着きが無く、衝動的である
といった特性を持つ発達障害であり、いずれの特性も「脳にブレーキを掛けるのが苦手」という“脳の働き方のクセ”が根本的な要因となっています。
定型発達の人は、無意識に必要な情報と不要な情報を取捨選択し、必要な事だけについて考えることができます。
一方、ADHDの人は脳の働きにブレーキが利かず、全ての情報について処理しようとしてしまいます。
そのため、頭の中の交通整理が上手くいかず、集中しづらかったり、段取りが上手く立てられず思いつくままに行動してしまうという衝動性が現れたりします。
ADHDの方は、「頭の中で常に思考している感じ」「考えている内容が話し声となって頭の中を飛び交っている感じ」と仰ることが非常に多く、これはまさに、脳の働きにブレーキが利かず、情報の交通網が混乱している状態と言えます。
こうした脳の過剰な働きを落ち着かせたり、あるいは上手く情報整理させたりするために、インチュニブやコンサータなどの薬が処方される場合があります。
これらの特性から生じる困りごとの例は、以下のとおりです。
- ケアレスミスが多い
- 遅刻が多い
- 忘れ物が多い
- 物をよく失くす
- 片付けや整理整頓が苦手
- 段取りよく物事を進めることが苦手
- 急いでいるときに限って些細なことが気になる
- 思い付きで行動してしまう
- 良く考えずに発言してしまう
- カッとなって大声を出すことがある
- じっとしているのが苦手
- 人の話に集中するのが苦手
- 一つのことに集中できず、すぐに別のことを考えてしまう
- おしゃべりに夢中になり、やめられない
- 話の内容があちこちに飛んでしまう
- 話しているうちに、何を話したいのかわからなくなる
- ぼーっとしてしまうことが多い
- 思考がまとまらない感じがする
- 学校や仕事から帰ると疲れてぐったりしてしまう

ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)の特徴と困りごと

ASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)は、
- コミュニケーションの苦手さ、社会性の不全
- 限定的な興味とこだわりの強さ
を特性として持つ発達障害です。
このほかに、感覚過敏を併せ持つ場合も多くなっています。
ASDはその名称にもあるとおり、スペクトラム=連続性があります。ごく軽度の特性を持つ人から強い特性を持つ人まで様々であり、グレーゾーンの診断を受ける人が多いのも特徴の一つとなっています。
ちなみに、アスペルガー症候群は自閉スペクトラム症の分類の一つとなります。知的発達や言語の遅れの有無によって、自閉スペクトラム症は以下のように分類されます。
- 自閉症…知的障害と言語の遅れを伴う自閉傾向
- 高機能自閉症…知的障害は伴わないが、言語の遅れを伴う自閉傾向
- アスペルガー症候群…知的障害も言語の遅れもない自閉傾向
ADHDについては、特性の原因となる脳のメカニズム(※)が明らかになっており、そのメカニズムを制御する薬が開発されています。
一方、ASDの原因となる脳内のメカニズムは未だに明らかになっていません。
そのため、治療薬は存在せず、ソーシャルスキルトレーニングや環境の調整などによって社会に適応していくことが必要となります。
なお、ASDの治療薬として、脳内ホルモンの一種であるオキシトシンの経鼻スプレーの効果が期待されており、現在、臨床実験が行われています。(参考:改良型オキシトシン経鼻スプレーに自閉スペクトラム症中核症状に対する改善効果 | 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 (amed.go.jp))
コミュニケーション能力は、人間が生きていく上で欠かせないスキルの一つです。また、こだわりが強くイレギュラーな出来事が苦手なASDの方は、臨機応変な対応を求められる場面で困りごとを抱えることが多いでしょう。
感覚過敏についても、他の人にとっては何でもないような刺激が、ASDの方にとっては耐え難いものである場合があります。環境の調整と周囲の理解が重要となりますが、人知れず悩みを抱えてしまう方もいらっしゃいます。
このような特性により、ASDの方が抱えがちな困りごとには以下のようなものが挙げられます。
- 空気を読むのが苦手
- 身振り手振りでの表現が苦手
- 相手の表情や話し方から感情を読み取るのが苦手
- 言葉を額面通りに受け取ってしまう
- 「あれ・それ・これ」など指示語が指しているものがわからない
- 自分の好きなことについて一方的に話してしまう
- 会話のキャッチボールが苦手
- 的外れな発言をしないか不安で、会話に入れない
- 人付き合いが苦手
- 悪気無く相手を怒らせてしまうことがある
- デリカシーが無いと指摘を受けることがある
- 話の要点が理解するのが苦手
- 急な予定の変更でパニックになる
- いつものルーティンが崩れるとストレスを感じる
- いつもと同じ方法にこだわる
- ルールを守ることに固執する
- 興味のあることには熱中できるが、興味の無いものには一切やる気が出ない
- 物をコレクションするのが好き
- 全体より細部にこだわる

発達障害への大人向け・子ども向けの対処法
この章では、発達障害の困りごとについて、シチュエーションごとの対処法を紹介していきます。
本人ができることや周りの方が配慮する際のポイントなどを具体的に解説していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
発達障害への対処法(大人向け/仕事)

発達障害の方が仕事で抱えがちな困りごとには、「予想外の出来事に対応できない」「感情のコントロールが苦手」「段取りよく仕事を進められない」「疲れる、ストレスが溜まる」といったものがあります。
これらの困りごとが重なると、仕事で低い評価を受けてしまったり、精神的な負担によりうつや不安障害などの二次障害を抱えてしまったりする場合があります。
ストレスによって心身に不調が生じているときは、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
人間関係が築けない
仕事が上手く進められないことでチームの中で疎外感を感じてしまったり、ASDの特性により空気を読むのが苦手であったりと、発達障害の方は職場の人間関係において困難を抱える場合が非常に多くなっています。
人間関係は仕事をする上で最も重要な要素とも言えるため、本人・周囲とも適切に対処していく必要があります。
- 言葉で伝えるのが苦手な場合は、文章や図で説明してみる
- 発達障害であることを理解のある人に伝えておく
- 相性の悪い人とは程よい距離感を保つ
- 話の結論を確認するようにする
- 伝え方や話し方が適切か、仲の良い同僚にフィードバックしてもらう
- 意図が伝わったかどうか確認する
- 「ケースバイケース」「常識的に考えて」など曖昧な指示は避ける
- 障害のカミングアウトについては慎重に行う(必ず本人の意思を確認し、無理強いしない)
マルチタスクが苦手
発達障害の人はワーキングメモリーが低いため、「話を聞きながらメモを取る」といったマルチタスクが苦手な傾向にあります。
また、書字障害の方はメモを取るのに時間が掛かってしまうため、話の内容に集中できないなどの困りごとが生じる場合があります。
マルチタスクが苦手な方の場合は、以下のような対処法が考えられます。
- ボイスレコーダーを使う
- 無理にメモを取ろうとせず、話に集中する
- 口頭ではなくメモに書いて渡す
- 電話や来客の少ない部署に配置する
仕事の段取りが立てられない
ADHDの方は集中しづらいという特性によって、また、ASDの方は自分なりの順番にこだわりがあるなどして、段取りよく仕事を進めるのが苦手な場合があります。
効率良く仕事が進められないと、周りから叱責を受けたり、評価が上がらなかったりして、さらにストレスを抱えることになってしまいます。
仕事の段取りが上手く立てられない場合の対処法は、以下のとおりです。
- その日やるべきことを書き出し、タイムスケジュールを作る
- ToDoリストを作成する
- 段取りについて、周りの人に相談する
- 「締め切り順」「作業時間の短い順」など、優先順位にルールを作る
- アラームなどを使用し、時間を区切って仕事を進める
- こまめに進捗管理をする
- 仕事を振るときは、今ある仕事との優先順位をはっきりと伝える
言われたことを覚えていられない
ADHDの方は、いくつかの指示が重なると、先に言われた内容をすっかり忘れてしまうことがよくあります。
うっかり忘れは大きなミスにつながる場合もありますので、以下のような工夫により防止すると良いでしょう。
- 指示があれば必ずメモをする癖を付ける
- メモをあちこちに置かず、「メモの置き場所」を固定する
- メモを無くしてしまう人は、手帳やホワイトボードなど、無くしにくいものにメモする
- メモやホワイトボードを常に目に入る位置に置いておく
- 指示が重なり過ぎないようにする
- 本人が落ち着いた状態のときに指示を出す
- タスク管理のホワイトボードを全体で共有する
予想外の出来事に対処できない
発達障害の方の中でも、ASDの方は未来について想像するのが苦手な傾向にあるため、予想外の出来事にパニックになってしまったり、臨機応変に対応できなかったりして、仕事が上手くいかない場合があります。
ASDの方が予想外の出来事に対応できるようにするためには、以下の工夫が考えられます。
- 起こりそうなトラブルをあらかじめ予想し、対処法をメモしておく
- パニックになりそうなときは、理解のある上司に相談する
- 様々なパターンを想定したマニュアルを作成しておく
- 困ったときに周りに相談しやすい雰囲気を作る
- イレギュラーな出来事が起こりやすい部署に、ASDの方を配置しない
職場における発達障害の方と周りの方とのトラブルは、互いに悪気はなく、理解不足が原因となっていることがほとんどです。
障害の特性を正しく伝えることは、発達障害当事者の方にとっては難しいものに感じるかもしれませんが、双方にとってより良い働き方を実現するためにも、できる限り情報共有に努めましょう。
また、周りの方は、定型発達の人が当たり前に出来ることができない発達障害の方を非難したくなる場面があるかもしれません。
ただ、少しの配慮で困りごとが解消できるケースもありますので、どんな特性が要因となっているのかを理解し、適切な配慮に努めましょう。
負担の無い範囲で双方が気持ち良く働ける環境を整備することは「合理的配慮(※)」の一環であり、積極的に進めることが義務付けられています。
2016年4月の「障害者差別解消法」の施行により、企業等においても合理的配慮に積極的に取り組むことが義務付けられています。(厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進|厚生労働省 (mhlw.go.jp))

発達障害への対処法(子ども向け/学校)

お子さまの場合は、大人の場合とはまた違った困りごとを抱えることになります。
特にテストの点が伸びづらいなどはお子さま特有の悩みであり、高校受験や大学受験などの進路を決める際には大きなハンデキャップとなってしまう場合があります。
この章では、学校での過ごし方や勉強法を中心に、発達障害のお子さまの困りごとへの対処法をご紹介していきます。
授業に集中できない
ADHDのお子さまでじっとしているのが苦手であったり、ASDで興味が限定的であったりするために、授業に集中できないというお子さまは多くいらっしゃいます。
ただ、得意な教科や好きな先生の授業であれば集中できる(もしくは少しマシになる)というお子さまも多いため、「いかに授業に興味を持ってもらうか」がポイントになります。
具体的な対処方法は以下のとおりです。
- 簡単な問題をたくさん解き、解ける楽しさを知る
- クイズやなぞなぞ形式で楽しく学べる工夫をする
- 授業中に休憩タイムを設ける
- 問題を解けたときや集中して話を聞けたときにしっかり褒める
先生の指示が聞けない
発達障害のお子さまは、先生の指示を聞いていなかったり、一度言われただけでは理解できなかったりして、集団行動に遅れてしまうなどの困りごとを抱える場合があります。
発達障害のお子さまに指示を上手く伝える工夫としては、以下のようなものが挙げられます。
- 口頭だけでなく、文字・図・イラストを使って伝える
- 一度だけではなく、何度か繰り返して伝える
- 一度に複数の内容を伝えず、一つずつ切り分けて指示を出す
学力に伸び悩んでいる
他の子と同じように勉強していても、なかなかテストで点が伸びずに悩んでいる発達障害のお子さまはたくさんいらっしゃいます。多くの場合、お子さまの努力や知能の問題ではなく、お子さまの特性にあった方法で勉強できていないことが原因となっています。
お子さまに合った勉強方法を見つけるためのポイントは、以下のとおりです。
- ケアレスミスの傾向を分析し、対策する
- 「分かったようで分かっていない」箇所を分析し、基礎から復習する
- 周りのペースに無理に合わせず、本人のペースで勉強させる
- 優位感覚(※)に合わせた学習方法を取り入れる
※優位感覚…目で見た情報を処理するのが得意な「視覚優位」や、耳で聞いた情報を処理するのが得意な「聴覚優位」、言葉で理解するのが得意な「言語感覚優位」など、人がそれぞれ持っている得意な感覚のこと。

感情のコントロールが苦手
発達障害のお子さまで感情のコントロールが苦手な場合、特性そのものが関係しているほか、特性に伴うストレスが精神面の不安定さにつながっている場合もあります。
療育(※)によってソーシャルスキルトレーニングなどに取り組むだけでなく、ストレスの要因を取り除いてあげることも大切です。
発達支援センターや放課後等デイサービスで受けることができます。
- 感覚過敏などで不快な感覚に晒されていないか確認する
- 自分の気持ちを言葉にする練習をする
- 感情が爆発しそうになった時に、落ち着けるスペースを準備する
- 特性による失敗や苦手さを頭ごなしに叱らない
- 周りの大人はいつも本人を見守り、応援していることを伝える

発達障害の対処法のまとめ

この記事では、発達障害の困りごととその対処法について詳しく説明してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 発達障害はADHD・ASD・LDの3つに分類され、LDはADHDやASDとの併発と診断される場合が多い
- ADHDの特性は「集中のコントロールのしづらさ」と「多動性・衝動性」であり、脳のブレーキが利きにくい状態であると理解すると良い
- ASDの特性は「コミュニケーション・社会性の不全」と「限定的な興味・こだわり」であり、詳しい脳のメカニズムは明らかになっていない
- 発達障害の方が職場で抱えがちな困りごとには、人間関係の困難や効率良く仕事が進められないことなどがある
- 職場での困りごとを解消するためには、本人も周りも特性を正しく理解し、協力しながら解決に向かうことが大切
- 発達障害のお子さまは、生活面だけでなく学力面でも困難を抱えることが多い
- お子さまの特性をしっかりと分析し、個々に合ったサポートを行うことが重要
発達障害の認知度は、一昔前に比べれば格段に高くなったものの、特性について正しく理解し対応できる人はそれほど多くはありません。
発達障害の方は、周りの人がどう配慮すれば良いのか分かるよう、自分の特性について可能な範囲で周囲に伝えることを心掛けましょう。
また、周りの人は、苦手さや失敗が本人の努力不足ではないことを十分理解し、適切な声掛けや配慮を行うようにしましょう。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたり発達障害のお子さまのサポートを行ってきました。
お子さまの頃から特性をしっかりと分析し、生活面・学習面での困りごとに一つ一つ対処していくことは、大人になってからの生きやすさにもつながります。
発達障害に理解のあるプロ家庭教師をお探しの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。

授業や面談はオンラインでも承っています。
遠方にお住まいの方や海外在住の方、帰国子女の方にもこれまでご利用をいただき、たくさんのご好評の声をいただいてきました。
初回授業は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか不安な方もお気軽にお試しいただくことができます。

なお、プロ家庭教師メガジュンでは、体験授業を担当した講師が継続してお子さまを担当させていただきます。
「体験授業の先生が良かったのに、いざ申し込んだら別の先生になってしまった…」ということもありませんので、安心してご利用ください。
1人でも多くのお子さまが自分らしく人生を歩んでいけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。