ギフテッドの小学生の5つの特徴と育て方のポイント
こうした特徴を持っている小学生のお子さまはいらっしゃいませんか?
もしかしたらそのお子さまは「ギフテッド」かもしれません。
ギフテッドとは、高い知能や特別な才能を持った人のことで、平たく言えば「天才」と呼ばれる人たちです。才能があるなんてうらやましい!と思ってしまうかもしれませんが、実は良いことばかりではありません。
私は不登校・発達障害のプロ家庭教師として活動し、1500人以上を指導してきましたが、ギフテッドであるが故に不登校になってしまったお子さまや、ギフテッドでありながら発達障害と診断されたお子さまを何人も知っています。
特別な才能を持っているということは、「周りと違う」ということでもあります。
ギフテッドのお子さまは、高い知能や才能を持っているため、勉強やコミュニケーションの方法、精神面の成熟のスピードなどが他の子どもたちと違ってきます。
それによって、普通の公立小学校に通っていると成績が伸びづらかったり、環境に馴染めず不登校になってしまうケースがあります。
そこでこの記事では、ギフテッドのお子さまが小学校でどう過ごすべきか、才能を伸ばすための支援にはどういったものがあるかについて詳しくご紹介していきます。
- 勉強はできるけれど、コミュニケーション能力が育っていないように思う
- 言動が大人びていて、周りの小学生から浮いてしまっている
- 高い知能や才能を伸ばすためにやるべきことは?
こういった疑問にお答えする内容になっていますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

発達障害・ギフテッド専門のプロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
ギフテッドの小学生の特徴
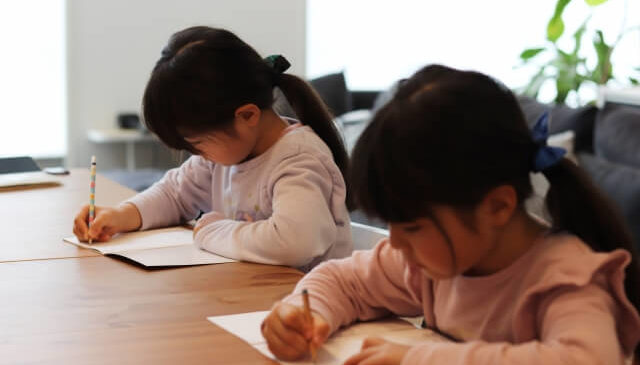
ギフテッドとは、IQが130以上である人のことを指します。また、芸術や運動など、知能以外に秀でた才能を持っている人もギフテッドに含まれることがあります。
IQが130以上であるかどうかは、ウェスクラー式知能検査(※)で調べることができます。お子さまがギフテッドかもしれず、学校や日常生活で困りごとを感じている場合は、発達支援センターや児童精神科などで検査を受けてみると良いでしょう。
…知的能力や記憶・処理に関する能力を測ることができる知能検査で、70年以上の歴史を持つ。日本においても、発達障害などの診断において広く用いられている。対象者の年齢によって、3つの種類に分かれる。
- WAPPSI…3歳~7歳3か月(幼児期) ※5歳~7歳3か月はWISCでも可
- WISC…6~16歳(学齢期)
- WAIS…16歳以上(成人期) ※16歳はWISCでも可
ギフテッドだからと言って必ずしも困りごとや生きづらさが伴うわけではありませんが、
などの困りごとがあり、その背景にギフテッドの性質がある場合は、その性質を踏まえたサポートが必要となります。
まずはお子さまがギフテッドがどうかをよく観察し、必要に応じて知能検査や発達検査を受けるようにしましょう。
また、学習面で困りごとがある場合は、ギフテッドのお子さまの性質に合わせた指導を受けられる塾やプロ家庭教師を検討することも大切です。
ギフテッドの小学生の特徴①具体的な特徴・エピソード
以下のようなエピソードは、ギフテッドの特徴として非常に分かりやすいものであり、耳にしたことがある方も多いかもしれません。
- 中学生で4か国語をマスターしている。英単語は一度見ただけで覚えられる。
- 小学1年生の頃から物理学書を読み、相対性理論を理解している。
- ピアノを触らせたらすぐに両手で弾き始めた。自分で和音を作って演奏し、後からコードの存在を知った。
これらは非常にわかりやすいギフテッドのエピソードの例ですが、こうした特徴的なもの以外にも、ギフテッドのお子さまの特徴として以下のようなものが挙げられます。
特に、言葉を覚えるのが早かったり、好奇心が旺盛であるという点は、ギフテッドのお子さまの多くに当てはまる特徴です。
高い知能を持っているが故に、同年代の子ども向けの遊びや学習では物足りず、もっとレベルが高く刺激のある体験を求める傾向があります。
ギフテッドの小学生の特徴②5つの観点

「1.1 ギフテッドの小学生の特徴①具体的な特徴・エピソード」では、ギフテッドのお子さまに見られる具体的な特徴やエピソードを紹介しましたが、これらの特徴は、以下の5つの観点で整理することができます。
- 言葉を覚えるのが早い
- 好奇心が強い
- 記憶力や理解力が高い
- 集中力に優れている
- 心と体と知性の発達バランス
ギフテッドの小学生の特徴①:言葉を覚えるのが早い
ギフテッドのお子さまの中には、小学校に上がる前から読み書きができるお子さまが多くいらっしゃいます。
もちろん、話す・聞くといった能力にも優れていて、同年代の子どもと比べて明らかに語彙が豊富であるケースも少なくありません。
また、語彙だけでなく文章を組み立てる能力も高く、複雑な文章構成で書いたり話したりすることができます。論理的な思考も得意であるほか、おしゃべりで早口なお子さまが多いことも特徴の一つです。
ギフテッドの小学生の特徴②:好奇心が強い
好奇心が強いことは、ギフテッドのお子さまの大きな特徴の一つです。
ギフテッドのお子さまはいろいろなことに興味や関心を持ち、強い知的欲求を持っています。子ども向けの図鑑では満足できず、大人が読むような事典や専門書を好むこともしばしばあります。
会話を通じて知識を吸収することも、ギフテッドのお子さまが好むことの一つです。大人には思いもよらない鋭い質問や本質を突いた質問をして、周囲を驚かせることがあります。
ギフテッドの小学生の特徴③:記憶力や理解力が高い
ギフテッドのお子さまの中には、一度見ただけで単語を覚えてしまったり、地図や国旗といった文字以外の視覚的情報もすぐに覚えられる方がいらっしゃいます。
こういったお子さまにとっては、漢字ドリルや白地図の暗記テストは退屈で無意味と感じられるでしょう。
また、数字や図形のパズルといった、知識ではなくアイデアで解くタイプの問題が非常に得意なお子さまもいらっしゃいます。これは、平面や空間を認識する力が人一倍優れているためと考えられます。
ギフテッドの小学生の特徴④:集中力に優れている
疑問に感じたことや興味を持ったものについて、とことん集中して追求することができます。大人顔負けの知識を吸収したり、ハイレベルな内容を理解できるのも、高い集中力があってこそです。
また、音楽・芸術・運動など、知能以外の才能においても集中力は重要な要素です。一度聞いた音楽を一瞬で覚えてピアノで弾けたり、一度見た風景を精密画で描けたりするのは、高い集中力を発揮しているためと考えられます。
ギフテッドの小学生の特徴⑤:心と体と知性の発達バランス
ギフテッドのお子さまは、知能面では同年代のお子さまより発達していても、社会性や精神面での発達は年相応である場合があります。(→2.1 非同期発達)
突出した才能がある分、他と変わらない面が悪目立ちしてしまったり、あるいは同年代の子どもたちと付き合いづらいといったことが起こる場合もあります。
ギフテッドの小学生の特徴③男の子・女の子それぞれの特徴
男の子だから/女の子だからと一概に言うことはできませんが、一般的な傾向として男の子のギフテッドの場合は反抗心が強く、大人に注意されても「自分の方が正しいはずだ」と主張して言うことを聞かないなどがあります。
例えば、漢字の反復練習が宿題で出されても「もう覚えているんだから必要無い」と言ってやらなかったり、計算の途中式を書くように言っても「分かっているのに書く必要は無い」と聞く耳を持たなかったりします。
また、学校の授業も簡単過ぎてつまらないと感じていることが多く、好きな本を読んだり、教室を出て自由に過ごしたり、あるいは教科書に載っていないことについて質問して先生を困らせてしまったりといった行動が見られることもあります。(→1.3.1 浮きこぼれ問題)
女の子のギフテッドの場合は、男の子の場合のように明確に反抗するケースは少なく、どちらかと言えば過剰に適応して疲れてしまうことが多いです。
例えば、本当は自然科学や人文学などに関するアカデミックな話をしたいけれど、周りのお友だちに合わせて興味の無いアイドルやアニメの話をするなどのケースです。
また、女の子の場合は男の子に比べると社会性の発達が早く、協調性を重視する傾向にあります。
そのため、高い知能を持っていることを敢えて隠しながら過ごしている方もいらっしゃいます。
このように、興味が無い話題に合わせたり、年相応の女の子らしく振舞ったりすることは、ギフテッドのお子さまにとって「自分ではない自分を演じること」にほかなりません。
「自分ではない自分」を毎日演じ続けていると、本人も気付かないうちに少しずつストレスが溜まってしまい、ある日突然学校に行けなくなってしまうなどのケースがあります。
ギフテッドのお子さまで、疲れやすかったり、週末に体調を崩しやすかったりする場合は、気付かないうちにストレスを感じている可能性がありますので、適度に休養を取らせるなどの対応が必要です。
浮きこぼれ問題
勉強についていけない子を「落ちこぼれ」と呼ぶのに対し、ギフテッドのように知的能力が高すぎることが原因で学校に馴染みづらい子どもを「浮きこぼれ」と呼ぶことがあります。
浮きこぼれに関しては、理解度に関わらず一律的な授業をせざるを得ない学校のシステムそのものが根本原因であり、お子さまに課題があるわけではありません。
一方で、学校のシステムを今すぐに変えることは難しく、また、先生の人数や使える教材や設備などのリソースにも限界があります。
ですので、知能が高いゆえに学校に馴染みづらさを感じている場合は、「お子さまの教育において何を優先するか(知的能力の向上なのか、社会性を身に付けることなのか)」「どこまで例外を認め、どこまで周りと同じであることを求めるか」について、家庭と学校とできちんと方針をすり合わせることが大切です。
ギフテッドの小学生の困りごと4点

NHKが行ったアンケートでは、ギフテッドの方の9割以上が学校生活への違和感や生きづらさを感じていると答えています。
幼い頃から特別な才能を発揮したり、言葉を早く覚えたりできると聞くと、周りの人は「すごい!」「うらやましい!」と思ってしまいますが、ギフテッドならではの悩みや困難があることがわかります。(参考:ギフテッドとは?高いIQを持つ天才たち その素顔と苦悩に迫る – NHK クローズアップ現代 全記録)
この章では、ギフテッドの困りごとについて、①非同期発達、②過度激動、③周りの目、④浮きこぼれの4点から解説していきます。
ギフテッドの小学生の困りごと①非同期発達(発達のアンバランスさ)

ギフテッドのお子さまに見られる発達のアンバランスさのことを、「非同期発達」と呼びます。
通常、精神的な成熟やコミュニケーション能力、知能や言語能力は、互いに関連しながら一体的に(同期して)発達します。ですが、ギフテッドのお子さまは、知能の面は人並み以上であっても、情緒や社会性の面では年相応である場合があります。
知識や理解力は大人以上であるにも関わらず、コミュニケーション能力や判断力は年相応で、場違いな発言をしてしまったり、友人関係でトラブルを起こしてしまうことがあります。
また、大人びた賢い子であると思われているため、年相応の言動をするたけで周囲をぎょっとさせてしまうことがあります。
そのため、接し方がわからないと距離を取られてしまったり、「扱いづらい子」と思われてしまう場合があります。
ギフテッドの小学生の困りごと②過度激動(知性・感覚過剰)

過度激動(OE; Overexcitabilities)とは、知性や感覚が人よりも過剰に働いてしまうギフテッドの性質のことを指します。
ギフテッドには感受性が高かったり、非常に強い知的欲求を持っている方が多く、普通の人が何となく受け流してしまうことでも反応せずにはいられないことがあります。
周りの人からすると過剰に反応しているように見えるため、集団生活になじめなかったり、生きづらさを感じたりすることがあります。
- 精神運動性過度激動…新しい経験やスリルなど、強い刺激を求める
- 感覚性過度激動…五感の刺激を求める、あるいは不快に感じる
- 想像性過度激動…想像力が逞しく、時にはぼーっとしているように見える
- 知性過度激動…非常に強い知的好奇心を持つ
- 情動性過度激動…感情の起伏が激しく、コントロールが難しい場合がある
実は、この過度激動が原因で、ギフテッドのお子さまは発達障害と誤診されることがあります。
例えば、知性過度激動によって一つのことに集中してしまい、そのことでクラスメイトとコミュニケーションが取りづらくなっている場合、ASD(アスペルガー、自閉スペクトラム症)と診断される場合があります。
また、想像性過度激動によって空想にふけってしまったり、情動性過度激動によって衝動的な行動が目立つ場合は「授業中にぼーっとしている、気になったことがあると立ち歩いてしまう」というADHD(注意欠如・多動症)の特性と重なるため、発達障害であると診断されることがあります。
ギフテッドのお子さまが発達障害と誤診され、さらに投薬治療を受けてしまったために、うつ病などの精神疾患を発症してしまうケースもあります。
また、発達障害とギフテッドの両方を併せ持った2E型ギフテッドであるケースもあり、ギフテッドの過度激動なのか、発達障害なのか、それとも2E型ギフテッドなのか、診断には高度で専門的な知識が求められます。
ギフテッドによる過度激動の場合は、知的な欲求を満たしてあげることで過剰な反応が落ち着く傾向にあると言われています。
誤診には気を付けなければならない一方で、早い段階でお子さまの特性を見極め、適切に対応していくことも重要です。
ギフテッドの小学生の困りごと③周りの目
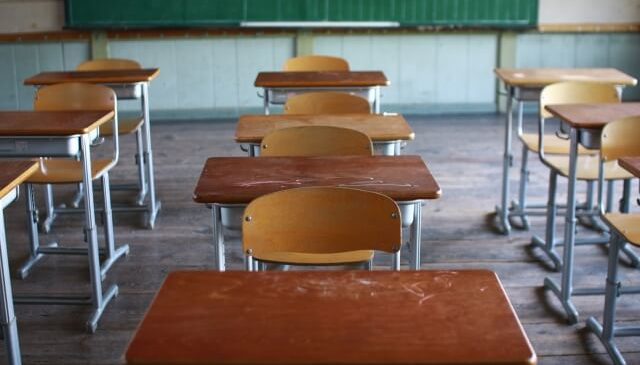
小学校低学年ぐらいまでであれば、ギフテッドのお子さまが少し周りと違った様子であっても、周りの子どもたちも、そして本人もあまり気にしません。
ですが、小学校3年生くらいになると、少しずつ「普通かどうか」が気になり始めてきます。
小学校2年生くらいまでは、同年代の他の子どもたちが決して読むことのないような専門書を読んでいても、気にしないか、もしくは好意的に取られることが多いのですが、小学校3年生にもなると「周りと違うことをしている」「あの子は変だ」と騒ぎ立てられたりする機会が増えてきます。
また、一度見た漢字は覚えられるからといって、漢字ドリルの宿題をしないわけにはいきません。サボってしまうと、周りからずるいと言われたり、先生から叱られ成績が下がってしまうのも小学校3年生頃からが多いです。
ギフテッドのお子さま本人は、自分と周りが違うことに幼い頃から気付いていることが多いものの、直接非難されたり集団生活がしんどくなってくるのがこの時期で、学校への行き渋りや不登校の傾向が表れることもあります。
学校や家庭での配慮によってお子さまのその後の生きづらさは大きく左右されますので、「最近学校を嫌がっているかも?」と感じたときは、お子さまとしっかり話をするとともに、学校の先生にも早めに相談するようにしましょう。
ギフテッドの小学生の困りごと④浮きこぼれ
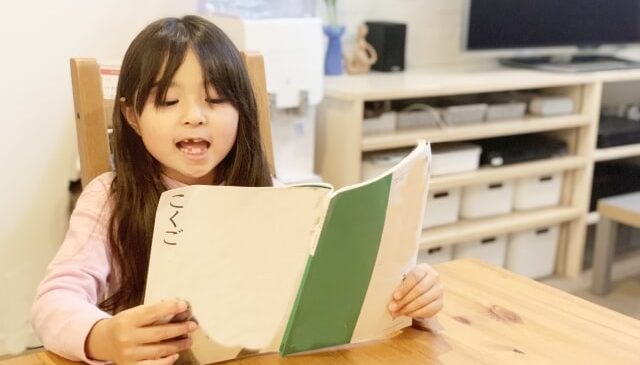
勉強が苦手でついていけない子どものことを「落ちこぼれ」と言いますが、逆に知能が高すぎて学校の授業が退屈だったり、周りの子どもと馴染めない子どものことを「浮きこぼれ」と呼びます。
落ちこぼれと言われる割合は全体の約15%と言われていますが、学校の授業が簡単すぎて退屈だと感じている浮きこぼれも13%程度いるとされています。
落ちこぼれに比べて認知度は低いものの、浮きこぼれの子どもたちへの対応も非常に重要です。
学校の授業は分かるけれど退屈だというお子さまに対し、学校では「とにかく授業を聞きなさい」「好きな勉強は家に帰ってからしなさい」と言われることがほとんどです。
朝8時から夕方3時過ぎまで、知的好奇心を全く満たしてくれない授業を座って聞き続けるのは、ギフテッドのお子さまにとって苦痛にほかなりません。
この問題を解決するためには、ギフテッドのお子さまが、自分の関心のある分野について思いっきり学び、才能を伸ばせる場を作る必要があります。
文部科学省が定める学習指導要領では、「学びの個別最適化」が謳われており、小中学校における一人一台端末の整備(GIGAスクール構想)も記憶に新しいところです。(参考:学習指導要領「生きる力」:文部科学省)
これまでの画一的な一斉授業を脱し、個別最適化された学びを実現するために、文部科学省も少しずつではありますが歩みを進めています。
学校の先生だけでなく、私たち大人全員が、子どもたちを見守り、一人ひとりの個性や良さを受け入れ伸ばしていける社会を作っていくことが大切です。
>>無料相談を申し込む
ギフテッドの小学生の育て方
この章では、ギフテッドの小学生のお子さまの育て方のポイントについて解説していきます。
ギフテッドの小学生の育て方の3つの視点
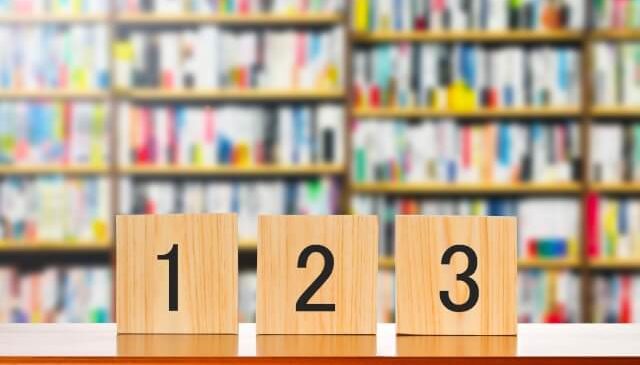
ギフテッドの小学生のお子さまをお持ちの保護者さまに、ぜひ持っていただきたい視点が3つあります。
それぞれについて、以下で順に解説していきます。
ギフテッドの小学生の育て方の3つの視点①得意分野を伸ばすことが最優先
「3 ギフテッドの小学生の困りごと4点」でお伝えしたとおり、ギフテッド=何でもできる問題の無い子というわけではありません。
ギフテッドであるが故に困りごとを抱えることがありますし、2E型ギフテッドのように発達障害の側面を併せ持っている場合もあります。
しかし、困りごとを解消するよりも、得意なことをどのように伸ばすかの方が格段に重要です。
他の子と違う面や上手くいかないところばかりを指摘されてしまうと、生まれ持った才能そのものがコンプレックスになり、良いところが潰れてしまう可能性があります。
ギフテッドとは少し異なりますが、とある自閉傾向があるお子さまは、言葉の発達には遅れがあるものの、絵画においては類稀な才能を持っていました。
周りの人たちは言葉の遅れを解消するため、様々な療育を施しました。その結果、言葉の遅れは取り戻せたものの、絵画の才能はすっかり消えてしまったというケースがあります。
日本はどうしても、「普通でいなければ」という同調圧力が強い社会です。
ですが、個性をしっかり伸ばすことが、ギフテッドのお子さまを育てる際には最も大切であることをぜひ意識していただきたいと思います。
ギフテッドの小学生の育て方の3つの視点②苦手のサポートは負担にならない範囲で
ギフテッドのお子さまは、知能や言語能力が高い分、精神的な成熟やコミュニケーション能力といったその他の面の発達が遅れているように見えることがあります(→2.1 ギフテッドの小学生の困りごと①非同期発達(発達のアンバランスさ))。
ですが、精神面や社会性の発達は、遅れているわけではなく、あくまで年相応なだけですので、焦らず見守るようにしましょう。
また、2E型ギフテッドで苦手なことがある場合も、本人が負担にならない範囲でサポートするようにしましょう。
発達障害は生まれつきの特性であり、苦手を解消するのが難しいケースも多いです。過度な期待はプレッシャーになってしまいますので、本人のできる範囲かつ無理のないペースを心がけましょう。
ギフテッドの特性から過度激動が出てしまっているときは、行動をたしなめるのではなく、知的好奇心を満たしてあげることで根本的な解決を図るようにしましょう。
ギフテッドの小学生の育て方の3つの視点③お子さま自身が自分を肯定できるように
幼い頃は自分の才能に自信が持てていても、小学校に上がるにつれ「自分は周りとは違う」「変だと思われていないかな」など、自分自身を手放しで肯定することが難しくなってきます。
大人が思っている以上に学校での同調圧力は強く、集団行動に馴染めないことから自信を無くしてしまうお子さまも少なからずいらっしゃいます。
ご家庭では、お子さまの持っている才能を言葉にして褒めるとともに、お子さまとの会話を大切にし、お子さまの自己肯定感をはぐくむように 心がけていただければと思います。
ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイント

ここからは、ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイントについて解説していきます。
ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイント①得意を伸ばせる環境作り
お子さまが強い関心や突出した才能を持っている分野について、本人が満足のいくまで学べる環境を整えてあげることが大切です。
子ども向けの科学教室などだけでなく、専門家と話せる公開講座や大人向けのセミナーに参加するのもおすすめです。
東京大学先端科学技術研究センターが運営しているLERANプロジェクトでは、「それぞれの個性が出会う学びの場」をテーマに様々な探求学習のプログラムが実施されていますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
家庭や学校以外にも学びの場はたくさんありますので、ぜひ検討してみてください。
ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイント②新しいことにチャレンジ
知能は高いけれど、特定の分野に突出しているわけではないタイプのギフテッドのお子さまもいらっしゃいます。
そんなときは、日常生活ではあまりできない体験にチャレンジしてみると良いでしょう。意外な才能が見つかるかもしれませんし、お子さまにとって良い刺激になるはずです。
ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイント③お子さまの才能を肯定する
同年代の子どもと話が合わないというのは、ギフテッドのお子さまにとって切実な悩みです。
私が指導したとあるギフテッドのお子さまは、知的な欲求が非常に強く、休み時間でも常に新しい知識を吸収していたいという特性を持っていました。
ですが、休み時間のクラスメイトとの会話はアニメやテレビドラマに関するものばかりで、到底、お子さまの知的欲求を満たすものではありません。
それでも頑張ってクラスメイトと話を合わせていましたが、本人が自覚している以上にストレスが溜まってしまい、最終的には頭痛や嘔吐といった身体的な症状が出てしまいました。
現在は海外に留学し、知的欲求を満たすことのできる環境で伸び伸びと過ごしているそうですが、日本にいる間は本当に地獄のようだったと話されていました。
ギフテッドのお子さまが持っている知的な欲求は、私たちが想像する以上に激しいものです。
ですが、周りから理解されず、さらに周りに合わせなければならないストレスから心身に不調を来してしまうことさえあります。
ご家庭におかれては、お子さまの才能が素晴らしいものであることを伝えるとともに、学校では無理をしてまで周りと合わせる必要は無いことも伝えるようにしましょう。
ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイント④集団での活動に参加してみる
ギフテッドのお子さまは、高い知能を持っているために、学校では周りから孤立してしまうことがあります。ですが、他人と一緒に何かに取り組むことは、お子さまの成長において必要な経験です。
同年代同士だと上手くいかない場合は、地域の趣味サークルやスポーツクラブなど、老若男女を問わず参加できる活動を探してみるのも良いでしょう。お子さまの視野を広げるという点でもおすすめです。
ギフテッドの小学生を育てるときの5つのポイント⑤家庭での会話を重視する
ギフテッドのお子さまは、「自分を理解してくれる人は誰もいない」という孤独感を感じていることがあります。
お子さまが持っている知識や世界観のすべてを理解することはできなくても、可能な限り会話を重ね、「いつでも見守っていること」「何があっても味方であること」を伝えるようにしましょう。
まとめ:ギフテッド小学生の特徴と育て方
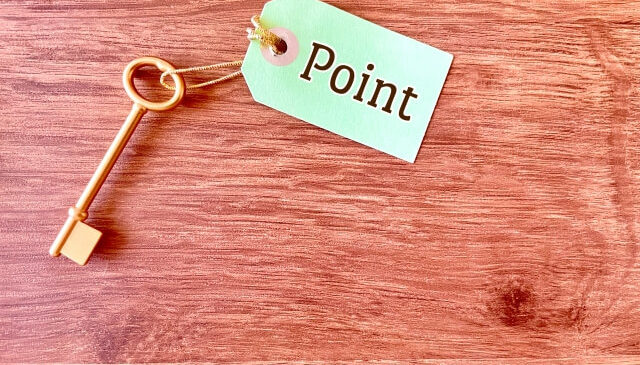
この記事では、小学生のギフテッドの特徴や育て方について詳しく紹介してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- ギフテッドとは、高い知能(IQ130以上)や音楽・芸術・運動などに特別な才能を持った人のこと
- ギフテッドの小学生のお子さまには「言葉の発達が早い」「理解力・記憶力・集中力が高い」「知的好奇心が強い」といった特徴がある
- ギフテッドの小学生のお子さまの困りごとには「非同期発達」「過度激動」「周りの目」「浮きこぼれ」といったものがある
- ギフテッドの小学生のお子さまを育てる際には、得意を伸ばす視点が最も重要
ギフテッドは何でもできる天才児と思われがちですが、ギフテッド特有の困りごとも多く、さらに相談先も少ないために困っている保護者さまも多くいらっしゃいます。
プロ家庭教師メガジュンでは、ギフテッド・発達障害専門の家庭教師として一人一人にとことん寄り添った指導を大切にしています。
お子さまが持っている才能や個性はそれぞれ違いますので、まずはお子さまのことをしっかりお伺いし、お子さまや保護者さまと関係を築きながらサポートを進めてまいります。
ギフテッドのお子さまの学習や生活のことでお悩みの方は、ぜひ一度プロ家庭教師メガジュンまでお問い合わせください。
また、授業や面談はオンラインでも可能です。
これまで日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方にも利用いただき、ご好評をいただいてきました。初回相談と初回授業は無料で承っていますので、「オンラインは少し不安・・・」という方も、お気軽にご相談いただけます。
お子さまが生まれ持った才能を存分に生かし、より良い人生を切り拓いていけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



