ギフテッドの子ども(小学生・中学生)の特徴とは?才能や発達障害との違いを解説
ギフテッドとは、IQが130以上、または特定の分野で優れた才能を持つ子どもたちのことを指します。
近年では映画や小説の題材にもなっているギフテッドですが、お子さまの場合は同年代のクラスメイトとの関係が築きにくかったり、学校に馴染みづらかったりなどの困りごとを抱えることもあります。
また、ギフテッドのお子さまが持つ特徴や才能が注目される一方で、発達障害や日常生活の困りごととの違いがわかりにくいと感じる保護者さまも多くいらっしゃいます。
この記事では、ギフテッドの特徴や、発達障害との違いについて具体的に解説し、ギフテッドならではの育て方やサポートのポイントをご紹介します。
ギフテッド専門のプロ家庭教師の視点から、お子さまの才能を正しく理解し適切に伸ばすためのヒントをお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。

ギフテッド・発達障害専門のプロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
ギフテッドとは
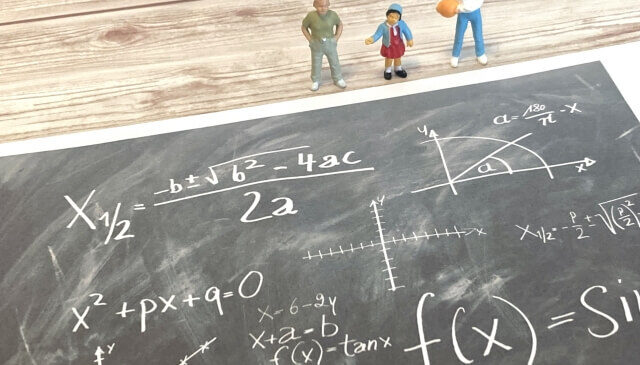
ギフテッドとは、IQ130以上の高い知能、もしくは芸術や運動に突出した才能を持つ人のことを指します。
IQ(知能指数)については、児童精神科やメンタルクリニック、民間のカウンセリングルームなどで測ることができます。発達障害などの困りごとがある場合は保険適用されますが、特に困りごとが無い場合は自費での検査になりますので注意しましょう。
自費での知能検査は、クリニックにもよりますがおよそ2~3万円程度かかります。
芸術や運動の才能については、知能検査やテストで測ることはできません。また、「絵が上手い」「運動神経が良い」だけでなく、「自然への造詣が深い」「哲学的に思考することが好き」といったこともギフテッドの才能の一種と捉えることができます。
この章では、知能指数の測り方や知能以外の才能の見つけ方について詳しく解説していきます。ギフテッドの困りごとや解決方法について知りたい方は、「2.ギフテッドの子どもの特徴とは」までお進みください。

ギフテッドの定義①IQ130以上または芸術などの才能を持つ
一般的にギフテッドとは、IQが130以上である人のことを指します。
IQで測れない芸術や運動の才能がある場合もギフテッドに相当しますが、知能の面で言えば「IQが130以上であること」がギフテッドの定義です。
最も広く用いられている知能検査「WISC-IV」では、IQは偏差値として、平均が100となるように調整されています。
IQ130以上の人の割合は約2%とされており、体感としては「40人のクラスに1人いるか、いないか程度」ということになります。
WISC-IV検査は、発達障害の診断の際などに広く用いられている知能検査であり、言語理解・処理速度・ワーキングメモリ・知覚推理の4つの指標を測ることができます。
さらに4つの指標を合わせて、全検査IQ(FSIQ)と呼ばれる総合的な知能を測ることができます。なお、WISC-IVは子ども用であり、大人(16歳以上)の場合は「WAIS-IV」を用います。
全検査IQの数値によってギフテッドをさらに分類する場合もあります。
ギフテッド教育の先進国であるアメリカなどでは、知能指数ごとにギフテッドを分類することで、それぞれの層に合ったサポートや教育を行っています。
- mildly gifted ~IQ130以下
- moderately gifted IQ131~149
- highly gifted IQ150~159
- exceptionally gifted IQ160~179
- profoundly gifted IQ180
知能面におけるギフテッドについては、WISC-IVなどの知能検査で測ることができますが、芸術や運動に関する才能は知能検査で測ることはできません。
お子さまの隠れた才能を見つけるためには、心理学者であるハワード・ガードナー博士が提唱した「多重知性理論(8種類の知性)」を参考にすると良いでしょう。
ガードナーが唱えたこれらの能力は、ほとんどの場合、知能検査で測ることはできません。
私たちは「学校のテストで良い点が取れる=頭が良い」と考えてしまいがちですが、芸術や運動、自然への深い興味やコミュニケーション能力も、ひとつの才能であると捉えることができます。
ギフテッドかどうかといった定義だけでなく、「お子さまの良いところを見つける」という点でも、このガードナーの多重知性理論は大きな気付きを与えてくれるのではないでしょうか。

ギフテッドの定義②2E型ギフテッドと英才型ギフテッド
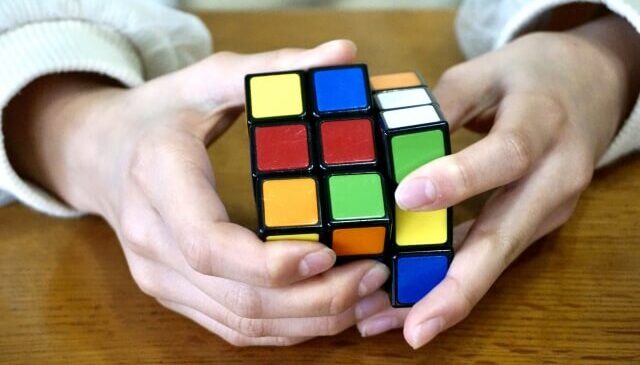
ギフテッドは、特定の分野については突出した才能があるものの、その他の分野では能力が平均を下回るなど、発達に凸凹がある「2E型ギフテッド」と、全ての分野で平均以上の能力が見られる「英才型ギフテッド」に分類することができます。
- 2E型ギフテッド
- 特定の分野に突出した才能があるが、その他の分野では平均を下回ることがあるなど発達や能力に凸凹があり、ADHD・ASDなどの発達障害を併せ持つこともある。
広義では、発達障害以外の疾患や障害を併せ持つ場合も2E型ギフテッドに含む。 - 英才型ギフテッド
- あらゆる分野において平均以上の能力が見られる。
知能だけでなく、芸術・運動・コミュニケーションにおいても優れた能力を発揮する場合がある。
2E型ギフテッドの場合、WISC-IV検査においても各指標のバラつきが大きいなどの特徴が見られることがあります。
指標間のバラつきは「ディスクレパンシー」と呼ばれますが、このディスクレパンシーが15~20以上かつ全検査IQが130以上の場合は、2E型ギフテッドの傾向があると考えられます。
ただし、ディスクレパンシーは全検査IQが高くなるほど大きくなる傾向がありますので、各指標が平均を下回らない(=100以下とならない)場合は、それほど気にする必要はありません。
また、WISC-IV検査は、お子さまの今後のサポートを考える際の参考指標であり、WISC-IV検査だけで発達障害やギフテッドの判断ができるものではありません。
点数に一喜一憂するのではなく、お子さまの普段の様子と照らし合わせながら、「お子さまの○○の行動は、この特性が関係しているのだな」など、お子さまをより深く理解するために役立てるようにしましょう。
2E型ギフテッドの場合は、発達障害の特性を併せ持つことも多いことから、“苦手が目立ち、得意が埋もれる”傾向にあります。
周りの大人も苦手を解消することを優先するため、本人が自信を無くしたり、せっかくの才能が開花しないままになったりするケースもあります。
もちろん、社会で生きていく上で苦手を解消することも大切ではありますが、苦手なことを指摘されるよりは、自分の得意なことを褒めてもらう方がお子さまにとって何倍も嬉しいものです。
ですので、苦手を解消するためのトレーニングは必要最小限にとどめ、得意を伸ばしていけるようなサポートを心掛けていきましょう。
ギフテッドの浮きこぼれ問題|男の子・女の子で生じやすいケースについて
ギフテッドのお子さまは、「浮きこぼれ」の問題で悩むことがあります。
浮きこぼれとは、落ちこぼれの逆で、授業が退屈で学校に行くのが億劫になってしまったり、同年代の子どもたちと馴染めなかったりといった困りごとを抱えるケースを指します。
日本の学校では、皆と同じ内容を、同じスピードで学ぶことが求められます。画一的な授業の在り方を見直そうという流れもありますが、実現までには長い時間が掛かるでしょう。(参考:学習指導要領「生きる力」:文部科学省 (mext.go.jp))
学校では平均以上にできる子よりも、平均よりも苦手が目立つ子(いわゆる落ちこぼれ)の方が優先してサポートされます。学校の先生も、ギフテッドや浮きこぼれについては存在自体をあまり認識しておらず、「賢いから放っておいても大丈夫」と思われてしまうケースも少なくありません。
適切なサポートが受けられない結果、学校の授業のつまらなさや同年代の子どもたちとの会話の噛み合わなさなどのストレスが重なり、立ち歩きや攻撃性などの問題行動が現れる場合もあります。
中には、これらの問題行動から「発達障害の傾向あり」と判断されてしまうお子さまもいらっしゃいます。
生まれつき発達障害の特性があるわけではないにもかかわらず、ストレスによる問題行動から「発達障害である」と誤診されることは避けなければなりません。
集中力の低下やコミュニケーションの不全、その他の困りごとや問題行動の原因が、必ずしも発達障害であるとは限りません。発達障害以外にも、ギフテッドの浮きこぼれや生活習慣の乱れ、その他のストレスなど、様々な要因が困りごとの原因として考えられます。
例えば、授業中に立ち歩いてしまうお子さまの場合、
- 生まれつきじっとしているのが苦手なADHDの性質を持っている
- 授業がつまらないと感じているから立ち歩いている(本人が面白いと感じる授業であれば座っていることができる)
- 何かイライラすることがあって立ち歩いている(イライラしていないときは座っていることができる)
など、様々な可能性を検討する必要があります。
特に低学年の男の子のギフテッドのお子さまにありがちな、「授業中に立ち歩く」「宿題をしない」「反抗的・攻撃的な態度を取る」などはADHDの特性として捉えられることが多いです。
ですが、これらの行動は、ギフテッドゆえのストレスが原因であり、それらを取り除けば落ち着く場合も多いので、しっかりと行動の背景を分析していただければと思います。
ギフテッドの女の子の場合は、このような立ち歩きや攻撃性よりも、過剰適応で疲れてしまい不登校になるケースが多いです(男女差はあくまで傾向であり、全ての男の子・女の子に当てはまるものではありません)。
例えば、本当は自然科学や人文学などに関するアカデミックな話をしたいけれど、周りのお友だちに合わせて興味の無いアイドルやアニメの話をするなどで、少しずつストレスが溜まってしまうケースです。
また、女の子の場合は男の子に比べると社会性の発達が早く、協調性を重視する傾向にあります。そのため、高い知能を持っていることを敢えて隠しながら過ごしている方もいらっしゃいます。
このように、興味が無い話題に合わせたり、年相応の女の子らしく振舞ったりすることは、ギフテッドのお子さまにとって「自分ではない自分を演じること」にほかなりません。
「自分ではない自分」を毎日演じ続けていると、本人も気付かないうちに少しずつストレスが溜まってしまい、ある日突然学校に行けなくなってしまうなどのケースがあります。
ギフテッドのお子さまで、疲れやすかったり、週末に体調を崩しやすかったりする場合は、気付かないうちにストレスを感じている可能性がありますので、適度に休養を取らせるなどの対応が必要です。
場合によっては、無理に学校に通うのではなく、フリースクールやホームスクーリングで学ぶという選択肢もあります。
ただし、学校レベルの勉強であれば自学自習で問題ありませんが、お子さまの知的好奇心を満たすような学びを得るためには、塾やプロ家庭教師といった専門的なサポートを受けることが望ましいでしょう。
また、学校に行かないことで、集団生活や他者とのコミュニケーションを学ぶ機会も減ってしまうことも、不登校に伴う大きなデメリットです。学校の集団生活がどうしても苦手な場合は、地域のサークルや習い事など、学校以外でそれらを学ぶ機会を得られるようにすると良いでしょう。

ギフテッドの子ども(小学生・中学生)の特徴とは

ギフテッドのお子さまには、「強い知的好奇心」「膨大な知識」「大人びた態度」などの特徴が見られます。
ですが、一口にギフテッドといっても一人一人個性があり、「IQは130以上あるけれど、何に対しても興味を示さない」といったケースもあります。
以下では、全米才能児協会(the National Association for Gifted Children: NAGC)が示しているギフテッドの特徴などを元に、ギフテッドのお子さまによく見られる行動・特徴をまとめましたので、お子さまの性質を分析するための参考としていただければと思います。
また、次の章では、ギフテッドのお子さまに見られる「非同期発達」「過度激動(OE)」についてもご紹介していきます。
- 記憶力が非常に良く、どんな知識もすぐに定着する
- 身につけた知識を使いこなし、物事の判断にも優れている
- 同年代の子どもよりも語彙がはるかに豊富で、複雑な文章を書いたり話したりする
- 数字やパズルなどの問題が好きで、勉強ではなく楽しみとして解くことが多い
- 感受性が豊かで、神経質に見えることもある
- 社会問題に関心があり、政治などの話題にも難なくついていける
- 想像力が逞しく、空想に耽ることもしばしばある
- 知的好奇心が強く、常に新しい知識や学びを求めている
- 年齢に比べて集中力が非常に高い
- ユーモアや皮肉をよく理解し、ウィットに富んだ会話ができる
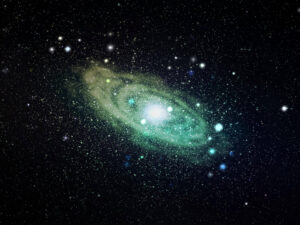
ギフテッドの子どもの特徴①非同期発達

非同期発達とは、ギフテッドのお子さまが成長していくときに、「ある部分は速く発達するが、他の部分は年齢相応のスピードで発達していく状態」を指します。
通常、子どもの能力は、あらゆる面で同期的に(=互いに影響しながら一体的に、足並みをそろえて)伸びていきます。
言葉の理解やコミュニケーション能力、未来を予測する力や算数的に考える力、さらには精神的な成熟や運動機能まで、それらは密接に関わり合いながら成長していきます。
一方、ギフテッドのお子さまの場合、「言語理解だけ」「数学的思考だけ」など、一部の能力だけが他の能力に先立って成長する場合があります。
その結果、「話し方は達者なのに、態度は子どもっぽい」というアンバランスな状態になることを非同期発達と呼びます。
突出した才能以外の部分が年齢を重ねても成長しなかったり、年齢不相応に発達が遅れている場合は、発達に凹凸があるということで2E型ギフテッドに分類されます。
ですが、幼いうちは個人による発達スピードの差も大きいため、ギフテッドの非同期発達と2E型ギフテッドを見分けるのは困難でしょう。
ギフテッドのお子さまに非同期発達が見られたとしても、特別な対応は必要ありません。
お子さまが成長するにつれて、徐々に発達の度合いは揃ってきますので、「ギフテッドとは言え、まだまだ子どもの部分もあるのだな」と落ち着いて見守ることが大切です。
知識や学力などが優れているからといって、幼いうちから何もかもが優れているというケースは非常に稀です。
ギフテッドのお子さまは、周りと比べて賢い分、子どもっぽさが悪目立ちしたり、周りと馴染めなかったりして、「扱いにくい子」と見られてしまいがちですが、ギフテッドとはいえあくまで子どもであるということは常に念頭に置いて接するようにしましょう。
また、ギフテッドのお子さまは「自分が周りより優れている」ということに気付いておらず、「こんな簡単なことも分からないの?」などと悪気無く発言してしまうこともあります。
そのため、お友達から仲間外れにされてしまったり、学校の先生から「生意気だ」と思われてしまったりすることがあります。ご家庭においては、お子さまの成長に応じて、言い方・伝え方の工夫の仕方を教えてあげると良いでしょう。

ギフテッドの子どもの特徴②過度激動(Over Excitability: OE)

過度激動(Over Excitability: OE)とは、感覚や知性が人よりも過敏である特性のことで、ギフテッドのお子さまによく見られます。
ギフテッドのお子さまは、感覚や知性が敏感であるために、強い知的好奇心を持っていたり、普通の人では気付かないような点に気付いたりすることができると考えられています。
ただし、ちょっとしたことでも敏感に反応してしまうため、疲れやすかったり、集団生活に馴染みづらかったりといったマイナスの側面も持っています。
「考えすぎて疲れる」「感情が豊か過ぎてしんどい」といったことはギフテッドのお子さまのお悩みとしてよくあるもので、メンタル面でのケアが非常に重要となります。
また、過度激動には、五感の鋭さや感受性の豊かさ、知的欲求の強さなど、様々な種類があります。
- 知性過度激動
- 知的好奇心が非常に旺盛で、強い知識欲を持つ
- 精神運動性過度激動
- スリルや冒険、新しい経験など、精神面での強い刺激を求める
- 感覚性過度激動
- 五感が敏感で、細かな違いを楽しんだり、あるいは強い刺激が苦手で避けたりする
- 想像性過度激動
- 想像力が非常に豊かで、普通の人には思いつかないような発想ができるが、妄想に耽ることもある
- 情動性過度激動
- 感受性が強く、ちょっとしたことでも感情の浮き沈みがあるほか、他者への共感性に優れる
これらの過度激動の分類のうち、一つだけに当てはまる人もいれば、複数に当てはまる人もいます。また、それぞれの強弱も人によって異なります。
過度激動はギフテッドの特性として強みになることもありますが、困りごとが目立つために発達障害と誤診される場合もあります。
例えば、感覚性過度激動は、ASD(アスペルガー症候群)の特性である感覚過敏と非常に良く似ていますし、想像性過度激動によって空想に耽ってしまうことが多い場合、「ぼーっとしてしまう」というADHDの不注意特性と区別が難しくなります。
困りごとと才能は表裏一体です。
もしギフテッドのお子さまに「想像を膨らませる(ぼーっとする)のは良くない」という指導を続けたら、せっかくお子さまが持っていた豊かな想像力が失われてしまうかもしれません。
また、ADHDと誤診されることで、誤った投薬治療を受けてしまう可能性もあります(※)。
お子さまがADHDと診断されたら、まずは療育と環境の調整を行いましょう。薬物治療については療育や環境調整によって困りごとの改善が見込まれず、かつ明らかにADHDである(その他の原因によるものではない)と確証が得られてから行うことが大切です。
ギフテッドの過度激動と、2E型ギフテッドの発達障害の特性を区別するのは、専門医であっても非常に困難であり、場合によっては明確な区別ができないケースもあります。
診断名は今後のサポート方法を考えるための指針であり、診断名だけにこだわる必要はありません。
大切なのは目の前のお子さまをしっかり見て、状況に応じてサポートの内容を調整していくことですので、お子さまの困りごとは何か、どんな状態にしていきたいかをお子さま本人ともしっかり話していただき、必要に応じて学校の先生や専門医、カウンセラーにも相談するようにしましょう。

ギフテッドの中学生の具体的な特徴
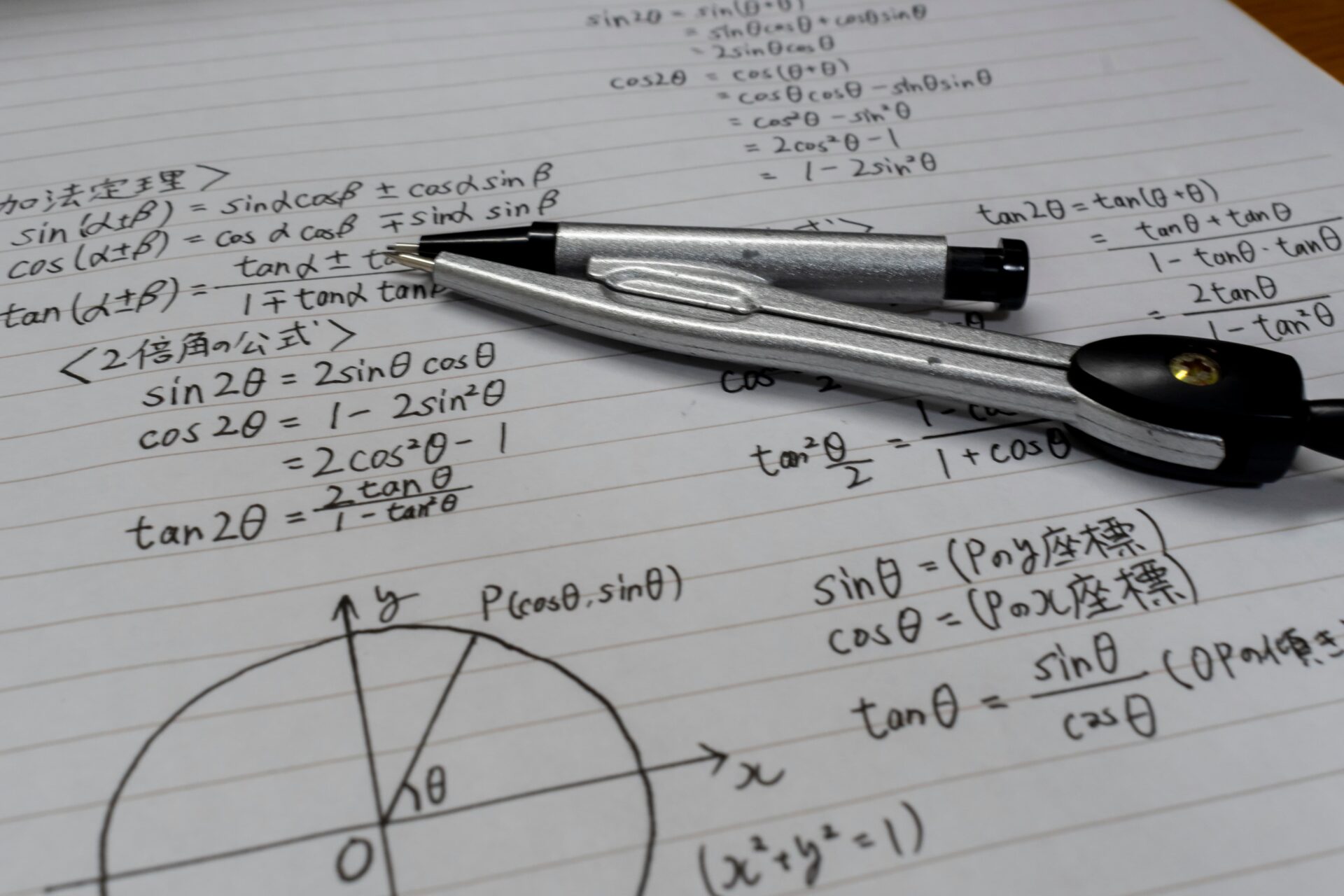
この章では、ギフテッドの中学生のお子さまの特徴について詳しく解説していきます。
ギフテッドのお子さまは、中学生くらいの年齢になると、周りに合わせて同年代の子どもらしく振舞うことがストレスなくできるようになる場合もあります。
一方で、同年代の子どもらしく振る舞うことに大きなストレスを感じたり、小学生のころに比べてギフテッドらしさがより顕著に表れるお子さまもいらっしゃいます。
以下では、中学生のギフテッドのお子さまの特徴について、
- 学業面での飛躍的な成績向上
- 趣味・興味の追求
- 学校生活における浮きこぼれ
の3点から解説していきます。
ギフテッドの中学生の具体的な特徴①学業面での飛躍的な成績向上
ギフテッドの中学生は、特に数学や科学などの抽象的な思考を要する分野で突出した才能を見せることが多いです。
例えば、学校の授業で初めて習う難解な数学の公式や理論を、ほとんど予習せずに直感的に理解するケースがあります。
クラスメイトが苦労している間に、ギフテッドのお子さまはその知識をすでに吸収し、より高度な課題に挑戦したがることもしばしばあります。
ギフテッドの中学生の具体的な特徴②趣味・興味の追求
中学生になると、ギフテッドのお子さまは知的好奇心を自分で満たす方法を獲得し、学校の枠を超えて自分の興味を深掘りできるようになることも珍しくありません。
例えば、私が以前指導したギフテッドの中学生のお子さまは、歴史や哲学に強い関心を持っていらっしゃいました。
中学校の教科書の内容では飽き足らず、高校の教科書を先取りして一通り読んだ後は、大学の学部生が読むような入門書や専門書を自主的に読み進めていきました。
そのお子さまは、最初のうちは私や他の講師に読むべき本について相談していましたが、しばらくすると自分でインターネットで調べたり、参考文献から芋づる式に書籍を調べ、図書館などで読むという方法で知見を広げていらっしゃいました。
ギフテッドの中学生の具体的な特徴③学校生活における浮きこぼれ
中学生になることで、浮きこぼれの問題が一層顕著になることもあります。
小学生の間は、学校で習う内容も簡単なため、ギフテッドのお子さま以外でも「先生の話を聞かなくても理解できる」という子がクラスの中に一定数いることが多いです。
しかし、中学生になって授業の内容が高度になってくると、「授業を聴かなくても完全に理解できるのはギフテッドのお子さまだけ」という状況になってきます。
一方で、中学生になるとお子さま同士のコミュニケーションは高度になり、教室の中での同調圧力もますます強くなります。
その結果、「分かっているけれど、分かっていないふりをしなければならない」「頭の良いことをひけらかしているように思われた」などの状況が生じやすくなります。
結果として、「学校に行きたくない」「集団生活に馴染めない」など、心理的な負担が増していく可能性があります。
中学生は多感な時期ですので、小学生の頃よりもさらに丁寧に見守ることが必要です。

ギフテッドの子ども(小学生・中学生)に効果的な5つのサポート方法とは

ギフテッドのお子さまの困りごとを軽減し、才能を存分に伸ばしていくには、周りの大人のサポートが欠かせません。
この章では、ギフテッドゆえに周りと馴染みにくかったり、知的欲求を満たせなかったりといった困りごとを解決するためのポイントについて、順にご紹介していきます。
- 才能を肯定できる自分になる
- 知的欲求を満たす
- 新しい分野へのチャレンジ
- 集団活動への参加
- 家庭での会話の充実
ギフテッドのお子さまに効果的な5つのサポート方法①才能を肯定できる自分になる
ギフテッドのお子さまは突出した才能を持っていますが、才能や特性がコンプレックスになってしまうこともあります。
私が以前受け持ったギフテッドのお子さまは、非常に強い知的好奇心を持っており、過度激動のうち「知性過度激動」が強いタイプのお子さまでした。
新しい知識を常に吸収していたいという強い欲求があり、その欲求が満たされないとストレスが溜まってしまいます。ですが、学校の授業や同年代の友達との会話は、当然ながら彼女の強い知的好奇心を満たすものではありませんでした。
「もっと難しく、面白く、ワクワクすることを知りたい!」と心の中で思っていても、それを叶えることは難しく、彼女は無理をして“普通の子”として振る舞っていました。
ですが、中学生になったある日、彼女のストレスは限界に達しました。
頭痛や嘔吐といった身体的な症状が現れ、その日から彼女は学校に行くことができなくなりました。
自分の気持ちを抑えて無理に周りに合わせることが、小中学生の心身にどれだけ大きな負担となっていたかを想像すると胸が痛みます。
学校そのものがトラウマになってしまった彼女は、中学はそのまま不登校に、高校は通信制に進学しました。
高校の時、あるきっかけで彼女は海外留学に行くことになったのですが、カリキュラムに縛られず、それぞれが好きなものを好きなように学ぶ学校の在り方に彼女は感銘を受け、海外の大学への進学を目指すようになりました。
元々ギフテッドで高い知能を持っていた彼女は、無事に海外の大学に合格し、今では研究者として活躍しています。
先日連絡を取った際には、日本にいた頃とは見違えるほど生き生きとした様子で、「やっと自分が自分で居られる場所を見つけた」と話していました。
日本の学校教育は画一的で横並び重視のため、ギフテッドのお子さまは「出る釘が打たれないように」と自ら才能を隠してしまうケースも多くなっています。
周りの子と違うことで育てづらさを感じる面もあるかもしれませんが、まずは保護者さまが才能を肯定し、お子さまが自信を持って生きていけるように応援していただきたいと思います。
特に、他者への共感性が高く、空気を読むことが得意なギフテッドのお子さまの場合は、自分の心が壊れるまで我慢をしてしまうことがあります。
お子さまの心や体以上に大切なものはありませんので、無理に周りに合わせる必要が無いということをしっかりとお子さまに伝えるようにしましょう。

ギフテッドのお子さまに効果的な5つのサポート方法②知的欲求を満たす

日本の学校においてギフテッドのお子さまのために特化した教育を受けることは、現段階では難しいでしょう。
文部科学省ではギフテッド教育に関する有識者会議が開かれており、徐々に検討が進められていますが、実際に学校現場でギフテッド教育が行われるのはまだまだ先になると思われます。(参考:特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議)
学校でのギフテッド教育が期待できない中で、ご家庭においては、お子さまが才能を持っていたり、興味・関心がある分野について、存分に学べる環境を整えてあげるようにしましょう。
子ども向けの児童書や図鑑でなくても、本人が読みたがるのであれば高度な内容の本でも手に取らせてあげるようにしましょう。専門書は高価な場合もあるので、図書館を上手く活用するなど、適宜工夫すると良いでしょう。
大学教授や研究者など、専門家と直接話せるセミナーや講座への参加もおすすめです。
大学の研究室やNPOなどでギフテッドの子どもたち向けのプロジェクトを実施している団体もありますので、ご家庭だけでお子さまの知的欲求を満たすことが難しい場合は、こういった様々なプロジェクトを活用するのも良いでしょう。(参考:東京大学先端科学技術研究センター中邑研究室 異才発掘プロジェクト ROCKET)
ギフテッドのお子さまに効果的な5つのサポート方法③新しい分野へのチャレンジ

知能検査の数値は高いけれど、これといった特定の分野に才能や関心があるわけではないお子さまもいらっしゃいます。
このタイプのお子さまの場合は、自分の好きなものに出会えていない可能性がありますので、いろいろなモノにチャレンジしてみるのがオススメです。
ギフテッドのお子さまはワクワクするような経験を好む方も多いため、新たな挑戦をきっかけに、意外な才能が見つかるかもしれません。
ギフテッドのお子さまに効果的な5つのサポート方法④集団活動への参加

ギフテッドのお子さまは、周りの子どもたちと異なる感覚を持っていることが多く、学校のクラスなどで孤立してしまうことが多いです。
授業の内容に興味が持てなかったり、同年代の友達との会話が合わなかったりするため、集団生活になじめず、登校自体が難しく感じられることもあります。
とはいえ、他人と協働して何かに取り組む経験は、お子さまが将来社会に出る際に大切な力となります。
集団での活動を通して得られるコミュニケーションスキルや共感力は、お子さまが「社会の一員」として成長していくための重要な要素です。
ただし、集団活動の場が必ずしも学校のクラスである必要はありません。
むしろ、学校のように同年代が集まる環境は、お子さまにとって気疲れやストレスの原因になりやすいため、学校外での集団活動が適している場合も多いです。
例えば、地元の趣味のサークルやスポーツクラブに参加するのは非常におすすめの選択肢といえます。
私が指導したあるギフテッドのお子さまは、学校生活では友達と話が合わず孤立していましたが、週末には地域の図書館で行われている「歴史研究サークル」に参加していました。
サークルの参加者は子どもから大人まで幅広く、特に歴史に詳しい年配の参加者から多くの知識を吸収し、議論を楽しむ姿が見られました。
この経験を通して、お子さまは大人と対等に話をする力や、多様な視点から物事を考える力が身についていきました。
また、異年齢が集まる環境においても、ギフテッドのお子さまは新しい発見をすることが多いです。
例えば、地域のボランティア活動に参加するのも、良い経験の一つです。
年に数回行われる清掃活動や地域行事の手伝いなど、さまざまな年代の方と協力しながら役割を果たしていく体験は、お子さまに「人のために動く」という責任感を育む機会になります。
実際、過去に地元の清掃ボランティアに参加したギフテッドのお子さまは、「自分の働きが誰かの役に立つことが嬉しい」と話し、ボランティアを通じてコミュニケーションスキルや自己肯定感を高めていました。
さらに、学校外の「習い事」も集団活動の場として有効です。
ギフテッドのお子さまの場合、興味を持つ分野が明確な場合が多く、その分野の専門性を高めるために塾や専門スクールで学ぶことで、自分と似た興味を持つ人々との出会いが期待できます。
例えば、科学に興味があるお子さまがサイエンススクールやプログラミング教室に通うと、そこで同じような興味を持った仲間と一緒に課題に取り組むことができ、協働することの楽しさを感じることができます。
あるお子さまは、プログラミング教室で年齢の異なる子とチームを組んでゲーム制作に挑戦し、コミュニケーションスキルだけでなく協調性や忍耐力も身につけていらっしゃいました。
多様な年齢構成の集団に参加することは、お子さまの視野を広げ、学校でのクラス活動以上に「生きる力」を養う場となるでしょう。
多くの人と触れ合い、多様な価値観に触れることで、「世の中にはいろんな考え方があるんだ」と実感することができますので、ぜひチャレンジしていただければと思います。
ギフテッドのお子さまに効果的な5つのサポート方法⑤家庭での会話の充実

お子さまの高度な話に周りがついていけないとき、幼い頃は「どうしてわからないんだろう?」という単純な疑問を感じるだけですが、成長するにつれ「自分のことを分かってくれる人は誰もいない」という孤独感を抱える場合があります。
解決策の一つに、同じように高い知能を持ったギフテッドの人々と交流するという方法もありますが、誰よりも一番身近な存在である保護者さまから「あなたは一人ではないよ」というメッセージを伝えることもとても大切です。
お子さまが考えている内容の全てを理解することは難しいかもしれませんが、「いつも家族が見守っていること」「どんなチャレンジも応援すること」を、日頃からしっかり伝えるようにしましょう。

ギフテッドの子どもの特徴のまとめ
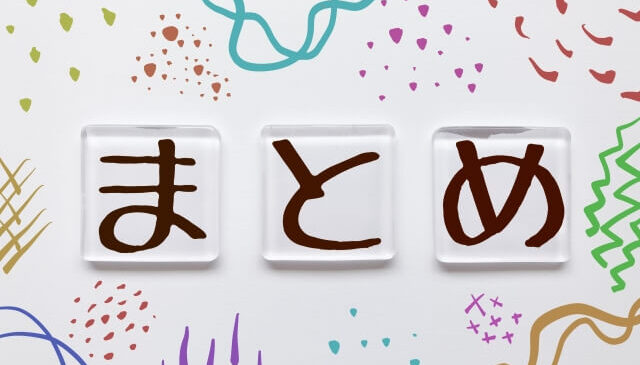
この記事では、ギフテッドのお子さまの特徴やサポートの方法について詳しくご紹介してきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- ギフテッドとは、IQ130以上の人や、芸術・運動などに優れた才能を持った人のこと
- ギフテッドは、発達に凹凸がある2E型ギフテッドと、全体的に能力の高い英才型ギフテッドに分けられる
- 2E型ギフテッドは苦手が目立ちやすく、得意が埋もれやすい傾向にある
- 英才型ギフテッドは、浮きこぼれなどの困りごとを抱えることがある
- ギフテッドの過度激動と発達障害の特性は、専門医でも見分けるのが難しい
- ギフテッドの非同期発達は、焦らず見守ることが大切
- ギフテッドのお子さまの知的な欲求を十分に満たし、才能を肯定することが大切
ギフテッドは、高い知能や特別な才能を持っていてうらやましいと思われがちですが、ギフテッド特有の悩みがあるほか、さらに相談先が少ないという困りごともあります。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、ギフテッド専門のプロ家庭教師として一人一人にとことん寄り添った指導を行っています。
長年の指導で積み上げたノウハウを元に、ギフテッドのお子さまの才能を最大限伸ばせるようにサポートしてまいります。
代表の妻鹿は現役のキャリアアドバイザーでもありますので、受験だけでなく、その後の人生全体を見据えた進路のご提案が可能です。ギフテッドのお子さまの勉強や進路でお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
また、授業や面談はオンラインでも行っています。
これまで日本国内だけでなく、海外在住の方や帰国子女の方にもご利用いただき、ご好評の声をいただいてきました。
オンラインで授業が受けられるか不安なお子さまも、初回相談と初回授業は無料で承っていますので、お気軽にご相談ください。

お子さまが才能を存分に発揮し、自らの力で人生を切り拓いていけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。




