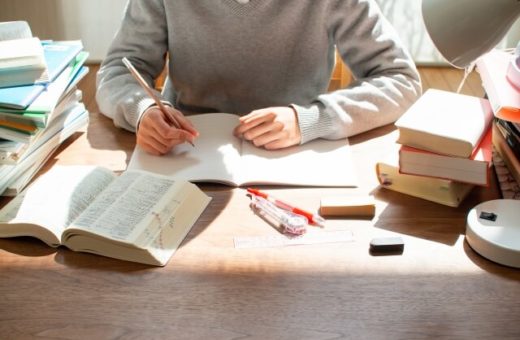ギフテッドなのに勉強が苦手?高IQでも学校の成績が悪い場合に親がすべきこと
ギフテッドとは、IQ130以上の高い知能を持つ人のことを指します。
知能が高いということは、ギフテッドのお子さまは学校の勉強もそつなくこなし、成績優秀な優等生ばかりなのだろうと思ってしまいますが、実は、ギフテッドであるからといって必ずしも学校の勉強ができるとは限りません。
というのも、そもそも知能指数とは、学校の勉強とはあまり関係がありません。
基本的に学校の勉強は、教えられたことを教えられたとおりに再現する力(漢字の書き取り、九九、英単語など)を指しますが、知能指数とは、言語や図形を認識し、理解したり処理したりする生まれつきの能力のことを指します。
もちろん、知能指数が高いと学校の勉強を効率良く進めることが可能にはなりますが、高い知能を学校の勉強のために使えるかどうかはまた別の問題になります。
むしろ、高い知能を持っているがゆえに、「もっと難しいことを学びたいのに、学校の勉強はつまらない」と感じたり、「なぜ勉強しなければいけないのか」と深く考えてしまったりして、学校の勉強に気持ちが向かわないギフテッドのお子さまもたくさんいらっしゃいます。
このようなお子さまの場合は、学校の勉強に集中できないことから立ち歩きなどの問題行動が見られたり、集団生活に馴染めず不登校になったりすることがあり、いわゆる優等生とは違ったタイプとなります。
また、このような困りごとが現れたことをきっかけに知能検査を受け、初めてギフテッドであることが判明するケースも多くなっています。
私はギフテッド専門のプロ家庭教師として活動していますが、保護者さまからは「ギフテッドの我が子に学校の勉強を頑張らせるべきか、それとも好きなように学ばせるべきか」というお悩みをよく伺います。
社会で生きていくためには、学校で揉まれながら社会性を身に付けることや学歴を取得することも重要ですので、保護者さまがこのような悩みを持たれるのは当然と言えます。
そこでこの記事では、ギフテッドのお子さまの勉強について、周りの大人はどのようにサポートするべきかをお伝えしていきます。
お子さまが才能を伸ばし、より良い人生を歩んでいくための参考にしていただけますと幸いです。

ギフテッド・発達障害専門のプロ家庭教師
妻鹿潤
・個別指導塾の経営・運営でお子様の性質・学力を深く観る指導スタイル
・yahooやSmartNews、Newspicksなどメディア向け記事も多数執筆・掲載中
▼目次
ギフテッドのお子さまが勉強が苦手になる理由(=浮きこぼれ)とサポート方法

高い知能を持っているにもかかわらずギフテッドのお子さまが勉強が苦手になってしまう根本的な要因は、「生まれ持った知能を学校の勉強に生かせていないため」です。
ギフテッドのお子さまが心から興味を持ち、前向きに学校の勉強に取り組むことができれば、テストで良い点を取ることは容易でしょう。問題は、学校の勉強に「興味がわかない」「やる気が出ない」ということです。
皆さんは、「浮きこぼれ」という言葉をご存知でしょうか。
浮きこぼれとは落ちこぼれの逆で、勉強が出来すぎて集団からこぼれてしまう子どもたちのことを指します。
ギフテッドに該当しない知能指数120程度のお子さまであっても浮きこぼれの状態になることはあります。特に、小学校低学年頃までの勉強の内容が簡単な期間において生じやすい問題となっています。
小学校入学までに平仮名が一通り書け、簡単な足し算・引き算ができるお子さまにとって、平仮名を一文字ずつ練習したり、数の数え方から習ったりするような小学1年生の勉強は非常に退屈なものです。
こうしたお子さまは、授業や宿題に意義を感じることができず、先生の話を聞かなかったり、宿題をやらなかったりします。その結果、テストで点は取れても授業態度の面で問題ありとされ、成績が落ちてしまうことがあります。
また、最初のうちは授業を聞かなくてもテストで点が取れていたとしても、勉強が難しくなるにつれ点が取れなくなってしまうこともあります。
テストで点が取れなくなったことをきっかけに授業や宿題に取り組めるようになれば良いのですが、低学年の頃に「先生の話を聞く」「宿題をする」といった習慣が確立できていないと、学年が上がってからも面倒に感じて勉強に前向きに取り組めなくなってしまうケースがあります。
浮きこぼれのお子さまたちは元々の知能が高いため、適切なサポートがあれば成績を向上させることは十分可能です。
ですが、お子さまのモチベーションを上手く誘導してあげる必要があり、単に「勉強しなさい」というだけではなかなか勉強に向かわせることができません。
さらにギフテッドのお子さまの場合は、学校の勉強以外のものに強い興味や関心を持っていることもあります。
「学校の勉強なんかより、プログラミングを極めたい!」というお子さまの場合は、無理に学校の勉強はさせず、好きなことを好きなように学ばせてあげる方が良いケースもあります。
ギフテッドのお子さまを学校の勉強に前向きに取り組ませるためには、お子さまの性質を十分に見極め、お子さまのやる気を無理やりではなく上手に誘い出す指導者の手腕が必要です。
ギフテッドのお子さまに学校の勉強を頑張らせたいと考えている方や、そもそも勉強を頑張らせるべきか悩んでおられる方は、ギフテッドの指導に長けた先生にまずは相談してみることをおすすめします。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは初回相談を無料で受け付けていますので、こうしたお悩みをお持ちの方はぜひお気軽にお問合せいただければと思います。
また、以下ではご家庭でできるギフテッドのお子さまのサポート方法を紹介していきます。
専門家への相談と併せて、ぜひ参考にしていただければと思います。
ギフテッドのお子さまの勉強のサポート方法①勉強のレベルを上げる

ギフテッドのお子さまの勉強のやる気をアップさせる最もシンプルな方法は、勉強の難易度を上げることです。
上の学年の内容を先取りしたり、中学受験を目指したりすることで、ギフテッドのお子さまもやりがいを持って勉強に取り組むことができます。(参考:ギフテッドの子どもは中学受験すべき?メリット・デメリットと学校選びのポイントを解説)
ただし、学校では習っていない漢字を書いたり、計算方法を使ったりすると先生に怒られてしまう場合もあります。
こうしたトラブルを避ける方法としては、
- ① 学校と連携し、先取りで勉強していることを認めてもらう
- ② 学校では周りに合わせ、知っている内容でも知らないかのように振る舞う
- ③ 怒られてしまっても気にしない
などが考えられます。
最も理想的なのは①で、お子さまの特性を学校にもきちんと説明し、先取り学習をしていること、そのため習っていない内容でも使ってしまう場合があることを伝え、頭ごなしに叱ったり否定したりしないようにしてもらう形です。
ただし、当然ですが教室はお子さま一人だけのものではありません。みんなが習っていないことをお子さまが答えた場合には、先生はほかの子どもたちにも分かるよう補足で説明をしなければなりません。
保護者さまにおかれては、そのプロセスが生じることを十分理解した上で、学校側に対応を依頼するようにしましょう。
「② 学校では周りに合わせ、知っている内容でも知らないかのように振る舞う」に関しては、器用なお子さまであればこなせるものの、知識を制限されているようでストレスを感じるお子さまもいらっしゃいます。とはいえ、①に比べると学校との調整が要らないというメリットもありますので、お子さまの特性に合わせて選択しましょう。
「③ 怒られてしまっても気にしない」に関しても、お子さまの特性によっては取り得る選択肢です。
習っていない内容を使うと怒られてしまうかもしれませんが、お子さま自身に非があるわけではないことを説明し、特に気にしないようにするという方法になります。
そもそも先生に怒られることを全く気にしないタイプのお子さまの場合は、こうした割り切った選択肢を取るのも一つの方法になります。
ギフテッドのお子さまの勉強のサポート方法②より本質的な話をする

ギフテッドのお子さまは、より深く本質的な学びを好む傾向にあります。
漢字の書き取りにしても、ただ覚えるだけではなく、漢字の成り立ち(部首は意味を表し、旁(つくり)は音を表す場合が多いなど)を教えてあげたり、そもそもなぜ勉強しなければいけないかという哲学的な話をしてあげたりするのも良いでしょう。
私が以前受け持った小学校低学年のお子さまは、「私は1+1=2であることを知りたいのではなくて、1の次がなぜ2なのかを知りたいのだ」と仰っていました。
なかなか難しい問いに私も頭を悩ませましたが、1の次は実は2では無く、0.1、0.01、0.001…と無限に続いていくことや、分数の概念をお伝えすると納得してくれました。
また、算数を深めていくといずれ微分や積分を習い、0.1、0.01、0.001…という極限や無限の概念についても学ぶことになります。足し算や引き算はそのスタート地点であり、決して無駄ではないことを説明すると、そのお子さまは前向きに算数に取り組んでくれるようになりました。
ご家庭だけで学問的な深い話をするのが難しいと感じる場合は、大人向けの教養番組や、YouTubeの教養系の動画なども活用しながら、お子さまの知的好奇心を満たしてあげると良いでしょう。
- ・WIRED.jp – YouTube
- 各界の専門家が視聴者からの質問に答えていくチャンネル
- ・TED – YouTube
- 様々な分野の先駆者がプレゼンテーションを行う。日本語字幕をまとめたプレイリストもあり。
- ・ナショナル ジオグラフィック TV – YouTube
- 世界の自然や歴史の謎に迫るドキュメンタリー。
ギフテッドのお子さまの勉強のサポート方法③学校の勉強にこだわらない

勉強の本質は、テストで良い点を取ることではありません。
「何で勉強しなくちゃいけないの?」とお子さまに聞かれて答えに窮したことのある方も多いかもしれませんが、その答えは明確で、「勉強するとはどういうことかを知るため」です。
勉強するという経験が無いまま大人になってしまうと、新しい知識を身に着けたいと思ってもどうすれば良いのかが分かりません。分からないことがあって調べたくても、調べ方が分からないかもしれません。
そうならないために、子どもの頃から“勉強の方法を勉強する”という経験が必要になります。
もちろん、「学歴があると社会で生きていくのに有利だから」という実利的な側面も否定できませんし、それはそれで大切な価値観ですが、ギフテッドのお子さまの場合は前者の方、すなわち「勉強するとはどういうことかを知るため」ということを優先して伝えた方がより勉強の意義が伝わりやすいでしょう。
勉強の意味や目的についてはこちらの記事(→勉強する意味・目的って?大人は何と答えるべきか、プロ家庭教師が教えます!)にも詳述していますので、併せてご覧ください。
極端に言うと、勉強のやり方が学べるのであれば、勉強の内容は教科書の内容でなくても構いません。
お子さまが興味や関心を持っていることについて深めても構いませんし、座学だけでなく様々な体験やプログラムに参加して、お子さまの知的好奇心を刺激することも大切です。
子どもは本来、知的好奇心にあふれた存在です。
様々な体験をさせてあげることで、もっと知りたいという気持ちが自然と芽生えますし、ギフテッドのお子さまであれば知りたいという気持ちはより芽生えやすいでしょう。
大人があれもこれもと用意するのではなく、お子さまが自ら学びたいと思う気持ちを大切にし、大人はそのサポートに徹するという姿勢も大切です。
東京大学先端科学技術研究センターの中村賢龍教授が中心となり運営されている「LEARN (learn-project.com)」」では、ギフテッドや発達障害など学校に馴染みにくい特性を持つ子どもたちを対象とした様々なプログラムが実施されています。
先生が知識を一方的に与えるのではなく、子どもたちが自らの知的好奇心の赴くままに、様々に考え行動できるプログラムとなっています。
LEARNのプログラムは、東京だけでなく福島・熱海・山口など様々な地域で実施されています。タイトルだけでも好奇心をくすぐられるものばかりですので、ぜひ積極的に参加してみてはいかがでしょうか。
ギフテッドのお子さまの勉強のサポート方法④優位感覚を知る

目で見た情報を処理するのが得意な「視覚優位」の人や、耳で聞いた情報を処理するのが得意な「聴覚優位」の人、言葉での説明が分かりやすいという「言語感覚優位」の人など、人はそれぞれ得意な感覚(=優位感覚)を持っています。
発達障害の特性を併せ持つ2E型ギフテッドの方の場合は、得意な感覚と不得意な感覚の凸凹が激しい傾向にあるため、得意な感覚を上手く使いながら勉強を進めることが大切です。
また、発達障害を併せ持たない場合でも、ギフテッドの方はいずれかの感覚が突出して優れていることがありますので、優位感覚を上手く使うことでより効率的にストレス無く勉強を進めることができます。
例えば、視覚優位のお子さまの場合は絵カードを使って学習を進めたり、聴覚優位のお子さまの場合は問題文を声に出して読んだりすることで情報が頭に入りやすくなり、勉強がより捗ります。
自分の優位感覚を知っておくと、大人になってからも情報のインプットやタスク管理が効率的にできますので、子どものうちから意識してみると良いでしょう。
プロ家庭教師メガジュンでは、ギフテッドに特化した学習サポートを提供しています。まずはお気軽にご相談ください。
ギフテッドとは|WISC-IV 知能検査、2E型と英才型、過度激動
ここまで、ギフテッドのお子さまが勉強が苦手になってしまう原因と解決方法について述べてきました。
以下からは、2E型ギフテッドや過度激動など、ギフテッドの性質に伴う困りごとなどについて解説していきます。
2E型ギフテッドと英才型ギフテッド

ギフテッドと発達障害の特性を併せ持つ人のことを、「2E型ギフテッド」と呼ぶことがあります。
2Eとは「twice-exceptional(二重に例外)」の意味で、日本では発達障害を併せ持つ場合のみを指すことが多いですが、海外では発達障害のほかにも様々なハンデキャップや特性を持つ人を含めて2E型ギフテッドと呼ぶ場合があります。
また、2E型ギフテッドに対し、特段のハンデキャップや困りごとを持たないギフテッドのことを「英才型ギフテッド」と呼ぶこともあります。
- 2E型ギフテッド…発達障害の特性を併せ持つギフテッド(広義には、発達障害以外のハンデキャップや疾患を持つ場合も含む)
- 英才型ギフテッド…発達障害やその他の疾患・特性が無いギフテッド
2E型ギフテッドの場合、WISC-IV知能検査(※)における4つの指標の数値の差(ディスクレパンシー)が大きくなると言われています。
ですが、FSIQが高いほど指標間の差は開きやすくなるため、それぞれの数値指標の差が大きいからといって必ずしも2E型ギフテッドであるとは限りません。
<4つの指標>
- 言語理解(VCI):言葉の理解力や表現力
- 知覚推理(PRI):視覚情報を処理し、パターンを認識する力
- ワーキングメモリー(WMI):記憶した情報を使って考える力
- 処理速度(PSI):情報を素早く正確に処理する力
2E型ギフテッドの方の場合、WISC-IV検査の結果において「ワーキングメモリー」又は「処理速度」の数値がほかの指標に比べて極端に低いことが多くなっています。
言語理解や知覚推理は150近くある一方、ワーキングメモリーや処理速度が110を下回るようなケースでは、発達のアンバランスさから様々な困りごとが生じやすくなります。
また、ワーキングメモリーや処理速度が平均以下(=100以下)になると、日常生活の中でも困りごとを感じる場面が増え、発達障害であると診断される場合もあります(※発達障害については、WISC-IVの結果だけでなく、問診や普段の生活の様子などを総合的に鑑みて診断されます)。
言語理解や知覚推理は、いわゆる国語や数学の力ですので、それらが苦手であっても「作文だけが苦手」「計算だけが苦手」といったように、特定の分野においてのみ困難が現れます。
一方、ワーキングメモリーや処理速度は特定の分野の勉強だけでなく、日常生活のあらゆる場面で必要な能力であり、これらの能力が低いと様々な困りごとが生じやすくなります。
また、言語理解や知覚推理が非常に高い一方で、ワーキングメモリーや処理速度が平均かそれ以下である2E型ギフテッドのお子さまの場合は、「難しい勉強が好きなのにケアレスミスをしてしまう」「考えることが好きだけれど非常にゆっくりしか思考が進まない」など、特有のストレスを抱えてしまいます。
周りからすると「年齢相応のことをそれなりにこなしてくれたら良いのに、なぜか高度な事にチャレンジして、その結果ミスをしたり、遅れたりしている変わった子」と捉えられてしまいます。
その結果、才能が評価されず単なる“困った子”として扱われてしまうケースも多くなっています。
生まれつきのワーキングメモリーや処理速度の低さについては、無理に矯正しようとするのではなく、言語理解や知覚推理の高い能力を認めて伸ばしてあげながら、困りごとを少しでも減らせるようサポートしていきましょう。
苦手よりも得意なことに注目して伸ばしてあげるというのは、発達障害やギフテッドのお子さまのサポートにおいて最も基本的かつ重要なことですので、常に意識しながらお子さまに接していただきたいと思います。
知能指数の測り方(WISC-IV知能検査)

お子さまの知能指数は、WISC-IVと呼ばれる知能検査によって測ることができます。
WISC-IVは発達障害の診断の際にも広く用いられている検査であり、言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度の4つの指標と、それらの総合点であるFSIQ(全検査IQ)を測定できます。
このFSIQがいわゆるIQであり、130以上であればギフテッドということになります。
学校の集団生活が苦手であったり、極端な(または急激な)学業不振が見られたり、あるいは不登校の状態になったりしたお子さまは、発達に問題が無いかを調べるためにまずはこのWISC-IV検査を勧められることが多くなっています。
立ち歩きが多く、集団行動を求められる時でも自分の関心の赴くままに行動するなどは、一見すると発達障害の特性にも見えるため、保護者さまも「おそらく発達障害なのだろう」と予想して検査を受けさせたところ、IQが130以上もあったので驚いたというお話も伺うことがあります。
WISC-IVで測ることのできる能力は、基本的には生まれつきの特性であり、トレーニングによって点数を伸ばすことにはあまり意味がありません。
例えば、生まれつき言語理解が苦手なお子さまに、単語カードを使ってたくさん言葉を覚えさせ、言語理解の数値が伸びたとしても、元々の言語理解の力が伸びたとは言えません。
ギフテッド教育の先進国では、子どもをギフテッドクラスに入れさせるためにIQテストの練習をさせる親などもいるそうですが、本来のギフテッド教育の趣旨とは離れてしまいます。
また、IQテストの点が良くても本質的な知能が伴っていないとなると、お子さまはいずれ周りについていけなくなり、後から苦労することになります。
WISC-IVなどの知能検査は、学校のテストとは目的が違います。
高い点を取ることが目的なのではなく、今のお子さまの特性を客観的な数値として測り、今後の支援の参考にすることが目的です。
ギフテッドかどうか、発達障害かどうかにこだわるのではなく、それぞれの指標の数値や所見をしっかりと読み込み、お子さまがどんな特性を持っているのかを理解するために検査の結果を活用いただければと思います。
ギフテッドの過度激動

ギフテッドの方は、一般的な人と比べて知的好奇心が旺盛であったり、感覚が敏感であったりします。
そのため、どんどん新しいことを学んだり、細かな違いに気付いたりできるという良さがある一方、知的好奇心が満たされないとストレスを感じたり、敏感過ぎて疲れてしまったりといったデメリットが生じる場合もあります。
ギフテッドの特性によって生じるデメリットは「過度激動(OE; Overexcitability)」と呼ばれ、以下の5つに分類されます。
- 知性過度激動
- 旺盛な知的好奇心と強い知識欲があり、それらが満たされないとストレスを感じる。
- 精神運動性過度激動
- スリルや冒険、新しい経験といった精神的な強い刺激を好み、わざと危ない行動を取ったり、危険な場所に行ったりする。
- 感覚性過度激動
- 五感が非常に敏感なため、大きな音や強いにおいなどの刺激が苦手で体調が悪くなることがある。
- 想像性過度激動
- 想像力が非常にたくましく、妄想に耽り自分の世界に入り込んでしまう。
- 情動性過度激動
- 感受性が強く他人の感情に敏感なため、人間関係で疲れやすく情緒不安定になりやすい。
一部の過度激動は、発達障害とよく似た特徴を持っています。
例えば、スリルを求めて危ない行為をしてしまう「精神運動性過度激動」はADHDの多動性・衝動性とよく似ていますし、「感覚性過度激動」はASD(アスペルガー症候群)の感覚過敏と似ています。
これらの特性が過度激動によるものなのか、発達障害によるものなのかを判別するのは非常に難しく、知能検査だけでなく日頃のお子さまの様子などを踏まえて総合的に判断していく必要があります。
また、お子さまの様子を詳しく観察した上で、それでもはっきりとは判別ができないケースもあります。
問題行動や不登校などから受診や検査を勧められた結果、ギフテッドであることが分かったお子さまの中には、「発達障害のような行動を取っている。知能指数は高い。すなわち2E型ギフテッドである」と安易に判断されてしまう場合もあります。
ですが、“発達障害のような行動”の要因が、発達障害ではなく過度激動である場合もあるため注意が必要です。
特に、ADHDと診断されてコンサータやストラテラの服用を検討する場合は、ADHDの診断が確実であり、その特性が中枢神経系の働きの不全によって引き起こされているという確証が得られてから薬物療法に進むことをおすすめします。
さらに、“発達障害のような行動”の要因が、ギフテッドの特性を周囲に理解してもらえなかったり、学校で孤立してしまったりしていることから生じるストレスである場合もあります。
特に小学校低学年頃までのお子さまは、自分の気持ちを言葉で表現することが苦手なため、学校でのストレスが他害や自害といった暴力性や、立ち歩きなどの多動性・衝動性として現れることがあります。
ギフテッドのお子さまの困りごとの要因には様々なパターンがありますので、安易な判断は避け、様々なサポートを試行錯誤しながらお子さまに合った支援方法を見出していくことが大切です。
ギフテッド専門のプロ家庭教師メガジュンでは、お子さま一人ひとりの性質に合わせた指導を行い、得意を伸ばしながら様々なお悩みに寄り添います。勉強だけでなく、コミュニケーションや生活上の困りごともサポート。まずはお気軽にご相談ください。
ギフテッドのお子さまの勉強のまとめ
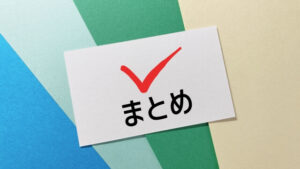
この記事では、ギフテッドのお子さまが勉強が苦手になる理由と、そのサポート方法についてお伝えしてきました。
改めてポイントをまとめると、以下のとおりです。
- 知能指数が高いからといって、必ずしも学校の勉強ができるとは限らない
- ギフテッドの子が勉強が苦手になってしまうのは、簡単すぎるなどの理由で学校の勉強に気持ちが向かわないのが一番の理由
- ギフテッドの子どもたちが、高い知能を持つがゆえに学校に馴染めない状態を「浮きこぼれ」という
- 本人に合ったレベルの勉強をさせてあげることで、ギフテッドの子どもも前向きに勉強に取り組むことができる
- 発達障害の特性を併せ持つ「2E型ギフテッド」の場合は、得意と不得意の差が大きくなりやすく、そのために勉強が苦手になることもある
- WISC-IV検査の4つの指標のうち、ワーキングメモリー又は処理速度の数値が低いと、日常生活で困りごとを抱えやすい
ギフテッドのお子さまは高い知能を持っていますが、それゆえに学校の勉強が退屈に感じて気持ちが向かわなかったり、発達にアンバランスさがあるために上手く能力を発揮できなかったりする場合があります。
お子さまの特性をしっかりと見極め、どうすればストレスなく勉強に気持ちを向けることができるのか、あるいは能力のアンバランスさを上手くカバーできるのかを検討していくことが大切です。
私たちプロ家庭教師メガジュンでは、長年にわたりギフテッドのお子さまを支援してきました。一人ひとりのお子さまの性質を徹底的に分析することで、お子さまに適したサポートを提供できるのが強みです。
ギフテッドのお子さまの性質に合わせた学習指導や生活・コミュニケーション支援を受けてみたいとお考えの方は、ぜひプロ家庭教師メガジュンにお問い合わせください。
また、指導や面談はオンラインでも承っています。遠方にお住まいの方でもご利用いただけるほか、これまで海外在住の方や帰国子女の方にもご利用いただき、ご好評の声をいただいてきました。
初回授業や面談は無料ですので、オンラインで授業が受けられるか心配な方もお気軽にお試しいただくことができます。
一人でも多くのお子さまが自分らしく生きていけるよう、一同全力でサポートしてまいります。
最後までお読みいただきありがとうございました。